artscapeレビュー
熊谷晋一郎『リハビリの夜』
2013年05月01日号
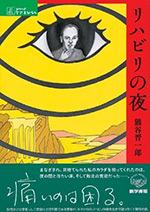
著者:熊谷晋一郎
出版社:医学書院
発行日:2009年12月
価格:2,100円(税込)
判型:A5判、264頁
例えばこんな文章が出てくる。
──「これがあるべき動きである」という強固な命令とまなざしをひりひりと感じながら、焦れば焦るほど、その命令から脱線する私の身体の運動がますます露わになっていく。
脳性まひの体とともに生活してきた、小児科医で研究者でもある熊谷晋一郎。少年期に通ったリハビリ施設でのトレイナーとの時間を振り返って綴った一文がこれなのだが、まるでダンスをめぐる文章のように読めてしまう。トレイナーが思い描く理想像を実現しようと努力しながら、それが叶わず、自分の体がバラバラになったかのように感じる。その切なさ、情けなさがとても丁寧な筆致で描かれる。この本の読みごたえがそこにあるのは間違いない。けれど、本書の白眉は、熊谷がトレイナーとトレイニーの関係性を、《まなざし/まなざされる関係》であるとき、《ほどきつつ拾い合う関係》であるとき、《加害/被害関係》であるときとに分けて論じる、その考察の確かさにある。
「自らすすんで私に従え」と告げているかのように、運動目標を押しつけるトレイナーの態度はトレイニーに対して監視的で、トレイナーにまなざされるトレイニーの体はこわばり、自壊する。こうした空しい《まなざし/まなざされる関係》やさらに強引に体の現状を見捨て体を矯正しようとする《加害/被害関係》を回避し、相互的に情報を拾い合うようにトレイナーがトレイニーに介入する状態、つまり《ほどきつつ拾い合う関係》こそ両者の望ましい関係なのではないか、と熊谷は説く。
熊谷の考察は豊かな発見に満ちている。介護という場の問題にとどまらず、ぼくが専門にしているダンスの現場にとっても充分刺激的だ。ナタリー・ポートマンが主演したバレエ映画『ブラック・スワン』に描かれたような、まなざし/まなざされる関係の苛烈さは、ダンスにおけるダンサーと見る者とのあいだに潜む基本的な状態であろう。それはそうとしてそこからさらに、ほどきつつ拾い合う関係というものへと意識を向けるのは、ダンスという枠のなかではなかなか難しい。ダンサーが目指すエリート的な身体ではなく「脳性まひの体」にフォーカスしたがゆえに、熊谷は「ほどきつつ拾い合う」などという関係を解きほぐしえたのではないか。そう思うと、ダンスという場の硬直性に気づかされる。しかし、それ以上に大事なのは、こうした視点の移動が体へ新鮮な向き合い方をうながしてくれる点に気づくことだ。他者にもわかるように自分の体験を内側から語る「当事者研究」という方法を推進してもいる熊谷の狙いは、まさにそうした新鮮な気づきを与えることにあるのだろう。
この本にはもうひとつの大きな魅力がある。「敗北の官能」「退廃的な官能」と熊谷が名づける、不可能性に直面したときに生じる独特の快楽に言及しているところだ。これをマゾヒズムに還元してしまうのは容易いが、トレイナーやボランティアと接して感じさせられる切なさや苦しさが、ある種の官能を喚起させもするということについての具体的で繊細な記述には、文学的な感動さえ受ける。授けられたこの体で生まれて死ぬほかないということは万人に共通の運命なのだ。この運命とどうきちんと向き合って自分の体ととともに生きていくか、その問いに熊谷はひとつの解答を与えてくれている。綾屋紗月との共著『つながりの作法──同じでもなく違うでもなく』もあわせて読むと、熊谷の考えをより深く知ることになるだろう。
2013/04/27(土)(木村覚)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)