artscapeレビュー
星野太のレビュー/プレビュー
ルネ・デカルト『方法叙説』(講談社学術文庫)

翻訳:小泉義之
発行所:講談社
発行日:2022/01/11
古今東西の哲学書のなかでも、デカルトの『方法叙説』(1637)ほど広く知られているものはそうそうないだろう。同書の「我思う、ゆえに我あり(Cogito, ergo sum; Je pense, donc je suis)」という言葉は、哲学や思想にまったく興味がない人であっても、どこかで一度は聞いたことがあるはずだ。
同時に本書ほど、その知名度に比して読まれていない本もあるまい。世間では「我思う、ゆえに我あり」という定式──ないしキャッチフレーズ──だけが一人歩きしているきらいがあるが、『方法叙説』の内容は、そのようなひとつの文章によって要約しうるものではまったくない。
今年のはじめ、講談社学術文庫に加わった本書は、そのあまりにも有名な古典の新訳である。巻末の訳者解説によれば、20世紀後半だけにかぎっても、本書の日本語訳は6種類におよぶという。訳者の小泉義之(1954-)は『ドゥルーズの哲学』(講談社学術文庫、2015)をはじめとする現代フランスの哲学・思想をめぐる仕事によって知られているが、最初の本である『兵士デカルト』(勁草書房、1995)をはじめ、デカルトを中心とする近世哲学が元来の専門である。
そもそも『方法叙説』とはいかなる書物か。若き日のデカルトは母国フランスで学業を修めたのち、「文献による学問」を捨て兵士としてオランダ、ドイツに赴いた。その間も、デカルトは「世界という大きな書物」(17頁)に学びつつ思索を続け、最終的に9年間の放浪を経てオランダに隠棲することになる。本書は、デカルトがそれまでの20年におよぶ精神の遍歴を綴ったものであり、間違っても第四部に登場する「私は思考する、故に、私は存在する」(45頁)というひとつの命題に収斂するものではない。
知られるように、そもそも本書は『屈折光学』『気象学』『幾何学』という三試論に先立つ「方法」についての概説であった(従来、方法「序説」という日本語訳が採用されてきたのもそのためである)。しかし、以上のような成立経緯をもつ『方法叙説』は、デカルトという人間の半生を綴った自伝的な書物でもある。げんにかれはこう言っている──「この叙説で、私が辿ってきた道の何たるかを示し、私の人生を一枚の絵画のように表象することができれば、私としてはとても喜ばしい」(12頁)。そう、本書は何よりもまず、40歳になったデカルトがおのれの半生を振り返りつつ書いた「一枚の絵画」なのだ。じっさい、全六部からなる本書を虚心坦懐に読んでいくなら、そこで第一にせり上がってくるのはデカルトというひとりの人間の肖像にほかならない。
この小泉義之訳の『方法叙説』──ちなみに、本書のタイトルが方法「序説」でない理由は訳者解説で説明されている──は、これまで同書を手にとり挫折した人にとっても、あるいは人生のどこかの段階で同書を読んだことのある人にとっても、ひとしく参照に値する一冊である。全体を通してきわめて行き届いた訳注を含め、本書はいわゆる学術書の翻訳作法に則っているが、そこに不必要な読みにくさはまったくない。なおかつ、エティエンヌ・ジルソンやフェルディナン・アルキエによる定評ある註解書にもとづいた訳注の数々は、あるていど専門的な内容を期待する読者の期待にも応えうるものである。
2022/08/18(木)(星野太)
川端茅舎『川端茅舎全句集』(角川ソフィア文庫)
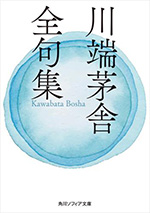
発行所:KADOKAWA
発行日:2022/01/25
ホトトギスの同人であった俳人・川端茅舎(1897-1941)の作品は、これまで長らく歴史の影に埋もれてきた。その(ほぼ)全作品を収めた『川端茅舎句集』(角川文庫、1957)が刊行されたのはすでに半世紀以上前のことであり、以来、この俳人の作品集が新たに編まれることはなかった。本書はその『川端茅舎句集』を底本としつつ、これに然るべき増補改訂を施した待望の一冊である。
東京・日本橋に生まれた茅舎(本名:信一)は若くして俳句を始め、18、19歳のころには『ホトトギス』をはじめとする雑誌に投句を始めた。やがて頭角を現した茅舎は、高浜虚子の愛弟子にして、ホトトギスを代表する同人のひとりとして長く活躍した。35歳で脊椎カリエスを患ってからはおおむね病床で過ごすも、44歳で没するまで、闘病しつつ作句に励んだことで知られる。
川端茅舎は、美術とも縁の深い俳人である。日本画家・川端龍子(1885-1966)を兄にもち、本人もまた洋画家を志して岸田劉生に師事していたこともある(しかし闘病のため画家になることは断念)。塚本邦雄の『百句燦燦──現代俳諧頌』(講談社文芸文庫、2008)をはじめ、茅舎の作品を論じた文章のなかにしばしば絵画的な比喩が散見されるのも、おそらくそのあたりの事情に起因していると思われる。ちなみに『ホトトギス』に連載された茅舎の「花鳥巡礼」(本書195-335頁)は、古今の句の鑑賞という体裁をとりながら、デューラー、シャヴァンヌ、ロダンといった芸術家の名前がたびたび登場する不思議なエセーである。茅舎という俳人は、そうした近代芸術の素養を──実作者として──身につけていた数少ない人物であった。
その肝腎の俳句については、ここにいくつか抜粋してもよいが、やはり本書でその全体を味わっていただくに如くはない。私見では、茅舎の句がまとう何とも言えぬ気魄は、やはりその多くが長い闘病生活のなかで詠まれたという点に起因しているような気がしてならない。
たとえば茅舎は「花鳥諷詠」のなかでこんなことを言っている──「俳句は花鳥を諷詠する以外の目的をば一切排撃する事によって、種々雑多な目的を持った他の芸術と毅然と対している。又僕はかような啓蒙めく言葉を繰返しておきたい」(201頁)。この勇ましい文章は、茅舎の偽らざる本心であっただろう。だが、かの人の境遇を知るわれわれの目から見れば、この言葉はいささか皮肉な響きをともなわざるをえない。なぜなら現実の茅舎は、こうした「花鳥」をじかに愛でうる状況には必ずしもなかったからである。あらためて繰り返せば、茅舎は俳句が「花鳥を諷詠する」以外のいっさいの目的を排するという点で、それが「種々雑多な目的を持った他の芸術と毅然と対している」と考えた。しかしその「花鳥」は、長らく病に臥していたこの俳人にとって、接近したくても叶わぬ超越的な位相にあった──おそらく、そのように言うことができるのではないだろうか。
ここで大方の読者は、茅舎と似た境遇にあった正岡子規のことを思い浮かべるかもしれない。だが、晩年をほぼ仰臥で過ごさざるをえなかった子規とはまた異なり、茅舎は10年におよぶ闘病の間にしばしば著しい回復を見せ、時には地方に吟行することもあった。その意味で、茅舎の作句の「凄味」(松本たかし「解説」177頁)は、子規の晩年における「写生」の壮絶さとは前提を異にしている。いずれにせよ、茅舎にとっての俳句が「花鳥を諷詠する以外の目的をば一切排撃する」ものであったにせよ、そのような断言の背後にはいくつもの含みや捻れがある。そのことが、虚子に「花鳥諷詠真骨頂漢」(48頁)と言わしめたこの俳人の句を、唯一無二のものとしているように思われる。
2022/08/18(木)(星野太)
カール・ゼーリヒ『ローベルト・ヴァルザーとの散策』

翻訳:新本文斉
発行所:白水社
発行日:2021/11/10
本書は、スイスの伝記作家・ジャーナリストであるカール・ゼーリヒが、作家ローベルト・ヴァルザー(1878-1956)との40回以上におよぶ散策の記録を書き留めたものである。本書は晩年のヴァルザーの人となりを伝える書物として長らく知られてきたが、たとえヴァルザーの作品について何も知らなくとも、本書はそれ自体できわめて興味深い読み物として成立している。
ごく個人的な話になるが、わたしはかつて、エンリーケ・ビラ=マタスの『バートルビーと仲間たち』(木村榮一訳、新潮社、2008)を通じて、このローベルト・ヴァルザーという作家に大きな関心をもった。ハーマン・メルヴィルの小説中の人物「バートルビー」に類する人物を文学史のなかに探っていくこの驚嘆すべき書物は、まさしくこのスイス人作家をめぐるエピソードから始まる。そこで描き出されるヴァルザーの実人生は、カフカやゼーバルトを魅了したその作品と同じく、あるいはそれ以上に興味をそそるものだった。
本書の主役であるローベルト・ヴァルザーは、この「散策」が始まった時点ですでに文学的には沈黙し、スイス東部ヘリザウの精神病院に収容されていた。かたや、編集者でもあった本書の著者ゼーリヒは、この散策に先立って──世間がヴァルザーにあらためて目をむけるべく──その作品をふたたび世に問おうとしていた。そうした背景のもと、1936年以来、ゼーリヒはヴァルザーのいた精神病院をたびたび訪れ、本書に収められた長期間にわたる「散策」を敢行する。本書の初版が世に出たのは1957年、ヴァルザーが亡くなった翌年のことである。
したがって本書はまず、晩年に沈黙したこの作家の言葉を伝える貴重な資料として読むことができる。しかし同時に、本書には「著者」ゼーリヒによる数多の脚色が施されていることに注意せねばならない。訳者あとがきでも指摘されるように、本書の端々にあらわれる箴言めいた言葉のなかには、どこかこの作家には似つかわしくないものも含まれる。この『ローベルト・ヴァルザーの散策』は2021年にズーアカンプから出た最新版の邦訳だが、その編者のひとりであるペーター・ウッツの指摘によれば、本書には「後見人」ゼーリヒの政治的な身振り、さらにはひとりの「作家」としての介入が数多くみとめられるという。
だが、それを単純に本書の瑕疵と考えるべきではないだろう。本書が、ローベルト・ヴァルザーという謎めいた作家との散策を伝える貴重な「資料」であり、それをもとにしたカール・ゼーリヒという人物の「作品」でもあるということはいずれも事実であり、この二つは単純な排他的関係にはない。晩年に沈黙したひとりの伝説的な作家の「生」が、ここには幾重にも捻れたしかたで描写されており、そのことが逆説的にも本書を魅力的なものとしている。さらに本書には、ゼーリヒ本人によるヴァルザーの肖像写真が多数収められている。二人きりの散策の「真実らしさ」を強調するかのようなその数々の写真をいかに「読む」か──それもまた、このミステリアスな書物がわれわれに突きつける問いのひとつである。
2022/06/07(火)(星野太)
フリードリヒ・シュレーゲル『ルツィンデ 他三篇』

翻訳:武田利勝
発行所:幻戯書房
発行日:2022/02/09
2019年6月に刊行開始された〈ルリユール叢書〉(幻戯書房)が、先ごろシリーズ30冊に達したという記事を読んだ★。その玄人好みのラインナップもさることながら、たったひとりの編集者が、月に一冊を超えるペースでこの叢書を切り盛りしているというのは驚異的というほかない。ところで数ヶ月前、その新刊書のなかにひときわ目を引く表題を見つけた。それが本書、フリードリヒ・シュレーゲルの『ルツィンデ』である。
フリードリヒ・シュレーゲル(1772-1829)といえば、兄アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲル(1767-1845)とともに雑誌『アテネーウム』を立ち上げるなど、多彩な活動で知られる初期ドイツ・ロマン派の作家だ。そして、この学者肌の作家による唯一の小説作品が、かれが27歳のときに発表した『ルツィンデ』(1799)なのである。
これは翻訳にして140頁ほどの中篇小説であり、ドイツ・ロマン派に格別の関心を寄せる読者を除けば、本書の存在を知る読者はそう多くはないだろう。ただ、『ルツィンデ』はけっして「知られざる」作品というわけでもない。戦前には1933年と34年に二種類の(!)翻訳が出ており、文芸同人誌『コギト』第30号(1934年11月号)には、かの保田與重郎による『ルツィンデ』論が掲載されている。すくなくとも戦前の日本では、本書は──おもに日本浪曼派を通じて──それなりに知られていた作品であった。戦後に目を転じてみると、1980年代から90年代にかけて刊行されていた『ドイツ・ロマン派全集』の第12巻に、やはり『ルツィンデ』の新訳が収められている(平野嘉彦訳、国書刊行会、1990)。そしてこのたびの『ルツィンデ 他三篇』は、当該作品に加え、関連する「ディオテーマについて」「哲学について」「小説についての書簡」の三篇を収録した、いわば決定版とでも言うべきものである。
そもそも本書はいわくつきの小説である。哲学および文学に深い造詣を示した若きフリードリヒ・シュレーゲルは、本書『ルツィンデ』が引き起こした一大スキャンダルによって、アカデミズムへの道を永久に絶たれることになった。それは、本書がシュレーゲル本人と、8歳年上の人妻ドロテーアの恋愛をただちに想起させる「モデル小説」だったからだ。本書におけるユーリウスとルツィンデは、その数年前、すでにベルリンのサロンで噂になっていたフリードリヒとドロテーアを明らかにモデルとしたものだった。本書の解説によると、『ルツィンデ』をめぐる騒動は、1801年に行なわれたシュレーゲルの教授資格審査の場にまで及んだという(293-294頁)。その小説としての内容の評価以前に、本書はそうしたスキャンダルとともに受容されたのだ。
だが、『ルツィンデ』の本当の「スキャンダル」はそこにはない──かつてそのことを指摘したのが、批評家のポール・ド・マンであった。ド・マンは「アイロニーの概念」(『美学イデオロギー』上野成利訳、平凡社ライブラリー、2013)において本書『ルツィンデ』を取りあげ、ヘーゲルやキルケゴールといった錚々たる哲学者たちが、この小説をなぜかくもヒステリックに論難するにいたったのかを説明する。ごくかいつまんで言えば、その理由は次のようになる。この小説──とりわけ「ある省察」と題されたパート(124-129頁)──では、性愛と哲学をめぐる議論がほとんど不可分なかたちで繰り広げられる。つまりこの小説では、性愛的描写と哲学的思弁が、明らかな意図をもって同じ平面のもとにおかれているのだ。ここに読まれるのは、「性愛のコード」と「哲学のコード」のアイロニカルな混淆であり、そのことが本書を読んだ哲学者たちを激しく苛立たせた原因だ、というのである。
実際に本書を読んでみると、このド・マンの立論にはそれなりに理があるように感じられる。つまり『ルツィンデ』が挑発的なのは、おのれの秘すべき恋愛をモデルにしたという表層的な次元にはおそらくない。むしろ読者は「小説(ロマン)」というこの文学形式に依拠した文学的かつ思想的な挑発にこそ着目すべきなのだ。本書に収録された「小説についての書簡」をはじめとする小品は、そうしたシュレーゲルの意図をうかがい知る助けとなるだろう。巻末の充実した註や訳者解題とあわせて、本書は日本語における『ルツィンデ』の決定版と言える一冊である。
★──中村健太郎「果てなき“文芸の共和国”を目指す〈ルリユール叢書〉とは──ひとり編集部で30冊刊行できたわけ」(じんぶん堂、2022年4月25日)https://book.asahi.com/jinbun/article/14601870
2022/06/07(火)(星野太)
前田英樹『民俗と民藝』、沢山遼『絵画の力学』、北大路魯山人『魯山人の真髄』

著者、書名:前田英樹『民俗と民藝』
発行所:講談社
発行日:2013/04/10
著者、書名:沢山遼『絵画の力学』
発行所:書肆侃侃房
発行日:2020/10/17
著者、書名:北大路魯山人『魯山人の真髄』
発行所:河出書房新社
発行日:2015/08/06
先日閉幕した「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」(東京国立近代美術館、2021年10月26日〜2022年2月13日)をきっかけとして、民藝が新たに脚光を浴びている。柳宗悦・河井寬次郎・濱田庄司の3人が「民藝」という言葉を考案したのが1925年のことであるから(翌1926年に「日本民藝美術館設立趣意書」を発表)、いまや民藝の歴史もほぼ一世紀を数えることになる。そうした節目であることに加え、昨今の時代の趨勢もあり、民藝をめぐる入門書や専門書の類いはここのところ百花繚乱の様相を呈している。そこで今回は、あえて新刊書に限定することなく、いわゆる「民藝」を論じたものとしては見落とされがちな幾つかの書物を取り上げることにしたい。
前田英樹『民俗と民藝』は、柳田國男(1875-1962)と柳宗悦(1889-1961)という「互いにほとんど通い合うところがなかった」2人の仕事を、「輪唱のように」歌わせることに捧げられた書物である(同書、3頁)。著者は、柳田の民俗学と柳の民藝運動に共通の土壌を「原理としての日本」という言葉で言い表わしている。ただし、著者もことわっているように、ここでいう「原理としての日本」とは、狭隘な日本主義や日本特殊論とはいかなる関係もない。それは、近代化の過程で抑圧されてきた数ある伝統のうち、かつてこの列島に存在した何ものか──たとえば「稲」に対する強い信仰──を名指すための暫定的な言葉である。
同書は『民俗と民藝』と題されているだけあって、柳田國男による民謡の採集にまつわるエピソードから始まったかと思えば、いつしか柳宗悦による李朝陶磁の発見をめぐる話題へと転じるなど、「民俗学」と「民藝運動」をまたぐその構成に大きな特徴がある。なかでも強い印象を残すのは、この2人の仕事や思想を記述する、その力強い筆致であろう。本書をぱらぱらとめくればすぐさま明らかになるように、その文体は、ごく整然とした伝記的な記述とは一線を画している。柳についてのみ言えば、著者の眼目は、柳が李朝陶磁と木喰仏との出会いを通じていったい何を「発見」したのか、というそもそもの始まりを復元することにある。まるでその場に立ち会ったかのような迫真的な記述は好みが分かれるだろうが、すくなくとも本書は、民藝思想の始まりにいかなる「原光景」が存在したのかを、われわれの目にまざまざと映し出してくれる。
沢山遼『絵画の力学』には、柳宗悦論である「自然という戦略──宗教的力としての民藝」が収められている(初出『美術手帖』2019年4月号)。同論文は、柳の思想における「芸術」と「宗教」という二つの立脚点に照準を合わせ、この両者の不可分な関係を批判的に論じたものである。知られるように、初期のウィリアム・ブレイク研究から、晩年の一遍上人研究にいたるまで、思想家・柳宗悦の核心にはつねに宗教をめぐる問いがあった。1920年代に誕生した「民藝」の思想が、それを放棄するのではなくむしろ深化させたということも、柳のその後の著述活動から知られる通りである。
沢山の前掲論文は、こうした柳の宗教=芸術思想に対する、ある重大な臆見を拭い去るものである。柳は、わずかな個人の天才性に依拠する近代芸術を退け、むしろ中世のギルド的な生産体制を評価した。こうしたことから、今も昔も、柳の民藝思想は近代芸術のまったく対極にあるものと見なされるきらいがある。しかしながら、宗教や神秘主義への関心は、柳と同時代の抽象芸術にもしばしば見られるものである。具体的に挙げれば、青騎士(カンディンスキー)やシュプレマティスム(マレーヴィチ)のような同時代の美術実践・思想は、民衆芸術や神智学を通じた「現実の階層秩序」の解体や無効化をめざすという点で、柳の民藝思想と大きな親和性を有している(同書、324頁)。
民藝運動が、従来の近代芸術へのアンチテーゼであったとする見方は、以上のような視点を欠いたごく一面的なものにすぎない。沢山が「階層秩序の脱構成」と呼ぶこの視点を確保することによってこそ、柳宗悦の思想を同時代の美術潮流のなかにただしく位置づけることが可能になる。これに加え、最初の著書である『科学と人生』(1911)において心霊現象やテレパシーに関心を寄せ、やがて主体なき「自動性」に基づく芸術生産を謳うことになった柳の民藝思想が、シュルレアリスムの「自動記述(オートマティスム)」と同時代的なものであるという指摘も示唆的である。
最後に、柳宗悦の同時代人である北大路魯山人(1883-1959)の著作を挙げておきたい。古今の書画に通じ、すぐれた料理家・美食家でもあった魯山人は、柳をしばしば舌鋒鋭く批判したことでも知られる。過去の偉大な思想は、しばしば過剰なまでの神秘化を呼び招くものだが、柳を批判する論敵・魯山人の筆は、等身大の人間としての柳宗悦の姿をわれわれに伝えてくれる。
それだけではない。幼少より書画の分野で才覚を発揮した魯山人は、1926年、43歳のときに鎌倉で本格的な作陶を開始する。これは柳らが「日本民藝美術館設立趣意書」を公表したのとほぼ同時期のことであった。柳宗悦と北大路魯山人と言えば、人格的にも思想的にも対極的な人物と見られるのが常である。しかし、平野武(編)『独歩──魯山人芸術論集』(美術出版社、1964)などに目を通してみれば、読者はそこに「自然」を唯一無二の範とするこの人物の芸術思想をかいま見ることができる。それは柳の言う「自然」──沢山の前掲書を参照のこと──と、いったいどこまで重なり合い、どこで袂を分かつのか。生前、民藝運動を批判して止むことのなかった魯山人だが、『魯山人の真髄』に所収の「民芸彫刻について」や「柳宗悦氏への筆を洗う」をはじめとする論攷を傍らに置いてこそ、民藝そのものもまた新たな姿を見せるのではないか。魯山人が生前に書き残したものは、平野雅章(編)『魯山人著作集』(全三巻、五月書房、1980)にまとめられているほか、主だったものは『魯山人味道』『魯山人陶説』『魯山人書論』(中公文庫)などでも読むことができる。
2022/04/09(土)(星野太)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)