artscapeレビュー
木村覚のレビュー/プレビュー
冨士山アネット『DANCE HOLE』

会期:2016/02/04~2016/02/09
のげシャーレ[神奈川県]
フライヤーの「本作は出演者の居ないダンス公演」とは本当だった。のげシャーレの普段は通らない廊下を抜けて、観客はまず楽屋に通される。待っているのは、例えれば〈食べるはずが食べられてしまう〉あの「注文の多い料理店」。「見る」担当であるはずの観客は、真っ暗な舞台空間へと連れて行かれ、指示の声に促され、それに応えるうちに、いつの間にか「踊る」担当にされてしまう。天からの声が指示を出し、観客たちは二人ひと組で向き合うと、手をつなぎ、体を接近させて回るといった「ダンス」を踊る。この「ダンス」を見る普通の観客はいない。しかし、この場で唯一の見る者として指示の声がいるわけで、この声の主に観客=ダンサーは見られたまま、上演の60分を過ごす。ダンスを見る者は、大抵、踊る身体に同化したり突き放されたりして見る。それと、見る者が見られる者へと立場を実際に交換することとは、雲泥の差がある。筆者は、この体感型アトラクションを満喫しながら、ひたすら怖がっていた。本作タイトルは「DANCE HALL」ではなく「DANCE HOLE」。不意に「穴」に落とされた感じだ。それは指示の声にひたすら応えるマゾヒスティックな官能さえあった。これはダンスの追体験である以上に、舞台あるいは舞台本番というものの追体験であり、それ故の怖さがあった。ダンスの追体験を目論むのであれば、緊張感を削いだワークショップ形式であってもよいはずだ。しかし、そうではなく、冨士山アネットの狙いとしては、舞台に身を置く緊張こそ観客に体感してもらいたいということがあったのではないか。最後に渡された紙には「これからが本番です」といった言葉が書かれてあった。つまり、本番のはずの時間を過ごしたあとこそ、人生という本番がある。これは、そのためのリハーサルだったわけだ。その狙いはとても面白いのだが、ここで経験するダンスが、もう少しダンス史を観客が知るきっかけになっていたらよいのではないかと思った。踊ることを通して、もう少し踊りとはなにかがわかってくるとよいのだが、なかなかそうはならない(しかし、1時間くらいの「本番」でわかるはずもないのだが)。もうひとつ気になったのは、これを楽しみたい観客ってどんな観客なのだろうということ。ワークショップのマニアみたいな人がダンスの世界にいるようだけれど、そういうひと向け? あるいは、この世にいろいろと理解したらよいことがあるなかで、ほかならぬ「ダンス」を体験させることの意味とは? といった問いが明確になると、こうしたアトラクション型の公演がいま以上の脚光を浴びるなんて日が来るのかもしれない。
2016/02/07(日)(木村覚)
プレビュー:村川拓也『終わり』、手塚夏子『15年の実験履歴──私的な感謝状として』

先月は京都造形芸術大学でBONUSのイベントを行ないました。来客者の方たちからはおおむね好評だったのですが、自分のイベントを自分では批評できないというジレンマに陥っております。取り上げるのが恥ずかしいといった類のためらいではなく、批評対象のインサイダーになってしまうと批評のポジションに立てず、ゆえに物理的に批評できなくなるわけです。このことは自分に降りかかった「前衛のゾンビ」(藤田直哉)問題といっても良いかもしれません。ご覧になった方、どうかぜひあのイベントの批評を書いてくださいませ。
さて、今月は秋季に負けないくらいダンスの公演・イベントラッシュです。そして横浜ダンスコレクション、TPAM、国際交流基金(障害×パフォーミングアーツ特集)、『〈外〉の千夜一夜 VOL. 2』と横浜でのプログラムがとても多いことが特徴です。その喧騒のなかでかき消されてしまいそうですが、STスポット横浜での二つの公演が要注目なのです。
ひとつは村川拓也『終わり』(TPAMショーケース参加作品、STスポット横浜、2/12-14)。村川は2011年の『ツァイトゲーバー』で介護をテーマにした舞台をつくり話題になった作家。その彼が今回ダンスを扱った舞台作品を上演します。昨年やはりSTスポット横浜で上演された相模友士郎『ナビゲーションズ』がそうだったように、出発点がダンス分野ではなく演劇やパフォーマンスの上演を経た作家がいまダンスに注目しているということが、筆者としてはじつに興味深いのです(同じような感慨は2014年の多田淳之介『RE/PLAY (DANCE Eidt.)』からも受けとっていました)。とくに無視してはならないのは、相模も多田も「ダンス」に一定の距離を保ちながら、しかし、けっして軽んじるわけではなく、それどころか、ダンスの可能性を多くの振付家たちが思いつかないような仕方で引き出していることです。村川のこの新作にも同様の期待を抱いてしまいます。
もう一作は手塚夏子『15年の実験履歴──私的な感謝状として』(STスポット横浜、2/15-16)。昨年の山縣太一×大谷能生『海底で履く靴には紐が無い』(これもSTスポット横浜だ!)公演のアフタートークでも話題になっていたことですが、いまの日本の演劇が「チェルフィッチュ以後」と呼ばれるその光に隠れた影の歴史として「手塚夏子以後」というべき側面があることは、忘れてはなりません。いまだ「手塚夏子」に出会っていない若い皆さんにこそ、お勧めしたいです。
2016/01/31(日)(木村覚)
『サウルの息子』

新宿シネマカリテほか[東京都]
アウシュヴィッツにもユーモアがあったと、ヴィクトール・フランクルは『夜と霧』であの日々を振り返る。彼によれば「ユーモアとは、知られているように、ほんの数秒間でも、周囲から距離をとり、状況に打ちひしがれないために、人間という存在にそなわっているなにものか」だ。
絶滅収容所では、千人単位で運ばれてきたユダヤ人を、次々とガス室に押し込め、死体を焼かねばならない。その仕事を遂行したのはゾンダーコマンドと呼ばれた同じユダヤ人だった。数カ月間その「絶滅」の任務を負うことで生きながらえた後、ゾンダーコマンドの一人であるサウルには証拠隠滅のため皆と同じ運命が待っている。サウルはあるとき、死体となった息子を見つける。息子をユダヤ教の祈りのもとで埋葬したい。そう思った瞬間、いったん失われていた「人間という存在にそなわったなにものか」をサウルは回復し、過酷で過密な労働をかいくぐって、運命が定めたのとは別の生を生き始める。
「アウシュヴィッツ」をテーマにした映画に向けてこんなことをいうのは不適切かもしれない。だが、絶望的な状況に無表情で挑むサウルは、まるで『ミッション:インポッシブル』の主人公のようだと思ってしまった。さもなければ処刑台の前で「この髭だけは大逆罪を犯していないからね」とユーモアを飛ばす、トーマス・モアのようなユーモリストのようだ。フロイトはユーモリストのなかに「自己愛の勝利、自我の不可侵性の貫徹」を見た。心を苦しめてくるものに対する徹底的な抵抗は、死の瀬戸際でも、いや、死の瀬戸際であるからこそ求められるのだ。ただし、一点、サウルの行動を「自己愛」と解釈するのでは片がつかない点がある。それは息子への愛が彼をそう変容させたというところだ。
ところで、サウルの息子は本当にサウルの子なのだろうか。あれはお前の子ではないと彼の仲間は言う。そうしたセリフは、サウルが誤解しているとか、サウルを不憫に思ってということより、サウルの行動がより普遍的な未来へ向けられていることを示唆してはいないか。幽霊のように少年がサウルの前に現われるラストシーン。その少年がたんにサウルの息子ではないことは重要だ。少年が森のなかを走り逃げるところで映画は終わる。この少年は変容したサウルが救い出した未来の子ども(=私たち)であり、あるいはその子どもが生きているあいだに示すべき「人間という存在に備わっているなにものか」だろう。
映画『サウルの息子』予告編
2016/01/27(水)(木村覚)
第3回超連結クリエイション

会期:2016/01/24
京都芸術劇場 studio21[京都府]
今月の推薦公演は、私がディレクターを務めているBONUSの第3回超連結クリエイションにします。BONUSは2014年の7月にサイトをスタートさせた「ダンスを作るためのプラットフォーム」です。批評の活動だけが自分の仕事なのかと自問自答した結果、「作る」ことにコミットして二年目になります。多様な活動があるのですが、なかでもBONUSの中心になっているのは「連結クリエイション」と名付けた、作家たちにテーマに基づいた制作を依頼するプロジェクトです。第1回は『雨に唄えば』、第2回は『牧神の午後』を取り上げ、ダンスに限らず、美術や演劇の分野の作家たちに人類の歴史的遺産を解釈してもらいました。第3回はちょっと角度を変えてテーマを「障害(者)とダンスを連結させて映像のダンスを制作してください」としました。「映像のダンス」という依頼については、今回はあまり重視しないことになり、イベント当日は、調査・研究を重ねたその成果報告が中心になる予定です。参加作家は、砂連尾理、塚原悠也(contact Gonzo)、野上絹代(FAIFAI)の3名。また、砂連尾さんのチームでは東京大学の教員で『リハビリの夜』(医学書院、2009)の著者として知られる熊谷晋一郎さんやYCAM、野上さんのチームでは多摩美術大学の教員でクリエイターの菅俊一さんはじめ、舞台美術で活躍する佐々木文美さんらが協力してくださっており、多種多様な知恵の集う場になることでしょう。昨年8月の研究会でも調査報告してもらった伊藤亜紗さんにコメンテイターを、石谷治寛さん、古後奈緒子さんにはゲスト・コメンテイターをお願いしております。濃密な「未来のダンス」を発見する場になるかと思います。入場は無料。ただし、事前に予約してもらえると助かります。
2016/01/14(木)(木村覚)
福留麻里『そこで眠る、これを起こす、ここに起こされる』
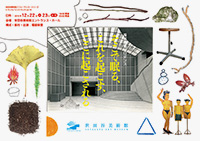
会期:2015/12/22~2015/12/23
世田谷美術館[東京都]
本作は、「トランス/エントランス」という企画の第14弾。毎度、世田谷美術館のエントランス・ホールを使って行なわれるパフォーマンスのプログラム、10年目を迎える今回は福留麻里のソロダンスだった。特定の場をリサーチして、その場の歴史や環境を掘り起こし、そこから見出された事象の意味を芸術の方法を用いて引き出すというタイプの試みは、とくに美術の分野ではいまや当たり前の形態だ。とりわけ、「地域アート」として括られる多くの国際トリエンナーレでは、個々の作家が最新作の展示をその場で披露する意味が乏しく、その代わりに価値が感じられるのは、地域をリサーチしたうえでそこから見出されたものに光を当てた展示といった状況がある。すなわち、ホワイト・キューブのニュートラルな(展示する作品を限定しない)性質にふさわしいニュートラルな(展示する場を限定しない)作品ではなく、むしろ場のローカリティを無視せずにその場所の性格にふさわしい表現、その性格に拮抗する表現が求められているということだろう。そういうことであるならば、自ずとアートはこれまでの自分自身の性格(例えば、作家という個の内面の発露といった性格)を変更せざるを得なくなるだろうし、現在、その過渡期にあらゆるアート表現は直面していると考えるべきだろう。さて、そんな状況にダンスはどう答えるのか? 福留麻里が今作で挑んだのは、こんな問いだったのかもしれない。世田谷美術館は広大な砧公園に置かれているが、本作は、福留が公園と美術館とに足繁く通ったその「調査」の様子を反映したものとなっていた。ときに、その場に棲む鳥や小動物や昆虫のようになって、また福留本人として、福留はエントランスホールに散りばめたオブジェたち(小枝や靴や小物たち)と対話する。その動きは福留らしく、とても繊細で、丁寧だ。とはいえ、同時に感じられるのは、「なぜ、ここにいるのが、福留なのか?」という問いだったりする。ダンサーはここで観客と「ここ」をつなぐ役割をなす。あるいはダンサーは反響板となって、観客の前に「ここ」を映し出す。それがどうしてこの(福留麻里という)反響板なのか? 筆者は個人的に福留麻里という振付家・ダンサーを敬愛している。繊細で丁寧なダンスは掛け替えのないものだ。だからこそあえて問いたくなる。観客とリサーチ対象とをつなぐ「メディア」として、ダンサーはその個性をどう発揮するべきなのか? 個性は「メディア」のノイズとなる面もあるかもしれない。もし欲深くなってよいなら、この上演に「振り付け」があったらよかったのではと思う。福留麻里という特権的な身体でしか踊れないものではない「振り付け」が。その振り付けが場と観客とをダイレクトにつなぐものとなるならば、福留麻里は「機能」として透明化する(公共化する)ことだろう。そのとき福留の身体を観客は、福留らしい、場へのまなざしを体験しつつ、身体化することだろう。
2015/12/23(水)(木村覚)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)