artscapeレビュー
2013年10月01日号のレビュー/プレビュー
花珠爛漫「中国・庫淑蘭の切り紙宇宙」

会期:2013/08/01~2013/09/17
ミキモト本店6階ミキモトホール[東京都]
「剪紙(せんし)」とは、古くから中国の農村地方でお祭りや屋内の飾りとして用いられてきた切り絵の一種。中華街のお祭りなどでも見かけるものは日本の切り絵の技法に似た単色のものが多いが、庫淑蘭(クー・シューラン、1920~2004)の剪紙はそのような切り絵とは、技法もイメージもまったく異なるものであった。モチーフとなっているのは、四季の生活、子ども、動物、神話など。色彩鮮やかな作品は、色紙を糸切りばさみで切り抜き、糊で貼り合わせてつくられている。一枚の紙を切り抜いて絵にするのではなく、切り絵と貼り絵を混合したような技法である。
中国陜西省旬邑県に生まれた庫淑蘭はもともと生活の合間に剪紙や刺繍を楽しんでいたが、1980年に旬邑県文化館美術研究員に才能を見出されて県での剪紙制作指導を始める。1985年、農作業の帰りに自宅近くの深い溝に落ちて重症を負い、2カ月近く寝たきりの生活を送った庫淑蘭は、夢に現われた「剪花娘子(切り絵を作る女神。手元には小さな鋏を持っている。チラシ画像参照)」と自身とを重ね合わせ、使命感に突き動かされるかのように剪紙作品をつくり続けるようになったという。それまでは農村の生活などをテーマとしていた作品が多かったが、事故の後は「剪花娘子」や生命力の源泉であり豊穣のシンボルである「生命樹」をモチーフとした作品が生み出されていった。没後の2005年には米国ボルチモア美術館で個展が開催されているが、日本での紹介は今回が初めてとのこと。つくらずにはおれない、描かずにはおれない。そうした衝動から生み出された鮮やかな作品の数々。独自の美意識と表現から溢れ出るエネルギーに圧倒された。[新川徳彦]


会場風景
2013/09/13(金)(SYNK)
芸劇eyes 番外編・第2弾『God save the Queen』(前半)

会期:2013/09/12~2013/09/16
東京芸術劇場 シアターイースト[東京都]
演劇ジャーナリスト・徳永京子のコーディネートにより選ばれた若手劇団5組が、20分の作品を立て続けに上演する企画。5組の共通点は作・演出が皆女性であること。トリを務めたQのことはartscape誌上ですでにレビューしてきているけれども、これほど粒ぞろいの個性ある女性作家たちが演劇の現場を賑わせているとは思わなかったので正直驚いた。あとひとつ驚いたのは、舞台に置かれた役者の身体をどう動かすか、その点をどの作家もとてもデリケートに取り組んでいたことだ。彼女たちの肩書きは劇作家なのかもしれない。けれども、セリフを発話する身体が舞台上でどう振る舞うべきかを、セリフに身体が単純に従属するのではない仕方で模索している時点で、彼女たちは「劇作家」であると同時に「振付家」でもあった。今回、振付家として彼女たちをとらえることで、演劇の現場がじつは〈ダンスの現場〉になっているのではないか、そのことを確認してみようと思う。
最初の2組、うさぎストライプとタカハ劇団には〈振付〉の点で共通するところがあった。セリフが喚起する物語世界とは直接関係ない動きを、役者たちがひたすら行なうという点だ。うさぎストライプ(『メトロ』)は恋愛における後悔の念を4人の役者が口にする。その最中、役者たちはシンプルなタスクをあれこれ続ける。最後に舞台奥の壁を全身でぜーぜー言いながら押したのは、後悔の思いの高まりを「思い」とは別のレイヤー(ゼーゼー言いながら壁を押す)によって表現することで、セリフ中心主義的な芝居にならないようにしていた。なるほど。でも見ているうちに、これほどセリフと動作が基本的に無関係ならば、朗読劇でいいのではないかと思ってしまった。問題は、セリフを通してテーマを伝えることが作家の主眼である場合、舞台上の身体が基本的に不要な存在になってしまうところにある。すなわち身体をもてあましている。それ故に身体にタスクが課されているのでは、そう見えてしまったのだ。
このことは、タカハ劇団(『クイズ君、最後の2日間』)にもあてはまる。ネットの自殺サイトに「最後」の瞬間まで投稿を続けた「クイズ君」という実在の人物を取り上げ、彼と彼の投稿に反応するネットの住人たちの書き込みをセリフにし、またスクリーンにディスプレイした。テーマはそこに凝縮しているのだが、舞台上では、若い男の子2人が「クイズ君」の言葉を読む一方で、政治・経済のキーワードを口にしながらテニスのラリーに興じたり、数十個のテトリスみたいな形の白い箱をあちこちに移動させたり(最終的には高い塔ができ、その上から青白い花吹雪がドカッと落とされ、自殺の遂行が暗示された)と、「クイズ君の自殺」とは直接関係のない出来事を展開する。自殺をほのめかす男(「クイズ君」)が目の前(ネット画面上)にいながら助けることができない、もどかしく空しい人間関係。これを絶望の絶叫で表現してもしょうがない、ならば、その空しさを掘り下げて見よう。そう考えたのにちがいない。そしてその掘り下げの演出が、身体へのアプローチを引き出したのだろう。物語と直接関係ない身体動作は「空しさ」のメタファーとして機能したかもしれない。けれども、そうである限り、身体動作は「空しさ」を察知させるための手段にしかなっていない。そこがちょっともったいない。ところで、こうも思ってしまった。なぜ舞台上にいるのが、白いシャツ、黒いズボンのかわいい男子2人なのだろう。そこにはテーマに即して読みとるべきメタファーがない。その分、劇作家の無意識的な欲望が垣間見えた気がする。ときに2人はまるでゲームに興じる嵐みたいだ。観客も彼らの挙動に笑みをこぼす。「クイズ君」と「嵐」の両方に足がかかっている舞台というのが、本作のポイントに見えた。
そのことをより自覚的に舞台にしたのが、鳥公園(『蒸発』)だった。シェアハウスで暮らしているのか、姉妹とは思えない若い女2人がおしゃべりをしている。ぼさぼさの髪に度のきつそうなめがねをかけた1人の女は双眼鏡越しに男(ヒロキ)を眺めている。ヒロキは自慰行為に夢中。女はヒロキに目が離せない。ここで描かれているのはただひとつ、女の性だ。リア充の恋愛ではなく、自慰的な一方通行の性。「ヒロキは鶏とセックスしている!」(鶏姦!)と同居人に報告すると、ヒロキの様子に共振して、女は延々と腰を前後に振り続ける。無意識的な自慰の模倣は、執拗に繰り返されると奇妙なダンスに見えてくる。手前勝手で嫌悪感を催すこのダンスは、女性が解放されてゆくプロセスにおいて、ぼくたちの避けることが許されない光景を象徴しているものかも知れない。なにより、女たちの外見の不細工なこと! この不細工さは醜いがリアルな女性の一面を示しているはずで、こんな女性の表象は珍しいと思えば思うほど、既存の演劇がいかに男の眼差しのためにあったのかを証しているようでもある。
2013/09/13(金)(木村覚)
芸劇eyes 番外編・第2弾『God save the Queen』(後半)

会期:2013/09/12~2013/09/16
東京芸術劇場 シアターイースト[東京都]
4組目のワワフラミンゴ(『どこ立ってる』)も、性のテーマにアクセスする。冒頭、ガーリー(?)なルックスの女の子が2人現われ、テーブルを前に坐ると、コンビニで購入してきたエロ漫画(男性向け)を交換したり、並んで読んだりする。ウブな照れなど描かれない。だからといって、ストレートな性欲の表現に向かうのでもない。ワワフラミンゴが狙っているのは、小刻みに発生し続ける女のイライラや自尊心や欲望(等身大で、ちっちゃい人間の心)の姿を描いて示すこと、しかもそれをいいものともわるいものとも即断せずに、結論としてイライラしたり尊大だったり欲望を曝したりしている様を「かわいい」と観客に思わせることではないか。ガーリーなルックスもかわいさも、あくまでも女子向け。男への媚びはみじんもない。その分、デリケートにしつらえられたセリフや動作には独特な浮遊感があって、見ていて(男の筆者でも)「かわいい」とつい笑みが漏れてしまう。着眼点がいいのだ。舞台横の扉から腕だけが見えている。たぬきのかぶり物を着けた女(たぬき)が興味を示す。さっと消えた腕に執着したたぬきは、知り合いの女を連れてきてその腕の形をとらせる。例えばこんなささいなシーンに、この劇団のエッセンスが詰まっている。腕の形への執着に、さしたる意味はない。けれども、それだけに、執着の様子が滑稽に見えるし、また執着する様を描くことで独自の審美感が伝わってくる。あるいはけんかして、追いかけっこが始まる。追う側の脚は素早く回転しているのだが、前への推進力にならず空回りする。「待てー」と言いながらの空回りが、かわいくまた滑稽なのだが、その「空回り」の動作をチョイスする着眼点にはっとさせられる。ダンスらしい動きがあるというよりは、こうしたデリケートな動きや形のチョイスにダンスを感じさせられる。
それにしても、今回の5組の劇団名を見ていると生き物の名を冠したものばかり。うさぎ、鳥、フラミンゴ。タカハ劇団のシンボルには鳩が象られているし、Qの名の由来は確か虫という文字に似ていることだったはずだ。なぜ生き物が劇団名に入るのか? そこに女性らしさを見てもいいのか? 生き物=かわいい? それとも、変身願望? 本企画の上演順は、この点であらためて見ると、ほ乳類から鳥類へ、さらに虫(昆虫?)へと進む格好になっている。しかし、Qが今作でとりあげるのは、昆虫ではなく魚類。寿司屋の娘、その友人とアルバイトの女。友人はスルメをおいしそうに食べる。彼女はエイと人間のハーフなのだという。そう、Qにとっても性は重要なテーマ。ただし、いつものように、Qの性は雑種化することに憧れる。人間の男じゃないものへと向かう性欲は、人間の男を否定する。でもそれだけではなく、そこには女のどん欲さ、変身可能性へのエネルギーが溢れている。といっても、その衝動を容易く制御できるわけではなく、女の体ではいつも予期できないなにかが発現しようとしていて、その様を表現する際に役者の身体はなんとも不思議な動作を繰り出す。独特のくせのある発話もそうなのだけれど、発話に引きずられてなのか、身体動作がぎこちなくつなぎ合わされ、ときにはバレエの動きも取り込まれ、奇っ怪でユニークな動きのフレーズが生まれる。Qはそう思えば、ダンスを創作している劇団なのだ。今回見た5組の劇団は、性をテーマにするところや舞台上の身体を扱う意識の高さなど、重なる点が多く、いまの女性作家たちがなにをどう表現しようとしているのかが、とても明瞭に示されていた。そのなかで、Qの「ダンス」は、際立って見えた。女であること、女の身体とともに生きていること、その不思議や戸惑いやいらだちや希望が「ダンス」にぎゅっと凝縮されているのだ。男たちを置いてけぼりにして、女たちが表現をはじめた。いっそ直視できぬほど赤裸々に、徹底的にやって欲しい。その後で、ミサンドリー(男嫌い)と従来からのミソジニー(女嫌い)が互いに自己主張したその果てに、なにが見えるのかが恐ろしくも楽しみだし、そこまでやらなきゃならない事態に至っているのは間違いないからだ。
2013/09/13(金)(木村覚)
六甲ミーツ・アート 芸術散歩2013
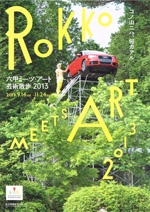
会期:2013/09/14~2013/11/24
六甲ガーデンテラス、自然体感展望台六甲枝垂れ、六甲山カンツリーハウス、六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、六甲山ホテル、六甲ケーブル、六甲ヒルトップギャラリー、オテル・ド・摩耶(サテライト会場)[兵庫県]
今年で4度目の開催となる「六甲ミーツ・アート(以下、RMA)」。そのテーマは、ピクニック感覚で山上に点在する現代美術を鑑賞することにより、六甲山の豊かな自然環境を再認識することだ。回を追うごとに評判が高まり、いまや秋の関西を代表する美術イベントになりつつある。今年は39組の作家が出品し各会場で見応えのある展示を行なったが、なかでも六甲高山植物園と六甲オルゴールミュージアムは質・量ともに充実していた。この2会場は昨年も見応えがあり、もはやRMAの顔といっても差支えないだろう。また、今年からパフォーマンスを中心とした「公演部門」が新設されており(5組が出演)、その成否が注目される。いま数多くあるアート・イベントのなかで、珍しく民間企業(阪神電鉄)が主催するRMA。それでいて無闇に企業色を押し出してこないところも好感が持てる。今後紅葉の時期になれば、一層魅力的なアート&自然体験ができるだろう。
2013/09/13(金)(小吹隆文)
肥やしの底チカラ
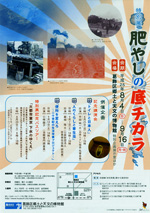
会期:2013/08/04~2013/09/16
葛飾区郷土と天文の博物館[東京都]
文字どおり人糞尿についての展覧会。2004年に同館で催された「肥やしのチカラ」展をグレードアップした内容で、ひじょうに見応えがあった。展示されたのは、このたび新たに発見された綾瀬作業所の資料をはじめ、古文書や写真、器物など。関係者にインタビューしたにもかかわらず、その映像資料が含まれていなかった点が惜しまれるにせよ、それでも緻密な研究成果を反映した良質の展覧会だった。
展示を見て理解できたのは、かつての江戸が極めて合理的な循環型社会だったこと。近郊の農村で生産された野菜を江戸の人びとが消費し、そこから排出された糞尿を農村に運搬し、肥料として活用する。運ぶのは長船で、下げ潮に乗って江戸まで行き、上げ潮に乗って帰ってきた。とりわけネギやレンコン、クワイ、ナスには効果てきめんだったようで、下肥として盛んに利用されていたようだ。水洗式便所がデフォルトになった現在では考えにくいことだが、当時の人糞尿はかなり重宝されていたのである。事実、外国人が使う水洗便所の糞尿は、水で薄められていたため肥料としては価値が低かった。
明治以後の近代化に伴い、こうした循環型社会は次第に影を潜めていく。下水道の整備や、安価で有効な化学肥料の登場、そして衛生概念の普及により、人糞尿を肥料として再利用する発想が制度的に退けられていくのである。とはいえ、鉄道による屎尿輸送は昭和20年代後半まで行なわれていたし、下水道が到達していない地方の農村で、この循環システムがいまも機能していることは言うまでもない。しかも屎尿の海洋投棄にいたっては、東京都の場合、じつは平成9年まで続いていた。現在の都市社会は人糞尿を不浄のものとして不可視の領域に囲い込んでいるが、じつはそれは、部分的とはいえ、現在の社会にもなお通底する合理的なシステムなのだ。
近代という価値観に重心を置いた社会のありようが、いたるところで綻びを見せ始め、それに代わる新たな価値観が模索されているいま、この糞尿を循環させるシステムは、近代的合理性とは異なる、もうひとつの合理性として見直すことができるのではないだろうか。何しろ、それらは1日もやむことなく、果てしなく生産されるのだから、これらを無駄にする手はない。
あまり知られていないことだが、美術評論家の中原佑介は、かつて「科学的糞尿譚 東京の排泄物」(『総合』1957年7月号、pp.174-179)というルポルタージュを書いた。東京の砂町処理場を取材した中原は、当時の東京で1日に排出される糞尿が約45,000千石であり、そのうち30%は下水道、65%は汲み取り、残る5%は自己処理されるというデータを明らかにしている。さらにその65%の汲み取りのうち、下水処理場に回収されるのは30%だけで、残りはすべて農村還元ないしは海中投棄されていたという。中原によれば、ゴルフ場の芝生の育成には、それらを加工した「発酵乾粉」という肥料が使用されていたらしい。
興味深いのは、このルポルタージュの末尾で中原が糞尿と放射能を併せて記述していることだ。当時の原水爆実験を受けてのことだろう、中原は次のような危機を暗示している。「糞尿の処理にまごまごしているうちに、糞尿が放射能をおびるようになるかもしれない」(同、p.179)。中原の予見が半ば現実化してしまっていることを、今日の私たちは知っている。人糞は循環しうるが、放射性物質は蓄積する。資本の蓄積が資本主義を内側から蝕む恐れがあるように、放射性物質の蓄積は人類を内側から滅ぼしかねない。私たちはいま、来るべき社会をどのように想像することができるだろうか。
2013/09/13(金)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)