artscapeレビュー
2016年05月15日号のレビュー/プレビュー
ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞

会期:2016/03/19~2016/06/05
Bunkamura ザ・ミュージアム[東京都]
幕末に一世を風靡した浮世絵師、歌川国貞(1786─1864)と歌川国芳(1797 1861)の展覧会。ウィリアム・ビゲロー(1850-1926)がボストン美術館に寄贈した日本美術コレクションのなかには、国芳が3200枚以上、国貞が9,000枚以上の作品が含まれていたという。ビゲローが来日して日本の美術作品を収集したのは1880年代、国貞没後まもなくのことであった。その後ボストン美術館では日本の版画コレクションを拡大し、いまでは52,000枚以上もの作品を所蔵しているというが、質量ともに国外では最高のコレクションと言ってもよいであろう。本展にはそのなかから170点が出品されている。
国貞と国芳は同門の兄弟弟子。美人画や役者絵で人気を博した兄弟子、国貞に対して、遅咲きの弟弟子、国芳は『水滸伝』や『里見八犬伝』といった歴史怪奇小説の物語絵で世に知られた。国貞の醍醐味のひとつは、女性の着物や髪型、そしてしぐさや表情である。繊細かつ丹念に描かれた着物の模様は注意深く組み合わされ、二つとして同じ着物姿はない。例えば、《縞揃女辨慶》シリーズでは、弁慶縞といわれる大胆な二色の格子柄をまとった女性たちを武蔵坊弁慶の逸話に見立てて描いた10枚の揃いものだが、同じような柄の着物でも帯や小物、髪型や髪飾りをさまざまに組み合わせることで表情豊かに描き分けており、さしずめスタイルブックのようである。一方、国芳は意表をついた大胆な構図とドラマティックな人物の表情が見所だ。荒れ狂う波涛が、巻き上げる風が、あやしく燻る煙が画面いっぱいにうねる空間をつくり出し、その場を舞台に、亡霊や妖怪、鬼の形相の武者たちが所狭しと暴れまわる。豪快で闊達、しかもどこかに陰や毒がある。浮世絵の爛熟期、幕末の陰鬱な世相を写した二人の画に現代の劇画や漫画の原点を見る思いがした。[平光睦子]
2016/04/16(土)(SYNK)
MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事
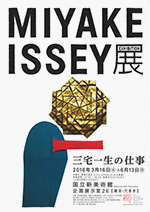
会期:2016/03/16~2016/06/13
国立新美術館[東京都]
ファッションデザイナー、三宅一生の回顧展。会場はA、B、Cの3つのセクションにわかれ、セクションAには1970年代の作品、次のセクションBには1980年代の作品、そしてもっとも広いセクションCには代表作である「PLEATS PLEASE」をはじめ、「A-POC」、「132 5. ISSEY MIYAKE」など独自の方法論をもちいた革新的な作品群が展示された。初期の作品がまったく古びて見えないことに驚き、「一枚の布」というコンセプトが三宅の服づくりにおいていかに一貫した確かなものであったかをあらためて知ることとなった。
三宅一生は「ISSEY MIYAKE SPECTACLE: BODYWORKS」展(1983年)、「ISSEY MIYAKE MAKING THINGS」展(1998年)、「A-POC MAKING: ISSEY MIYAKE &DAI FUJIWARA」展(2001年)など、国内外で充実した展覧会を重ねてきた。また、2007年にはデザインのための美術館、21_21 DESIGN SIGHTを開設し、展覧会のディレクターとしても積極的に活動してきた。ふりかえればその原点は1975年の「現代衣服の源流」展にはすでに認められ、展覧会の実績もかなりのものである。本展では、グラフィックデザイナーの佐藤卓が一部の会場デザインを、デザイナーの吉岡徳仁が「グリッド・ボディ」によるインスタレーションを担当するなど、三宅にゆかりのあるクリエイターたちが結集して、開放的だが緊張感のある、楽しく美しい空間がつくり出された。ファッションにとどまらない、三宅一生の世界の広がりを存分に堪能できる展覧会であった。[平光睦子]
2016/04/16(土)(SYNK)
福岡道雄展「ことばと文字─つくらない彫刻家のその後」

会期:2016/04/01~2016/04/28
ギャラリーほそかわ[大阪府]
「ピンクバルーン」の彫刻シリーズや、黒い立方体の上面に波打つ水面や小舟の彫刻を施した作品群、FRPの板に「何もすることがない」「僕達は本当に怯えなくてもいいのでしょうか」などの一文をびっしりと刻みつけた平面作品で知られる福岡道雄。2005年の個展を最後に「つくらない彫刻家」宣言をしてからは、制作を絶っている。
本展では、制作を絶ってからの福岡が近年書きためた断片的な文章やドローイングが、数十枚展示されている。日々の雑感を書きとめた、日記の一部のような文章。脳内制作のコンセプトを練る、メモ書きのようなもの。小さな「つぶ」として存在する作品の見せ方についてのアイデアスケッチ。「生きろ馬鹿な生きろ馬鹿な……」の反復が、渦巻き状に沿って呪文のように書かれたもの。「何もすることがない」の執拗な反復は、今回のドローイングメモにも現われ、脅迫的な制作衝動をパラドキシカルに露わにする。
それらの大半は、スケッチ帳やメモ帳からちぎり取られ、裏面にも何かが書かれた紙片も多い。今回展示されたものの背後には、日々即興的に書きためられた膨大な紙片が存在するのだろうと思わせる。それらは、実体はなくとも、「作品」や「つくること」の周囲を旋回しながら、作家の思考の連続性と不連続な断片を垣間見せている。慎ましやかながらも、作品と非─作品を峻別する境界、「作家の純粋な思考は作品と等価と言えるのか」という問いを投げかけていた。
2016/04/16(土)(高嶋慈)
青木万樹子展「心を照らす」

会期:2016/04/09~2016/04/23
CAS[大阪府]
バーネット・ニューマンの連作《十字架の道行き》からインスピレーションを受け、20号キャンバスの絵画14枚が並ぶ。ただし時系列順の場面展開はなく、モチーフの色や形が連想的に変奏されながら、始めも終りもない流れの中に浮かんでいるような感覚を受ける。例えば、縦に真っ二つに切ったリンゴの断面の形は、手前に突き出された尻のエロティックな輪郭と呼応する。その曲線は、中国雑技団のようなブリッジのポーズで柔軟性を見せる人体の形象へと引き継がれる。モチーフの多くは、単純な形象ながら、ぼんやりと発光しながら背後の暗闇から浮かび上がるように描かれ、記憶や夢の中のイメージのように淡い光をまとっている。
図式的な見方をすれば、真っ二つにされたリンゴの断面は子宮を思わせ、真正面から描かれた牡鹿の角は男性器の暗喩であり、ベッドに横たわる人の上に浮遊するもつれ合った人体は性的な夢を暗示し、神前結婚式の花婿と花嫁の肖像が、その欲望の帰結として描かれる。しかしそれらは、私たちを脅かす抑圧された夢の昏(くら)さというよりは、暗闇を照らすほの明かりのように、生を祝福し肯定するような、柔らかな光に包まれている。
2016/04/16(土)(高嶋慈)
「マルティン・チャンビ写真展」

会期:2016/04/19~2016/05/16
ペルー大使館 視聴覚室“マチュピチュ”[東京都]
マルティン・チャンビ(1891~1973)は南米・ペルーを代表する写真家。アンデスの先住民の出身で、鉱山技師の下働きをしながら、イギリス人から写真を学び、1918年、クスコ県シクアニ村に写真スタジオを開業する。1920年にクスコに移り、先住民を含むその地の住人たちの、堂々たる威厳を備えたポートレートや、緊密な構図の集合写真を撮影した。マチュピチュ遺跡や建築物の記録写真、スナップショット的な街の写真も多数残している。
リアルな描写に徹してはいるが、どこか「魔術的リアリズム」の伝統に根ざしているようでもある彼の写真は、近年評価が高まってきており、2015年10月~2016年2月にリマ美術館で開催された大回顧展に続いて、2017年にはサンフランシスコ近代美術館(SFMOMA)での個展開催も決まっているという。カーニバル評論家としても知られる、写真家の白根全の企画で開催された今回のペルー大使館での個展は、チャンビの作品の日本での初公開である。30点余りと数は少ないが、ガラス乾板から引き伸ばされたクオリティの高いプリントが展示されていた。
今年になって、ラテンアメリカの写真家たちの写真展が相次いでいる。グアテマラの屋須弘平(あーすぷらざ)、メキシコのグラシエラ・イトゥルビデ(タカ・イシイギャラリー フォトグラフィ/フィルム)、ブラジルの大原治雄(高知県立美術館)と展示が続き、このチャンビ展に続いて2016年7月2日からはメキシコの写真家、マヌエル・アルバレス・ブラボの大規模展が世田谷美術館で開催される。こうなると、ラテンアメリカの写真家に共通する特色を抽出できそうな気もしてくる。先に述べた、リアルさと幻想性が同居する「魔術的リアリズム」も、その重要な一要素となりそうだ。
2016/04/16(土)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)