東浩紀『不過視なものの世界』
 |
東浩紀
『不過視なものの世界』
朝日新聞社、2000 |
|
処女作『存在論的、郵便的』を出版して以降の東浩紀の活躍(及びそれをめぐる毀誉褒貶)に関しては今さら説明の必要もあるまい。デリダ研究者、エヴァンゲリオンの「使徒」、オタク文化の擁護者、サイバースペースの論者、等々……様々な話題を横断するその議論は絶えずメディアの高い関心を集め、また批判の対象ともなってきた。だが、ややもすると極めて拡散しているように見えるその議論が、彼のポストモダンへの関心を核として緩やかな統一を形成している事実は、多くの読者がその立場の如何を問わずに見落としてしまっているのではないだろうか。その意味では、今回の新著『不過視なものの世界』は、ポストモダニスト・
東浩紀(本人はこのようなレッテルを拒否するかもしれないが)へとアクセスする格好の導き手としても貴重な書物である。対談集という書物の性質上、当然のように本書の話題は極めて多岐に渡る。斎藤環と精神分析について語り、村上隆とアニメやスーパーフラット絵画について語り、阿部和重と映画の状況について語るといった具合に、本書で展開されている様々な話題は未整理のまま放置されている印象が強いのは確かで、一見ひどく散漫に思われるかもしれない。だが、少し注意してみれば、例えばミステリーにおける謎解きがサイバースペースにおける暗号の問題へと接続されていたり、スーパーフラットな絵画と最近の映画には共通して誤視覚(ここには、本書のタイトルが「不可視」ならぬ「不過視」である理由も潜んでいる)の問題が指摘されていたりと、様々な話題の間には相互リンクが張り巡らされていることがわかる。ポストモダンの基本的な定義を了承している読者には、まさしくこの概念がリンクの起点に位置していることが強く実感されるであろう。
それにしても、あらためて考えさせられるのは現時点でポストモダンに徹底して拘る東の姿勢である。当然の話だが、昨今の言説状況下でこの立場が主流を占め得るはずはないし、それは当の東が別の場所において、近年の支配的な知的言説を三つの系列――1−東大表象などが牽引する「美学系」/2−浅田彰と柄谷行人の求心力によって形成される「批評系」/3−高橋哲哉や鵜飼哲のような代表的なデリダ研究者らが中枢を占める「政治系」――に分割して整理していることにも端的に現れている。もちろん、この三者は相互に重なり合う部分が大きく、この図式化そのものが強引の謗りを免れないわけだが、しかしそんなことは、三者のいずれにも該当する東本人が誰に指摘されるまでもなく弁えているだろう。単純化して言えば、この強引な図式化は三者のいずれとも異なる「第四の道」を行こうとする東の意志を裏返しに物語っているのであり、ポストモダンとはその選択の別名に他ならない。必然的に孤独を強いられるこの選択の当否が明らかになるのは、しばらく先の話なのかもしれない。
ジョナサン・ビグネル『Post Modern−Media Culture』
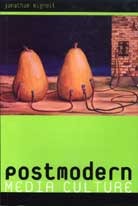 |
| Jonahthan Bignell ,postmodern-media culture, Edinburgh Unive Press, 2000 |
|
ところで、ポストモダンをめぐる議論の停滞は、やはり近年、欧米圏の言説でも広く指摘されてきたことだった。80年代後半にバブル経済の思想的同伴者として振舞ってしまった日本の特異な状況は論外としても、欧米にしたところで、数多の概説書・研究書は基本的な定義――ほぼ同時期に提唱されたチャールズ・ジェンクスのデザイン原理とJ=F・リオタールの「大きな物語の終焉」に、モダンなるものの閉塞状況を突破しようとした新しい思考の雛型を見出し、その起源を68年5月のパリ革命が象徴するマルクス主義の危機感に求める一方で、フレドリック・ジェイムソンやデヴィッド・ハーヴェイらの後期資本主義論と接続し、モダン「以降」の文化的表現の可能性を探る知的言説の試み――の反復に終始していたのである(今にして思えば、80年代後半の日本では、ポストモダンの理解はこの程度の水準にすら達していなかったのだ!)。だが、最近になってようやく、この反復から抜け出して、ポストモダンの現在形を90年代以降の思潮との関連によって問おうとする本格的な研究が現れつつある。その具体例として、ここではジョナサン・ビグネルの『Post Modern−Media Culture』とダナ・ハラウェイの『猿と女とサイボーグ』の二冊を手短に紹介しておきたい。
まず前者だが、これはタイトルから察しがつく通りのメディア論であり、映画,TV,ITなど、いかにも今日的なメディアや消費文化のケース・スタディを展開し,その中にポストモダンの兆候を探ろうとする試みである。もちろん、そうした試み自体類例には事欠かないわけだが、先の基本的な定義を念頭に置いた場合、本書は極めて異質な性格を持っていることに気づかされる。実のところ、本書で話題の中心となっているのはカルチュラル・スタディーズやグローバリゼーションといった極めて90年代的なキーワード/キーパーソンなのであり、その一方で著者は従来の定義にも関心を払い、モダニティ/ポストモダニティ/ポストモダニズム/ポストモダンといった用語の混同を厳しく戒めてもいる。その当否を問うには本欄は狭すぎるのだが、少なくとも本書が90年代的な言説を軸に、袋小路に陥ったポストモダンの再構成を意図した書物であることだけは強調しておかねばなるまい。
ダナ・ハラウェイの『猿と女とサイボーグ』
 |
ダナ・ハラウェイ
『猿と女とサイボーグ』
高橋さきの訳、青土社、2000 |
|
一方で後者は、極めて広い視野から従来型のポストモダンの更新を迫るものだろう。これまたタイトルが象徴的なのだが、猿/女/サイボーグはいずれも西洋近代が確立してきた人間/男性中心主義を脅かしかねない存在であり、霊長類学者でもありフェミニストでもある著者は、まさしく自らの専門的立場から人間/男性中心主義という物語への問いを発しようとする。500ページ以上に及ぶ長大なボリュームの中で、ポストモダンへの言及は決して多いとは言えないが、しかし先の定義に立ち戻り、そのそもそもの意図が近代的な人間概念の更新にあったことを再確認したとき、多くの読者は本書の定義がまぎれもなくポストモダンの圏域に位置していることを理解するはずである。
このように、ポストモダンをめぐる言説の国際的趨勢は、現在確実に地殻変動を迎えつつあるのだが、一方で今年その翻訳出版が大きな反響を呼んだアラン・ソーカルらの『知の欺瞞』に対する(元)ポストモダニストたちの黙殺振りを見てみても、日本ではまだポストモダンの本来的意義は失墜したままだと言わざるを得ないし、その点で東浩紀の孤独はやはり際立っている。80年代の記憶が払拭され、真に現代的な知的言説としてのポストモダンが再検討されるのは、果たしていつのことなのだろうか。
関連文献
東浩紀『存在論的、郵便的』新潮社、1998
東浩紀インタビュー「新たな時代にむかって」――「週刊読書人」2000年11月3日号
東浩紀「ポストモダン再考」――「アステイオン」第54号、TBSブリタニカ、2000
Fredric Jameson "The Cultural Turn-Selected Writings on the Postmodern,1983-1998", Verso, 1998
Perry Anderson "The Origins of Postmodernity" Verso, 1997
Allex Callinicos "Against Postmodernism" Polity Press, 1989
デイヴィッド・ライアン『ポストモダニティ』合庭惇訳、せりか書房、1996
港千尋『自然 まだ見ぬ記憶へ』NTT出版、2000
A・ソーカル/J・プリクモン『知の欺瞞――ポストモダン思想における科学の濫用』田崎晴明他訳、岩波書店、2000