|
|
「シンク・プロダクション」誕生――インターメディウム研究所(IMI) |
| |
デジタルメディア工房 [IM-LAB]
|
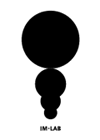
IM-LAB
シンボルマーク
グリコのCI等を手掛けるグラフィックデザイナー、奥村昭夫(IMI「大学院」講座講師)
によるIM-LABシンボルマーク
|
|
大阪にインターメディウム研究所が設立されたのは96年。今年で開設5年めになる。“マルチメディア時代のバウハウスを目指す”という志しのもとにIMI「大学院」講座と銘打って、大学や専門学校などの課程を終えた人々を対象としたアートスクール(教育機関)を運営している。時代に対応したクリエーターの育成につとめてきたわけだ。
5月31日、IMIは新たにデジタルメディア工房「IM-LAB」を千里万博記念公園内に開設することになった。実践の場で活躍できる人材育成をIMI「大学院」講座では主眼にすえてきたが、これまでは研究生の教育ということを第一義に、内に向けての活動だった。この間の蓄積を外に向けて発信する環境が整ったということで、かねてより準備をすすめてきた工房の設立が実現した。
いわゆる芸術系大学の場合、カリキュラムにおいても、思考そのものも文系に偏りがちであるが、 IMI「大学院」講座で学ぶ研究生は、理工系出身者が多いことも特徴だ。アートとサイエンスの間を自由に行き来できる共通言語をもっている。ここから育っていった卒業生のネットワークを通して、コンテンツ制作から発信に至る仕事を受注できる工房をつくったことになる。
アメリカにはdo-tankと呼ばれる工房があるが、ディレクターの伊藤俊治氏はIM-LAB をイメージする言葉として「シンク・プロダクション」という造語をつくり出した。研究・市場調査をし、分析していくシンクタンク的な部分から、実際にかたちのあるものをつくり出していく場=LABをひとつにしたものを目指している。
同じくディレクターをつとめる畑祥雄氏は「IMIのビジョンを視覚化する場が必要であった。集約されるべき工房がなくては、講座のカリキュラムそのものが空洞化する恐れがある。必然性があって生まれた工房です」という。
卒業生がベンチャーを起業する場としても、この工房は活用されていくことになりそうだ。
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|