イリヤ&エミリア・カバコフ夫妻が4度目の来日をすることを知らせるEメイルを受けたのは、その日程の10日間程前のことで、知らせの主は、イリア・カバコフの日本の担当ギャラリーである佐谷周吾ギャラリーであった。最近はこのような形でデジタル情報による報道資料が届くことが増えてきた。もちろん、依然として郵便での配付も行われているが、電話やFAXでの方法は圧倒的に激減して、Eメイルによる情報発着信というのは日常になりつつある。それは、国内外を問わずである。とくに海外だと時差で困ることが多かったが、Eメイルになってからは安眠をとれる生活で快適だ。こちらからの報道資料の請求にも、パソコンに送信されれば確実に迅速に届くので、私はこの方法が気にいってる。それに相手にとってもぎりぎりまで決まってなかったり、いつでも変更や訂正を入れられるEメイルやウェブサイトでアップデートな情報を提供できる。私は国際展(リヨン・ビエンナーレやマニフェスタなど)の情報はこうして手に入れている。「コンビニより便利で近い情報」とウェブ・マガジンの利点を八谷和彦がいっていたが、まったくの正論である。
電話がリンリンと鳴りっぱなしという状況は、昔の仕事の風物詩のように思える時さえある(単純に仕事が激減してるのか!?)。今では、帰宅をするとメイルBoxを確認するのが習慣になった。もっといえば、携帯電話によるメイル交換があたりまえになってきているのだから、ビジネスレベルで活用されていることをわざわざいうまでもないのかもしれない。それにしても、私のような煩雑な仕事場で増えつづける郵便物に翻弄されている身にとって、デジタルで管理できる情報は、便利なツールである。もし、詳細を忘れてしまっても何度も確認ができるし、大したことと思っても簡単に質問ができたりするのもよい。今回のような日程が迫っているような情報にもきちんと対応しやすいといえるだろう。
さて、本題の「カバコフのプレス・コンファレンス」だが、4月19 日6時半より日本外国特派員協会(プレスクラブ)で行われた。私も海外で美術誌の海外特派員という立場で活動した時期があったが(少なくともそういう肩書きで出版社に名詞を作られた憶えがある)、外国人記者クラブなどには所属したことはない。そんな偉そうに!と罵声が聞こえそうだが、こうしたシステムによって外国での活動のサポートや言語や文化の違う記者がある意味で保護されているのは羨ましいなと思ってしまうのだ。かつて、私もブリティッシュ・カウンシルやテイト・ギャラリーなどの大型組織主催のプレス・コンファレンスに自国の記者と肩を並べて出席して、同レベルで取材ができたのは良い経験だったといえる。外国での情報収集は非常に困難であるから、記者発表と言うのは直接的で効果的な方法になるのである。来週はテイトの新館である近代美術館に関する記者発表に出席する予定だ(5月9日ロンドンにて)。
この日本外国特派員協会は、戦後から出発した歴史的なクラブとして評判の高いかなり有名な組織である。最近では、サッチーの学歴詐称疑惑や元力士の八百長発言などでTVに登場する機会が多いが、ノーベル賞受賞者や海外からのVIPなどの記者発表にも活用される文化的な組織である。パンフレットによればジャーナリストや作家などの出版関係者を前提としながらも広く一般の人たちが費用を負担すれば参加できるメンバー制のクラブとなっている。どうやらイギリスでステータスシンボルとしてポピュラーな紳士クラブと同類のものといえそうだ。したがって、国内の政治家や弁護士、学者、経済界の人間などのバッチ軍団が、そのメンバーとして登録しているようだ。日本でも、会員制クラブが結構重宝され活用されているのだと改めて認識することができた。
会場に入るとまさにその場所で、カバコフ夫妻が記者発表用のフリフリのテーブルクロスのついたテーブルに並んで座っていたわけである。当日は、英語による応答のみというのは予想がついたが、カバコフの話が始まる前に食事が用意されたのは欧米式クラブの方式を継承している。イギリス時代に私がメンバー制のクラブ会員になることはなかったが(会員になるためには推薦や収入などさまざまチェックを受けるので、簡単に入会することはできないのである)、会員の友人がいればゲストとして入場することができるのみだ。その意味ではかなり閉鎖的な環境であるが、ひやかしのような野次馬を避けることができる。今回の記者会見も佐谷氏がゲストをまとめる形で仕切っていたため、私のようなフリーのライターも入場(参加費は必要)することができたのである。
好奇心旺盛な私はこういう機会は面白くて仕方がないので、なるべく逃したくないほうである。だから、いってみればひやかし半分なのだが、なかなか機会のなかった外国人記者クラブを覗けることできたことは、充分にその気分を満足させてくれた。カバコフ夫妻はヨーロッパから来日したばかりでかなり疲労していたことやカバコフ自身が風邪を悪化させていたので、夫人が代弁して質疑応答に対処していた。もともと英語が得意でないこともあって夫人が通訳をすることが多いようだが、まるで一心同体の存在であるかのようにカバコフに相談することもなく質問に応えていたのは印象的である。
|
|
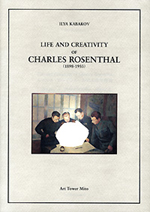 |
|
「シャルル・ローゼンタールの
人生と創造」
水戸芸術館現代美術センター
カタログ表紙 1999年
|
私はこれまでカバコフの展覧会を国内外でみる機会が多かったので、一方的に親しみを感じていたが会うのは初めてだった。67歳になる初老の雰囲気がでてきたアーティストは、ロシア人風の頑強な体格でありながら、人が良さそうで気さくな物腰の人物である。もちろん、熱があって具合が悪いのだから静かにしていたのだが、ソビエト時代はこどもの絵本を描いていたとうだけあって、はにかんだ笑顔が柔和なイメージである。92年にすでにNYに拠点を移したが、市民権を得たのはごく最近である。また、今年はアメリカの美術雑誌で世界でもっとも重要な作家10人に選ばれた。彼のような国際的評価を受けている作家にしては、アメリカ国内の評価にはずいぶん時間がかかったように思う。日本では、1991年に世田谷美術館での「ソビエト現代美術――雪解けからぺレストロイカ」に初出品したのと、軽井沢のセゾン現代美術館「境界線の美術――絵画と彫刻を越えて」に初来日した。その後、97年にヤン・ファーブルとの対談のためと、99年に水戸芸術館現代美術センターで個展「シャルル・ローゼンタールの人生と創造」が開催されたのが本格的な紹介だった。メディアの露出度も高いために、かなり親密な作家と勘違いしていたのかもしれない。
今年は、第1回越後妻有アートトリエンナーレ(7月20日〜9月10日)にパーマネント・コレクションを制作するために来日したのをきっかけに、今回の記者会見が開催されたのである。新潟で開催されるこのトリエンナーレは、6市町村の共同開催で実施される町興しのプログラムである。立川フォンターレを手掛けた北川フラムが総合ディレクターとして世界32カ国140名が参加するという大掛かりなものだ。その多くは、地域に野外彫刻を設置するパブリックアートのプロジェクトで地域のアート化を促進するものである。ただでさえ、現代美術に関心が低い状況にある地方において、このイヴェントが打ち上げ花火的なアートの祭典であることは想像できるが、地域住民を無視したオーガナイズでは長続きはしないだろうという厳しい眼差しがあるのも事実だ。
それは、住民と芸術組織団体のあいだに生じている世界共通の問題であるといえるだろう。ドイツのミュンスター彫刻プロジェクトは美術界では高い評価を受けているが、地域住民にはなかなか受入れられてこなかった。しかし、地域住民との対話を重視したカスパー・ケーニッヒが、10年に1度という急がない組織運営を慎重に行っているため、地域住民にも巧く認められつつある。10年に1度というスパンでは、初めて体験する住民も多くなるし、組織運営事体も毎回最初から作り直すことになるだろう。だから新鮮な活動ができるということになるが、運営組織の蓄積という点では難しいかもしれない。前回の97年の開催では、カバコフも参加している。その時は、公園内に設置するアンテナを模した作品をデザインしたパーマネントのパブリック・アートだった。この作品の制作費を確保するために、大掛かりなアドバタイジング・キャンペーンを実施して住民から寄付を募った。そういえば、カタログを入れる紙袋はカバコフによるプレゼンテーション用の作品のドローイングが描かれていた。今回の越後妻有アートトリエンナーレでは、そのような住民との接点という活動はアーティストの口からは聞けなかったが、企画書では「アーティストと地域住民との協働による場所に根ざした作品づくり」を唱っている。一過性の大型イヴェントを巨額を投じて実施してしまう日本の芸術運営の方法には、建て前と本音というものに隙間が見え隠れてしまうことが多々あるので、果たして今回も疑心暗鬼になってしまうのだが、それについてはカバコフの知るところではないのかもしれない。
|