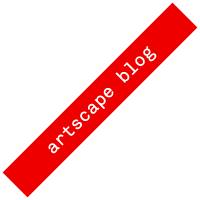第一回目は美術手帖をはじめ、多くの美術誌、またファッション誌などでNYからアートに関する執筆をされているアートジャーナリストの藤森愛実さんにインタビューさせていただきました。
下記に、インタビューの要旨をかいつまんでテキストに起こしてあります。インタビュー全体はこちらから音声ファイルでお聴きください。(約30分)

まずは、先週マイアミのアートフェアに行ってらっしゃったということで、感想をお聞かせください。
私自身、訪れるのは今回で8、9回目。マイアミがすばらしいのは多くの個人コレクター達が、彼らのコレクションを見せてくれること。ただ、少し考えさせられたことがあって、著名コレクターのデラクルス夫妻が美術館を2年前にオープンしたのだが、メディアが作品や、展覧会についてではなく、パーティには誰が来たとか、セレブのことばかり書いてとても落胆しているそうで、来年からフェア期間には閉めることまで考えていると。ジャーナリストとして自分自身もいろいろ考えさせられた。
フェア自体は盛況でしたか?
はい。ハイエンドのコレクターは不景気とは関係ないところで動いているようで、大御所のギャラリーは初日で売り切れたりとかなり戻ってきているよう。また、サテライトフェアのNADAには日本から三軒ギャラリーが出ていたが、こちらも活気があってよく売れているようで、よかった。
あらためて現在、どのようなお仕事をされているかお聞かせください。
フリーランスで、様々な美術誌、女性誌、ファッション誌などにアートの執筆をしている。定期的には美術手帖にNYやNY近郊の展覧会のレビューを書いているのと、世界のホットトピックという1ページのコーナーで世界のアートビジネスの動きを日本人に分り易いように紹介している。これは自分でもとても面白くて、以前はNYにいると世界のアートの動きがだいたいわかったと思っていたが、今はアジア、南米などなどとてもグローバルに広がっており、リサーチが必要で、とてもやりがいを感じている。
どのような経緯でNYにいらっしゃったんですか?
大学ではスペイン語を勉強していた。大学4年のときに、政府の交換留学でメキシコに留学する機会があった。当時ラテンアメリカ文学研究の中心はNYで、漠然としたあこがれがあった。大学卒業後は日本航空のスチュワーデスをやっていて、世界中に仕事で行った中、NYにとても魅力を感じ、またラテンアメリカ文学というよりはアートに興味が転換していった。
80年代当時はソーホーにどんどんギャラリーができていて、ギャラリストに憧れていた。ある日ギャラリーの受付の人にどうすればあなたのような仕事につけるのかと聞いたところ、まずは美術史を勉強しなければと教えてくれた。それがきっかけで準備をはじめ、30代を過ぎていて英語も大変だったが、NY市立大学のハンターカレッジで美術史を勉強するにいたった。
米国の大学で、アート関係の勉強をしている学生は、ギャラリーでインターンをすることが普通なのだが、自分も先生にすすめられてある現代美術のギャラリーでインターンをはじめた。ラッキーなことに、当時はアートブームで、日本もバブルにのってかなりアートを買っている時期だった。それで、そのギャラリーでもどんどん幅広い仕事に関わることができた。仕事自体も大学での学業とそれほど変わらず、作家についてリサーチをしたり、資料をつくったりというものだった。
日本の作家を扱っていたんですか?
いいえ、アメリカの現代作家と、アメリカ20世紀の作家を扱っていた。その作家の展覧会を日本に持っていったり、日本語のカタログをつくったりというのが仕事だった。
それは80年代ですよね。
はい。80年代終わりから90年代はじめのこと。
ただ、バブルがはじけて、ニューヨークでもギャラリーを閉じたり、縮小したりということになっていった。ちょうどその頃アーティストで美術手帖にも書いてらした杉浦邦恵さんにご紹介いただいて、自分も美術手帖に書くようになった。また、ニューヨークローカルの日本語の新聞にも書くようになった。
日本人が米国で仕事をするにあたって、色々とビザが面倒だと思うのですが、藤森さんの場合はいかがでしたか?
前述のインターンをやっているときに、当然学生ビザだったのだが、学生ビザだと給料を払えないから通常のワーキングビザを申請してみないかとギャラリーのディレクターに言ってもらえた。ただ、実際に弁護士と話してみると、かなり時間がかかることがわかり、通常通り卒業して、トレーニングビザを経てワーキングビザの申請にしようと考えた。ある日弁護士から電話があって、抽選でグリーンカードが支給される制度があるから申し込んでみないかと言われ、申し込んだところ、ラッキーなことに、当選していきなりグリーンカードがもらえることになり、通常のプロセスの苦労はあまりなかった。中国系、韓国系が親戚伝いに移民してくる人が多いのに対し、当時、アジアでは日本かシンガポールからの移民のグリーンカード抽選の倍率が有利だったと言われた。なんにせよ色々やってみることは大事。
お仕事のどういうところがプロフェッショナリティーか?
とにかく見ること。自分の尊敬する先輩ジャーナリスト達も見ている量がすごい。本当に小さなギャラリーでも芳名帳で彼らの名前を見てとても励みになる。レセプションだけでなく、通常の日にも行って他の観客がどう見ているかも見るようにしている。書くときは3回展覧会を見るようにしている。1回目に書くかどうか決めて、もう一度しっかり見に行って、最後の確認にもう一回みるようにしているのだが、著名批評家のロベルタ・スミス(NY Times)やジェリー・ソルツ(NY Magazine)なんかは十何回見て、何度も電話で質問をすると聞いてとても驚いた。今アジアソサイエティでやっている奈良美智展で、ロベルタ・スミスが朝から何時間も見ていたそう。
NY以外の展覧会にも行かれますか?
フィラデルフィアなどの近郊は行く。ただ、交通費も自分持ちで、バカにならない。
ここ10年のアートマーケットの成長で、成功したアーティストやディーラーはお金持ちになって、ジェットセッターになったけれど、ジャーナリストとキュレーターはそういうわけではない現状をどう思われますか?
その状況を反映して、大きな美術館や国際展などではプレスの旅費を向こうが負担してよんでくれることもある。だからといっておもねる必要はなく批判的なレビューを書くこともある。主催者側としてはとにかくプレスに見てほしいということ。
そのようなケースは増えているのか?
景気にかなり左右されるもので、2000年代前半からリーマンショックまではかなり多くて、米国国内はおろか、アイスランド、オーストラリア、台湾などかなりあった。あとはプレスを呼ぶだけではなく、半年ほど前に主催者がニューヨークに来て、プレスプレビューをやることも多かった。そこで実際にキュレーターと話ができることは大きな違いだった。どちらもリーマンショック後はかなり減った。
日本でのアートジャーナリズムとニューヨークのもので何か違いはありますか?
私は日本でジャーナリストをやったことは無いので、書かれたものからしか判断できないが、ニューヨークでは同じ展覧会についても媒体によってかなり切り口が違うことが多い。日本の以前の新聞などの文化欄だと各紙あまり大きく違わない内容になっていることが多かったが、最近はそうでもなくなってきているかもしれない。
また、ニューヨークにはギャラリーや美術館が数多くあること、またそれに対してカバーする媒体も多いことで、複合的に見ることができるかもしれない。あるギャラリーの展覧会が、別のギャラリーの展覧会と関連していることがあったり、アートだけではなく、ファッション、写真、劇場、テレビなど幅広く関わり合っている感じもニューヨークならではかもしれない。
日本にいたら同じ仕事をしていたと思いますか?
やはりニューヨークにいるからこそこの仕事をやっていると思う。
ありがとうございます。
実際のインタビューの音声録音(約30分)はこちらからお聴きください。
プロフィール
藤森愛実
Manami Fujimori
北海道函館市生まれ。航空会社勤務を経て、1985年渡米。ニューヨーク市大ハンター・カレッジで美術史を学ぶ。好奇心と美への憧れ(ダ・ヴィンチの二大特質)を胸に、ベストなアートを見て回る毎日。現在、『美術手帖』の海外ニュースを担当。