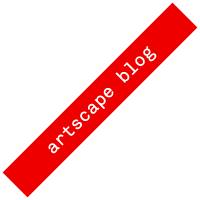今回は板橋区立美術館の学芸員をされている弘中智子さんです。これまで「池袋モンパルナスの作家たち」(2007年)「新人画会」(2008年)「日本のシュルレアリスム」(2009年)など、専門である日本の近代美術に焦点を絞った企画を担当されています。
ぼくは2010年に行われた館蔵品展『日本の美術運動』の仕事ではじめてご一緒させていただき、2010年1月まで同館で開催されていた『福沢一郎絵画研究所展』の広報物のデザインは2回目のお仕事になりました。今回のインタビューでは『福沢一郎絵画研究所展』をきっかけに、展覧会が作られるプロセス、作家と作品の関係、残された作品をどのようにとらえるべきかといったお話などを中心にお話しいただきました。
『福沢一郎絵画研究所展』について
加藤 今回の『福沢一郎絵画研究所展』は画家として著名な福沢一郎だけでなく、彼の絵画研究所に集まっていた人たちの作品も含めた展示でした。その展示の性格上、作品が日本各所に散っていて、しかも美術館に収蔵されているものだけではなく、個人蔵でご遺族の方もどこにしまっておいたか分からない(笑)、みたいな状況だったそうですね。弘中さんが各地を行脚してひとつひとつ作品を集めて歩く話がとても面白かった。たぶんいろいろなエピソードもあったと思います。
弘中 福沢一郎絵画研究所は日本でのシュルレアリスムが広がるひとつの温床だったのですが、一般的な認識では福沢研究における一番の謎とも言われていました。今回の企画をスタートするときにはまだ私のビジョンが明確ではなく、誰が研究所に通っていたかもよくわからなかったし、それを探し当てる自信もなかった。当時研究所に在籍されていた作家の雑誌記事や著書にあたったり、唯一ご存命の作家やご遺族の方、さまざまな美術団体に聞き込みをしました。ほとんど探偵のような仕事です。そうやって地味に痕跡をたどっていたんですよ。
ご遺族の方は快く受け入れてくれました。福沢一郎さんはまめに人を集めたり手紙のやりとりをしていたようで、写真や年賀状がしっかり残っていてそこから作家の存在や住所が確認できたりしました。福沢一郎や作家の死後もその娘さんからまだ年賀状が来ていたり、まだ交流は続いているようですね。
加藤 年賀状って昔は今で言うソーシャルメディアだったのかもしれませんね。
弘中 そうなんですよ。昔の人はね。福沢家にはご存命の頃からまとめていた年賀状や手紙をもとにした帳簿が残っているんです。メールと違ってちゃんと物として残ってるのは大切ですよね。そうやって福沢一郎のネットワークが今もまだ生きている。
今回、作品をお借りした場所で、一番遠かったのは徳島ですね。あとは名古屋、浜松、あとは福沢一郎の出身地の群馬。美術館に収蔵されているものは少なくてそれぞれのご自宅で保存されていた作品がかなりありました。
加藤 あらかじめ作品の当たりをつけていくのか、それともとりあえずご遺族に会いにいくんですか?
弘中 最初の調査の段階では、とりあえずご自宅にお邪魔して「作品はありますか?」とお尋ねすることから始めました。名古屋のある作家のご遺族は倉庫や天袋などの物を動かさないと見つけられないというお話でしたので、私の他にお手伝いの方を引き連れて出向きました。まさに引っ越し作業のようでしたよ(笑)。もちろん作家は亡くなられていて、娘さんと息子さんしかおらず、それぞれが「子どもの時に食パンから手が生えてる絵を見た覚えがある…」とかわずかな記憶をたどっていくんですよ。天袋からその作品が発見された瞬間はみんなで大喜びしました。本当に家族一緒にみんなで探してもらった感じです。探し物をしてたら従軍した時の手帳だとかいろいろ思いがけない物が出て来て面白かったですよ。
この研究所に通った画家たちの遺品を拝見していて、共通しているのは、福沢さんからの手紙だけは大事に取ってある。その後も福沢さんの退院祝いやお年始の会で研究生が集まっていました。先生と生徒の関係が卒業しても60年ずっと続くことはなかなかないですよね。福沢さんは彼らのことを気にかけてただろうし、彼らも福沢さんを師匠として敬って人間同士付き合っていたことが良くわかりました。絵を習うこと以上に絵描きとして生きていくとは何かということが重要だったんだと思います。
加藤 もはや一家の歴史を掘り返す作業のようになっていますね。

『福沢一郎絵画研究所展』会場風景 2011年
面としてみえてくるもの/絵画が残るということ
加藤 今回、あらためて展覧会を見て福沢一郎の絵はなんだか「リッチ」だなと思ったんですよ。
弘中 絵の具はすごく良いものを使っているようです。戦前にフランスで描かれたシュルレアリスム風の絵画は、修復家の方に伺うと、良い絵の具を使ってしかも正しい油絵の扱い方で描いてるから、あまり劣化はしてないそうなんです。やはり経済的なこともあると思いますし、技術をきっちり西洋で勉強してきたっていうことが大きいと思います。あともうひとつあるとすれば、福沢さんは最初から絵描きになりたかったわけではなく、最初は彫刻家を目指していたそうなんです。だから普通の絵描きよりは立体的な表現だったりとか、ちょっと切り口が違うんですよね。
加藤 なるほど。一方で、良くも悪くも福沢さん以外の方の絵は総じて何かしら「貧しさ」みたいなものがある。そんな印象を受けました。でも、そのことが面白かったんですよ。福沢さん以上に時代を映しているように感じました。そういうことは一点一点別々に観ただけではやはりわからないなと思いました。
弘中 福沢絵画研究所に通われていた多くの人は青春時代が一番戦争が激しい時期で、物資が非常に乏しかったんでしょうね。一方、福沢さんは20代をパリで過ごし、海外の文化状況を直接見ている。もともと東大文学部の学生で思想的な形成期もあり、総体としての厚みもある。だから彼の絵は「綺麗だな」で終わる感じではないんです。
加藤 絵を残す方法としては美術館に収蔵するという方法がありますよね。「価値があるもの」として保管される一方、今回のようにかろうじて納屋の中に残っているようなものもあれば、最悪捨てられてしまうような絵もある。作家個人としてきちんと評価されていたら残りやすい。今回のように一点一点での価値を見いだすのは難しいけれど、それらを集めてひとつのボリュームとして見せると面白くなるようなものも当然あるわけですよね。
弘中 そうなんです。今回はまだご遺族が作品やご家族である作家のことをいろいろお話いただけたので随分助かりましたが、10年後だったらこの展覧会は実現しなかったかもしれないですね。
加藤 絵画が残るっていうのはどういうことなんでしょうかね。いろいろ考えさせられるな。
弘中 そうですね。あらゆるものを分別をつけずに美術館に収蔵してしまうのはやはり難しい。でも例えばそれぞれの地域の美術館ができるだけフォローしたり、ご遺族の方が私設の美術館を建てたり、絵が好きな人がそれぞれの基準で収集することもできると思います。
その意味では、今回展示した何人かの作家さんとその地域の美術館を繋ぐことができたんです。それは本展の一つの成果ですね。
今回展示した作品は時代を限定しているので、その画家の1番の見せ所ではない時代かもしれない。でもどの作品もある一時期の面白い作品としてできるだけ多くの方に見てもらったんです。個人のお宅にあると、ご家庭の事情で作品が失われることもありますから。展示すればたくさんの人に知ってもらうきっかけにもなる。
加藤 それは面白い展開ですね。すでに価値が認められている絵画をあらたに組み直して提示することもあれば、今回のように調査の上で掘り起こし、新たに価値を見いだしていくような作業も重要ですね。
弘中 私は展覧会を作る時に切り口をすごく意識しています。単に「福沢一郎はすごいぞ」みたいな見せ方はしたくない。福沢一郎だけでもいろいろな側面があり、さらにそこに他の作家達の作品を集めることによって、さらなる問題意識が生まれる。この展覧会で福沢の元の集まった作家に興味を持った人がいれば、何でわざわざ東京にやってきてこの人の所に行くんだろうとか、そのように多角的に観ることができる展覧会を作れたら成功だと思っています。
今回面白かったのは、絵を描いて暮らしていた人がいる一方で、美術を教える先生になったり先生を指導する教育学部の先生になった人がいたんですが、いろいろな立場の人がいることが面白い。画家と、絵画教育その2つを両方ともやっていたのが福沢一郎だったということもどこかで見てもらえれば良いと思っています。
福沢一郎に限らず日本の近代の作家は西洋の画家に比べると認知度が低いので、これから少しずつ普及させたいという目標が私の中にあります。ゴッホとかピカソの絵も楽しいしとても刺激になるけれども、それらをふまえた上で日本の画家は一体何を成してきたのか、日本の社会状況の変化の上に今の日本や美術があるということを是非若い人に見てもらいたいです。
他のエピソードとしては、会期中に満州に旅行中の福沢さんと会ったことがあるという今年100歳を迎える人が来館されました。その人は当時の満州で満州鉄道に勤めながら絵を描いていたそうです。その人はそこで福沢さんに絵を指導してもらったそうです。そんな思い出を大切にしていた。今回のような展覧会は思わぬところでの再会が多いですね。
あと出品作家中唯一ご存命な方がいましたが、展覧会会期中に亡くなられたんです。私がカタログの中でインタビューをしていたので大切な証言になりました。
加藤 すごいですね。今回のように調査をしたり作品を発掘するプロセスなどの展覧会を作る前の段階もあり、その後にもたくさんのコンテンツがある。是非そういったこともまとめられたら面白いと思います。
亡くなった作家の作品を扱うということ
加藤 福沢一郎絵画研究所は最終的に戦争の雰囲気の中で霧散してしまう。あの戦争ぐらいのインパクトがあった直後と、現在のようにそれがある程度相対化された時代に語れることの幅はかなり変わってきますよね。物事を理解したり判断するにはある程度時間がかかる。終わった後に何らかの判断はできると思いますが、そのできごとの最中に人は何かを考えたり判断したりすることが本当に可能なのかと。あの戦争のことを考えるとそういう不安もありますよね。
そういう意味で今は戦争と美術の関係を提示するのがやっとできるようになった時代だと思います。
弘中 そうですね。一面的には捉えられないので、美術史だけではなく社会状況も把握しなきゃいけない。やることはいっぱいありますね。でもいろいろな時代の状況を知ることによって、今を生きる自分達はいろいろな情報を見たり聞いたりすることは必要だけれども、情報に操作されずいかに自分の意見を持ちそれを貫くかということはとても大切だと思いますね。
加藤 やっぱり亡くなった人の作品を扱うのと、生きている人の作品を扱うのは全然違いますよね。弘中さんは普段亡くなっている作家を扱うことが多いですか?
弘中 私は日本近代美術が専門なので、すでに亡くなっている作家を扱うことが多いです。作家が亡くなられていると作家との付き合いがないので、作品だけを純粋に観ることができるという利点がありますね。でも福沢一郎さんには会ったら面白いだろうな、いろいろお尋ねしてみたいな、とは思いますけどね。今回の展覧会ポスターの大胆なトリミングを見てどう思うかなぁとか(笑)。研究所とかの様子をしっかり聞き出せたとは思いますけどね。
反対に作品を語る上でその作家のキャラクターが邪魔をするということは少なからずあると思います。人間的にすばらしい人に辛辣に発言するのは難しいかったりしますし、性格悪いけどすばらしい作品を作ってる人とかもいるかもしれませんね(笑)。
とはいえ、作品と作家っていうものがはたして同一のものなのかという問題もあります。また、パフォーマンスをする人と絵を描く人でもそのとらえかたは違うでしょうね。
作家が亡くなることよりも作品の行方の方が心配かもしれないですね。まとめて売りに出されるか、燃やされるか、どこかに一括寄贈になるのか。その作家さんがちょっと有名な作家さんだとご遺族は遺産相続がすごく大変みたいですね。
加藤 ところで、例えば美術館に所蔵してある作品がまた別の場所に所蔵し直されるということはあるんですか?
弘中 一度収蔵されたら動かないですね。海外で特に私立の施設では別のところに売却されたりするらしいですが。日本の公立美術館の場合はないですね。
加藤 トレードみたいなこともないんですか? 例えばこの絵10枚とそちらの1枚取り替えてもらえませんかみたいな(笑)。
弘中 ないですよ!できたら嬉しいですけどね。でも作品の貸し借りは公立の美術館同士であれば仲間同士なので容易にできます。所蔵作品は美術館の顔でもあるのでお貸出するのもうれしいですね。でも、所蔵作品も額縁の趣味が悪いものとかたまにあるんです。すごくシンプルな絵に驚くほどごてごてした額が付いていたり、それが画廊を経由したときに付けられた額だとわかっていたら替えたりします。調査してその額縁が作家自身が付けたものだとわかっていればそれは絶対に変更しない。こういう額が好きな作家でしたとエピソードとしてお伝えする(笑)。
加藤 そういうのも痕跡のひとつですね。今日はどうもありがとうございました。