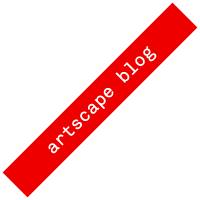先日、あるシンポジウムに参加する機会があって、そこでの「公共財」という用語の使われ方が気になっていました。特に、あのシンポジウムで使われていた日本語の「公共財」という用語を、僕は英語としてどう理解すべきかというようなことを考えていました。僕の頭に直観的に浮かんだのは、’Public Domain’と’Commons’の二つの英語です。
僕がこの言葉に何となく引っかかっているのは、「文化は公共財である。」という言い回しが頻繁に会場を飛び交っていたからです。「『文化』は同時代の社会を生きる人々がおしなべて共有すべき財産である。」という含意なのであれば、それは全くもって正しいだろうと。例えば、文化を基底から支える言語が私有財産として所有可能であると考えるのはというのはあまりに馬鹿げています。ただし、演劇が公共財である、映画が公共財である、芸術が公共財であるというときそれは自明なことでしょうか?逆に、芸術が特権階級によって独占されていたとき、それは私有されていたのでしょうか?さらに、その時芸術は公共財ではなかったのでしょうか?
実はこの論点に関して二点触れておきたいことがあるのです。その一つは、ある文化財がある個人に占有されているという状態そのものは必ずしも「公共財ではない」とは言えないということです。社会学の領域で公共性を論ずるとすれば誰もが言及することになるのが、ドイツの社会思想家ユルゲン・ハーバーマスの『公共性の構造転換』です。ここでは合意形成に至る透明な言説のアリーナとして公共性(実際は、彼の公共性は空間概念であり「公共圏」という訳語が正しいのですが)は理念型化されていますが、この公共性を支えていたのは近代に新たに勃興する社会階層である市民です。ところが、実はこの市民の必要条件こそが、「彼」が可処分財産を持っていること。つまり、財産を私有していることだったのです。ゆえに、ある側面では「公共的ではない(と日常的な語感では理解される)」財産の私有こそが公共性を支えていたとも言えるはずです
また、このハーバーマスの初期の公共性概念は必ずしも社会の構成員全てに対しては開かれていませんでした。確かに、公共性は言説のアリーナにおける透明な合意形成へのプロセスを通じて担保されます。ただし、その議論の場に参加できる可処分財産を持つ市民とは一部の富裕層だったのであり、さらに言えば、当時の市民の合意形成を促進する場であったコーヒーハウスは男性の社交の場であり、子供や女性の存在は軽視されていました。つまり、公共圏もまた富裕成人男性という特定の社会階層が私有する社会空間だと考えることも可能だったわけです(誤解を恐れずに言えば)。
つまり何を言いたいのかというと、プライベートな所有の保証自体が公共性の基盤なのであり、逆に公共性もまたある集団の私有する社会圏域だとも言えるわけです。ここでは、例えば公設民営の文化施設などという際の「公私」の二項対立は機能せず、むしろお互いの概念がお互いを支えるという意味では不可分な概念です。僕は、この認識をスタートにアートにおける公共性の概念を考えてみたいと思っています。