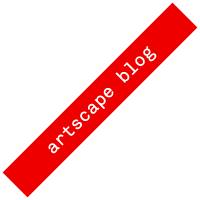前回のhanareの件に引き続いて、今日は狩野さんのフォトログについて少し考えていたことを。狩野さんは実は初めましてではないのですが、こちらでは初めまして。
狩野さんのブログは「路傍」をテーマにした組写真として解釈できます。この一連の画像を何気なく見ながら、二つのことが頭を過ぎっていました。一つは、この一枚一枚の写真に収められた路傍の風景は誰もが訪れることのできる「公共」空間であること。しかし一方で、この路傍には人が決定的に不在であることです。
以前言及したハーバーマスの「公共圏論」を少しでも聞きかじった方であれば、失われた理念型のとしての「公共性」が担保されてきたのは、市民の間での透明な討議のプロセスであり、それは「コーヒーハウス」という具体的な場を通じて維持されていたことをご存知かと思います。もちろん、この「公共性」自体がヨーロッパ由来の概念ですから、それをナイーブに日本へと援用することにはあまり意味がありません。ただ一方で、日本における路傍とはまさに、人々が長年に渡って議論をする場だったのではないでしょうか?長屋の軒下、団地の踊り場、極めつけは「井戸端会議」という言い回しそのもの。これらは長い間、人々が日々の生活を送るなかで互いの情報を交換し、意見をぶつけ合う場でした。もちろん井戸端会議などには、暇な主婦が集まってくだらない話をしているというイメージが与えられることもありますが、まさにこのような井戸端会議こそ、保育所の問題や扶養控除の問題などについての愚痴や不満という形で、福祉国家の綻びが顕在化する場だったのであり、少なくとも井戸端会議に参加する主婦の間では誰でも発言が原則としては確保された小さな議論の場だったわけです。その意味では、日本の場合は飲み屋や床屋が男性の日常的な議論の場として機能してきたのかもしれませんが、女性の持つ「公共」的なる場として、路傍は機能してきたと考えることはできるはずです(但し、それでも井戸端や踊り場はジェンダー化された劣位の空間としての限界を背負うという批判は甘んじてお受けします)。
ただ、狩野さんの作品が示唆的なのはこの路傍には人が不在だということです。恐らく、時の経過に伴う変化はあるにしても、この路傍は路傍として何十年も誰もが訪れる場であり続けたはずです。でも、一方でその痕跡を留めるのはプランターの植物や石ころでしかない。もちろん、狩野さんの意図として人間不在のカットを掲載しているにしても、この写真は路傍における人間の不在の「不気味さ(uncanniness)」を喚起しています。それは、日常的な意味でコミュニティの不在を、もしくはこの場を生きる人々の間でのコミュニケーションの不在を暗示してしまうのです。あまりにナイーヴな発言に響くとしても、「公共」は人が担保するものであって、現在の「公共」の抱える問題は、制度の劣化などではなくその前提となる「人」の不在に起因するのではという連想を促します。その意味では、狩野氏のこの一連のプロジェクトもまた、公共を巡る一つの側面として読んでもいいのかもしれません。
僕はこの業界を生き抜く研究者の戦略として、自覚的に作品論へと踏み込まないことを重視してきました。このような形で禁を破るきっかけを与えてくれた、編集部と狩野さんの作品に一言お礼を述べておこうと思います(苦笑)。