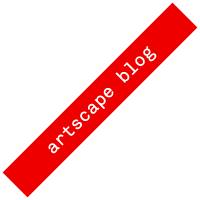現在の職場で仕事を始めてから、数多くの芸術文化に関わるレクチャーや情報を伺う機会に恵まれています。その中で、もともと僕個人のアイデアレベルで考えていたことがニョキニョキと頭をもたげ始めています。今回に関しては、直観レベルでしか考えたことがないので、研究者としてではなく光岡一個人として悩んでいることとして読んで頂ければと思っています。
当たり前のことだと思うのですが、アーティストは専門職だと思います。何らかのメッセージを他者へと発信するという技術において抜きんでた職業であると。それは、医者や弁護士ともある側面では似ています。つまり、ある分野に造詣が深く、特定の技能を持った専門職であるという点においてです。そしてもう一つの当たり前のことですが、一般に専門職は国家がその技術を保証し、社会に最適な規模をコントロールしています。でも、専門職としてのアーティストには、その資格の認定というプロセスが存在しません。僕自身、この議論が乱暴なのは認めます。ただ、一方で言えるのは、例えば弁護士や医者の場合は、国が専門職の数をコントロールしているからこそ、現状日本では医者が足りないとか弁護士が余り始めたという適正規模の議論が成立するわけです。つまり、国家の専門職のコントロールは一つの指針としては有効であると。
ところが、アーティストの場合には専門職であるにも関わらず、基本的にはその適正人数は国家がコントロールをしていない。結果として、研究者としてきちっとデータを踏まえて議論している方は別ですが、そもそもなぜ芸術支援が必要なのかの理由が良く分からないことが多い。つまり、あなたは芸術生産に関わる人々を支援するシステムが必要だと思っているかもしれないが、実は既に日本にはアーティストの数もアーティスト希望者の数も十分に足りていると。むしろ、一時的な芸術支援はさらなる希望者を生み、結果的にはキャリアパスを狭めてしまうと。つまり、これ以上いくら芸術文化の支援を行ったとしても、その出口──アーティスト、もしくはアートをサポートするプロフェッショナルとして──が存在しないかもしれないということです。
これは単にアート業界の需給関係のバランスを保つべきではないかという現状維持だけを意図しているわけではないのです。もちろんこれも論文であればもう少し繊細な論を立てる必要があるけれども、適正規模を超えた芸術支援はまず、アーティストやアーティストをサポートする仕事を目指す人を増加させます。その中には、自分の将来を迷っている‐例えば就職活動に苦戦する‐若者もいるわけです。彼女/彼らの中には、自分の好きな仕事ができないのであれば、多少雇用が不安定で収入が低くても好きなことをやろうと、アート業界に参入することを考える人々も出てくるでしょう。実は、アートマネージメントが叫ばれた始めた時期は、結果的には僕らロストジェネレーションの就職氷河期とも重なっています。つまり、何が言いたいのかというと、国家が芸術文化を国家社会主義的に管理するべきだと言っているのではないのです。むしろ、少なくとも国家や地方政府といった公共団体は、ある規模の社会に対して適正な芸術に携わる人々の規模を提示することが有効だろうと指摘しているのです。誤解を避けるために付け加えれば、それは国家から各地方公共団体まで人口比で一律にしろなどと言っているのではなくて、それぞれの政策目標に応じて適正な規模の枠組みを提示して欲しいのです。基準が示されて初めて、賛否の意見を建設的に交わすことが可能になるはずです。この芸術従事者の適正規模の議論なしに芸術支援を行うのは、若年層の就業率という観点からしても懸念があるという可能性を提示しているのです。芸術とは魅力的であるからこそ、社会の不安定要素にもなり得るはずです。
最後に私事ですが、拙稿「なぜミュージアムでメディア研究か?──ロジャー・シルバーストーンのミュージアム論とその射程」が、日本マス・コミュニケーション学会の第四回優秀論文賞を受賞しました。社会学というよりは、よりメディア研究者としての視点が前景化した論文ですが、ご興味ある方は図書館、アマゾン等で手にとってみてください。『マス・コミュニケーション研究』第76号に所収です。