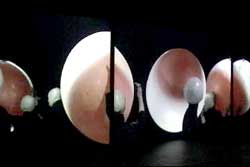1
新世紀を迎えて最初のビエンナーレが、この6月にヴェネツィアで開幕した。2年に1度を意味するビエンナーレと題された国際展が、ヴェネツィアで開かれるようになってからすでに百年以上が経過する。その間に、時代は19世紀末から20世紀を経過し、21世紀の初めにまで辿りついた。激動の20世紀を生き延びたビエンナーレは、その時々の社会情勢を直接的にではなくても間接的に反映してきた。その受け皿となった展覧会形式が、国家単位で設置された空間に作品を展示するシステムである。欧米の先進国を中心として展示場(パヴィリオン)を公園(ジャルディーニ)内に建設し、単数あるいは複数のアーティストを選んで国を代表させる。それは、国民国家が隆盛を極めた20世紀の政治状況では、基本的にスムースに機能したといえよう。
しかしながら20世紀末に到り、冷戦の終結に伴って安定した国際秩序が揺らぎ始めると、人、物、情報の頻繁な交流によって国家間の境界が不安定に曖昧になってきた。その結果アートにおいても、国を準拠枠として取り扱うことが難しくなった。ヴェネツィア・ビエンナーレでは、国境を横断して活動するアーティストが非常に増えたために、国を代表することが無意味になったり、また国別の展示では、それぞれの国の事情によって作品の質にむらが出る、すなわち大きく分けて、現代とモダンとプリミティヴの作品を一挙に並べて見せるちぐはぐさが、特に近年のビエンナーレで顕著になり問題視されるようになってきたのである。
前回のビエンナーレのディレクター、ハラルド・ゼーマンによる改革への取り組みは、国別のパヴィリオンを外国人アーティストにも開放するということだった。その彼が、世紀をまたいで再びディレクターとなった今回のビエンナーレでは、イタリア・パヴィリオンを除いてそのような企図を実現した国はなかった。その代わり、これまで現代アートでは遅れていると思われていた国に、大きな変化が生じつつあることが見てとれた。勿論すべてではないが、現代アートにおいて発展途上の国(パヴィリオン)の作品が、その先進国に展示された作品と勝るとも劣らない素晴らしいものだったのだ。具体的に国名とアーティストを挙げれば、ブラジル(エルネスト・ネト、ヴィク・ムニッツ)、ポルトガル(ジョアン・ペナルヴァ)、ギリシャ(ニコス・ナヴリディス)、ラトヴィア(ライラ・パカルニーナ)、エストニア(イネ−リース・センパー)、ウクライナ(グループ・アーティスト)、ニュージーランド(ピーター・ロビンソン)など。付け加えておきたいのは、これらのアーティストの多くが、すでに最近開かれた様々な国際展に招待されて活躍しているということである。つまりこれらの国でも、文化行政の責任者が代表の選出に当たり、ようやく現代アートの力を認め始めたということだろう。
さらには、東欧の諸国(ルーマニア、スロヴェニア、ハンガリー)が、メディア・アートの分野で新しい表現を模索したり、台湾、香港、シンガポールというアジアの国々(これらは、ジャルディーニ内にパヴィリオンを持てずヴェネツィア市内にスペースを確保している)が、自国の現代アートを積極的に広めようと努めている姿勢が注目された。特に香港やシンガポールは、バポレット(水上バス)に船内広告まで出していたのである。まさに現代アートが文化産業となり、(それだけでは珍しくないが)その上グローバル化しつつあることの証だろう。それが良いか悪いかは別として、アートと経済を結びつけてその繁栄をもくろむアジアの諸国の積極的な姿勢と比較すると、ビエンナーレのみならず現代アートに消極的な、というより無関心な日本の現状が気になる。ところで日本パヴィリオンの展示作品について語れば、周囲のパヴィリオン(ドイツ、カナダ、イギリス、フランス)と対比させた場合、優劣の問題はおいても、日本とそれらの国の間の、作品を産み出す背景となる文化的ギャップが一層際立つだけの結果に終わったように思う。