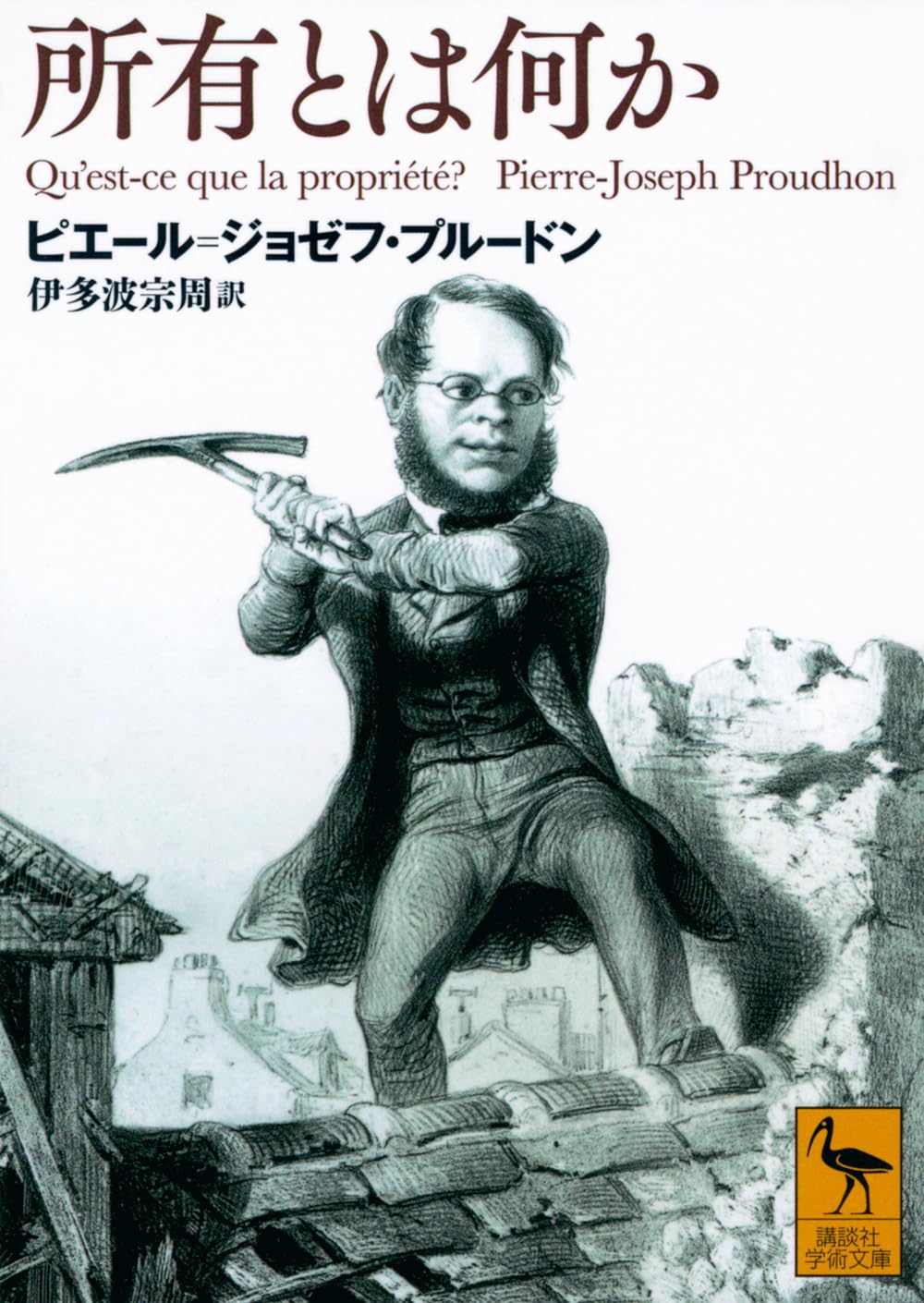
翻訳:伊多波宗周
発行所:講談社
発行日:2024/01/11
この数十年あまり、わたしたちの「所有」をめぐる感覚は驚くべきスピードで変化してきたのではないだろうか。自動車や自転車をはじめ、かつては個人の所有物というイメージが強かった乗り物は、カーシェアやシェアサイクルの普及によって、昨今ますます不特定多数の人間の共有物へと置き換えられつつある。また、映画や音楽をはじめとする文化的領域においても、CDやDVDなどの「所有」から、サブスクリプションをはじめとする「使用」への移行が急速なスピードで進行してきたことは周知の通りである。むろん、それと相補うかたちで、レコードやカセットテープの売り上げが増しているという現実もある。だがいずれにせよ、われわれが数十年前と比べて、はるかに「物」を所有しなくなったのは一般的な事実だと言えるだろう。
そうした時代状況ゆえにか、近年「所有」を原理的な次元で考えなおそうとする試みが、さまざまなところで目立つようになった。個人的に目についたところでは、岸政彦/梶谷懐編『所有とは何か』(中央公論新社、2023)、鷲田清一『所有論』(講談社、2024)をさしあたり挙げることができる。だが、ここ最近でとりわけ驚きだったのは、「所有」についてのもっとも原理的な考察のひとつに数えられる本書『所有とは何か』(1840)が、ほぼ半世紀ぶりに新訳されたことだ。
プルードンの『所有とは何か』は、「所有(propriété)」というテーマについての古典中の古典である。「所有とは盗みである」という印象的なテーゼによって知られる本書は、人間のあいだにやみがたい不平等をもたらす(私的)所有という営為が、いかに正当化しえないものであるかを徹底的に論じる。通常、所有をめぐる(道徳的)議論は、それがどのような範囲/理由/方法であれば妥当(正当)か、という現実主義的なものに終始する。これに対するプルードンの立場は、資本家をはじめとする少数の人間たちによる所有が、いかに社会に害なすものであるかを力説するものだ。「所有とは盗みである」というテーゼはそれを端的に言い表わしたものだが、本書にはそれよりもラディカルな文言がいくらでも登場する。
もちろん、本文のはじめに話題にしたような「所有」と、プルードンが論じる「所有」とは、言葉こそ同じであっても前提や文脈を異にするという考えもありうるだろう。前者はあくまで「共有」に対比される営為としての「専有」のことであるが、プルードンはそもそも、いわゆる「私的所有権」に相当するものすべてが──道徳的にではなく──論理的に擁護しえないと論じたのだった。だが、所有に対する基本的な前提が崩れつつある現代のような状況でこそ、そもそもの所有を根本から批判したプルードンの思想に立ち返ってみるべきだろう。
本書はけっして平易な書物とは言いがたいが、所有をめぐる昨今の議論に真摯に応答しようとする読者にとって、これほど有益な一冊もあるまい。なおかつ特筆すべきことに、本書にはいくつもの有益な訳註が添えられている。プルードンの専門家である訳者の導きにより、19世紀半ばのフランスという特殊な時代状況のなかで書かれた本書は、ふたたび現代へと接続される。
執筆日:2024/04/07(日)






