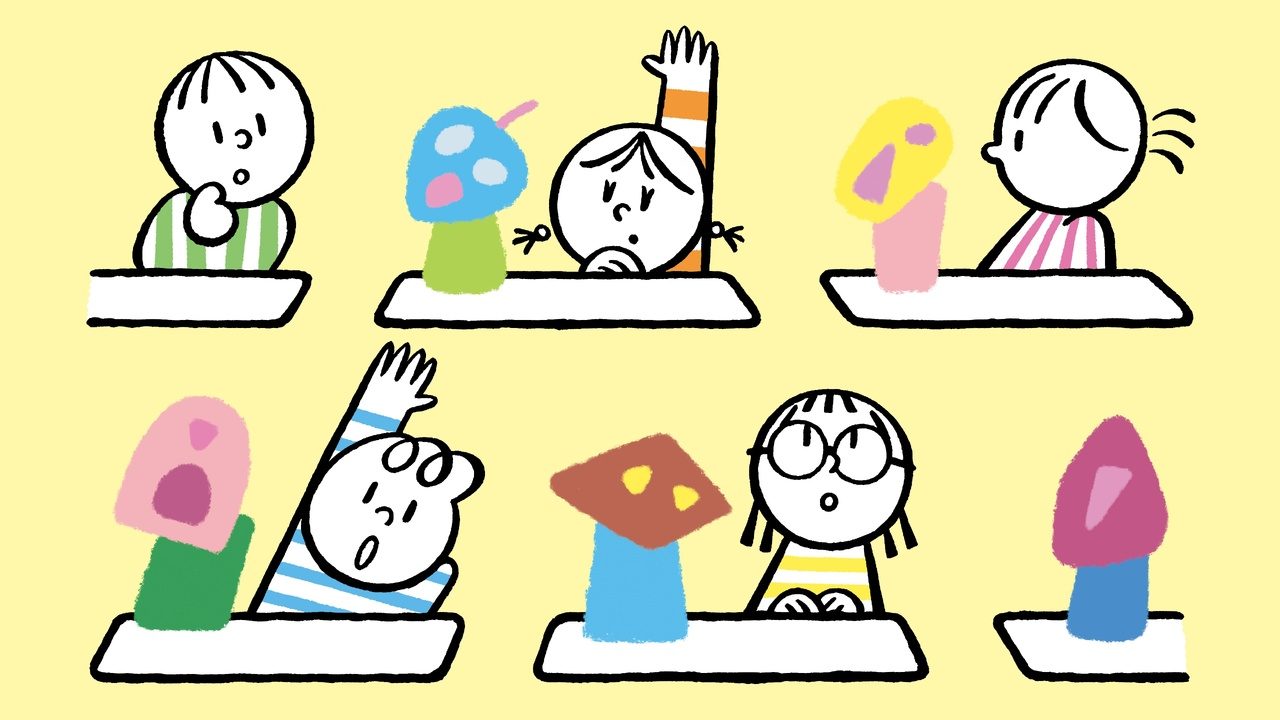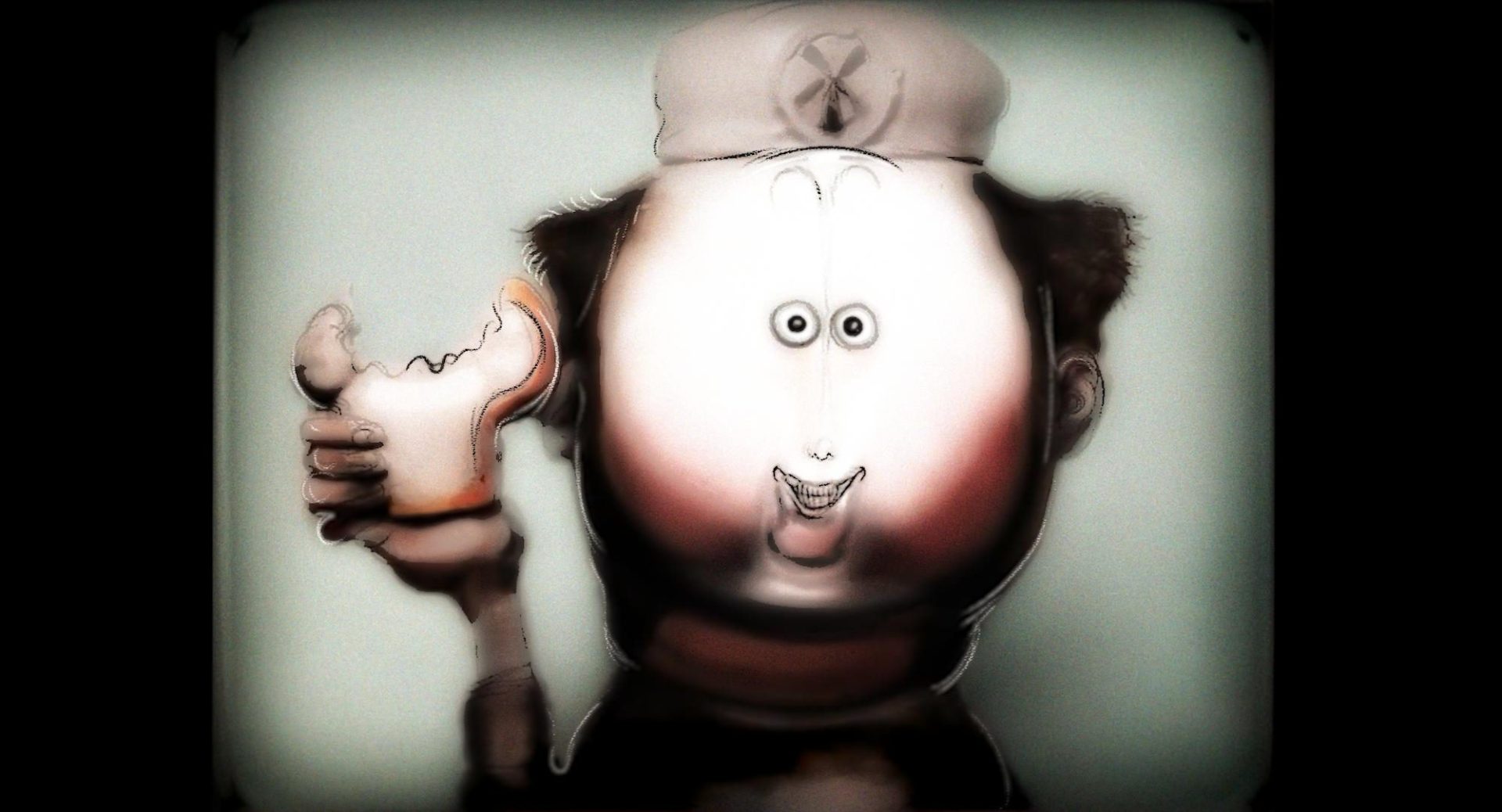会期:2024/04/24~2024/06/30
会場:世田谷美術館[東京都]
公式サイト:https://mingei-kurashi.exhibit.jp
誕生からまもなく100年を迎えるとあって、近年、民藝への関心がとみに高まり、関連した展覧会が増えている。そうなると、展覧会自体の切り口にもセンスが問われてくる。本展は「衣・食・住」をテーマに据えていたことから、柳宗悦の小難しい評論をひも解くことはそこそこに、あくまで生活者目線に立った展示内容であったように感じた。衣・食・住に分けられた展示品を一望してみると、当時といまとで最も変化が大きいのは衣である。それは当然で、約100年前の大正末期、ほとんどの日本人が普段着に和服を着ていたからだ。住もかなり変化がある。当時の住まいはほとんどが伝統的な日本家屋で、それに合わせた暮らしの道具に囲まれていた。一方、最も変化が小さいのは食である。いまは和洋中どんな料理にも使えるモダンな食器は多いが、伝統的な和食器もまだ健在だ。となると、民藝の未来は食の分野に見出せるのか? などといった考えが頭を過ぎる。
本展の最初の章で、1941年に柳宗悦が日本民藝館で開催したという「生活展」の再現が試みられていた。当時にしては珍しいテーブルコーディネートのような展示だったというのは面白いとしても、全体の雰囲気にはやはり時代を感じてしまう。これらの器や家具、調度品をこのままいまの暮らしに置き換えるのには無理があるだろう。
 展示風景 世田谷美術館
展示風景 世田谷美術館
それを受けて最後の章で、テリー・エリスと北村恵子(MOGI Folk Artディレクター)による「これからの民藝スタイル」の展示があり、現代の暮らしにおける民藝の品々の取り入れ方の提案があった。確かに空間や一部の家具をモダンにすることで、洗練された雰囲気へと変わる。でも、なぜ、我々はそうまでして民藝の品々を手元に置いておきたいと思うのだろうか。実用性や機能性、利便性、価格からすれば、いまや工業製品の方がはるかに優れている。しかし人類は産業革命を経たにもかかわらず、工業製品一辺倒では味気なさや物足りなさを感じてしまった。それは何かといえば、人間味や温もり、美、感動といった類のものだ。
 展示風景 世田谷美術館
展示風景 世田谷美術館
最後の章ではまた、民藝運動を受け継いだ新しい世代の職人の活動が紹介されていた。私自身もこれまで多くの工芸作家や職人と接してきて、彼らの活動を伝えることや未来へつなげることを応援してきたが、いつも注目しているのは独自の技であり、挑戦である。彼らが工業製品に置き換えが可能なものを作ったとしても負けてしまう。もしそれが手作業でしか生み出せない価値を秘め、暮らしに潤いをもたらせてくれるものだとしたら、民藝の未来はまだ続いていくのだと思う。
鑑賞日:2024/05/26(日)