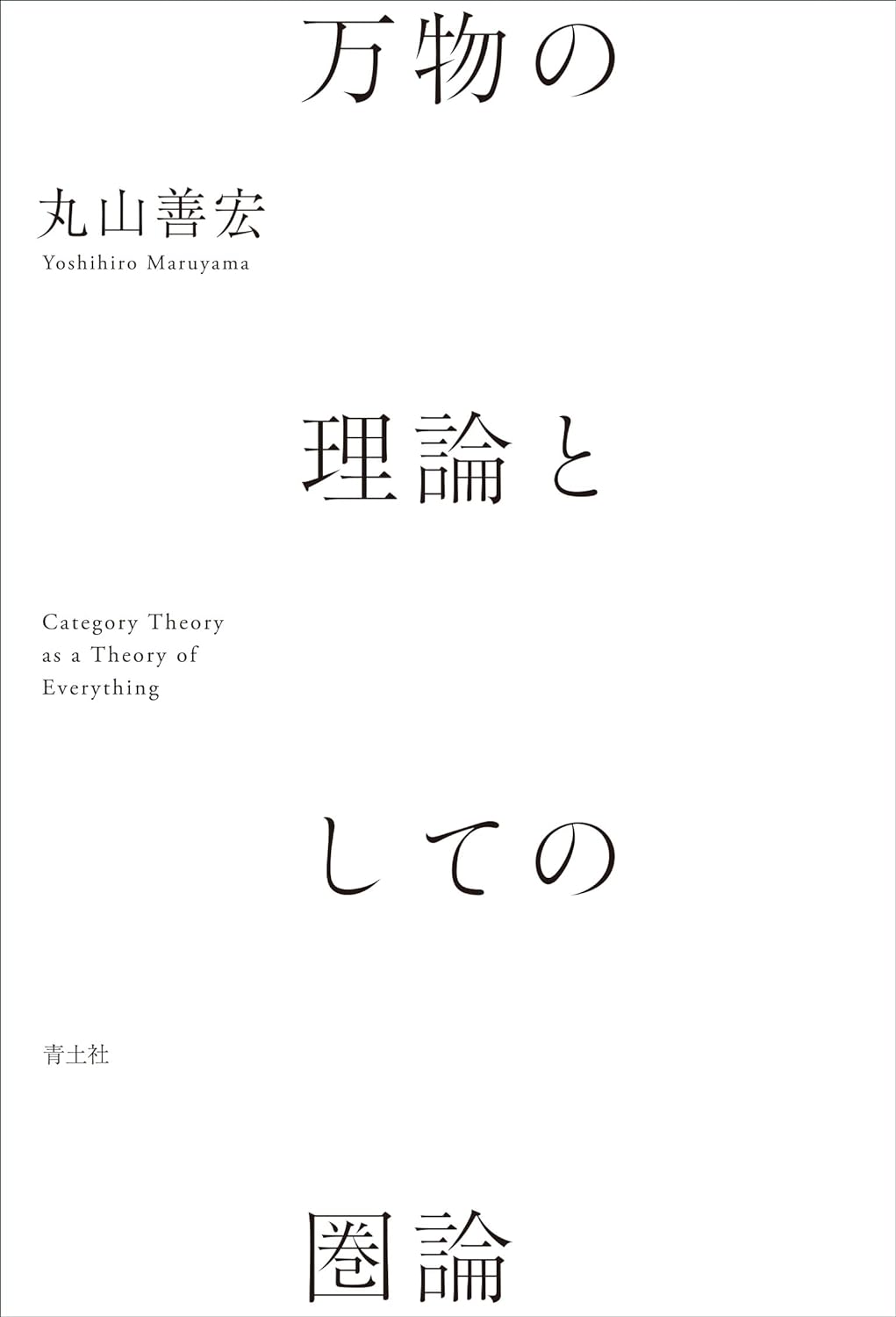
発行所:青土社
発行日:2023/12/30
本書が昨年(2023年)末に刊行されていたことを遅ればせながら知り、発売から数ヶ月遅れて手にとった。わたしの知るかぎり、現代の知をめぐるあらゆる議論のなかで、これほど野心的な見通しを示した本もめずらしい。そのような書物が、今のところそれほど大きな反響を呼んでいない(ように見える)のはなぜなのか。そのような水面上の静けさにはなにか理由があるのではないかと思わせるほどの独特な迫力が、本書にはある。
著者・丸山善宏の仕事には、本書にも収められている『現代思想』掲載の諸論文を通じて、以前から関心を寄せてきた。本書のテーマである圏論を専門とし、なかでも「圏論的統一科学」を唱えるその大振りな姿勢は、同誌の時々の特集に応じて書かれた十頁前後の論文を通じても、充分に大きなインパクトを残すものだった。本書はその『現代思想』に掲載された諸論文(2019-2023)を集成し、著者がかねてより唱えてきた「圏論的統一科学」の具体像をスケッチしたものである。
本書の「はじめに」で印象的に述べられるように、現代はかつてないほど知が氾濫し、なおかつそれらが深刻な分断をこうむった時代である。むろん、同様の認識はすでに19世紀には(ヘルムホルツなどによって)示されていたとはいえ、その後の状況が深刻化の一途をたどったことは誰もが知るとおりである。そして著者は、この状況を打開する唯一の理論こそ圏論であると考える。いわく、圏論は「現象の本質を構造的に抽象する」ことで、「森羅万象の多様性を簡潔な構造の中に圧縮して表現する」理論である(9頁)。圏論はそのように「知の構造」を高い効率性でもって抽出・圧縮する方途であるために、それは「世界観の対立を超克するための世界観の理論」とも表現される(52頁)。いずれにしても、本書において圏論が「万物の理論」と称されるのは、それが知の「再統合」や、異なる知の「ネットワーキング」を可能にする枠組みであることに由来する(66頁)。
本書は、こうした圏論のポテンシャルをさまざまに提案・実装する試みであり、圏論そのものについての数理的な説明はいっさい含まれない(後者に関心のあるむきは、実際に圏論の教科書に当たればよいだろう)。そのため本書は、おそらく熱狂的な読者と懐疑的な読者の双方を生み出しやすいと思われる。評者はこれまで圏論の参考書や、著者・丸山も執筆に携わった『圏論の歩き方』(日本評論社、2015)などを自己流で読んできたが、本書で唱えられる「圏論的統一科学」の可能性については、いまだに具体的なイメージを持ちえない。だが、それを少なからず説得的なものとしているのは、わずか200頁あまりの本書を通じてすら伝わってくる、著者の圧倒的な才気であろう。だからこそ、学界内外の安易なエピゴーネンに対して、著者は圏論の「濫用」を戒めることを忘れない。著者も述べるように、それは圏論が新たな「知の欺瞞」の温床として消費されてしまうことへの危機感に根ざしている(220-221頁)。かくして本書は、みずからが唱える「圏論的統一科学」の喧伝と、その消費への警戒という二重のモティーフに支えられている。ここに書かれている壮大な企てからすればいまだプロレゴメナ(序説)に等しい本書に、それでも大きな価値があるとすれば、それはやはり著者その人の筆の冴えによるものと思われる。
執筆日:2024/06/10(月)







