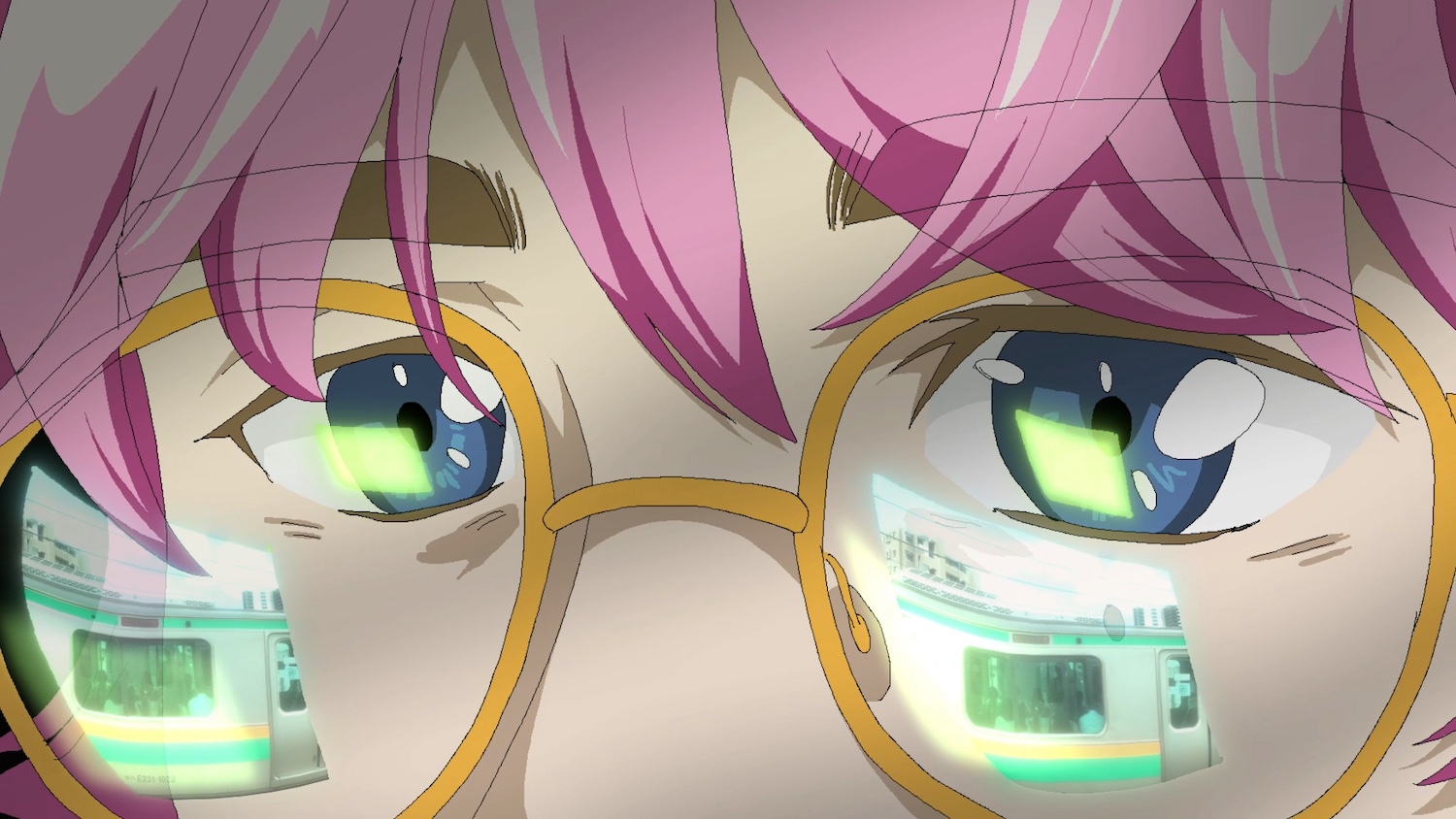発行日:2024/05/23
発行所:柏書房
公式サイト:https://www.kashiwashobo.co.jp/book/9784760155644
今はXと呼ばれているTwitterのタイムラインを追っていて、自分の言葉が奪われていると感じることがある。自分と同じ意見をもつ人のツイートをリツイートしようとするとき、すでに言われていることを私が繰り返す必要はないと思う気持ちと、それでも自分の言葉で何かを言うべきだと思う気持ちのあいだでいつも揺れる。しかしいざ「自分の言葉」を書き込もうとしてみても、出てくるのはどこかで見た「正しい」言葉のつぎはぎでしかないようで、書いた端から嘘くさいと思ってしまうのだ。そんなとき、言葉だけでなく思考までもがおそろしく貧しくなっているように感じられてゾッとする。だが、何かを言いたい、言うべきだという気持ちは必ずしも嘘ではないのだ。誰かと同じ意見をもつことだってもちろんあるだろう。しかし、切り詰められた140字からは微妙なニュアンスはこぼれ落ち、辿ったはずの思考の道筋やその過程にあったはずの逡巡も消去されてしまう。そうして書き込まれる言葉にはやはりどこかニセモノの気配が漂っているのだった。
『共感と距離感の練習』の小沼理の言葉はそれとは真逆だ。本書には「シスジェンダー男性のゲイである」小沼がクィアコミュニティで体験したことを中心に綴った20の文章が収められている。小沼が思考の道筋やその過程にある逡巡、微妙なニュアンスをこそ掬い上げようと言葉を重ねるのは、単純な言葉には還元され得ない、そこからこぼれ落ちてしまうもののなかにこそクィアの生があることを知っているからかもしれない。
例えば、小沼が高校生のときに公衆トイレで遭遇したある出来事をふり返る「安全なファンタジー」。高校生の小沼は「誰かを好きになることよりも、男性に抱く性欲のほう」に圧倒的にリアルなものを感じながらも、友情と性愛の区別がつかずに混乱し、男友達に送るメールにハートマークを使いたいと思う気持ちを恋愛感情と結びつけては考えることができなかったという。現在の小沼は「あれって恋愛だったんじゃないか? と思うような十代の経験は、ほかにもいくつかある」とふり返るが、予感と恐れを抱え、あるいはそれに気づかないふりをしながら過ごしていた当時の小沼の体験と心の動きを「ゲイの高校生」のそれとしてくくってしまっては取りこぼすものがあまりに大きいだろう。
小沼はまた、同性婚について書いた「別の複数の色」のなかで、小さい頃は性と愛と結婚とが結びついていなかったため、すでに男性に性的な感情を抱きながら、一方で自分もいつかは(女性と)結婚すると思っていたのだともふり返る。同性婚をめぐっては近年、その法制化の実現に向けて憲法の解釈や賛成反対の議論、あるいは同性婚が法制化されていないことによって不利益を被っている当事者の声などが広く聞かれる状況にある。小沼もまた、それらの情報を簡潔にまとめ、「まずは婚姻の平等が必要だけど、最終的には制度を解体すべき」と自身の現時点でのスタンスを示している。だが、その手前には、2015年に渋谷区と世田谷区で同性パートナーシップ制度が導入され、2019年には「結婚の自由をすべての人に」訴訟がはじまったのを目の当たりにしたことの戸惑いが書きつけられてもいたのだった。「その選択肢を持たないまま生きてきたから、自分の生活と地続きに『結婚』がある状況がうまく想像できない」。同性婚の法制化を後押しするような言葉ではない。だがここには一般論でも抽象論でもなく、ひとりのゲイ男性の生と生活に根ざした実感が確かに刻まれている。
賛成と反対、マイノリティとマジョリティ、あなたと私。共感と距離感、わからないとわかる、重なりと異なり。「はじめに」に付された「わからないけどわかるよ」という副題が象徴するように、小沼の思考と言葉はいくつもの対になる二項のあいだで行きつ戻りつし、あるいはむしろ、どこかほかの道はないかとうろうろするようにして進んでいく。クィアを描いた作品について。男性性について。日本や韓国のクィアイベントについて。クィアと音楽について。そしてパレスチナでいまも起きている虐殺について。いくつものトピックは小沼の生と生活を介して、思考と言葉を介してゆるやかに結びついている。全体を通して何かひとつのことを主張しているわけではないが、それでも一貫した姿勢のようなものを見出すことはできるだろう。自身の生と生活の実感を手放さずに思考し言葉を紡ぐ誠実さ。それは小沼の最初の著作である日記本『1日が長いと感じられる日が、時々でもあるといい』(タバブックス、2022)とも共通するものだ。
あるいはもちろん、自分の思考や言葉は十分ではないのではないかと疑い続けながら言葉を記すその逡巡もまた小沼の誠実だ。それは「『何が正常か』の線引きを解体する方法が知りたかった」という小沼がコミュニティの内部から声を上げることに、あるいはコミュニティの外部に/自らのコミュニティとは異なるコミュニティに目を向け足を運ぶことにもつながっているものだろう。逡巡し続けるということはその場にとどまり続けることではない。むしろ変わり続ける可能性を受け入れることなのだ。
そうして連ねられた言葉の先の、ひとまずの終わりで小沼は読者に呼びかける。会う機会があればあなたの個人的な話を聞かせてほしいと。それを読んだ私は考え込んでしまった。小沼のように自分を開き、生きた言葉でもって世界に働きかけることが私にできるだろうかと。私の逡巡はまずはそこからはじめるしかなさそうである。
執筆日:2024/05/24(土)