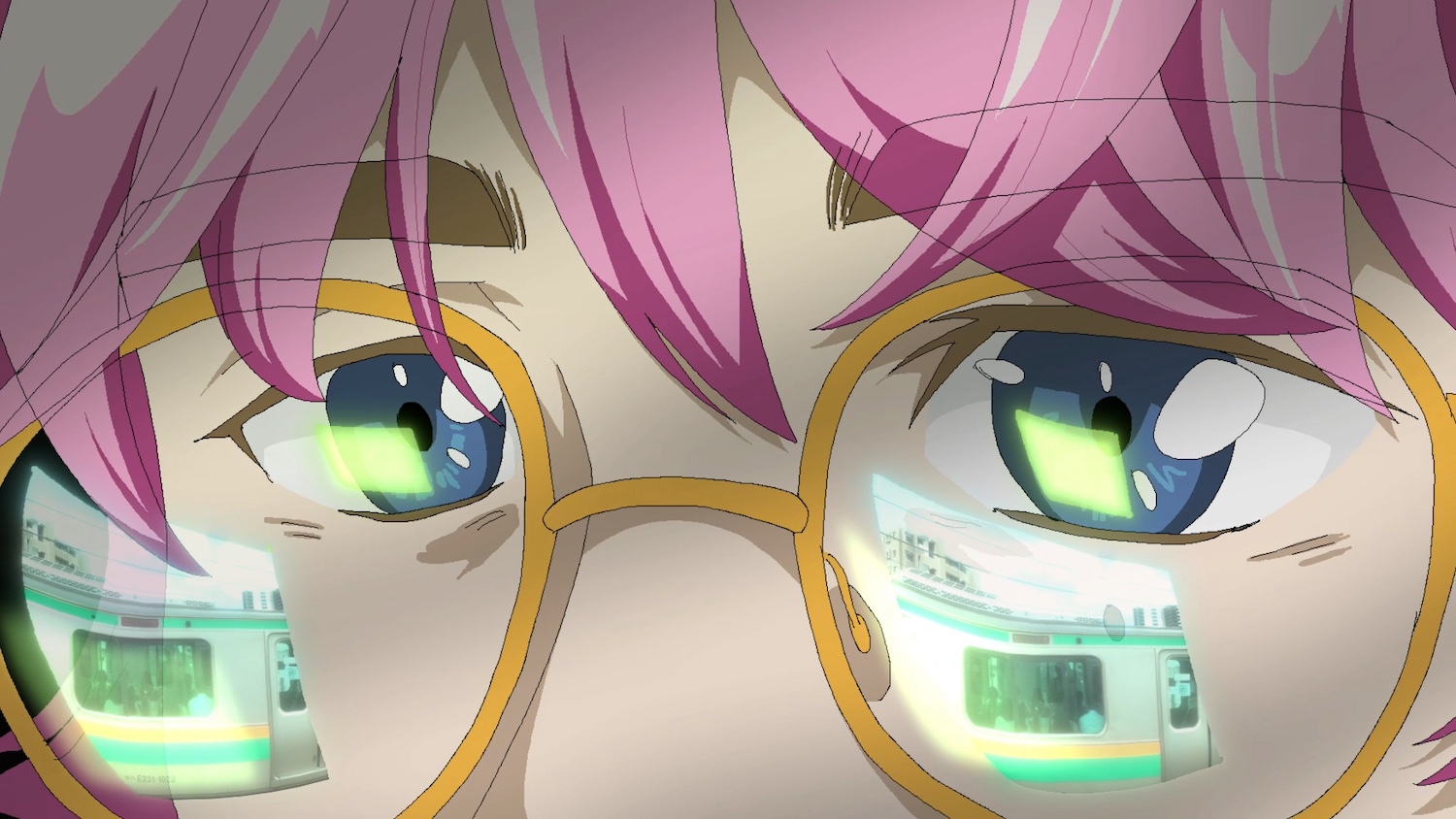会期:2024/5/18~2024/6/16
会場:東京日仏学院、CAVE-AYUMI GALLERY、神楽坂セッションハウス 2Fギャラリー[東京都]
公式サイト:https://gewaltdantai.com/ja/「ゲバルト」展/
太湯雅晴の《立て看 パビリオン》を横目に通り過ぎ、エントランスのドアを押す。一時的に野外彫刻と化した立て看は、歩きながら眺めたり、立ち止まったり、立ち去ったりしてもよい強制力のなさがよいと思う。
有事の際にはシールドとして、文字通り大学と学生のはざまに立つだろう「タテカン」から始まるゲバルト展は、「制度の暴力の中で特定の芸術形態がどのように発展していくか」「革命的な闘争における芸術の役割」を問うという。東京日仏学院とCAVE-AYUMI GALLERYを主な開催場所とし、それぞれに14作家、2作家が出品した。
中に入ってハンドアウト2種をもらう。入口脇にキャバレー・クラン・フェブル《我々の存在の条件 弱流宣言》のレコード、ヘッドフォン、パンフレット3種があり、ソファに座って聞くことができる。チリチリとしたノイズと周波数を変えた日本語、フランス語の朗読が組み合わさり、肉声とデジタルが中和していて面白い。
ヘッドフォンをしたまま正面を向くと、壁にプロジェクションされたナディール・ベ《Flatness-プレリュード》の波打つラインが目に入る。左を向くと、日仏学院の常設と思われる液晶モニターでTV5MONDEチャンネルのメロドラマが音声付きで放送されている。そのモニター奥の大窓、透明のガラス越しにジャン=バティスト・ファーカス《従う》の付箋付きボードがある。坂倉準三による広々とした建築空間の中で学院の機能と展示作品が奇妙に調和して、全体的に寛容さを感じる空間が広がっていてすばらしいと思う。

展示風景[筆者撮影]
ソファから立ち上がった対角線の先には、遠藤薫、三宅沙織、嶋田美子の作品がある。それぞれに沖縄、震災、女性といったテーマを自身の表現手段と撚り合わせる姿勢が窺える。彼らのスペースの壁には3つの扉があり、石川雷太、足立正生・若松孝二、城之内元晴の鑑賞空間に通じている。
城之内元晴『ゲバルトピア予告』(1969)について書きたい。国内では2018年にゲーテ・インスティトゥート東京のホールで上映されて以来と記憶しているが、ゲバルト展では窓のある小さな空間で映像に向き合うことができた。赤瀬川原平が唐十郎らの身体に筆書きしたレタリングが美しい本作は、足立正生らとVAN映画科学研究所を立ち上げた城之内による13分の作品である。

展示風景[筆者撮影]
映像は「ゲバルトピア予告」と文字の書かれたまぶたが、力を込めてまばたきをする様子から始まる。ついで核爆発の雲が映る。カメラに向かってはしゃぐ子どもたちの祝祭的な雰囲気(城之内の作品『プープー』(1960)の一部)、裸体の男性、ドイツ表現主義の映画、日大闘争の映像が組み合わさり、ときおり「春なんぽうのゲバルトピア」「一もんめの春がきた」「人の世は」「地獄かよ」「地獄ぞよ」「地獄のみ」といった、肌に書かれた文字が映る。そこに反響音や動物の鳴き声のような音が重ねられ、嗚咽のような声も混じる。
この作品に感激するのは、映像の連なりが一般的なモンタージュとして機能しないために、意味の伝達という映像における既存の表現手段から解放されているためだと思う。だからといって観客とのコミュニケーションが放棄されているわけではない。呼吸の印象、臍の緒へのクロースアップ、「人の世」と「地獄(彼の世)」といった言葉への言及から感じられる出産や生死のイメージに加えて、個の身体に対する核の威力、静謐な文字に対する嗚咽の声といった対立項の提示が伝わる構成となっている。
そして、それらのあいだを行き来する映像が連ねられる。例えば、背中に書かれた「嗚呼無惨」という文字が、背筋の動きによって歪められ、徐々に読めなくなっていく。「読める」と「読めない」のあいだにある読みづらさをカメラは捉える。冒頭のまばたきにおける、力一杯まぶたを開けたり閉じたりするという身体性は単純にコミカルであり、全力で大したことのないことをするという対峙のムードも漂う。
『ゲバルトピア予告』にはさらに二つの階層における、対立項のはざまがある。膨らんだりへこんだりする腹の抑揚に合わせて、その様子を捉えるカメラのレンズも呼吸するようにピントを合わせたり、ぼけさせたりする。何を映すかというモチーフの選定にとどまらず、どう撮るかといった撮影の段階においても、撮影者の身体性を露わにしながら焦点距離を行き来する。
加えて本作には、ドイツ表現主義映画と城之内の過去作品の映像が挿入される。引用された『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922)は草月アートセンターが開催していたシネマテークで1969年の7月に上映されていたもので★1、やがて学生たちが造反する草月という機関★2や潤沢な資本をもって作られた映画に対する個人映画という対比も窺える。両者の映像は多重露光のように重ねられもし、編集の段階においても、意味を剥奪するサンプリングと意味を寄与するモンタージュとを彷徨う印象がもたらされる。
こうした幾重もの対立項の提示により★3、一定の意味や価値に集約されずに、あるものとあるもののあいだをめぐる感覚が刺激され続ける鑑賞体験となる。作品固有の映像言語を獲得している本作は、ゲバルト展の趣旨「制度の暴力の中で特定の芸術形態がどのように発展していくか」に対しても、最適解を呈していると言えるだろう。
本展はまた60年代の学生運動において主だって使われた、日本における「ゲバルト」という言葉の特殊性にも注目する。体制による暴力に対抗する「反暴力」を表わす言葉として、ドイツ語で「暴力」を意味する「ゲバルト」という言葉が用いられたという。これが皮肉を込めたものなのか、翻訳におけるミスに由来するのかはわからない。反暴力の象徴として、異なる言語世界で相対する意味を持つ言葉が選ばれる奇妙さは、バンパク(万博)の反対運動をハンパク(反万博)と呼び、濁点のありなしで意味を転換した同時期のトートロジー的な言葉遊びを思わせる。
加えて想起する反転の例に、1967年末にベルギーで開催された映像祭「EXPRMNTL 4」がある。ゲバルト展に足立正生との共作『赤軍-PFLP・世界戦争宣言』(1971)を出品している若松孝二の『胎児が密猟する時』(1966)がファシスト的だとして、ドイツの学生革命家を中心に上映が妨害され、舞台上では映画に代わってベトナム戦争反対を称揚するアジテーションが試みられたという★4。若松はドイツの学生らと同じく反米思想に理解があったはずだが、日本の学生がゲバルトという言葉の意味を反転して用いたように、彼の映画はドイツにおいて日本の観客とは真逆の意味合いを持って受け止められた★5。
意味や理念の受容は、変化を伴う。それはCAVE-AYUMI GALLERYの会場に出品されたユニ・ホン・シャープ《リピート》のテーマでもある★6。踊りを、言葉を、受け取るプロセスにおいてときに生じる捻転は、受容される土台に応じて暴力を反暴力に、ファシズムを社会主義に入れ替える。それはしばしば強い抵抗によって引き起こされ、結果として表現領域の拡張や更新を促す。本展はその駆動域に焦点を当て、制度との衝突によって逼迫的に立ち起こる熱量と表現の関係性に注目する。
2階の壁面にはミグリン・パルマヌ、バディ・ダルル、FanXoaの作品が展示されていた。とりわけダルルによる《King of the System》はボードゲームの造作物をゲームのルールから引き上げて彼の作品空間に転用するもので、可愛らしいミニチュアの中に制度の革新を潜めたものだった。

展示風景[筆者撮影]
鑑賞日:2024/05/24(金)
★1──草月シネマテークにおける「ドイツ表現派映画回顧」は、1969年2月、5月、6月、7月、1970年4月、5月の例会において、プログラムを変えて上映された。『ゲバルトピア予告』には、制作年より遅い1970年4月に上映された『ゴーレム』(1915)も引用されている。
★2──1969年10月、1964年に始まった草月アートセンターの「フィルム・アート・フェスティバル」は、フェスティバル粉砕共闘会議の学生および映像作家の金坂健二らによる妨害を受け、予定していた上映を中止して別の日程で開催した。
遠藤みゆき「評伝・金坂健二」(『東京都写真美術館紀要』No.11、東京都写真美術館、2012)
★3──対立項を行き来することへの城之内の偏愛について、足立正生がエピソードを記している。城之内はアパートの部屋にいくつもの皿や椀を並べ、そのなかで発達する黴の様子に宇宙的な小星雲を見出し、その観察に熱中していたと言う。
「城ちゃんは、皿の中に展開している小星雲の群れを日夜眺めながら、ミクロ世界の星雲群がマクロ世界の自然宇宙とつながる想像空間を往復渉猟すれば、誰もが楽しめると信じていたのだ。」
『“城ちゃん”在りき──城之内元晴回想文集』(七月堂、2011)
★4──ジュリアン・ロス「『もうヨーロッパに何も期待しなくていいんだ』──日本の非商業映画・実験映画ヨーロッパ公開史」(『言語文化』31号、明治学院大学言語文化研究所、2014、pp.44-65)
★5──上映中に妨害が始まったという経緯から、EXPRMNTL 4の観客は本作を最後まで鑑賞しなかったと思われる。映画の大部分の描写はたしかに強権的である。
★6──ユニ・ホン・シャープの《リピート》は、フランス語の発音を日本語のアクセントなしで発音する方法を教える映像と、朝鮮舞踊の動作を伝え合うダンサーたちが向き合う2画面の映像とを交互に上映する3画面の作品である。身体にインプットされた文化の記憶を、ズレのプロセスとともに他者と共有する方法を探る。