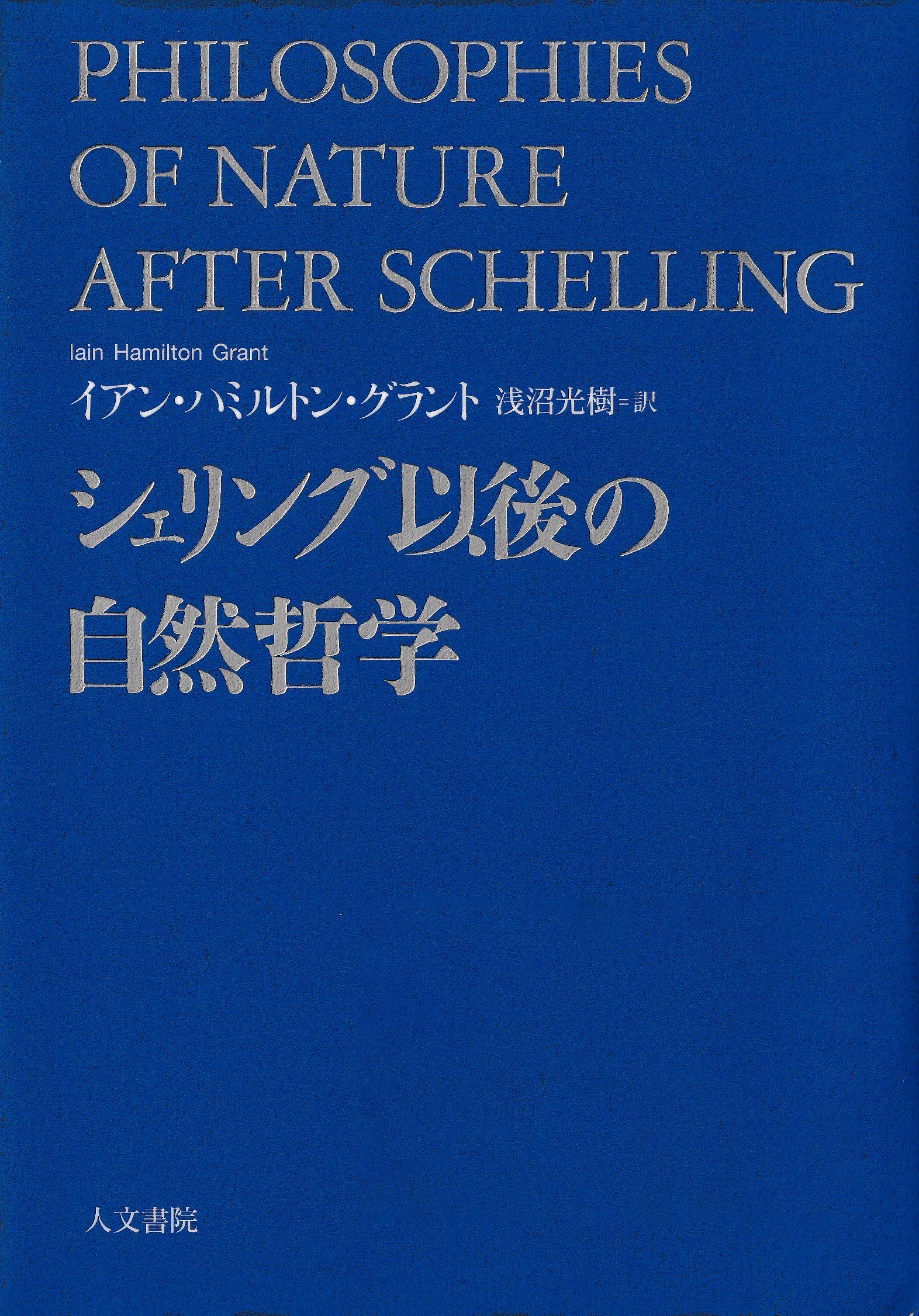
翻訳:浅沼光樹
発行所:人文書院
発行日:2023/12/20
21世紀の現代思想において注目を集めるキーワードのひとつに「自然哲学」がある。その大部分はジル・ドゥルーズの影響に負うところが大きいが、むろん自然哲学という問題系は古代ギリシア以来連綿と存在した。では、なぜ「いま」自然哲学なのか──それこそが真の問題であると考えるべきだろう★。
ただし厄介なのは、ここでいう「自然哲学」のもつニュアンスが(その単純な名前に反して)けっして飲み込みやすいものではないことだ。言うまでもなく、この世界を構成する「自然」を理解しようとする試みは、近代において自然科学へと場を譲った。それとともに、自然哲学は、いわば自然とは何かを思弁的に考究する形而上学へと変貌した。とはいえ、近代においてそうした問題に取り組んだ哲学者が多かったわけではけっしてなく、20世紀において自然哲学は──すくなくとも表面上は──ほとんど後景に退いたと言うべきだろう。
そのような情勢において、ドイツ観念論を代表する哲学者フリードリヒ・シェリング(1775-1854)を「自然哲学」という観点から包括的に論じたのが、本書の著者イアン・ハミルトン・グラント(1964-)である。2006年に刊行された同書において、カントの「コペルニクス的転回」を露骨に批判し、シェリングのなかにカントの道行きとは異なる可能性を見いだしたグラントは、その翌年にロンドンで開催されたワークショップ「思弁的実在論」をきっかけに、現代思想の表舞台に現われることになった。
本書『シェリング以後の自然哲学』の内容を要約することは難しい。基本的に本書はシェリング哲学についての浩瀚な研究書だが、そこではシェリングの(1)プラトン受容、(2)カントとの対決、(3)フィヒテとの対決、(4)ドゥルーズとの連続性、等々の複数の問題系がつねに並走しており、全体の見通しもけっして良いとは言えない。そこで、読者はまず第一章「なぜシェリングなのか、なぜ自然哲学なのか」(23-72頁)を一読し、本書の問題意識を把握するところから始める必要があるだろう。すくなくとも、序文で著者もことわっているように、本書に文字通りの「シェリング以後の自然哲学」──すなわち、近現代の自然哲学をめぐる歴史的な考察──を期待すると、おそらく大きな肩透かしを食らうに違いない。
そのうえで、あえて粗雑に言ってしまえば、本書でグラントが主張しようとするのは次のことである。すなわち、〈法則と自由〉〈認識と道徳〉〈人間と自然〉といったもっともらしい二分法は、いずれもカントによって導入ないし体系化された、近現代哲学の宿痾だということである(この点で、グラントは同じ「思弁的実在論」に括られるメイヤスーやハーマンと、もともと基本的な問題意識を共有していたことがわかる)。そのようなカントに対し、シェリングは自然を力動的な生成と考えるのであって、そこにはカント的な批判哲学には回収されない自然哲学の構想がある。グラントはそれを数回にわたり、〈超越論的なものの自然化〉という言い回しによって説明している──「超越論的なものとはポテンツを高め、新しい作用、新しい形式、新しい現象、新しい概念へと変身する自然である」(380頁)。
シェリングについては、グラントのみならず、かのマルクス・ガブリエルを通じてにわかに注目が集まっている。だがその一方で、今日の読者からすれば、その特殊な哲学体系は安易な接近を拒むように感じられるだろう。そのようななか、グラントはシェリングのなかに「自然哲学」という一貫したテーマを見いだし、それをもってカント的な批判哲学の乗り越えをめざす。昨今の現代思想ではすでにひとつの「作法」として定着した感のあるこうした「ポスト・カント的」な議論が、実際のところどこまで妥当性を有するのか──その具体的な検証のためにも、まずはその出発点(のひとつ)である本書にじっくり取り組むことは不可欠であるように思う。
★──この問題について、日本語で読める文献としては次を参照のこと。小林卓也『ドゥルーズの自然哲学──断絶と変遷』(法政大学出版局、2019)、近藤和敬・檜垣立哉編『21世紀の自然哲学へ』(人文書院、2024)。
執筆日:2024/8/19(月)







