私たちの日常にあふれる映画、音楽、ミュージアム、SNS──それらがいかに政治と関係し、社会を動かしてきたのか。そうした問題を考察する『楽しい政治』は、現代アメリカのカルチャーを軸に、政治がどのように私たちの身近な表現やコミュニケーションと結びついているのかを多角的に掘り下げている。本稿で同書を評するのは、カルチュラル・スタディーズや現代アートの領域で批評と実践を行なってきた川上幸之介氏。氏はここで、投票や議会だけではない、私たちの足元から始まる政治への関与のあり方を豊かな事例とともに照らし出していく。(artscape編集部)
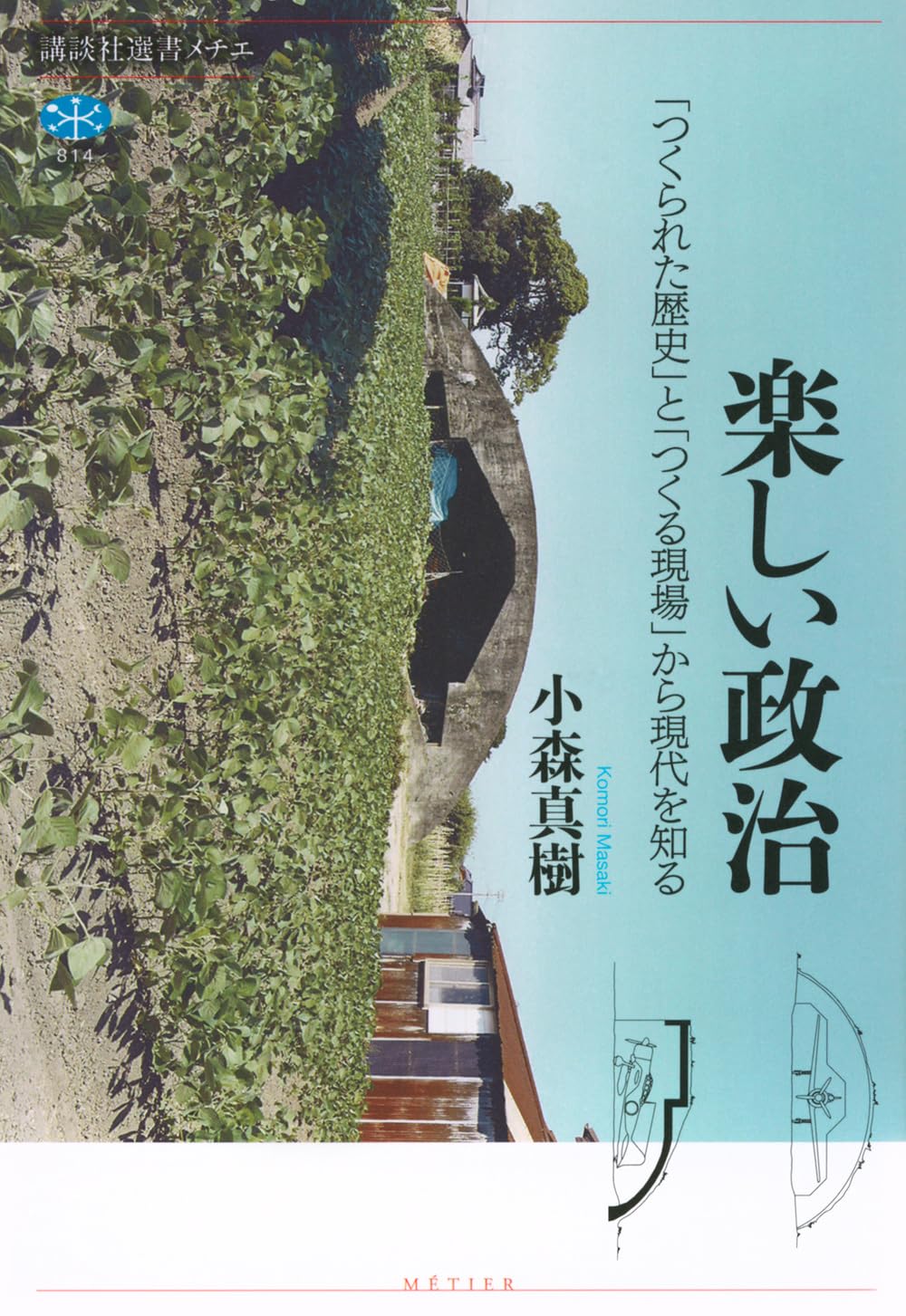
小森真樹『楽しい政治──「つくられた歴史」と「つくる現場」から現代を知る』講談社、2024
政治と文化をめぐる問いは権力のあり様と社会正義の実現を巡る議論をこれまで呼び起こしてきた。本書は、その政治と文化の関係を、アメリカというレンズを通して、映像作品、社会運動、博物館、ポピュラー音楽といった多岐にわたる領域を横断しながら、時にフィールドワークも駆使して紐解いていく。
異なる意見と立場の人々がどうすれば共存できるのか。いかなる方法であれば、政治に無関心な人々でも関わることができるのか。そういった現代社会における喫緊の課題について、本書はわかりやすく魅力的な文章と、多分野にわたるポピュラーカルチャーという親しみやすい素材を通して間口を広げ、政治の楽しさを描き出している。
著者の専門はアメリカのミュージアム研究であり、政治的、社会的、文化的な力学がミュージアムをめぐってどのように影響しあい、反映されているのかという問いを──すなわち「展示の政治学(politics of display)」を──研究している。その手腕は本書にも十分に発揮されており、政治についてさまざまなアクターの角度から楽しむことができる。そして、改めて政治とはどういうもので、私たちがどうそれに関与することができるのかといった具体的な提案までも含め、多くの示唆を与えてくれる。
本書では、アメリカにおいてこれまでさまざまな方法で政治にアプローチしてきた文化活動と、それと比較される日本の文化も取り上げられている。映画『トイ・ストーリー』シリーズや『ウォッチメン』(2019)、世界中で一世を風靡するKポップ、アメリカの極右が提唱する陰謀論とそれに基づく政治運動である「Qアノン」。2020年にアメリカで黒人男性が警察官に命を奪われた事件を発端に広がりを見せた人種差別抗議運動「ブラック・ライブズ・マター(BLM)」。そして国内で賛否を呼んだ「表現の不自由展」など、私たちにも馴染みのあるテーマに加え、『コンクリート・カウボーイ:本当のぼくは』(2021)『ゼム』(2020)『ノマドランド』(2020)といった映像作品やインターネット・ミーム「カエルのペペ」など、あまり国内では知られていない話題も含まれている。
本書を際立たせる、秀逸かつ示唆的な点は、歴史と文化を隔てている人種や性差の壁がオーソリティや特権階級といった特定の社会から要請され、決定されていること を、慎重に、かつ的確にポピュラーカルチャーを通じて指摘していることであろう。また第2部で展開される近年の社会運動とその実例は政治が理論だけではなく、社会への参加でもあるということを示し、私たちを政治へと駆り立ててくれる。
第1部「つくられた歴史から〈構造〉を知る」では、アメリカの負の歴史である奴隷制から脈々と続く人種差別、アフリカ系アメリカ人の歴史を振り返る。黒人の歴史の隠蔽について「タルサ人種虐殺」からはじめ、それがいかに隠され、時に修正されてきたのかを映画の物語と重ねつつ振り返る。ここでは勝者の歴史という、これまで自明視されてきた歴史の枠組みを解体し、相対化し複数化を試みる。また、例えばカウボーイという文化に抱く我々のイメージがいかにメディアによって作られてきたのか、そこにあった白人以外の人種の存在、その人種を隔離してきた都市計画までを追っていく。さらに、アメリカにおける社会経済的な成功概念である「アメリカン・ドリーム」が個人の向上心や社会的流動性を促進する一方で、現実との乖離や格差拡大をもたらし、それが家父長制的な物語であることを『トイ・ストーリー』や『ノマドランド』を分析しながら明らかにしていく。著者はキャッチーなテーマを参照しながらもアメリカの背後にある構造を分析することで、この社会のあり方を問い直そうとしているのだ。
第2部「つくる現場から〈コミュニーケーション〉を知る」では、多様化する社会運動の現場の変容にもフォーカスが当てられていく。今でも世界中に傷跡が残るコロナ禍で起きた反ロックダウン運動、そして著者も参加したブラック・ライブズ・マター、奴隷制を推進してきた人物などの彫像撤去運動、「表現の不自由展」、著者の専門とするミュージアム、SNSを使った活動、「カエルのペペ」が俎上にのる。文化と運動の関係が、どのように政治的な議論の場として機能しうるのかが探求されていくのである。加えて著者は、こういった社会運動によって起きた負の側面としてのキャンセルカルチャーや、その立場上参加できなかった人々にも目配りを忘れない。
著者は社会運動の事例を通して、SNSなどの情報伝達手段を介したコミュニケーションが アイデンティティの表明、社会変革の手段として機能することを指摘する。特にSNSがもたらす双方向性や匿名性が、従来のメディアとは異なるコミュニケーションの可能性とリスクを生み出している点にも着目しており、私たちがSNSも含めた社会、政治運動にコミットする際に見落としがちな点もカバーしていて、実践の際に大いに参考となるものだ。また、コミュニケーションの場としての文化施設が社会的な対話を生み出し、多様な意見を共有するための空間としてどのように活用できるのかが考察されていて、新しい文化施設のあり方までも提案されている。このように著者は政治をめぐる同時代の研究成果を紹介することも怠っていない。
本書は、アメリカの政治と文化という広大な問いを題材にしながらも、現代社会における政治と文化の関係性を軽やかに、そして緻密に考察し、私たち自身の社会を見つめ直すための視座を与えてくれる。政治の複雑な側面をわかりやすく解説し、読者に政治への関心を喚起する。国内の環境においては触れることが難しい政治について、それが必ずしも投票や国会中継とイコールではないことを明瞭に伝えてくれるのだ。政治、社会、文化研究、芸術といった分野に関心を持つ読者だけでなく、現代社会のさまざまな問題に関心を持つすべての人にとって、本書は刺激的で示唆に富む一冊となるだろう。








