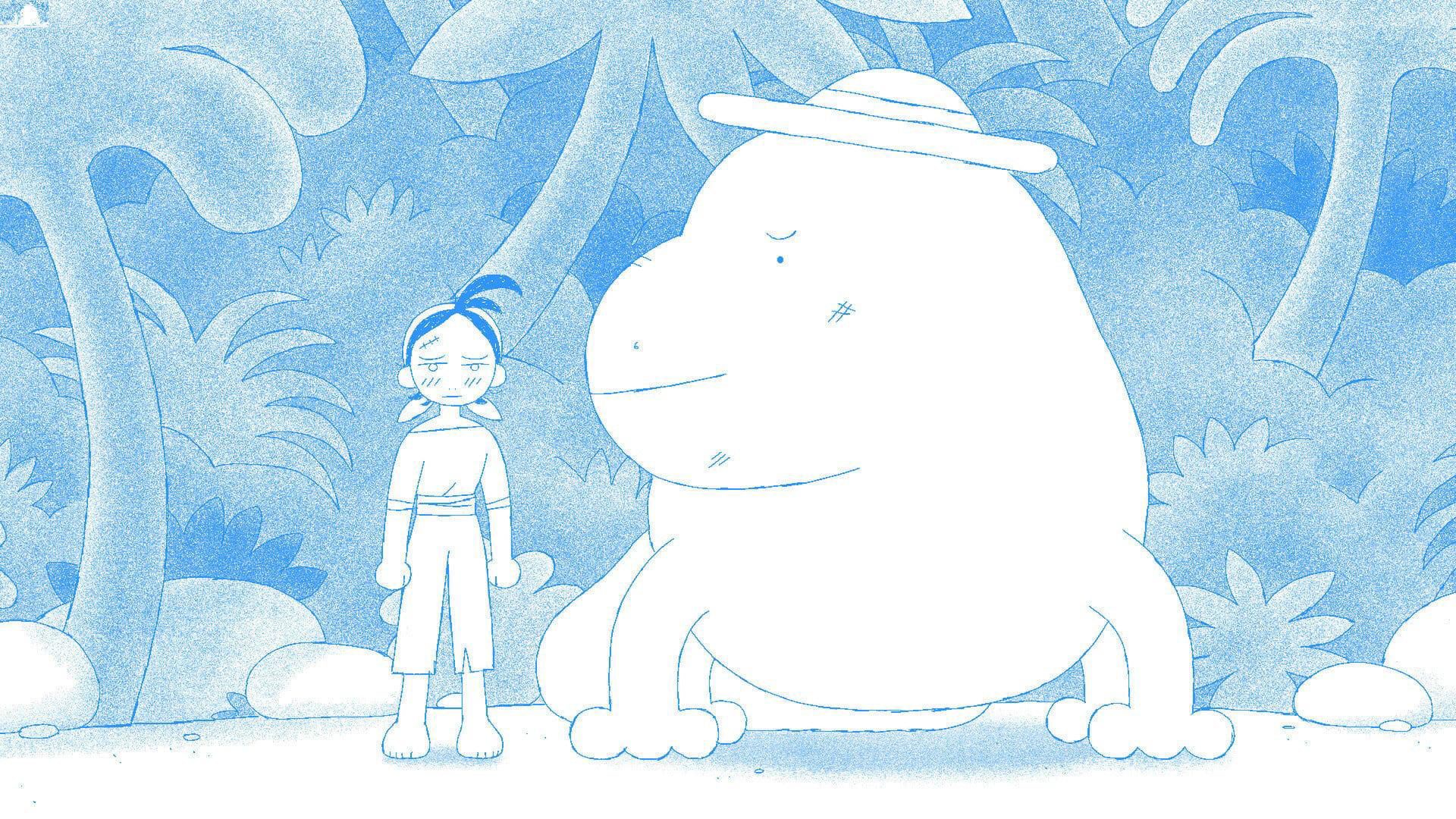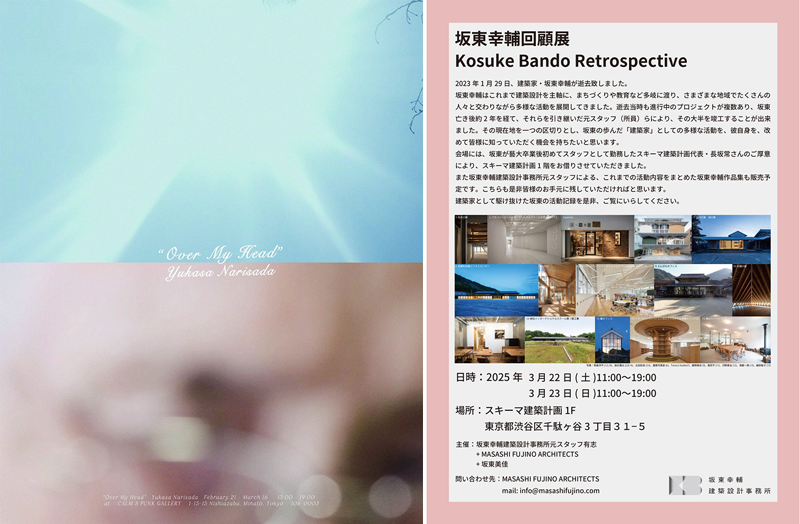
成定由香沙「Over My Head・あたまの上で」
会場:CALM & PUNK GALLERY[東京都]
会期:2025/02/21〜2025/03/16
展示コンサルティング:佐藤熊弥
公式サイト:https://calmandpunk.com/exhibition/jp-yukasa-narisada-solo-exhibition「over-my-head」/
「坂東幸輔 回顧展 Kosuke Bando Retrospective」
会場:スキーマ建築計画[東京都]
会期:2025/03/22〜2025/03/23
主催:坂東幸輔建築設計事務所元スタッフ+MASASHI FUJINO ARCHITECTS+坂東美佳
展覧会詳細:https://mag.tecture.jp/event/20250318-125365/
建築物は私たち人間よりも大きい。壁と柱は、天井と屋根を人間の頭より高い位置へ固定するための高さと、人間の身体より大きなボリュームを囲うための幅を持つ。それは、確実に、私たちよりも大きい。大きいために、その内外を私たちは動き回れる。しかし、暗く閉ざされたものの内、脅威の降りかかる外、確かにある危機的な現実を前にすると、動き回ることへの想像は容易に引き下がってしまう。現実の手前で、私たちはどう想像し続けることができるのだろうか。
美術家/建築家の成定由香沙が個展「Over My Head・あたまの上で」で目を向けたのは「我々の周りにある我々の手には負えないもの、ここではすなわち『放射能』について私たち人間が100年以上にも及ぶ混乱のなかにある(=Over my head)こと」であり、また大空のように「頭上を超えてゆくもの(=Over my head)」が潜在的に私たちにもたらす抑圧への不安感覚だ。
この空には放射能が飛散していたし、また飛散するかもしれない。成定はこの問題系を、漠然とした不安のままでなく、因果のあるトラウマとして、人間が人間に引き起こすこととして考える。
原子力発電所は、建築物のなかでもとりわけ大きなもののひとつで、またその大きさに比して人間の動き回るための気積が少なく、視覚的にも経験的にも不透明なものだ。一方で「原子炉は(中略)内部にまつわる不可視性とは裏腹に外郭自体はその風景に対して剥き出しの身体を有している」。外郭は放射能を封じ込め、一方で取り巻く世界を守ろうとする★1。原子力をいかに用いるかの説明は、資料館や教科書で明快になされているが、そのメカニズムを駆動するために必要とされる夥しい量の機械群、配管類、タンク、そして柱や壁と屋根天井の集合は、実際のところわかりやすいものとは言いがたい。複雑すぎる出来事を前にして、よくわからないけど、わかったことにすることが私たちにはできてしまう。そして、わからないままに、文字通り蓋をされたとき、その中身への想像力は遮断される。蓋を外せば、この世界を歩むこともできなくなるのだが。
成定は本展を、建築模型と写真を主なメディウムとして作っている。建築模型からなるパート「核と都市」では、アメリカのマンハッタン計画に際して作られた実験場ハンフォード・サイトの転用についてのアンビルト★2の作品『行方不明者の家』が展示されている。 分厚い金属壁によって放射能漏れを防がれ・塞がれたかつての原子炉──いまだに放射性物質は残るわけだが──の中身を、まったく異なる建築物として想像し直すも、その外郭に対して劇場や映画館として中身を再想像された建築物は、異なる都市に新築される、というのが作品のあらましだ。
ハンフォード・サイトは、福島原発事故の復興に際しての都市モデルにも挙げられているといい、東日本大震災を知るものならば、自ずと福島第1原発を覆う石棺を思い浮かべるだろう。もちろん、チェルノブイリも……。人間の立ち入りを拒む中心となった原発へ異なる想像力を重ね、異なる土地へそれを持ち込むことは、「集団的トラウマからの回復を目指す」ことだ。その地にいない私たちこそが引き受けるべきジオ・トラウマがここ──ハンフォード・サイトや福島のような現場、あるいはこの展示会場──にある。しかしそのためには、宇宙船からの侵略と撃退を夢想する娯楽映画や漫画のように消費されることを、アンビルトは拒まなければいけない。
 成定由香沙「Over My Head・あたまの上で」展示の様子
成定由香沙「Over My Head・あたまの上で」展示の様子
建築模型は、大きな建築物をある縮尺で小さく縮めることで、ひとかたまりとして外から眺めたり、同時には見えない部屋同士を上から覗き込むことができる。私たちは建築物よりも大きくなれる。もちろん窓から覗き込んで部屋の様子を伺うことができるが、逆に内へ入り込むことはできない。この大小の反転した関係のなかでやがて現われる建築物ともども想像することは、建築教育のもたらしたひとつの技術だ。だが、アンビルトの力点は、“このような建築物が現実に存在したらどうだろう? という経験の想像”ではなく、“このような建築物が現実に存在したらどうだろう? と想像する経験”の方にあるはずだ。つまり、アンビルトの模型やドローイングは、元の縮尺に戻される必要がない。いま、この私が想像していること自体が取り上げられている。
そう考えてみると、《行方不明者の家》の模型の重量感が不思議と気になってくる。原子炉を封じる外郭は薄手で半透明のビニールに置き換わり、金色のピンがビニールを中の躯体と固定している。ビニールは空気をその中に含んでいるが、パンパンに張り詰めているわけでも、重力に負けて垂れているわけでもない。この状態が、それぞれの「家」の重さを曖昧にしている。そもそも、大きさを縮めたからといって、重量も同じ比率で縮んでいるわけではない。模型において、重さはその大きさに比して圧倒的に軽くなっている。段ボールを巻いて作られた展示台もまた、重量感を狂わせる。段ボールは、軽さと弱さに比して重いものを支えられる素材でもあるからだ。重さは見てもわからないが確かにあるし、感知はしているのかもしれない。
(後編へ)
★1──赤瀬川原平《宇宙の罐詰》(1964/94)では、本来外側にあるラベルを缶詰の内側に貼って蓋を塞ぎ直す。内外の仕様が反転することで、缶に封じられているのは世界の側になる。あるいは、最短の柵の周長で羊たちを囲む知恵比べで、自分ひとりを囲んだ羊飼いがいた、という話を聞いたことがある。羊飼いの話を、私は学生時代に建築家の中山英之から聞いた。彼は成定の所属研究室の教員で、彼女の個展に際して発行された『不可視の存在として現れるあらゆる将来の形のための』(Tabula Press、2025)に寄稿している。
★2──unbuilt、すなわち建たない建築物を指す。実在しない建築物を総称してアンビルトと呼んでいるが、建築アカデミアにおいては、建てることを前提としないプロジェクトや作品を指すことが多い。それらは社会批評や思考実験の意味合いが強く、なんらかの理由で実現しなかったプロジェクトとは区別される。
観賞日:2025/02/21(金)[成定展]、2025/03/22(土)[坂東展]