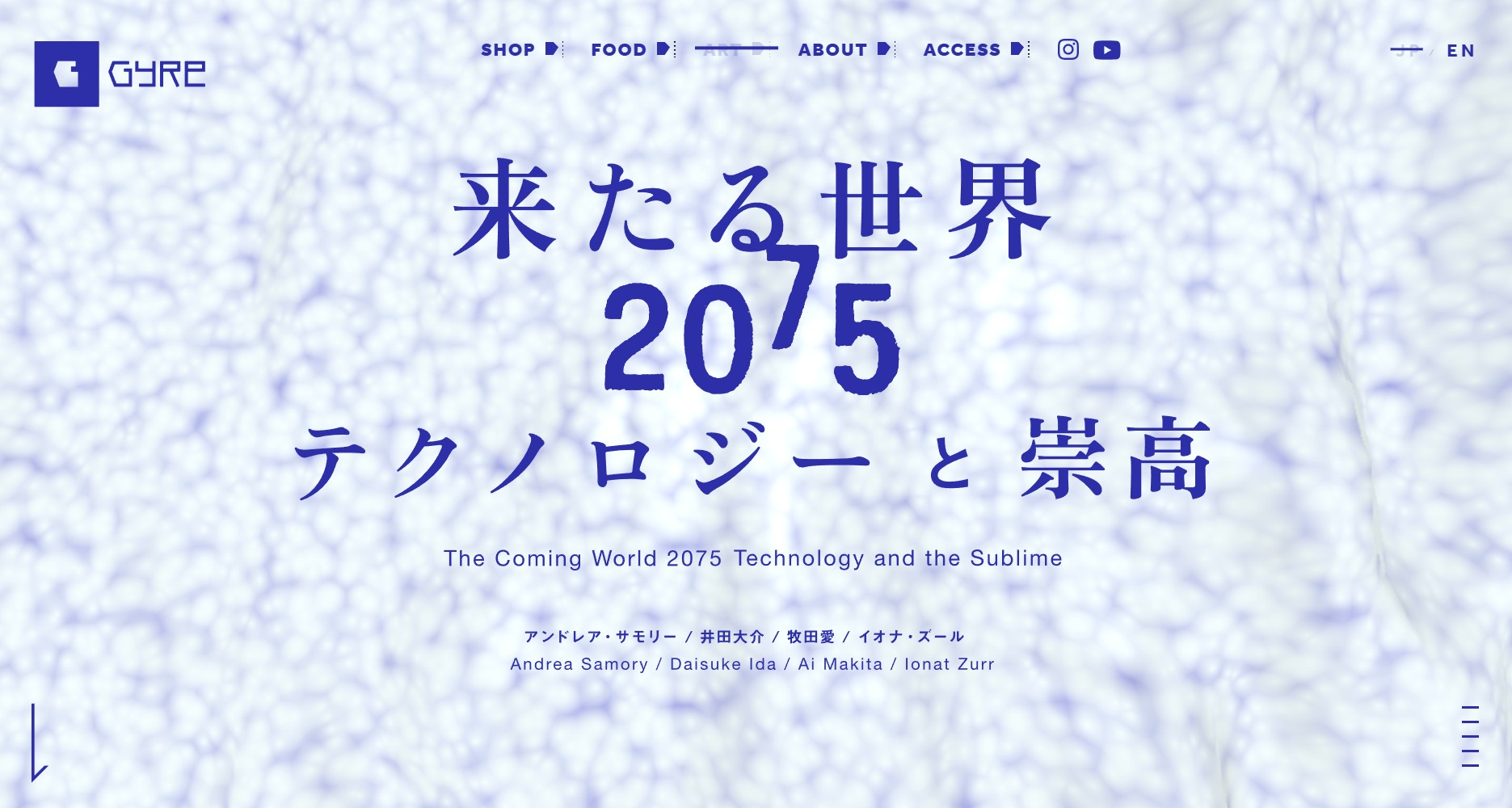
会期:2025/02/11~2025/03/16
会場:GYRE GALLERY[東京都]
公式サイト:https://gyre-omotesando.com/artandgallery/technology-and-the-sublime/
「来たる世界2075──テクノロジーと崇高」は飯田高誉の企画および、高橋洋介のキュレーション・展示統括のもと開催され、アンドレア・サモリー、牧田愛、井田大介、イオナ・ズールの四名の作品が展開された。
まず、本展のテーマである「技術崇高」について見てみよう。これは本展のために用意されたものというよりは、キュレーターの高橋がかねてより提言してきたコンセプトと言っていい。例えば、2019年に高橋はエッセイ「バイオデザイン──人新世における工学的救済」★のなかで、アレクサンドラ・デイジー・ギンズバーグの作品に触れつつ「しかし、ここで重要なのは、超越的な自然が生み出す『崇高』を懐古的に考え直そうとしたことではない。人間が生み出したにも関わらず人間の管理を超えたものに宿る崇高が表象されている点にある。思弁的ディストピアを表象するバイオデザインの多くは、この人工的な崇高を美学として共有している」と述べている。実際、これは2010年代に隆盛したバイオアート、バイオデザイン、スペキュラティブデザインといったものたちに通底するエッセンスであるように思える。では本展は、テクノロジーをめぐるここ十数年の創造的実践の単なるサマリーだと言ってしまっていいのだろうか。
まず指摘できるのは、スペキュラティブデザインに代表される当時のバイオテクノロジーへの着目には、少なからず「従来の生命倫理におけるタブーを意図的に犯すことによって議論を加熱させる」ような、煽情的な手つきがあったということだ。こうした「議論のための(皮肉を前提とした)アート/デザインムーブメント」が落ち着きを見せた2020年代において、改めてテクノロジーの超越性を素朴に検討する視点が回復されたのだと言うことができるかもしれない。
また、高橋によるイントロダクションでも触れられているが、本展の作家たちには「キメラ」というワードが通底している。アンドレア・サモリーはまさに「Chimera」と名付けた作品シリーズを展開しているし、牧田愛の作品は人工と自然を問わないあらゆるモノが混ざり合ったイメージを通じて、飽和した物質文明の怪物的な生命性を描く。また、井田大介の彫刻《Synoptes》におけるグリッチとコラージュを重ね合わせたかのような人体像の変形は、現代の私たちの世界認識がすでに無数の匿名的な視線による「イメージのキメラ」であることを表象しているかに見える。そしてイオナ・ズールの人工子宮プロジェクトも、妊娠・出産を外部化することによって従来の生物像・人間像を編集するという意味で(少々伝統的なバイオアートの手つきではあるが)、このテーマに連なるものと解釈できるだろう。
ここで思い出されるのは、高橋が本展と同じく前身のEYE OF GYREを会場として2018年に開催した「2018年のフランケンシュタイン──バイオアートにみる芸術と科学と社会のいま」である。この展覧会ではメアリー・シェリーによる小説『フランケンシュタイン』に焦点を当てながら、そこで提起された生命とテクノロジーを巡る問いに対する現代的応答として、バイオアートの実践の数々が紹介された。無論、死体を継ぎ剥いでつくられたフランケンシュタインの怪物を広義のキメラであると言うこともできるだろうが、私見ではいささか質的な差異があるように感じられる。フランケンシュタインの怪物は、自らの似姿をつくり出すことに対する人間の欲望を強く想起させる。それはつまり創造主の再演である。そこでは理想的な成果物=自然そっくりの人工物が目指されている。これに対して、キメラはもっとプロセス的であり、そこには最終的な理想像を持たないコラージュの混沌によって満たされている感覚がある。すなわち、理想化された創造から逸脱し、それを相対化し続けるオルタナティブの群こそがキメラである。ゆえにそれらは原理的に怪物的な存在であり続ける。実際、高橋は本展の作品を「抽象的具象」と表現している。断片の異様な具象性の高さと反比例するかのように、全体像は漠としており捉えどころがない。それこそがまさにキメラの質感であり、同時に、本質的には無目的であらざるを得ないテクノロジー発展の似姿でもある。いわば本展は、テクノロジーを通じて既存の物語を語ることを離れ、テクノロジーそのものが発する音──いまだ意味を持たない声──に耳を傾けることを提起しているのだ。
しかし、テクノロジーの捉えどころのない拡大を素朴にまなざすだけでは、充分とは言い難い。先に挙げたように、2000〜2010年代はバイオテクノロジーに限らず、先端技術が世界に与える影響の可能性がアート/デザインの境界領域において広く探索されていた。その中において、スペキュラティブデザインの中心的人物であるアンソニー・ダン&フィオナ・レイビーが2013年に発表した《United Micro Kingdom》は再度検討に値するだろう。これは近未来のイギリスを構成する四つの王国それぞれについて、その社会形態とそこで採用されているテクノロジーを、ポリティカル・コンパスの4類型(右派↔︎左派、伝統主義↔︎自由主義の二軸で描かれる四象限)にもとづいてデザインする作品だった。つまり、確かにテクノロジーは破壊的な影響力を持っているものの、いかなるテクノロジーが発展するのかは、いかなる政治・思想形態が採用されるかに大きく依っていることを指摘したわけである。このように、単に未来の可能性を生成するのではなく、私たちが何を現実として選び取るのかを巡る技術─社会─政治的な問いは継続的に議論され続け、現在ダン&レイビーが提唱する「Designed Realities」概念へとつながっている。こうした、現実におけるテクノロジーを取り巻く複雑な関係性に対して、技術崇高の概念はいかなる新たな視点を加えうるのだろうか。
本展では、ポンピドゥー・センター・メスで展覧会「崇高」を企画したフランスのキュレーター、エレーヌ・ゲナンによるテキストの邦訳「カオスモス 混沌=秩序」が公開されている。このなかでゲナンは、崇高概念の歴史的変化を指摘している。第一に、かつて崇高は世界の破滅を傍観する人々のまなざしによって特徴付けられていたが、時代が下るにつれてそこに当事者意識が入り込んできていること、そして第二に、崇高と紐づく厄災の概念のなかに人為的な事象が含まれつつあること。これらは言うまでもなく、本展の問題意識へと直結するものだろう。そもそも荒れ狂う自然を静かに観測できるような場所をつくること自体、テクノロジーの営みがもたらした成果なのであり、この観測所=人工的な領域が際限なく拡大し世界を覆い尽くした結果として、現在の状況が生まれていると言っていい。私たちは傍観者から当事者になったというよりも、もはやこの世界に傍観できる外部など存在しなくなったのだ。本展の作品たちはいずれも、確固たるテクノロジー時代の美学の片鱗を感じさせるものであった。しかしそれはどことなく、商業施設内のギャラリースペースにおいて許容可能な刺激に調整された「飼い慣らされた崇高」であるようにも見えた。それは、先に述べたような現実の「外部のなさ」にもとづく必然なのか、それとももっと質的に異なる崇高がそこには潜んでいるのか──そうしたことを立ち止まって考えるきっかけこそ、テクノロジーに追い立てられ続ける私たちがもっとも求めているものであろう。
鑑賞日:2025/02/27(木)
★──川崎和也監修・編集『SPECULATIONS──人間中心主義のデザインをこえて』所収、ビー・エヌ・エヌ新社、2019







