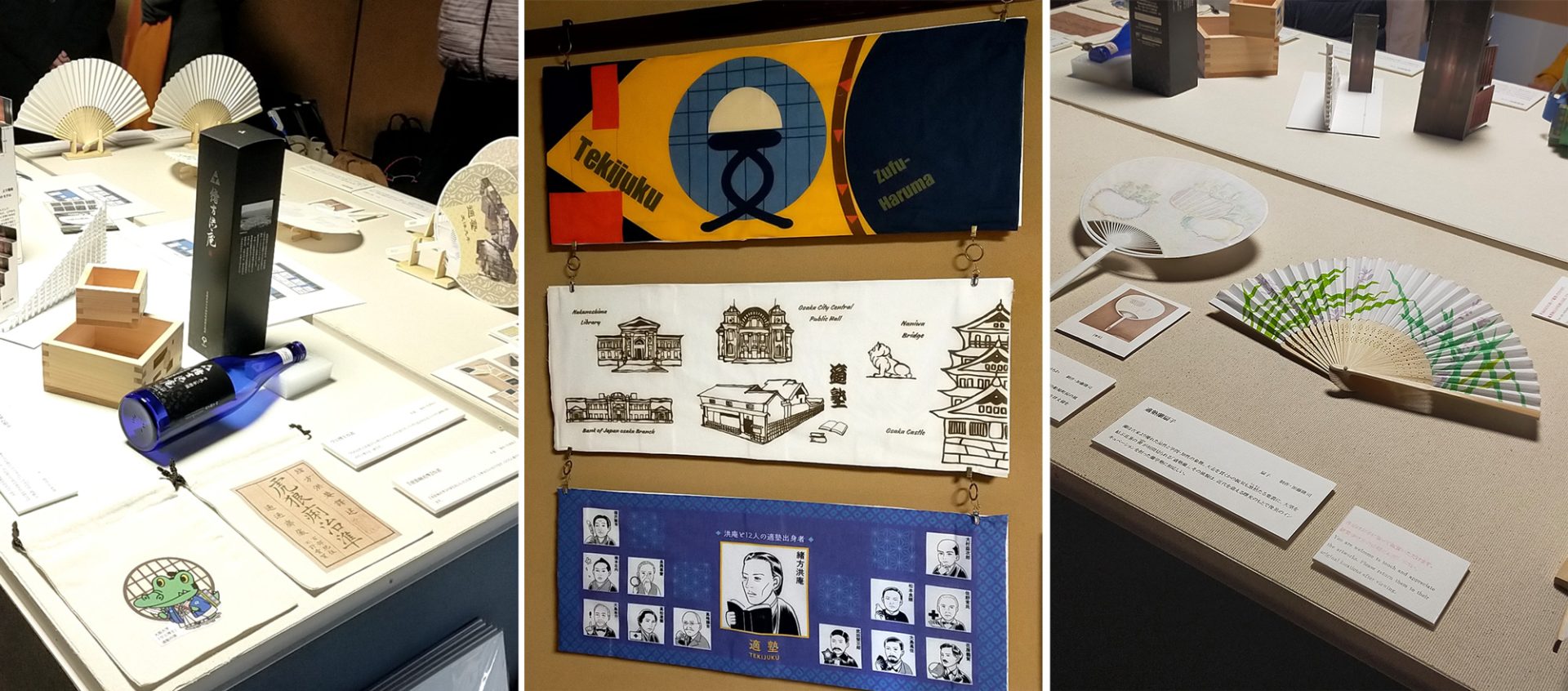五十嵐太郎さんの「建築遊歩」に2回連続で名前が登場したI.M.ペイ。「05──香港と台湾の建築展」でのM+での回顧展、「06──中東の文化施設をまわる」のドバイの《イスラム美術館》が取り上げられました。私が実際にいままでに見たことあるのはルーヴルのピラミッドくらい。I.M.ペイが設計したミュージアムは日本にもあります。「すごい美術館だ」「でも車でないと行けない」と聞いていたMIHO MUSEUMに行ってみようと思い立ちました。調べてみたら、公共交通機関で行けます、行けます。JR石山駅からバスで50分。1時間に1本しかないので、便利とは言い難いですが、関西からだと、ゴールデンウィークの1日をかけていくのにはちょうどいいかもしれません。
石山駅を出たバスは琵琶湖から流れる瀬田川の脇を抜けて、そして、ザ・里山というような風景のなかに入っていきます。やがて、バスは右に左に激しく揺れながら、新緑の山のなかを走っていきます。中国人らしき青年と、小学生くらいの女の子を含むフランス語を話す家族連れ、アジアのどこかの国から来た女性の二人組と、ささやかなインバウンドの乗り合わせ。
しかし、それは途中の道のりだけで、いざ、ミュージアムに着いたら、日本人の高齢者のグループや家族連れ、国内外からのいかにもな現代建築ファンを含め、多種多様な人たちがよくもこんな山奥に集まったと驚くくらいに賑わっていました。
有名なのは駐車場から入ったエントランスのエリアからミュージアムへと続くアプローチ。鏡面のように輝くトンネルを抜けた先に見える眩い緑。そんな写真を見たことがある読者もいらっしゃるのでは。オープンしたのは1997年なのに、まったく古びた感じがなく、それでいてギラギラしていない、静謐な輝きと申しましょうか。床面にはややクッションが効いたマットが敷き詰めてあり、これが消音効果をもたらしているのかもしれません。トンネルはややカーブを描いていて、トンネルの先にある木々の緑が反射して、その先の光景をじょじょに映し出し、期待させ、そしてやがて自然のなかの美術館を発見させて驚かせるという演出です。

正直にいうと、よく写真で見る建物の屋根は日本の藁葺き屋根をモチーフにした感じで、ルーヴルのピラミッドのシャープなイメージとはつながりませんでした。しかし、一歩建物のなかに入ると、圧倒的なキレのよい空間で、光と自然と技術の融合を見ることができます。
 建物のなかでファイカスの木が大きく育っています。
建物のなかでファイカスの木が大きく育っています。
 廊下の窓からの風景。遠くに《ベル・タワー》が見えます。100万2000平方メートルという広大な敷地と美術館の管理運営は宗教団体によるものです。
廊下の窓からの風景。遠くに《ベル・タワー》が見えます。100万2000平方メートルという広大な敷地と美術館の管理運営は宗教団体によるものです。
驚いたのは、壁面に使われていた石でした。壁面だけでなく床も、すみずみの細部まで、ぜんぶこの石が使われていました。どんだけの量!!! 帰って調べましたら、フランス産のライムストーン、マニドリという石で、ロマネコンティの原料になるブドウ畑の地下13mのところにあるのだそう。どんだけの量を持ってきたんだ!!!
この石のもつ柔らかく温かい印象がこの建物全体のイメージをつくっているんですね。ミュージアムの刊行物『Shangri-La』によると、ルーヴルのレセプションホールにも同じ石が使われているそうです。トンネルの手前にもまたこの石が使われていたことに、帰り道で気づきました。

復路の電気自動車の停留所になっているロータリー。自然光と人工照明があわさって絶妙な光の空間に。ここでもマニドリが一面に使用されています。
個々のコレクションとその展示プランが先にあって、展示室が設計されているので、展示室の広さと天井の高さ、個々の作品および鑑賞者への照明の配慮は完璧です。そして、いうまでもなくコレクションは一流品で、企画展「うつくしきかな─平安の美と王朝文化へのあこがれ─」でやっていた古筆の展示も見事なものでした。コレクションも美術館の建築も自然環境も丁寧に維持されています。
館内のやや奥まった一室で、建築に関するドキュメンタリー映像を上映しているシアタールームがあります。そこで現場であれこれ指示を出しているI.M.ペイの姿も見ることができます。五十嵐さんの中東のミュージアム巡りには及びませんが、それでもじゅうぶんにゴージャスな気分を味わうことができました。(f)