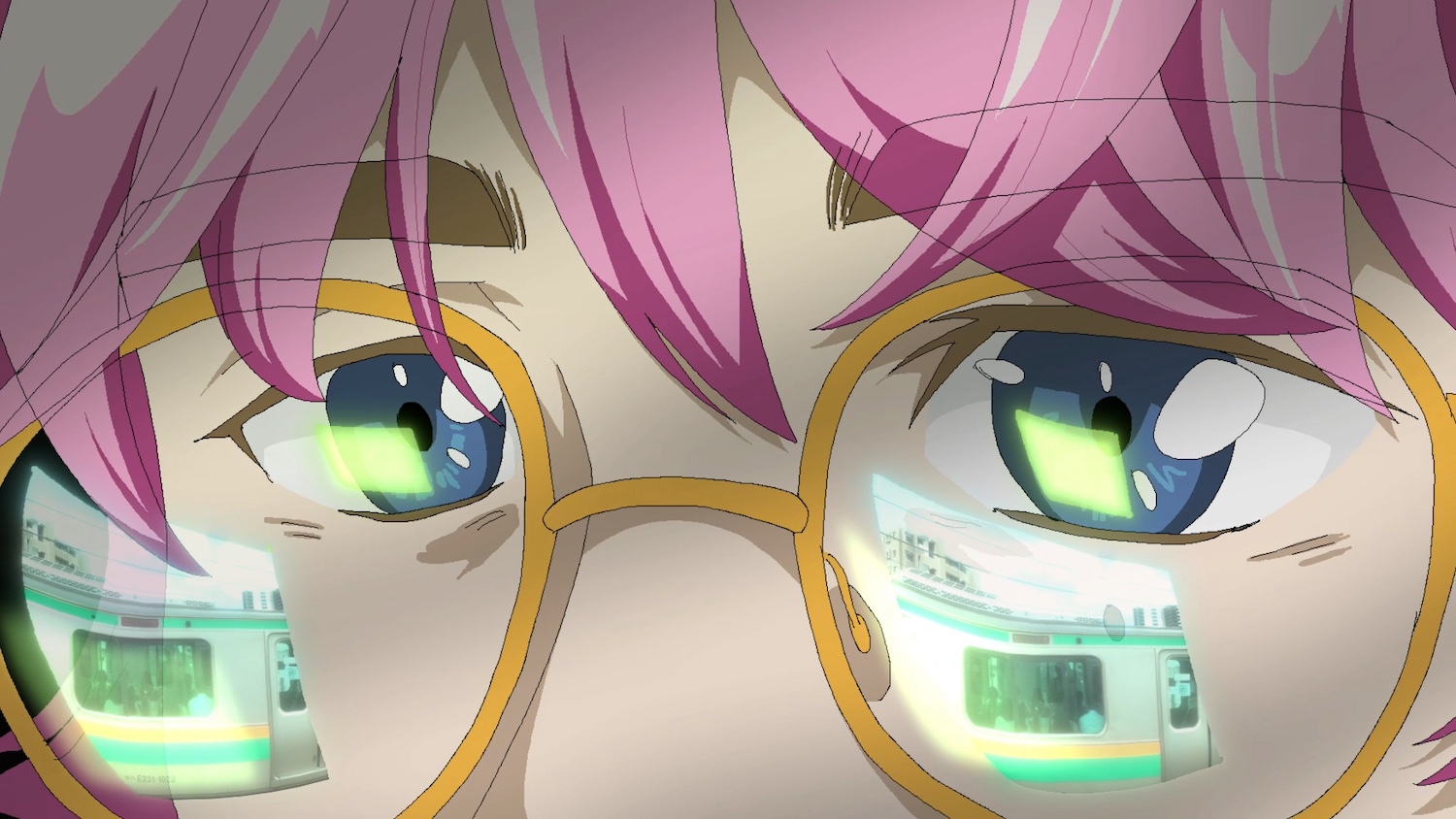Nicolas Winding Refn and Hideo Kojima / Photo Yuji Watanabe
“Satellites” by Nicolas Winding Refn with Hideo Kojima / Prada Aoyama Tokyo / 18.4 – 25.8.2025
会期:2025/04/18~2025/08/25
会場:Prada Tokyo Aoyama[東京都]
公式サイト:https://www.prada.com/jp/ja/pradasphere/special-projects/2025/satellites-prada-aoyama.html
(前編より)
モニタに映し出されるレフンと小島の姿は正面からのバストアップで、青白いオーラを纏うように発光しつつ、筐体の暗がりに浮かび上がっている。レフンの作品に明るい者であれば、彼がこうした構図を好んで用いてきたことを思い出せるだろう。ひとつには『ブロンソン』(2008)において、ブロンソンが闇のなかで半生を振り返りながら独白するシークエンス。あるいは『ネオン・デーモン』(2016)において、照明を落としたスタジオのなか、ジェシー(エル・ファニング)が全身に金粉を塗られるショット。もうひとつには『オンリー・ゴッド』(2013)において、ジュリアンが真っ赤な光に満たされた空間をさまよい、暗闇へと手を伸ばすイメージ。
ひとつの文献を参照してみるなら、山下研は論考「狂気の球体──レフン的空間と『分身』の臨界点」において、レフン作品に頻出するこうした非場所的な内面世界の表現を「レフン的空間」と名指していた。しかし、今回の展示においてレフンと小島の背景に広がるのは漆黒や赤ではなく、ネイビーがかった奥行きである。半透明のディスプレイを通して、2人の背後には筐体の内部空間がぼんやりと浮かび上がっており、その奥ではLEDがグリーンやブルーに明滅しているのだ。これはもちろん、2人の映像をホログラフィックに浮き立たせるための視覚効果なのだが、その結果として私たちは、彼らの背後を意識せざるを得なくなる──つまり、撮影されることのなかったバックショットを。
ここで、小島のクリエイションを思い出してみよう。小島の代表作である「メタルギア」シリーズや「デス・ストランディング」シリーズは三人称視点ゲームであり、そこで画面に映し出されているのはプレイヤーキャラクターの背中であった。つまりディスプレイに浮かぶイメージがあり、映画はそれを前方からまなざし、ゲームは後方からまなざす。これに関して、レフンは映画とゲームの関係性について問われた際に、物語と体験の観点においてこれらは正反対の印象を与えると述べた。「映画は過去を感じ、ゲームは未来を感じる。そして時として、ゲームは過去の一部のように、映画は未来の一部のように感じられる」のだと。
では、映画とゲームを合わせ鏡にしたような本展の体験は時間軸のどこを漂うのだろうか──レフンによるフロントショットと小島によるバックショットによるフォトグラメトリとして仮構される身体。それこそが衛星が取り巻く主星、あるいは探査対象なのだと言うこともできるかもしれない。

“Satellites” by Nicolas Winding Refn with Hideo Kojima / Prada Aoyama Tokyo / 18.4 – 25.8.2025 / Photo Yasuhiro Takagi / Courtesy Prada

“Satellites” by Nicolas Winding Refn with Hideo Kojima / Prada Aoyama Tokyo / 18.4 – 25.8.2025 / Photo Yasuhiro Takagi / Courtesy Prada
最後に少し余談を付け足しておこう。アフガニスタン系アメリカ人作家のジャミル・ジャン・コチャイは「きみはメタルギアソリッドV:ファントムペインをプレイする」という短編を書いている。これはタイトルどおり、主人公が『メタルギアソリッドV:ファントムペイン』をプレイするうちに、ゲームと現実の境界が混乱していくという筋書きを持つ。物語内の現実では、1980年代のアフガニスタンへのソ連軍侵攻によって主人公の父は拷問され、叔父は殺された。主人公は同じく1980年代のアフガニスタンを舞台とした『メタルギアソリッドV:ファントムペイン』をプレイしながら、ゲーム世界内で父と叔父を救出しようと試みる。これはまさしく、過去の一部でありながら、(ありえたかもしれない)未来を感じさせるものとしてのゲームを描き出している。物語は同作を特徴づける二人称の語りによって、次のように閉じられていく。「(前略)それでも進み続けなくてはならないと思い、暗闇へと潜り続けて完全に真っ暗になると、きみの目の前にはテレビのスクリーンに映るきみ自身の姿が見えてきて、まるで映像の中のキャラクターたちがきみの内側を旅して、体の中へと入り込んでいくようなのだ」。
本展の薄暗いディスプレイにはそれを覗き込む私たちの顔が映り、レフンや小島の映像がその上に重ね合わされる。あるいは向かい合わせになったディスプレイでは、レフンと小島の顔がそれぞれに重ね合わされる。一体、誰が誰と対話をしているのか。誰が映像を撮影し、誰がキャラクターをプレイしているのか──もちろん本展の体験は、それがわからなくなるほどの催眠的なスペクタクルではない。ただいっとき、衛星たちの影が互いをかすめたというだけのことに過ぎず、そしてそれだけで十分だった。
鑑賞日:2025/06/14(土)