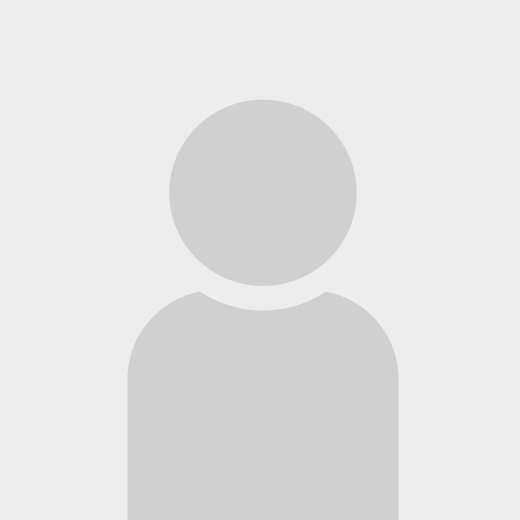会期:2025/06/06~2025/06/09
会場:大内木工所跡地[大阪府]
公式サイト:https://kondaba.tumblr.com/next#play
19世紀末のイプセンの戯曲を、現代において上演する意義はどこにあるのか。上演を介して、戯曲の再解釈を立ち上げることはどのように可能か。本公演は、生身の俳優が人形を操る「人形劇」という枠組みを巧みに活用し、かつて木工所だった廃墟のような木造建築に、人形、朗読の声、光と影、音響、遊び心に満ちた美術が濃密に交差することで、こうした問いに応える秀逸な試みだった。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
『棟梁ソルネス』は、『人形の家』(1879)で知られるイプセンの晩年の戯曲である(出版は1892年、初演は翌年)★。建築家として成功したソルネスの「家」を舞台に、夫婦関係、恋愛、出世欲と世代交代、近代的自己としての芸術家像が交わる会話劇だが、多義性や象徴性をはらんだ寓話的性格が強く、どう演出するかが大きく問われる作品である。
ソルネスは、世間的には建築家として成功を収めた男だが、独占欲や支配欲が強い一方、自分の成功の代償として払われた犠牲に対して良心の呵責に苛まれ、才気ある若者に追い落とされることに怯える、世俗的な人物である。ソルネスの「成功」と「幸運」は、12、3年前、妻アリーネの古い生家が火事で焼けた「不幸」から始まった。貧しい田舎町出身で元々は教会建築を手掛けていたソルネスだったが、焼け跡と広大な庭の跡地に建てた分譲住宅の設計が高く評価され、現在は住宅設計の第一人者となり、設計を依頼する夫婦が後を絶たない。だが、火事で焼け出されたショックで母乳が出なくなったアリーネは、それでも生後まもない双子の男児を育てようと無理をして死なせてしまった。加えて(後半で明かされるが)、大切にしていた人形も燃えたことから、心身を病み、夫婦関係も冷え切っている。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
成功と引き換えに支払った代償に「報復」されることに怯えるソルネスは、2方向から良心の呵責に苛まれている。1点目は、かつて自分の師を名声からつき落として出世したように、その師の息子ラグナールによって同様に自分も追い落とされるのではないかという恐怖。ソルネスは、設計事務所でラグナールを弟子として雇うが、彼の才能の芽を摘み、自分の元に縛り付けて独立させまいとする。ラグナールへの支配と束縛はまた、彼の婚約者で事務員のカイヤを「自分の手元に置いておく」執着心のためでもある。また、建築家としての出世と引き換えに、「家の火事」という象徴的な出来事によって子どもと妻の心身の健康を失ったソルネスは、妻に負い目を感じ、「明るく幸福な家庭生活」の断念を痛感している。代わりにソルネスが慰めを求めるのが、ほのめかされるカイヤとの肉体関係だ。ラグナールが独立してカイヤと結婚することを阻止するため、ソルネスは、この若いカップルを仕事面と性的関係の両面で支配下に置き続ける。
だが、ソルネスの心の中には、「やがて若ものがやってきて戸を叩く」「場所をゆずれ、場所を! 場所を!」という声が響いて脅かす。その予感は当たった──ただし、戸を叩いて現われたのは、ヒルデという若い女性だった。ヒルデは、10年前にソルネスが交わした「ある約束」を果たしてもらうために訪れたと言うが、ソルネスにはその記憶が曖昧だ。10年前、ある村で教会の塔をソルネスが建て、祝賀会で、塔の頂上に登って花輪をかけたこと。その後、ヒルデの家に招かれたソルネスは、誰もいない隙に13歳のヒルデを抱いて何度もキスをしたこと。「10年後にまた来て、王国を一つくれる」と約束したこと。軽い気持ちだったソルネスは「約束」をしたことも「日付」も定かではないが、10年後の同じ日に現われたヒルデは「約束の期限は切れた」「王国を出してちょうだい棟梁! テーブルの上に、さあ王国を!」と要求する。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
ヒルデの出現に翻弄されつつも、自由奔放で謎めいたヒルデに魅せられていくソルネス。性的な関心の対象をカイヤからヒルデに移したソルネスは、あっさりとカイヤを解雇して手放し、ラグナールの独立も認める。そして、「塔」のついた自分自身の新しい家を建てたばかりのソルネスに対し、ヒルデは2つの要求をする。10年前と同様に、新築の家の高い塔の頂上に登り、花輪をかける勇姿を見せてほしいこと。「約束された王国」のために、「空中のお城」を建ててほしいこと。だがソルネスは、「自分の建てた高さにも登ることができない」ほど、めまい持ちだ。しかし、ヒルデの賛美の獲得と、(ソルネスの臆病さを見抜いている)若ものたちに自分の偉大さを見せつけるため、「塔登り」を決行する。不安と緊張と高揚感に包まれた人々が見つめるなか、塔を登っていくソルネス。「棟梁ソルネス、ばんざあい!」というヒルデの歓声の直後、塔の頂上に立った彼の姿は消え、落下した。
本公演の会場は、かつて木工所を営んでいた空き家であり、「家」がキーワードとなる『棟梁ソルネス』にぴったりの空間だ。むき出しの土間、土と木材の匂い、土間の奥に掘られた深い穴。その向こうに中庭のような空間があり、さらに奥にはガラス窓の別棟がある。「大内木工所跡地を演劇の遊び場にする」というキャッチフレーズを掲げた本公演は、空間の奥行きをうまく活用するとともに、壁に古今東西の建築図面を貼り、天井や壁から仕掛けが飛び出すなど、新たに手を加えて空間をフルに遊び倒した。
演出は、維新派に所属していた俳優の石原菜々子と金子仁司によるユニット、kondaba。彼ら自身の出演と、客演でソルネスを演じた三田村啓示に加え、隅っこ人形劇団ニッチが大きな貢献を果たした。お団子ヘアと広がるスカートがプリンセスのようなヒルデ、幽霊のように蒼白な顔と修道女のような黒い服のアリーネ、白い鳥と人間が合体したようなソルネス、アリーネの往診に来る、ヨーロッパの古い絵本に出てくるような医者。それぞれ魅力的な造形の人形を、工務店のような衣装の俳優たちが操り、声と命を吹き込む。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
あえて「台本」を手に発話する俳優たちは、これが「寓話」であることを示す。10年前にヒルデと交わした「約束」と、出世と引き換えに妻の幸福を奪った火事という「過去」の幻影に何重にも怯えるソルネスの心象風景は、幻想的な影絵の人形劇で表現される。父親の家という「檻」から野鳥のように飛び出した自由奔放なヒルデと、「神に仕えることを辞めた自由な芸術家」であるソルネスは、共鳴する部分がありつつも、「私に何度もキスをしてくれた」と語るヒルデの人形は、鳥のくちばしのようなソルネス人形に激しく突かれ、これが一方的な性暴力であることを示唆する。また、「義務」が口癖で、「良き妻・母親であるべき」というジェンダー規範に縛られているアリーネの人形は、中庭の奥の暗い別棟のガラス窓の中に閉じ込められ、そこから出られる中盤以降も、スカートの裾かショールのように長い布で繋がれたままであり、「家庭への束縛」を暗示する。俳優が腕に抱いたアリーネ自身の人形は、赤子や、火事で失われた人形のようにも見えてくる。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
そして、本公演の演出の最大の仕掛けが、人形の操り手と「声」の分離である。ヒルデ人形は、カイヤ役の俳優によって楽しげにくるくると操られる一方で、ヒルデの「声」を朗読する俳優は、下手側の手前に置かれた梯子に座ったまま、動くことができず、ソルネスに対する異常な執着心にヒルデ自身も縛られていることを示す。だが、10年前に約束した「王国」の要求、そして「空中のお城」とはいったい何を指すのか? 後編では、カイヤ役の俳優が終始、ほかの人形の操り手である透明な「黒子」であったこと、そしてラストで果たす重要な役割という演出の企図から示唆を受け、現代における『棟梁ソルネス』の再解釈の可能性について、原作戯曲の解像度を上げて分析する。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
(後編は7月18日公開予定)
★──本稿の執筆にあたり、上演と同様に下記の翻訳戯曲を参照した。毛利三彌訳『イプセン現代劇上演台本集』(論創社、2014)
鑑賞日:2025/06/09(月)