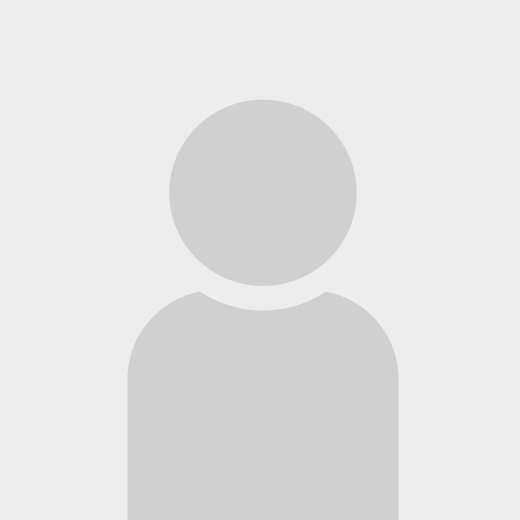会期:2025/06/06~2025/06/09
会場:大内木工所跡地[大阪府]
公式サイト:https://kondaba.tumblr.com/next#play
前編であらすじを紹介した『棟梁ソルネス』は、複数の軸線が緻密に書き込まれた戯曲である。まず、作中には3つの「家」が象徴的に登場する。火事で焼けた妻アリーネの生家、ソルネス夫妻の現在の家、そして完成間近の新築の家。火事の前は、アリーネが母親から引き継いだ古い家にソルネス夫妻が住み、外観とは裏腹に「かなり気持ちのいい住みやすい家だった」と語られる。火事で家と双子を亡くし、夫婦仲も冷え切ったソルネスだが、現在の家には「空っぽの子ども部屋」が3つある。そして、焼け跡の一部に再び建てられる家にも、奇妙なことに、子ども部屋が3つある。新築の家とは、「居心地がよく、理想的な数の子どもがいる模範的な家庭」というソルネス自身が失った幻想の「建て直し」である。本作のキーである「家」とは、前世代から継承した遺産であり、理想や規範に合わせて何度でも再建されるべき、家父長制の象徴だ。そのなかでは、アリーネは「模範的な妻・母親」であるべきことを強いられる一方で、夫・男性であるソルネスは、婚姻関係の内/外の境界を自由に行き来し、若いカイヤと恋愛することができる。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
2つめの軸線は、自分自身が師を追い落としたように、若い世代に場所を奪われるという世代交代だ。3つめの軸線が、「家」/「教会の塔」というメタファーの対比から導かれる、近代的な芸術家という自画像である。ここにはさらに、2つの側面がある。①「神に仕えるしもべ」という前近代的なあり方から解放された、「自由な芸術家」という近代的自我。前編でみたように、住宅設計の専門家になる以前のソルネスは、敬虔な信仰心をもち、教会建築を手がけていた。だが、10年前にヒルデの村の教会の塔を建て、頂上に花輪をかけたとき、ソルネスはそれまで仕えていた神に宣言する。「聞きたまえ偉大なる主よ。今日から私も自由な棟梁になる。自分自身の世界で」と。それは、「それまでどうしても高いところに登ることができなかった」ソルネスが、「不可能なこと」を成し遂げた瞬間だった。つまり、それまで「創造主」として君臨していた神の座に並び立ち、神から解放され、自分自身の世界を創造する近代的芸術家としての勝利を宣言したことを意味する。だがその代償として、ソルネスは、「他人が幸せに暮らす家を建てるために、自らの家を断念せねばならなかった」という後悔に蝕まれている。これは、②芸術至上主義か世俗的幸福かという近代的な芸術家の苦悩を表わす。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
一方で、「塔」は、芸術の自律性をめぐる、両義的なメタファーでもある。実用的な機能をもつ「家」と異なり、「高さ」だけを追求する「塔」は、機能や実用性といった世俗を超越した近代以降の自律的な芸術の象徴でもあるからだ。従って、「新築の家に備わった高い塔」に登り、再び頂上に花輪をかける行為とは、「生涯をかけた大仕事の完成」であり、同時に「芸術家は自らの死をもって仕事を完遂させる」というナルシシズムでもある。
こうした軸線で素直に(?)考えると、ソルネスが交わした「10年後の約束」とは「結婚」の比喩であり、「家」と対比される「空中のお城」とは、若く魅力的な女性との「婚姻外の性的関係」を意味するという解釈がまずは浮かぶ。だが、以上の考察は、あくまで芸術家=男性どうしが競う世代交代や神を超克した近代的自我という前提に基づくものである。また、よく知らない男にいきなりキスされた13歳の少女が、10年間自分のことを想い続け、既婚であると知りながら愛を求めて会いに来たという見方は、ソルネスつまり男性にとってあまりに都合の良すぎる解釈ではないか? 以下では、カイヤ役の俳優と「塔」をめぐる本公演の演出に着目し、イプセンの戯曲が別の解釈を読み込める潜在力をもっていることを掘り下げる。
本公演の演出のポイントは、ヒルデ人形が常にカイヤ役の俳優によって操られる点にある。妻の代替物として事務員のカイヤと肉体関係にあったソルネスは、ヒルデが登場した途端、性的関心をヒルデに移し、カイヤを理由なく解雇する。だが、カイヤには「抗議の台詞」すら与えられず、終盤では作中から完全に姿を消す。原作のカイヤは、ソルネス=男性にとって都合の良い交換可能な存在であり、カイヤ役の俳優が「ヒルデ人形」を操る演出は、「性的対象となる若い女性」の交換可能性をまさに示す。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
一方、本公演の終盤では、ソルネスの弟子のラグナール役や、ソルネスの師/医者の兼ね役を担っていた男性の俳優たちが、黙々と積み木を積み上げ、「新築の家の高い塔」を築いていく。「芸術家の偉大な仕事」も、それを書き記す「歴史」の積み重ねも、男性の手によって築かれるものだ──こうした男性中心主義を突き崩すように、ラストシーンでは、「カイヤ役/ヒルデ人形の操り手を担っていた俳優」が唐突に現われて、積み木の塔を一撃で崩す。立ち込める土ぼこり。それまで「黒子」として透明化され、原作の終盤では「不在」にされたカイヤが、「生身の人間」として現われ、his-storyの象徴としての「積み木の塔」を突き崩し、その脆さを見せつける、鮮やかな演出だ。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]

[撮影:中谷利明]
『人形の家』と比べて、日本での知名度も上演回数も少ない『棟梁ソルネス』だが、本公演を通して、その現代的な意義を認識することができた。「やがて若ものがやってきて戸を叩く」「場所をゆずれ、場所を! 場所を!」というソルネスを脅かす予感とは何か。「若い男性に追い落とされる世代交代」を周到にミスリードさせておき、意外にも「若く魅力的な女性」ヒルデがやってきて誘惑する……という展開としてまずは読めるが、これはあくまでソルネス=男性にとって都合の良い見方であり、まったく正反対の解釈も可能だ。「場所をゆずれ、場所を!」と戸を叩く若ものとは、19世紀末のノルウェーで、男女同権を主張するフェミニストの謂いではないか。「規範的な妻・母親に求められるケア役割」に囚われているアリーネと対照的に、ヒルデは、『人形の家』で夫の庇護から飛び出すノーラのように、父親の管理する「檻」としての家から飛び出してきたと語る。ヒルデとは、「『人形の家』では描かれなかったその後のノーラ」、もしくは「家父長制の支配者である父親の庇護から脱出し、規範的な妻となる前にそれを拒んだ、一世代後のノーラの分身」である。こうした解釈の裏付けとして、イプセンは「君も新しい旗を立ててやってきた」というソルネスの台詞をヒルデに対して言わせている。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
従って、ヒルデが要求する「王国」とは、女性が自分自身の王国の支配者となる、自己決定権の謂いである。さらに、「10年後に再会して、王国をあげる」というソルネスの約束が、未成年に対する同意のない性暴力と表裏一体であり、ヒルデは「性被害の告発者」として過去から現われたことも重要だ。「10年」という約束の期限は、「自分の気持ちや同意など一切関係なく、都合の良いモノとして扱われる性被害」であったことをヒルデ自身が自覚し、告発できるまでにかかった
だからこそ、「空中のお城」について2人が連ねる台詞には、根本的な食い違いが生じる。「私の素晴らしい空中のお城!」と言うヒルデに対し、ソルネスは「頑丈な土台の上に建つ」と繰り返す。ヒルデのビジョンに浮かぶ「空中のお城」とは、「法に保護された婚姻関係という、男性による性の支配構造」それ自体の瓦解だが、「家=家父長制という頑丈な土台」をまったく疑わず、家父長制の支配者であること自体に無自覚な旧世代の男性であるソルネスには、そうした「空中のお城」を建てることなど、もとより不可能なのだ。本公演では、土間に深く掘られた穴つまり「堅固な基礎」の上に「積み木の塔」が建てられるが、塔の崩壊は、それが「空虚な穴」であったことをさらけ出す。
従って、「棟梁ソルネス、ばんざあい!」というラストのヒルデの歓声は、彼の偉業と勇気を褒めたたえるものではなく、「無自覚な性加害者であり、家父長制の支配者である男性の権威の失墜」に快哉を叫ぶ、まったく正反対のものとして立ち上がるのだ。
ただし、「空中のお城」という表現には、「実現不可能なものの象徴」というイプセンの揶揄も読み取れる余地がある。現代の日本は、19世紀末のノルウェーと、どれだけの違いがあるだろうか。「古典」といわれる作品を再び読むことの意義は尽きない。
鑑賞日:2025/06/09(月)