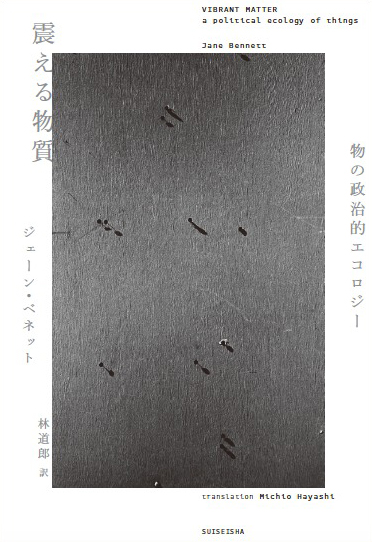テック産業批判としてのUI/UX論?
先日、「30年後のウェブメディアを構想する」と題された座談会に編集者として同席する機会を得ました。これは弊サイトの30周年記念企画の一環で行なわれた座談会であり、きりとりめでる氏が企画したものです。ウェブディレクターやグラフィックデザイナー、写真家、UI/UX研究者といった専門家たちが参加したこの会で、私は裏方の人間として聞いていましたが、その議論を通じて感じたことを、ここに記しておきたいと思います。なお、座談会記事の本体は来週公開予定ですので、もう少々お待ちいただければと思います。
座談会では多様な論点が展開されたものの、ひとつのありうる切り取り方として、つぎのような要約が可能そうです。すなわち、ビッグテックの圏域であるプラットフォーム資本主義から、いかに距離を取ってウェブメディアを考えるか? というものです。
かつて、初期インターネットには人間の知性を拡張するという理念がありました。ヴァネヴァー・ブッシュのMemex、アラン・ケイのダイナブック構想、テッド・ネルソンのザナドゥ計画(Project Xanadu)などの歴史的な構想に、それは体現されています。人々がコンピューターを利用するようになれば、人類の知性は発展していくと信じられていたのです。もちろん部分的にそれらは実現しているかもしれません。でも、子どもたちがスマートフォンを所有する時代にあっても、現実はいささか厄介な状態にありそうです。インターネットを見渡していると、テック産業がデバイスを販売し、アテンション(注意)を稼ぎ、個人情報を吸い上げることの弊害のほうに目が向きます。
こうした現状を批判するジャーナリズムは存在しています。ところが、今回の座談会でご一緒したみなさんのように、現場で制作を行なっている人たちの知見によっても、ジャーナリスティックな批判を鍛えることはできそうだ、という所感を私は持ちました。つまり、アートやデザインの現場知を応用して、テック産業を批判的に検討するような仕事が可能そうです。こうしたものの一例ですが、Amazon Primeを解約するための手続きがUIの面で煩雑化されており、それが「ダークパターン」として批判の対象になったことがありました。私はここでこのような事例を想定しています。
以下では、私なりにテック産業批判とデザイン論との関連についてケーススタディを示してみます。
Project Suncatcherに見る惑星規模のコンピュテーション
じつは、日常的なUI/UXの問題(ミクロなスケール)と、ビッグテックが追求する技術的な野心(マクロなスケール)との間には、のっぴきならない連続性があります。アテンションを稼ぎ、個人情報を吸い上げるという営みの裏には、計算基盤を駆動させるための惑星規模の開発があるわけです──巨大なデータセンターの建設や排熱の問題は、そのわかりやすい例です。そして、Google社内では、まさにこの惑星規模の計算の領域を探求する「Project Suncatcher」が実行されています。余談ですが、今日、人類全体の未来を考える主体は、アメリカのIT産業に従事するオピニオンリーダーたちへと移行している傾向がありますね。(20世紀に建築家が担っていたような仕事、と言ってみてもいいかもしれません。)ジェフ・ベゾス氏は月を、イーロン・マスク氏は火星を目指していることはその象徴です。
GoogleのProject Suncatcherは、宇宙で機械学習コンピューティングを大規模に展開することを目指すムーンショット的なプロジェクトです。この構想の背景には、太陽が究極のエネルギー源であり、適切な軌道ではソーラーパネルが地球上の8倍もの生産性を持ち、ほぼ継続的に発電できるため、将来的に宇宙がAIコンピューティングを拡大する最良の場所になる可能性があるという見通しがあります。
Project Suncatcherのような惑星規模のコンピュテーションが現実味を帯びるなかで、私たちは技術に対する新たな哲学的枠組みを必要としているようです。その補助線として利用できそうなのが、ベンジャミン・ブラットン氏の思想です。じつは去る10月に彼が来日し、イベントでキーノートスピーチを行なっていました。
2025年10月に開催された「Antikythera Tokyo」での彼のキーノート「Convergent Artificialization: Life, Intelligence, Planet」では、「人工的なものも進化する」という進化論的視点が示されていました。ブラットン氏は、「人類史が技術史の一部だとしたら?」という挑発的な問いを投げかけます。テクノロジーはツールではなく、複雑性に向けた構成要素の「足場(スキャフォールド)」であり、文字通り適応と外適応を経て進化していく、とされます。この思想によれば、テクノロジーは次々と複雑性への足場を築き、その進化の過程で人間の営みすらも技術の進化にとって利用される側面がある、というわけです。
ブラットン氏の思想が示すのは、テクノロジーと生命の進化に共振関係を見るという大きな流れであり、その中で人間の意図やコントロールが限定的になるという認識でしょう。
 「Antikythera Tokyo」でのベンジャミン・ブラットン氏のキーノートスピーチ[撮影:artscape編集部]
「Antikythera Tokyo」でのベンジャミン・ブラットン氏のキーノートスピーチ[撮影:artscape編集部]
ポストヒューマニズムデザイン
この「人間のコントロールの限定性」は、近年の脱人間中心的なデザイン理論とも響き合うところがあります。ロン・ワッカリー氏の著書『ポストヒューマニズムデザイン──私たちはデザインしているのか?』は、この視点からデザインを探求する理論書となっています。同書は、HCI(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)、新唯物論/バイタルマテリアリズム、参加型デザインといった領域を横断し、人間と非人間が深く絡み合いながら「ともにデザインする designing-with」ような思想を打ち出したものです。このようにワッカリー氏がデザインを「人間中心以上(more than human-centered)」のデザインへと移行させる理由には、気候危機や経済格差といった差し迫った問題があり、人間中心デザインのモデルでは、持続可能性やテクノロジーを利用できる人々の不平等をめぐって限界に達し、コストを払ってきたという認識があります。
そんなワッカリー理論には、おおざっぱに分けて四つの主要概念があります。(より詳しくは同書本体や訳者あとがきをご覧ください。)
- ・モノ(things):人間と非人間が相互接続し、依存し合い、常に変容させあう「アッサンブラージュ」(集い)のこと。単なる物体ではなく、「私-メガネ」のように、ヒトとモノが互いを変容させ続ける関係性を指す。モノは静的ではなく、デザインの結果は常に変容し、予期せぬ影響を生み出す、とされる。
・モノのデザイナー(designer of things):デザイナーは、人間だけでなく、人間と非人間が絡み合った「モノ」そのものである。人間デザイナーはデザインを始める「起源」にはなりえても、その結果を直接的に決める「原因」ではない。
・経歴書(biography):デザイナーとデザインされるモノの間で共有される「デザイン実践の痕跡」。デザインの結果として生じる予期せぬ帰結(例:レジ袋がもたらす海洋動物の死)に対し、人間デザイナーが説明責任を放棄するのを防ぐために提案された概念。
・協議体(constituency):デザインが行なわれる前の段階にある「チーム」や「デザインスタジオ」といった集団的な構造。その本義は「何かを選びだす集団」。
最後の協議体については少々わかりづらいかもしれません。著者へのインタビュー記事からその説明にあたる箇所を引用してみます。
(協議体という概念について)『ポストヒューマニズムデザイン』でも使ったのは、「キッチン」を例にした説明方法です。キッチンは料理をつくる場所ですよね。そして、そこには「モア・ザン・ヒューマン」なものが集まっています。肉や野菜などの素材、包丁やまな板といった道具、あるいはそのキッチンが「どこにあるか」も重要です。(中略)また、さまざまな「価値観」もそこには存在します。ヴィーガンであること、あるいは遺伝子組み換え作物を拒絶すること……キッチンには、そういった価値観も入り込むわけですね。
そこで料理をつくるのは誰——あるいは何——か。人間の視点で言えば、そこで料理をつくるのは私たち人間です。しかし、いま述べたように、キッチンにはさまざまなモア・ザン・ヒューマンなものが存在し、それらが集合体を形成していて、その集合体こそが料理を生み出しているのです。私はデザインも同じだと考えています。
つまり、デザインは人間という単独の主体ではなく、さまざまなモノ、歴史、文脈の集合体が生み出している。そしてこの集合体を「協議体」と呼んでいるのです。
ブラットン氏が提示する非人間中心的な技術史と、ワッカリー氏によるポストヒューマニズムデザインの理論的探求。このような議論から、惑星規模にまで広がりつつあるテック産業に関する批判的思考の材料を取り出すことができそうです。(o)