
日々の生活、活動、仕事で接しているものはSNSとスマートフォンだけじゃない。いまこそ不可視化されている「ウェブメディア」を再考し、これからの30年を構想せよ──。
座談会にお招きしたのは、写真家の竹久直樹、ウェブディレクターの萩原俊矢、グラフィックデザイナーの畑ユリエ、ユーザーインターフェース研究の水野勝仁。そして司会のきりとりめでると構成・編集の太田知也でSNS以降のウェブサイトとデザインとアートの関係性を探求します。こちら前編です。(artscape特別編集委員・きりとりめでる)
きりとりめでる(以下、きりとり)──デジタル写真論と美術批評をやっているきりとりです。本日はよろしくお願いいたします。今回の座談会の趣旨は、artscapeが30年という節目を迎えるにあたり、昔のウェブサイトから現在までを振り返り、ウェブメディアのあり方を再考したいというものです。
この企画は、artscapeが30周年を迎えた際、その古いウェブサイト(1995年のオープン当時)を見たことから始まっています。かつてのサイトを閲覧しても、ディスプレイの解像度やビューワーの環境が以前と違いすぎるため、現在と30年前の比較は難しいと思ったのですが、レビューやニュース記事の発信を軸とするウェブメディアでの実践自体にあまり変化はないと思いました。
ただ、コロナ禍においてウェブサイトやネットサービスが展覧会やオフラインでの活動の代替として集中的に検討されました。2020年からの数年間でインターネットでのアーカイブ公開や情報発信が活発になったものの、コロナの収束とともに、この再接続の機運が発散してしまった感があります。この流れをもう一度見直し、アートメディアにとってのウェブサイト実践における地図になるような座談会ができないかと考えました。
まずは、みなさんの自己紹介から一言ずつお願いします。
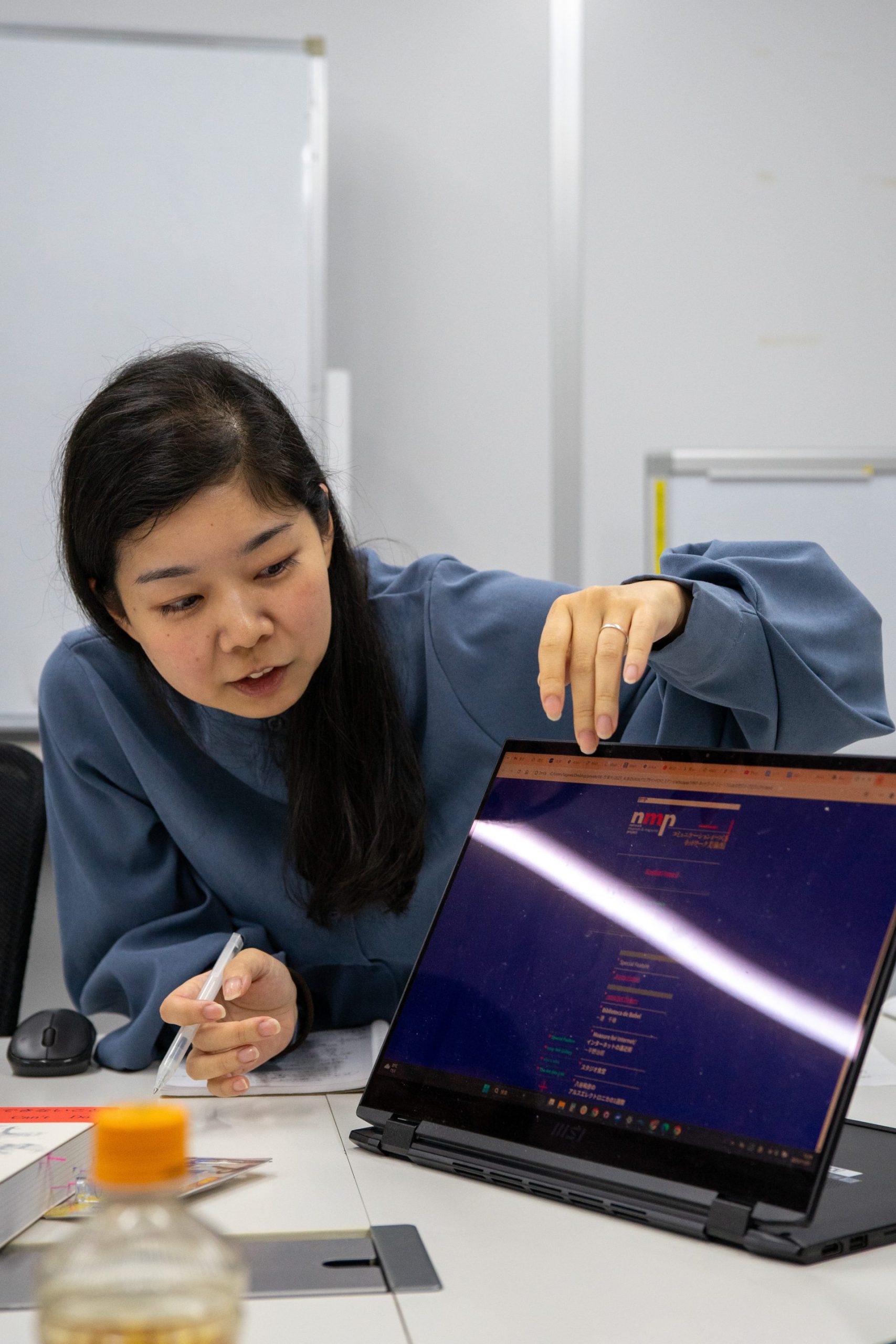
きりとりめでる氏[以下すべて、撮影:artscape編集部]
ウェブとインターフェイスをめぐる実践
畑ユリエ(以下、畑)──私はフリーランスのグラフィックデザイナーとして活動しており、主に現代美術やメディアアート分野の展覧会のチラシ、ポスター、図録をデザインしています。他にも、エンタメ系や一般書籍など、いろいろな分野の仕事を受けています。また、飯沢未央氏や(今日の参加者の一人でもある)萩原氏と共に、本の過去と未来を考える企画「TRANS BOOKS」も手掛けています。
きりとり──畑さんのお仕事を見ていると、コンピューターの中で作られるイメージをいかに物質へ変えるかという点、そしてその作ったものがフライヤーイメージとしてSNSで流通する時にまた変わってしまうという、物質的側面とインターネットというもうひとつの物質性との往還を考えられていると感じています。
竹久直樹(以下、竹久)──写真家として作品発表を行なう傍ら、主に展覧会の記録撮影の仕事をしています。現在はSemitransparent Designというウェブ/グラフィックデザイン制作の会社にも所属しています。また、中村陽道、八木幣二郎の2名とともにグラフィックデザインの展覧会や言説をつくる運動体「power/point」のメンバーとしても活動しています。
きりとり──竹久さんは2018年に「TRANS BOOKS」へ参加された際に、『Replotting』という写真集で、水平器のパッケージの裏にURLが書かれた紙を貼った作品を発表されており、今もそのURLからダウンロードページに飛べます。これはネット作品とも言えますが、オフラインにおける写真のあり方、つまりインターネットの境界を意識されているように私には見えました。このような「半即時性的メディアのあり方」にウェブがどう関与できるかを聞きたいと考え、お呼びしました。
萩原俊矢(以下、萩原)──ウェブディレクターの萩原と申します。デザイナー、プログラマーでもあり、簡単に言えばホームページの制作をしています。先ほど紹介のあった「TRANS BOOKS」では畑さんとご一緒しており、竹久さんとはSemitransparent Designの繋がりがあります。私がセミトラに在籍していたのは13年ほど前で、現在は独立してスタジオ・オータムとして活動しています。最近は特にウェブアクセシビリティとデジタルアーカイブの二つに力を入れているところです。
きりとり──萩原さんをお呼びした背景には、萩原さんが監修された『アートプロジェクトのためのウェブサイト制作 コ・クリエイションの手引き』があります。ここではウェブサイトを「アーカイブサイト」「ウェブメディア」「施設団体系紹介サイト」「記録活動のオンライン化」「展示などの告知サイト」の五つに分類しています。なかでも今回の座談会に引きつけて言えば、アートメディアが「技術者ではなくても更新できる」ことが求められ、それが制約になっているという指摘があり、はっとさせられました。
水野勝仁(以下、水野)──水野です。神戸にある甲南女子大学文学部メディア表現学科で教えています。コンピューターのインターフェイスとアートの体験を行ったり来たりしながら研究しています。近年はAIを使ってテキストやレビューを書くことに関心があり、教育の場でもAIをどう活用していくかを試行錯誤しています。AIと協働することで、自分が考えていることなのか、AIが考えていることなのかわからなくなるような状態がこれから出てくるのでは、と考えています。
きりとり──水野さんには、ウェブメディアをメタな視点で見直してもらえる方として、ぜひお話を伺いたいと考えました。マウスポインタひとつから考察を深めてこられたご経験からお伺いできることがたくさんあると思っています。
ウェブ前提のグラフィックデザイン──同一性を保つ弾力性
きりとり──畑さんは図録やフライヤーの仕事を多くされていますが、ウェブに関わるところだとバナーという形式になってくるでしょうか。
畑──今は情報が溢れているため、広報物に関しては埋もれないようにアテンションを引きつけないといけない部分がどうしてもあると思います。また、広報物は同時代性を強く反映するので、「この瞬間」がすごく重要視されます。一方、図録は残していくものなので、アテンションがあるだけではダメです。このように形式に応じて課せられている役割が違うのに、ディレクションとしては「同一性」を持たせる必要がある。また、私一人だけでなく複数の人の手を介して制作が進む場合もあり、そういうときも「誰が手を入れても同じように見える」という意味での同一性は大事になってきます。
広報物についてだけでも、さまざまなサイズのものを制作する必要があります。かつては縦型ポスターや横型の中吊り広告などというように、展開が数種類程度のものも少なくなかったのですが今は縦型と横型に加えて、Instagram用の正方形──直近だと3:4比率のフォーマットに変わってしまいましたね──や極度に横に長い比率など、とにかくいろんな種類のバナーをリサイズして作っています。出方が多様化しているため、いつどこでどのような状況で出てくるかも事前にすべて把握できているわけではなく、どういう人に見られているかわからない部分があります。
きりとり──つまり、グラフィックが乗る予定の背景色だとか、どういった環境で表示されるかなどはわからない。けれども、サイズの指定だけが来て、その後流用されうるものとしてバナーがある、と。
畑──artscapeさんの30周年記念のバナーを担当させていただいたときも、文字を大きくしたくなるという衝動がありました。見られるスクリーンのサイズもさまざまですし、特にウェブ中心の展開だと、細々していると伝わらないかもという意識があります。アテンションエコノミーについては批判的な言葉も聞こえてきますが、自分がそれに加担しているのではないかと思うこともあります。
きりとり──近年の畑さんは、「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館『中園孔二 ソウルメイト』展」など、展覧会フライヤーや図録と連動した動きのあるグラフィックに盛んに取り組まれている印象です。モーショングラフィックを作られるようになったきっかけはありましたか。
畑──2020年の春、コロナ禍で展覧会の仕事のいくつかが中止や延期になり、すごく時間ができたタイミングがありました。「チラシというメディアが減るかな」、あるいは少なくとも直近では「チラシは使われないだろう」と考え、「動画だ!」と思い立ち、After EffectsやBlenderを勉強し始めました。それまではモーショングラフィックには活用場所があまりないという印象でした。
そうするなかでオンラインイベントのフライヤーの依頼があり、「動くやつ(モーショングラフィック)でもいいですか?」とこちらから提案したところ、OKをいただき制作し、その後、「モーションもやる人だ」と認知されたことで、仕事にいくつか繋がりました。例にあげていただいた中園孔二さんは、生前、IAMASで芸術系のプログラミングについて学びたいという話をされていたというお話もお聞きして、このような表現にも親和性があるのかな、とも思う部分もありました。モーショングラフィックが一般化してくると、ウェブサイト側もそれに対応する変化(例えば、美術館のウェブサイトでGIFアニメを表示できるように改修するなど)をされていくようにもなりました。
きりとり──ウェブサイトではグリッド状に表示されるテーマやテンプレートがありますが、バナーを作る際には、そうしたウェブの一般的なパターンとの親和性をどう考えていますか。
畑──サイズや比率がとてもたくさんあるという先ほどお話した状況と似ているかもしれないですが、全体のグラフィック展開における同一性や、ディレクションの弾力性を保つことが必要になります。ポスター(メインビジュアル)がひとつあって、そこから展開していくというようなトップダウン型ではなく、全体を見渡した時にそのアートディレクションの方向性が見え、どんな形に変化しても同一性が保たれるように、初めから弾性と展開性を持ったかたちでグラフィックが設計されている必要があると思っています。

畑ユリエ氏
プラットフォームが規定する写真と「へたれグラフィックス」
竹久──畑さんの制作物は、SNS上で見たときにグラフィックが「表示崩れっぽくない」。具体的には、情報の可読性を最大限担保しつつ、書体と文字の色とぶつかりの雰囲気でアートディレクションをやっていくというもので、そこが現代の、文化領域に関わるデザイナーにおいて特異な点なのではないでしょうか。
畑──自分のは古い作り方だと思っていました。私はグラフィックデザインですべてのことを解決しようとしているタイプです。作る画面のなかですべての情報を完結させるというか。
竹久──現在、こと文化領域の仕事においてしばしば見受けられるのは、Adobe Illustratorが使い手たるデザイナーに要請する「図案を読みやすく整理する」ことをIllustratorの機能だけで脱臼する、というような手つきです。たとえば展覧会のポスターを想像していただきたいのですが、ものすごく細い文字のタイトルや、わざとガタガタに文字や図版を組んだり、文字情報をものすごく小さくしてスマホの画面内では読めない状態にしたりするというような事例があります。こうした手つき、そしてその結果生まれる「可読性を無視した宣伝美術」がなぜ成り立っているかを考えてみると、SNSというものと相性がものすごく良かった側面がありそうです。というのも、SNSにアップされる際には文字情報のキャプションが必ずつくため、宣伝美術単体での可読性は問われにくいのです。つまり、宣伝美術というものが情報を述べ伝える「ポスター」から、アティチュードを伝える「メインビジュアル」になったのだ、と言えると思います。
ところで、かつて原研哉が2010年代前半のデザインの流行について「うすらグラフィックス」★と形容したことがあります。これは主に、軽くてゆるい造形と脱構築的な文字組、Illustrator由来の未完成さや不安定さをそのまま定着させたような手つきを指すものでした。私を含めた現在25-35歳前後は「うすら」に影響を受けた世代の、さらにその下の世代にあたり、「うすら」をPinterestやTumblrなどのSNSで見て育ってきた世代です。
この「うすらグラフィックス」を踏まえて、先ほど述べたような現代的な宣伝美術における手つき・制作態度に名前をつけるなら、「へたれグラフィックス」ということになるのかもしれません。私は「へたれ」という言葉の意味合いにポジティブさを見出してあえて採用しているものの、一般的には攻撃的・自虐的な印象があるので、ゆくゆくはもう少し良い名前を考えたいと思っているのですが……。写真をメインフィールドにしているにもかかわらずこんなことを言うのは、ある面では写真も同じ状況のなかにあると考えているからです。つまり、SNS上でやり取りされるiPhoneの写真というデファクト──ある種のプラットフォーム──に対して、どのように差別化するか。これが現代の写真表現において主たる問題になっている気がします。

竹久直樹氏
情報伝達のための撮影──PhotoshopとiPhoneのあいだ
竹久──私が大学生から作家としてのキャリア初期を過ごした2015-22年ごろは、取り壊しの決まっている空きビルや民家をそのまま使うなど、何年も稼働しない前提の会場で行なわれる展覧会が多かった。また、大型のインスタレーション(単一の彫刻ではないところに留意すべきです)が屋外に設置されることもままありました。このような事情から、私が向き合うことになったのはホワイトキューブのインスタレーションビューとは対照的な、展覧会会場としては劣悪とも言える状況のなかで使役される作家の手つきをどう撮るか、ということでした。
例えば、「海沿いの造船所跡地にて瓦礫の山の中にスピーカーが仕込まれ、音が鳴っている」というサウンドインスタレーションを撮影したことがありました。普通に撮ったら瓦礫でしかないのですが、それをインスタレーションビューとして成立させるための技術がいつからか自分のなかで蓄積されていきました。そういう試行錯誤が、結果として自分の写真の清潔なトーンに繋がっているのだと思います。

小松千倫《Mob World Mix》 ft. Dove&Le Makeup, Young Celeb Naruto, 堀池ゆめぁ, Ruca Avril&Deaththrowers(2021)[撮影・提供:竹久直樹]
原理的な意味でのインスタレーションビューは、おそらくMoMAによって一般化された形式です。作品そのものではなく、作品同士に構築された関係を記録するための撮り方だと認識しています。その意味で、ホワイトキューブとヴォイドとのあいだというのが、当初自分のなかにあったテーマなのです。
きりとり──インスタレーションビュー自体は1938年のシュルレアリスム国際展などにも見られますが、MoMA(1929年開館)と共に広まったホワイトキューブという概念との比較で作品写真(インスタレーションビュー)を再考するのは興味深いですね。
竹久さんの写真のトーンについて、個人的には「ヴォルフガング・ティルマンス以後」と捉えています。人間と人間の接触は撮らない、であるとか、水平・垂直への意識が非常に強い、つまりスナップで撮らないという作家性があるように思います。これは、先ほど聞いたお話から補足すると、スマートフォンとプロの機材との連続性から離れようとしたときに、写真家がカメラを持つ意義として「水平・垂直を保つ」という態度表明があるのかな、と見ていました。
竹久──ティルマンスの特異さは、ドイツ写真の文脈における「複数のイメージの集積 – 構成」を、写真の組み合わせではなく展覧会の構造——つまりインスタレーションへと押し上げたところにある、と理解しています。ただ、「うすら」「へたれ」に重なる話かもしれませんが、私はティルマンスの直接影響下にある世代ではないんですよね。そんな私からすると、インスタレーションを見せるために写真自体は緻密に作り込みつつ静かでシンプルなものにとどめるティルマンスの制作方法には、僭越ながらかなり共感するところがあります。
私の場合は、水平・垂直を守るのが先に来ていたわけではありません。写真を表現方法というよりは、情報伝達のためのコミュニケーションツールだと割り切った結果、そのようになったのだと思います。そしてこの姿勢は、私の中長期的な作家としてのステートメントにも通じています。
きりとり──それはどういうことですか?
竹久──「PhotoshopとiPhoneのあいだ」にある写真の状況について、作家として掘り下げていきたいと考えています。写真家個々のテクニックというよりは、画像共有の文化に属する領域です。日本の写真史では、画像共有の文化(Tumblr、mixiなど)や、コミュニケーションツールとして写真を扱う文化に対する批評的な視座がかなり抜けていると感じているんです。私はこの現状に不満があるのです。
付け加えるなら、iPhoneにおける撮影が普通のカメラと決定的に違う点は、その画質や簡便性ではなく「撮影中にプッシュ通知が来てしまうこと」にあると思います。というか、その可能性を頭に入れながらシャッターを切らなければいけない。その場にいない不特定多数の(オンライン上の)他者が常に写り込んでいるような感覚に襲われます。翻って、自分が行なっているような見るときの情報的なノイズをなくす撮影とは、そうしたiPhoneでの撮影から相対化された技法なのかもしれません。
きりとり──なるほど。PhotoshopとiPhoneのあいだにある写真の社会学的な使用にまつわる状況。これを写真史の文脈に流し込むという問題意識は、ヴァナキュラー写真研究の流れの中で私も共有していますので、共感しつつ伺いました。
今の竹久さんのお話は、畑さんのバナーに関する議論(プラットフォームにフィットさせるためのグラフィックの同一性)とも繋がりがありますね。ここからは、畑さんと竹久さんの話を踏まえて、水野さんや萩原さんにもコメントをいただきたいと思います。
気ままに漂うイメージか、枠組みに囚えられたイメージか
水野──畑さんが言われていた「同一性を保つ」というお話から、写真家の中川ももさんの事例を思い出しました。彼女は「人間の皮膚や建物の壁のイメージを採取」した自らの写真作品のデータをデザイナーなどに渡し、好きにデザインしてもらっているそうです。それがポスターや立方体になっても構わず、それをまた自分で引き取ってきて「採取」し、次の作品に使うという「循環」を行なっていました。写真を一種の生態系として扱っている写真家さんです。インターネット以後、特に、ポスト・インターネット以後「生態系」という言葉を、写真や画像に使うことが増えたと感じています。中川さんの作品を見るまではあまりピンと来ていなかったのですが、彼女の作品はまさに「生態系」だなと思いました。

水野勝仁氏
データは同一なのに、好き勝手に物質へ変化する。それに対して「気ままに変わっていけばよく、想像つかない使い方をしてくれたほうがいい」という態度が面白いと感じました。畑さんのお仕事ではデータに対してもっと能動的に働きかけているとは思うものの、同一性と弾力性の点で似たようなものを感じました。
きりとり──イメージの見られ方や扱われ方については、萩原さんにぜひ聞いてみたいところです。萩原さんはこれまでウェブサイトを制作されるなかで、さまざまなイメージの提示の仕方を試みられてきたと思います。
萩原──写真家のウェブサイトを設計する際は、作品に対する作家の態度表明を反映していく感覚があります。どんな分類を作るか、どのように写真を並べるか、縦方向や横方向にスクロールする行為がどんなシーケンスを作るか。写真家がどんな態度で作品と向き合っているかをインターフェイスで表わすことに興味があります。
例えば、2007年頃にジェフ・ウォールのMoMAでの展示に合わせた特設サイトをGroup 94というベルギーのプロダクションが作っていました。ウォールは非常にディテールまでこだわって写真を制作しますよね。なので、ズームがすごく効くサイトになっていたんです。つまり、写真の側が求めているインターフェイスをいかに提供し、写真の見せ方をいかに「お膳立て」するかがインターフェイスの設計者には問われてくるんですね。
ところが、ソーシャルメディアの登場以降、多くのひとはInstagramのなかで写真を見せるという態度に変わっているようで、残念に感じるところもあります。これは先ほどの「へたれグラフィックス」の議論にも通じていますね。GAFAMなどのビッグテックやプラットフォーマーが強くなりすぎていて、コンテンツにとっての容れ物(コンテナ)のほうが支配的になってしまっているかのようです。特定のコンテナのなかで映えるコンテンツみたいな、そういうかたちで自分たちを表現しようとしてしまっていて。いやいや、枠組みから一緒に考えようよ、そこにステートメントがあるはずでしょう、というのが私の気持ちです。もちろん、Instagramのなかにも多くの創造的で魅力的な投稿はあります。しかし、アルゴリズムが前提となる環境のなかで、表現のかたちが自然と誘導されてしまう感じに、どうしても違和感を覚えてしまいます。

萩原俊矢氏
きりとり──インスタなら、ニュースフィードに何をピックアップするかのアルゴリズムの変化によって、収益化できるかどうかといったアテンション獲得の分岐が毎月のように変化し、それに応じて人々が表現を変化させているということが常態化していますよね。その一方で、レフ・マノヴィッチは2015年のインスタグラムを研究する中で、人々が美術教育を経ること無しに、Instagramというプラットフォームに投稿するときに、どういった写真や自身の表現がハードウェアとソフトウェアの両面に適するか理解していることに時代の変化を見いだしていました。このように現在の複合的なメディア環境をユーザーが理解できるのなら──プラットフォームに従うのみならず──「違うこともできるはず」という話を、萩原さんはおっしゃっているのだと思います。
ポートフォリオサイトとメディアサイト
竹久──少し問題提起的なことを話してもいいですか。一般的に言って、ウェブサイト制作においては、画像の扱い方やビジュアルに関する世界観の統一によってトーンを構築していくというのが、わかりやすいディレクションの方針だと思います。
ですが、アート系ウェブメディアの場合、見栄えに関するディレクションを徹底しづらい、という難点がありそうです。というのも、記事内で著作権のある図版を扱うことが多くなるため、画面をひとつの美学で統一するのが難しいからです。──アート作品の画像や展覧会の告知ビジュアルをめちゃくちゃに加工して掲載するなどはできませんからね。そして厄介なことに、近年のウェブでは画像をぞんざいに扱うこと自体が流行っていると思います(笑)。そのため、アート系ウェブメディアを見ていると「かたいな」という印象を持たれることが多そうです。
きりとり──もう一点思ったこととしては、アート系ウェブメディアにおけるインターフェイス設計の問題です。編集者などが自分たちの手で、エンジニアの手を介さずに、更新をし続けられるというのがメディアサイト/ウェブメディアの設計要件になってくるでしょう。こういう場合には、写真家のポートフォリオサイトのように独自企画のインターフェイスを作ることは難しいでしょうか。
萩原──テキスト主体のサイトと写真主体のサイトは、いくつかの観点で対照的です。写真はXY軸がはっきりした二次元的なメディアで、基本的なフォーマットが確立されています。一方で、テキスト(ハイパーテキスト)を中心とするメディアサイトは、記事の長さや構造、執筆者、タグなど、さまざまな要素が絡み合うぶん、より柔軟で多面的なメディアと言えます。
その柔軟さゆえに、写真ほど明確にインターフェイスの「発明」を提示するのが難しいところもあります。ただし、どこをどう切り取り、どの構造を前景化するかといった編集の妙が問われる領域でもあり、そこを丁寧に設計できれば、メディアサイトならではの面白さが生まれるはずです。
原理的なところから言うと、ウェブメディアは、自ら「私たちのメディアはこのような方針で運営します」という姿勢を、アーキテクチャ設計からコンテンツ企画、さらには読者選定と配信に至るまで貫くことができます。そういう独立性の高さこそが、SNSにはない魅力だと思うんですね。
ところで、今回の座談会のタイトルはすごくいいですよね。「未来を予想する」のではなく「未来を構想する」、すなわち「望ましい未来を創造していく」というニュアンスを含んでいるのだと受け取りました。自分にとっては、ビッグテックへの依存が強まる一方であるインターネットの現状は変えていくべきだし、自らの手で変化を起こしたいと思っています。
きりとり──では、萩原さんが今後ウェブメディアを作るとしたらどうしますか?
萩原──まず考えたいのは、アクセシビリティについてです。ウェブが一般化した今となっては、これまで以上に多様なユーザーによる利用が前提になっています。例えばファッション通販サイトのレビュー欄を見ると、60代や70代の方々が当たり前のように投稿していて、裾野が広がっていることを実感します。
また、私自身、視覚障害のある方や、多様な知覚特性を持つ方と一緒に仕事をする機会が多く、その中にはスクリーンリーダーを使ってウェブサイトを利用する方もいます。かれらはウェブサイトを「目で見る」だけでなく、「音で聞く」かたちでアクセスします。そのため、サイトが機械を介して正しく読み取れる構造になっていることが非常に重要なんですね。
さらに言えば、現在のインターネット利用者の約51パーセントはAIやボットによるアクセスだという調査もあります。こうした状況を踏まえると、情報がマシンリーダブル(機械に読みやすい状態)であることは、人間にとってのアクセシビリティだけでなく、情報の価値そのものを支える基盤になっているといえるでしょう。つまり、「機械にとってのアクセシビリティ」をどう設計するかという、エンジニアリング的な視点の重要度が高まってきています。
さまざまな環境から目で見て利用するユーザー、スクリーンリーダーなどを使って聴覚的に利用するユーザー、そしてAIやボットといった非人間的ユーザー。ウェブサイトの「ユーザー」という概念は広がり続けています。
SNSのように大規模プラットフォームが用意する環境では、こうした多様な前提に合わせてコンテンツを発信することは、なかなか難しい場合もあります。他方で、独立系のメディアであれば、「マシン向けにはこういう体験」「視覚で利用する人にはこういう体験」といった具合に、ユーザー層ごとに体験を設計する余地があります。そこにこそ、ウェブメディアをつくる面白さがあると感じています。
★──JAGDA 2012年度年鑑「GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2012」11頁
(後編へ)












