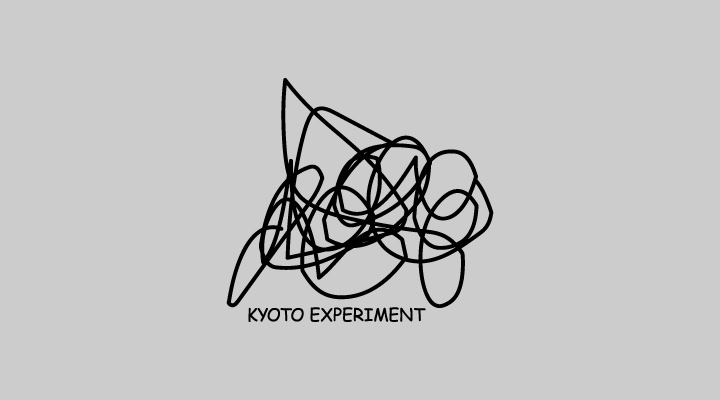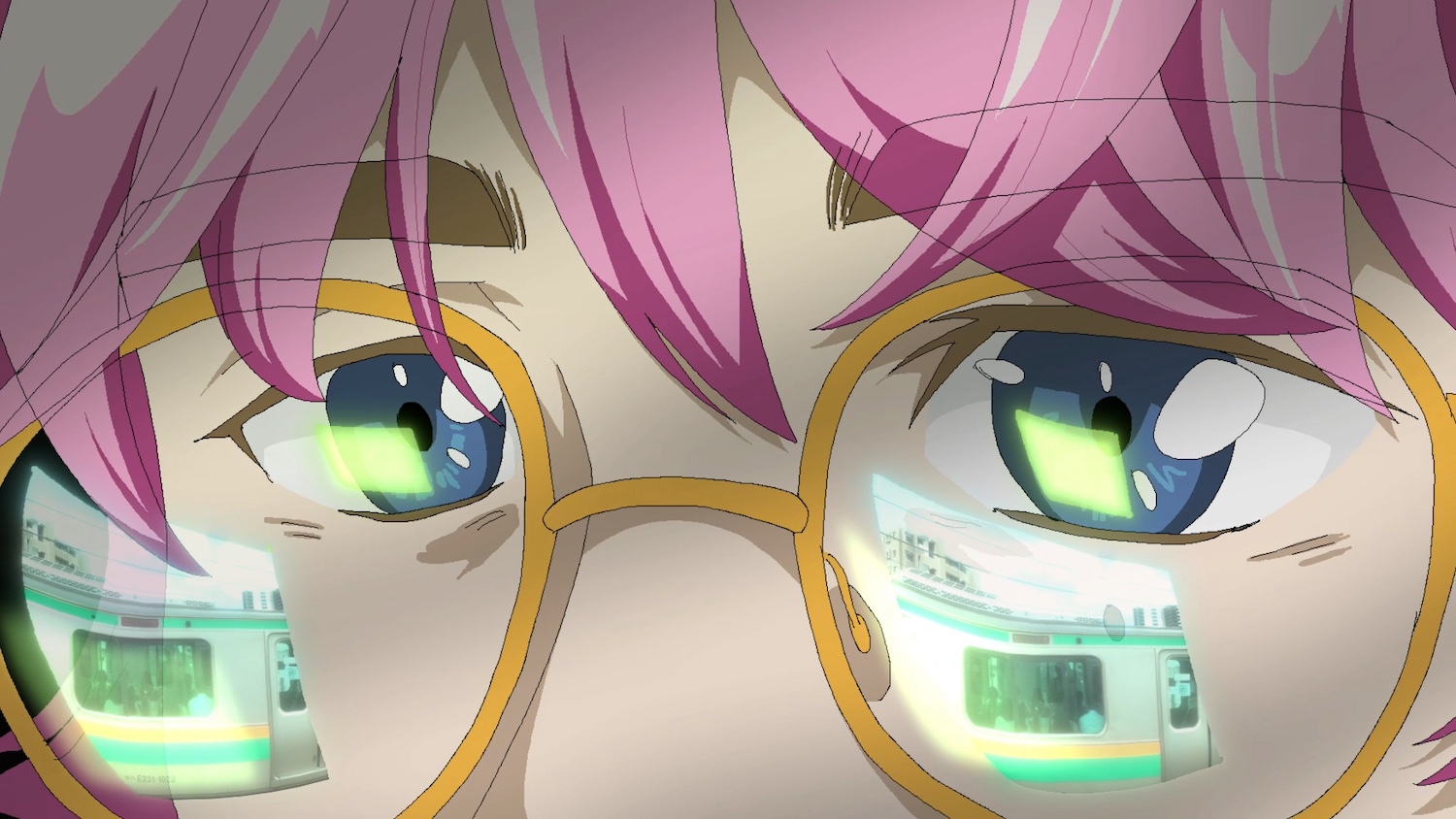会期:2025/10/24~2025/10/26
会場:京都芸術センター 講堂[京都府]
公式サイト:https://kyoto-ex.jp/program/martha-luisa-hernandez-cadenas/
(前編より)
前編で見たように、本作は、ユニコーンのマスク=拘束具、浮き輪=救命具という小道具を巧みに使いながら、「私はユニコーンではない」という否定形の生に孕まれたさまざまな矛盾をあぶり出しつつ、「ユニコーンの共同体」の一員としてどう肯定的に生き直すことができるかという問いに賭けられていた。その共同体は、異性愛男性中心主義的な世界から追放された/離脱した、「自由でポストヒューマンなシスターたち」のための避難所とされる。
「レディ・ホルン」という名前が召喚されるように、本作の着想源のひとつが、身体機能の拡張であり、かつ拘束具のような装置を着用したレベッカ・ホルンの初期パフォーマンス作品である。《ユニコーン》(1970)では、身長を半分ほども延長する白く長いツノを頭に装着し、バランスを保ちながら麦畑を横切っていく。また、「物語を書く百本の鉛筆」というカデナスの詩の一節は、ホルンの《ペンシル・マスク》(1972)も想起させる。アメフトのフェイスガードのようなグリッド状のマスクを頭部に装着し、グリッドの交点に「ツノ」のように鉛筆が取り付けられているため、頭を動かすことでドローイングを描くことができる。「腕を動かすことができなくてもドローイングできる」という身体機能の拡張と同時に、拘束具のような抑圧性や攻撃性をも帯びた作品だ。ホルンの《ユニコーン》を収めた写真立ては、ユニコーンのグッズが並ぶ祭壇のような空間に飾られていた。

[筆者撮影]
「迷ったことはないが 今 自分を見つけた」と綴るカデナスは、「ユニコーンなんてどこにもいない」という否定や無関心に対して、「いや、ここに いる 」という力強い肯定へと転じさせていく。そのとき、響きわたる蹄の音は、性と生殖の規範に異議申し立てをする者たちが連帯する世界へ向かって自らを運んでいく力となる。額に生えたツノは、抵抗と連帯の言葉を綴るための鉛筆となる。ユニコーンであること、それは、「別の何かになる」のではなく、自分自身の生を取り戻し、生き直すことにほかならない。
口を塞がれ、酸素を奪われた窒息状態から、海面に頭を出し、生へ再浮上すること。この救命道具こそ、「ユニコーンの浮き輪」である。カデナス自身が浮き輪に「息」を吹き込むパフォーマンスも多義性を帯びている。「いないこと」にされる存在に実体を与えること。ラップとして吐き出される抵抗の言葉に、文字通り「息」を吹き込むこと。生き延びるための救命道具を自分自身でつくり上げること。

[撮影:岩橋優花 提供:KYOTO EXPERIMENT]
こうした「浮き輪」の象徴性と対比させたとき、パフォーマンス前半に登場した「ユニコーンのマスク」のもうひとつの意味が浮かび上がってくる。マスクとは、「声を封じられる」という拘束性に加えて、「属性」によって 個人の顔 が見えなくなる事態の謂いでもある。「普通ではない」「自然ではない」とされる存在にとって、名を与えられることは、存在の可視化と承認である。だが同時に、「属性」のラベルに個人が矮小化されてしまう危うさもはらむ。だからこそ、「私はユニコーンではない」という反語に、何度でも立ち戻らねばならないのだ。

[撮影:岩橋優花 提供:KYOTO EXPERIMENT]
最後に、「ユニコーン」と同じく、「ヴァンパイア」という想像上の存在をクィアのメタファーに用いたイザドラ・ネヴェス・マルケスの秀逸な映像インスタレーション《Vampires in Space》(2022)を参照したい。マルケスの作品では、「地球から別の惑星へ旅する宇宙船に乗り込んだヴァンパイア」というSFの設定や比喩を借りて、終わりのない性別移行、地球すなわち生まれ育ったコミュニティとの絶縁、「首に噛みつく」という非生殖的な方法で増えていくクィアの共同体、人目につかない安全な隠れ家/朝の来ない永遠の夜といったトランスジェンダーの生が語られていた。さらに、「ヴァンパイア」というメタファーは、例えば女子トイレへの制限という形で噴き出すトランス女性に対するヘイトのように、実際に見たことはなくとも(あるいは見たことがないからこそ)「想像が恐怖を肥大させ、怪物を生み出す回路」として、トランスフォビアの謂いでもある。したがって、「私はユニコーンではない」という文言には、「実際には存在しない、想像上の怪物」に押し込められてしまうことに対する抵抗も響いている。あるいは、「ツノがあること」が唯一のアイデンティティとされる息苦しさからの解放の希求。マルケスの作品には、「牙が人を定義することはない」という示唆的な台詞がある。私はユニコーンであり、同時にユニコーンではない。この多重的な矛盾に引き裂かれて生きざるをえないことを引き受けつつ、それでもなお本作は、「ユニコーンであること」がもつ根源的な力を、翻訳不可能な地点に到達するほどの熱量を帯びた言葉によって開示していた。
鑑賞日:2025/10/24(金)