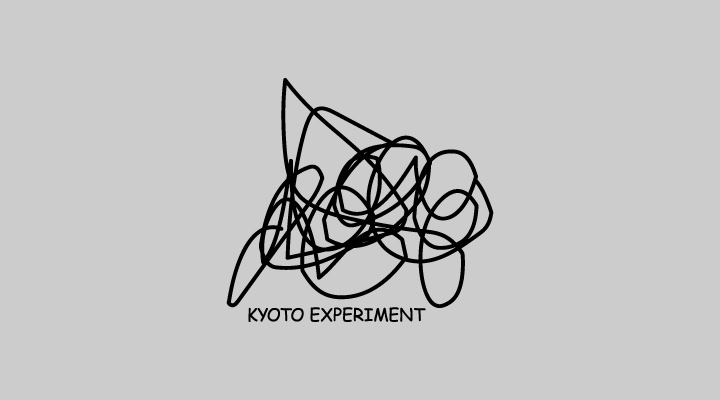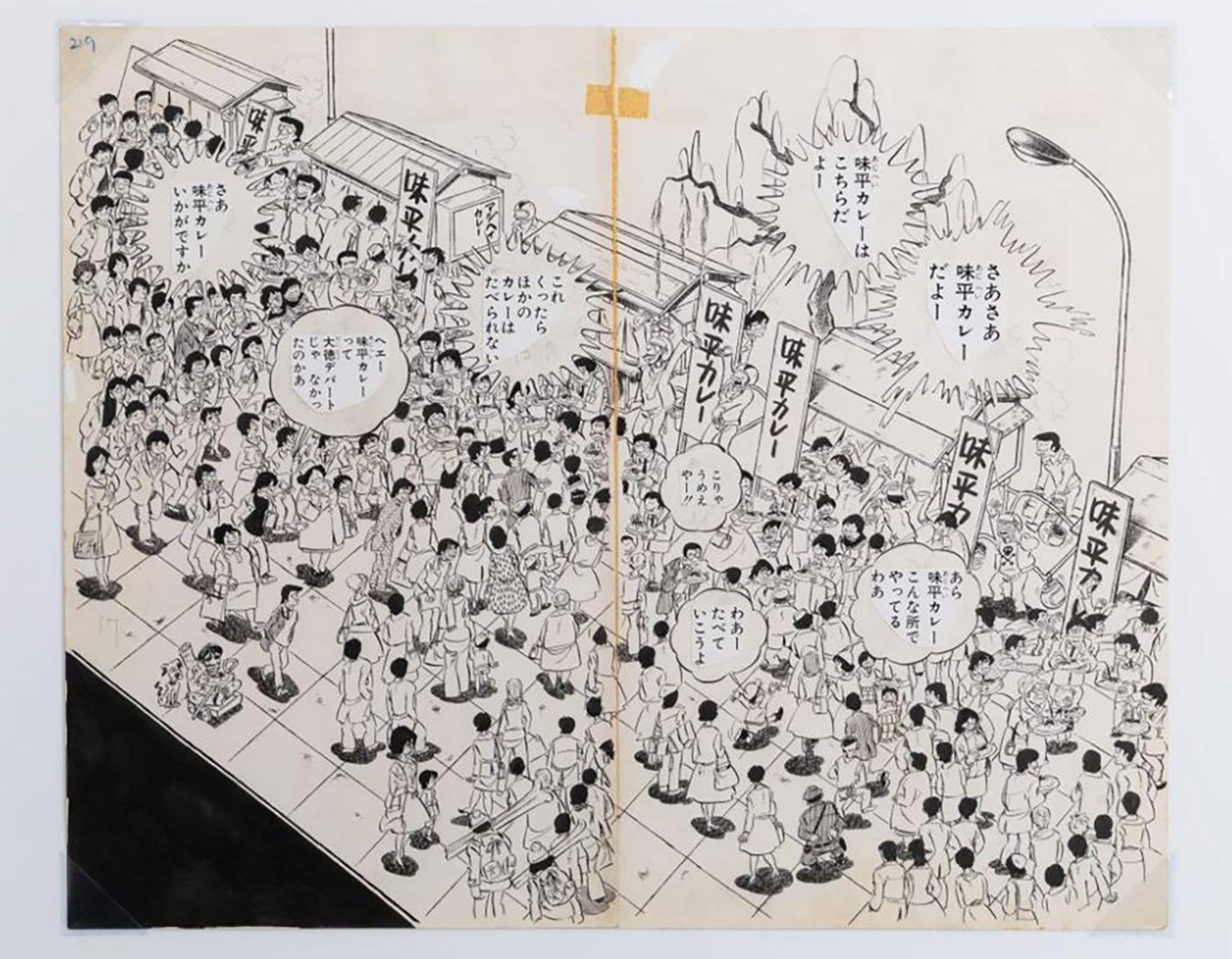会期:2025/10/13~2025/10/22
会場:伊藤記念図書館(京都市立芸術大学附属図書館)[京都府]
公式サイト:https://kyoto-ex.jp/program/adam-christopher/
すでにレビューで取り上げたように、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2025(以下、KEX)のプログラム前半では、マレーシアの民族主義的ナショナリズムを象徴する英雄像、レバノンで常態化した電力危機、明治初期に大阪に設置された陸軍墓地にそれぞれ焦点を当て、国家権力と個人の記憶を交差させる視座から近現代史を語り直すレクチャー・パフォーマンスやリサーチベースの優れた作品が並んだ。整然としたレクチャーやテキストベースの作品が続いた前半とは対照的に、プログラム後半では、バーバル/ノンバーバルの狭間を揺れ動き、言語化や翻訳の(不)可能性を問うような作品が強い印象を放った。KEXのレビューシリーズ後半では、「図書館」という「沈黙の場」を「知覚を研ぎ澄ます場」に変貌させていくアダム・キナー & クリストファー・ウィレス『MANUAL 』、抵抗と連帯の詩の言葉を即興のラップの熱量に変換していくマルタ・ルイサ・エルナンデス・カデナス『私はユニコーンではない』、アジアにおける「発酵食」の伝播をテーマに「異文化交流」「国際共同製作」そのものを自己批評的に問うようなJang-Chi×李銘宸(リー・ミンチェン)×ネス・ロケ×温又柔『クルージング:旅する舌たち』を順に取り上げる。
共にカナダを拠点とするアダム・キナーとクリストファー・ウィレスは、サウンドスケープに着目し、公共空間で上演される観客参加型の作品を手がけている。『MANUAL』は、図書館を舞台に、1人のパフォーマーが1人の観客のために上演する、親密で繊細なパフォーマンス作品。KEXでは、2023年に京都駅東にキャンパスを移転した京都市立芸術大学の伊藤記念図書館を舞台に、関西を拠点とするアーティストたちと協働して制作した。
そもそも「上演」はどこから始まり、どこで終わるのか。本作は、「上演空間である図書館の中へ入るまでの順路」を、最短距離ではなく、大きく迂回しながら、上演のための身体感覚をチューニングしていく。キャンパスの敷地内に置かれた小屋で受付を済ませ、ガイド役のパフォーマーがやってくるのを待つ時間。棟と棟を空中で結ぶ通路では、立ち止まって建物のガラス壁に映る景色を眺め、町の喧騒に耳を澄ませる時間が取られる。外階段を上り、建物の中へ。廊下の窓ガラス越しに見える景色に、再び向き合うよう案内される。音がシャットダウンされた感覚。「目をつぶって10回深呼吸したら、上演が始まります」と告げられる。再び目を開けると、先ほどのガイド役は消え失せ、別のパフォーマーが隣に佇んでいた。

[撮影:吉本和樹 提供:京都市立芸術大学、KYOTO EXPERIMENT]
ここからの静寂の領域では、メモと耳元の囁き声で案内される。いや、空間は静寂ではなく、微細な物音に満ちている。吹き抜けの図書館を見下ろす回廊に佇むと、「一番遠くの音を聞いてください」「一番近くの音を聞いてください」と促される。奥のカウンターで司書が作業している物音。手前の机で誰かが本をめくる音。音の遠近感として捉え直されたこの空間に、これから入っていく。

[撮影:吉本和樹 提供:京都市立芸術大学、KYOTO EXPERIMENT]
机に案内されると、レコーダーとイヤフォンを手渡され、この場所で録音した環境音が「周囲と同じボリューム」に聞こえるよう調整を指示される。傍らには積み上げられた多数の書籍。無言のパフォーマーは1冊ずつ取り出し、ページを覆う厚紙をゆっくりとスライドさせていく。さまざまな表情の「手」を写したモノクロ写真の図版が現われる。握った手、開いた掌、何かを掴む手。タイトルの「MANUAL(手動)」が指すように、「本のページを開く」というミニマルな行為が演劇を生起させる。すなわち、目の前の生身の肉体を通した、別の世界の開示 。本(写真集)というひとつの世界に閉じ込められていたものが表出し、イメージの連鎖と呼応によって、本どうしがシームレスに連続していく。そのとき、開いた本が次々と載せられていく机は、「演劇の四角い舞台」の謂いとなる。

[撮影:吉本和樹 提供:京都市立芸術大学]
遠くに鬱蒼と茂る森を見下ろし、指を狐の形にした手を写した写真が現われる。めくられる写真集は、森、雲、水面の水滴を写したものへと変わっていく。イヤフォンから流れる音も、鳥のさえずりや雨音に変化する。電子顕微鏡で神経網を写したとおぼしき写真が、光の網と化した夜の大都市を捉えた航空写真とリンクし、最後は月面の写真へ。ミクロコスモスからマクロコスモスへ連鎖する音とイメージの旅だ。
パフォーマンスの終盤では、本棚へ移動し、パフォーマーが選んだという別の本が開けられる。雨上がりのガラス越しに夜の路上をピントをぼかして写したような、抽象的な写真が現われる。「何も見えなくなるまで、見えるものを交互に言葉にする」というタスクが始まる。パフォーマーに合わせて、私の声も自然と囁き声になり、その声はレコーダーから同時再生されて聞こえる。「見えるもの」が尽きそうになると、本が90度回転される。知覚をギリギリまで研ぎ澄ませていくレッスン。同じイメージを見ていても、無限に近い微細な差異があることに気づくこと。あるいは、自分自身が見ているものと、言葉として聞こえるものの間にあるズレ。

[撮影:吉本和樹 提供:京都市立芸術大学、KYOTO EXPERIMENT]
タスクが終わると、後ろを向くよう指示され、パフォーマーの囁き声がイヤフォンから流れる。この場所にはかつて町があったこと。本棚には隙間があり、誰かが見つけた本が、京都のどこかへ旅し、またここへ戻ってくること。「私は先に行きます。耳を澄ませながら本棚の間を歩いて、上演を終わらせてください」と告げられる。もう隣には誰もいない。置いてけぼりにされたような孤独感と、不意に解放感を感じる。本棚から本棚へ歩くと、空きスペースに、小さな作品が展示されていることに気づく。「分類番号に従って本を探す」という目的がない状態で図書館を歩くとき、知らない町を歩くような感覚になる。秩序立った迷宮。整然と並ぶ本棚が、かつてここに建ち並んでいた市営住宅の棟と重なる。次の本棚の角を曲がると、何が見え、どんな風景が開けるのか。
魔法のような時間は、なかなか消え去らない。「図書館」という静寂の場所を、知覚を研ぎ澄ませるレッスンとメタ演劇、そして見知らぬ町の遊歩に変えていく本作は、読書というパーソナルな領域を他人と共有する親密さと少しの居心地悪さとともに、「上演の終わり」を体験者自身に委ねる。それは、寛容さであると同時に、ある種の過酷さでもある。本作の体験者は、日常と非日常の境界線をどこに引くのか、そもそも引くことが可能なのかという問いを引き受けさせられるからだ。あるいは、その過酷さは、上演の幕が完全に降りたのではなく、「摩耗した知覚を回復させ、解像度を上げていくレッスン」はいつでも自身の手で再開可能なのだ 、という手渡された信頼なのかもしれない。そして、上演の時空間に立ち戻りながら書いているこの文章も、想起のなかで「上演」を再び立ち上げ、終わりのない共有に向けて開いていく試みなのかもしれない。
鑑賞日:2025/10/13(月)