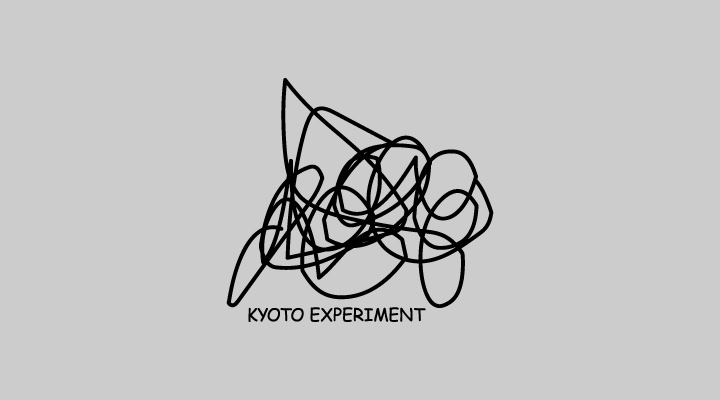会期:2025/10/24~2025/10/26
会場:京都芸術センター 講堂[京都府]
公式サイト:https://kyoto-ex.jp/program/martha-luisa-hernandez-cadenas/
想像上の架空の生物であり、美しさや気高さが憧憬の対象となり、同時に「奇形」として好奇や侮蔑の視線を向けられ、珍しさから捕獲されて追い詰められて姿を消し、あるいは「かわいいキャラクター」として無害化されて消費される。クィアの象徴でもあるユニコーンを、こうした多義性とともに捉え直し、他者から一方的にカテゴライズされることへの否定を、生身の身体でもってどう肯定的に生き直すことができるか。詩的なテキスト、映像、パフォーマンスが交錯する本作は、文字通り「息」が吹き込まれた抵抗と連帯の言葉が、翻訳不可能な地点まで熱量を上げていく。
キューバを拠点とするマルタ・ルイサ・エルナンデス・カデナスは、詩人として詩や小説を執筆しつつ、パフォーマンス作品も横断的に発表するアーティストである。『私はユニコーンではない』では、冒頭、ユニコーンが描かれたTシャツを着たカデナスが登場し、風船を膨らませるための「円筒形の空気入れ」を額に当て、シュコシュコと必死で操作する。「額にツノをつけてユニコーンになる」というパロディであると同時に、自らの身体と肺に言葉を紡ぐための酸素を送り込む、二重性を帯びたパフォーマンスだ。

[撮影:岩橋優花 提供:KYOTO EXPERIMENT]
だが、カデナスは、諦めたように舌を出して空気入れを中断し、舞台の下手に置かれた机の上に、スーツケースから取り出したさまざまなユニコーンのぬいぐるみやグッズを並べていく。次第に、祭壇のような空間が出来上がる。一方、スクリーンには映像とテキストの投影が始まる。2019年のハバナ建都500年祭に向けて、路上に屋台が並び、祝祭に浮かれていく町。その路上を、ユニコーンのマスクを被ったカデナスが孤独に彷徨う。映像のなかで「ユニコーン」となって歩くカデナスの身体は言葉を一切発さず、無関心に通り過ぎられ、あるいはあからさまな好奇や侮蔑の視線を向けられる。「あれを見ろよ!」「馬? 人間?」「男? 女?」という声が無遠慮に浴びせられる。ショッピングストリートのベンチにカデナスが仰向けに横たわると、通行人の男たちがツノを触り、無抵抗だとわかるとからかいはヒートアップし、マスクの口に空き缶が突っ込まれる。マスクすなわち「仮面」は、社会を空気のように覆っているマイノリティへの侮蔑的感情を暴き出す装置でもある。

[撮影:岩橋優花 提供:KYOTO EXPERIMENT]
同時に、「ユニコーンのマスク」という殻を被ることは、一種の拘束具であり、言葉を外に発することを奪われる事態でもある。マスクの内側に仕込んだカメラが映す映像は、くぐもった息の音と相まって、息苦しさを増幅する。それは、「ツノのある身体」という牢獄 に閉じ込められた閉塞感であり、声を奪われた窒息状態であり、(とりわけマチズモが支配的な社会主義国家である)キューバ社会で生きることの抑圧でもある。映像と同じくユニコーンのマスクを被った生身のカデナスがビートに身体を揺らせて踊るが、音楽が止んでも、激しい呼吸音が響き続ける。
一方、映像にオーバーラップするカデナスの声は、規範や権力への抵抗と糾弾、そして自分自身を自ら再定義するための詩的な言葉を紡いでいく。額のツノは「牢獄」であり、欲望が溢れ出す「熱い鉄」であり、「私そのもの」である。だが、「クィア・フェミニスト」と公言するカデナス★は、「私はユニコーンではない」という否定形の生を生きなければならない。なぜ否定形なのか。詩のなかで何度も反復される「私はユニコーンではない」という矛盾は、極めて多義的にパラフレーズされる。私は、あなたたちが一方的な想像のなかで作り上げた架空の存在ではない。道を歩くだけで好奇の視線をじろじろと浴びせられる、カーニバルの見世物ではない。「珍しい希少種」として捕獲され、隔離される対象ではない。無害なファンタジーの世界の住人として搾取してよい存在ではない。「私の愛は奇形ではない」という宣言は、異性愛規範やシスジェンダー規範によって「不自然なもの」と断罪されることに対する異議申し立てである。

[撮影:岩橋優花 提供:KYOTO EXPERIMENT]
パフォーマンスの後半では、ユニコーンの浮き輪にカデナスが息を吹き込み、実体化を与えると同時に、詩の言葉は力強い肯定へと転じていく。「私は青いユニコーン」という宣言は、「ツノが生え、かつ青い馬」という二重にかけ合わされた想像であり、人々の凡庸な想像力を超えた存在であることの自己肯定であり、その分類不可能性はカテゴライズされることへの抵抗を示す。「私は人間にうんざりした。あなたの規則と視野狭窄に。遊園地と畜殺場に」と述べるカデナスは、詩の中でユニコーンの共同体へと向かう。そこでは、レディ・ハラウェイ(サイボーグ・フェミニズムを提唱したダナ・ハラウェイ)、レディ・ガガ、プレシアド(トランス男性の哲学者・クィア理論家のポール・B.プレシアド)、レディ・ホルン(ドイツのアーティストのレベッカ・ホルン)といった先人たちの名前が召喚される。
そして終盤、空気で膨らんだユニコーンの浮き輪を抱えたカデナスは、馬のいななきから、スペイン語で即興のラップを展開していく。字幕の日本語は、通訳者がスペイン語を聞き取りながら同時通訳的に打ち込んでいるため、加速するラップのスピードに追い付けなくなり、バグを起こしたように「変換エラー」が出てしまう。スペイン語の韻のリズムが熱量の渦となり、言葉は翻訳不可能な地点へと連れ出されていく。観客席の通路に侵入しながら、目の前で力強いエンパワメントの言葉が繰り出されるハイライトのこのラップにおいて、「意味が完全に理解できない」ことは、惜しまれるべき事態である。一方でそれは、「(マイノリティどうしであっても)他者を完全に理解できる」という安直な思い込みを再考させる契機としても働いていたのではないだろうか。

[撮影:岩橋優花 提供:KYOTO EXPERIMENT]
後編では、本作で参照されたレベッカ・ホルンの初期作品について言及しつつ、「ユニコーンであること」がもつ自己肯定的な力とは何かについて、さらに掘り下げたい。また、「ユニコーン」と同じく、「ヴァンパイア」という想像上の存在をクィアのメタファーに用いたイザドラ・ネヴェス・マルケスの映像インスタレーション《Vampires in Space》(2022)を参照しながら、想像と恐怖、属性と個人、「ツノ」「牙」という象徴とアイデンティティの問題について考察する。
(後編へ)※1/9公開予定
★──【インタビュー】マルタ・ルイサ・エルナンデス・カデナス(KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2025 公式サイト)https://kyoto-ex.jp/magazine/martha02/
鑑賞日:2025/10/24(金)