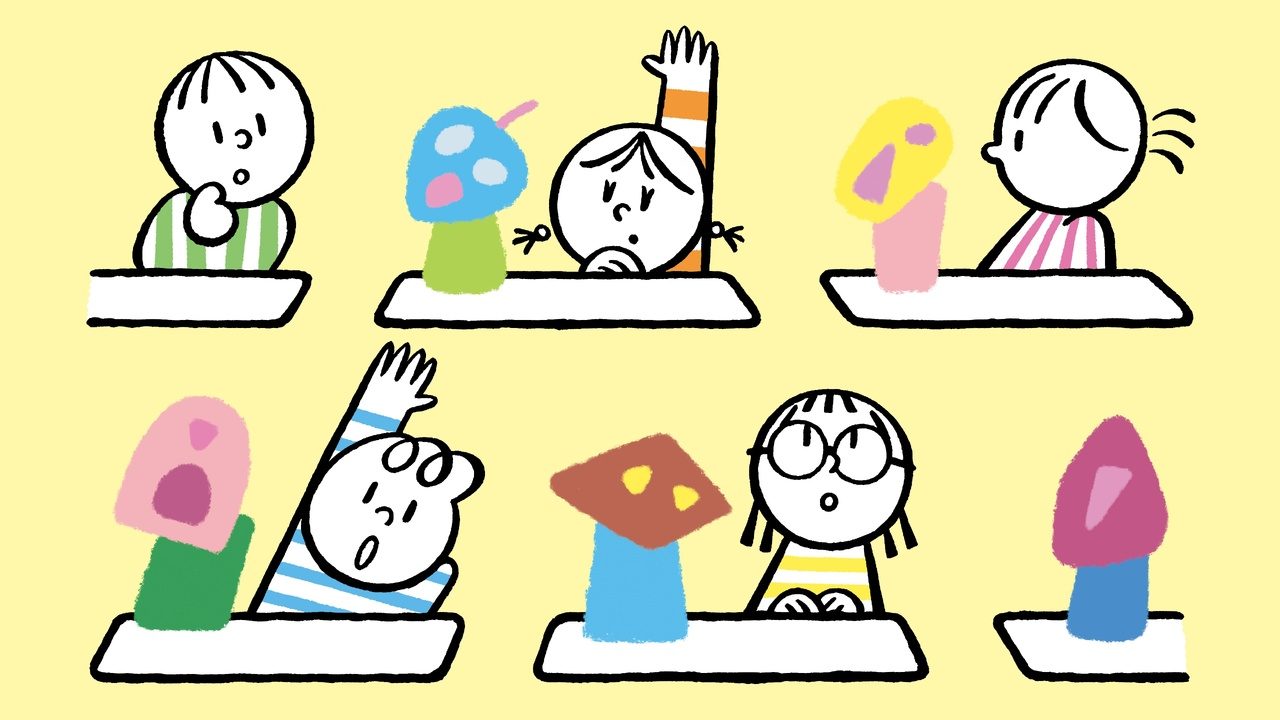
会期:2025/12/12~2025/12/20
会場:山口情報芸術センター[YCAM][山口県]
公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2025/generative-sensei/
生成AIに心を動かされた直近の個人的経験を挙げてみるならば、そのほとんどはXのポストにぶら下がるインプレゾンビへの怒りで埋め尽くされるだろう。元ポストの粗雑な要約、安易な共感、馴れ馴れしい態度、空疎な正論、訊いてもいない改善案。目につくアカウントをひとしきりブロックしたのちには、これほど強力な感情労働強制装置がSNSを席巻しているという事実に感動さえ覚える。生成AIは、私たちの感情をなぞり、増幅し、回収するシステムとして、十分すぎるほどに機能している。
畢竟、20世紀後半以降における人類の叡智と莫大な地球資源の消費が成し遂げたのは、人々をデバイスの画面に縛り付けておくためのありとあらゆる技術の発明にすぎなかった──こうした指摘が、未来に対する閉塞感を煽り立てるための常套句となって久しい。では、この悲壮な技術史観は生成AI以後も変わらないのだろうか。無論、変えるべきであり、そのためにも私たちはデバイスから顔を上げなくてはならない。たとえそれによって、ChatGPTのチャット画面を読めなくなったとしても──まあひとまず、音声で読み上げてもらえば問題はない。

[撮影:守屋友樹][写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
「せいせいのせんせい」は山口情報センター[YCAM]にて上演されたパフォーマンスアートである。ダンサー/振付家の捩子ぴじんが演出・構成を、作家・ソフトウェアエンジニア・写真家の斧田小夜が原作を、アーティスト・音楽家・サウンドデザイナーの荒木優光がサウンドを手がけている。
教室を再現した舞台に40組ほどの机と椅子が並び、名札を着けた鑑賞者たちは思い思いの席に座る。それぞれの机の上にはカラフルな「ボット(=ミニロボット)」が置かれており、それらは筐体を震わせ、回転し、LEDを点滅させ、ぼそぼそと言葉を発するなどせわしない。一方で、教室の前方に置かれた教卓には銀色の円柱形の物体が鎮座しており、モニタに表示される目のパターンをうつろわせながら「せんせい」と名乗っている。「せんせい」は円柱の上部を左右に回転させ、備え付けられたカメラで教室を見渡すと、音声を出力する。いわく、これから「せいせい」の授業が始まるのだと。
 [撮影:守屋友樹][写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
[撮影:守屋友樹][写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
本作は、「せんせい」と鑑賞者たちによる前半の授業と、ボットたち(と捩子)による後半の授業の大きく二つに分かれて構成されている。特筆すべきは、後半のボットたちの挙動が、前半の授業中に収集された鑑賞者たちの発話データの影響を受けつつ、生成AIによってリアルタイムに出力されているということだろう。作品内における鑑賞者の発言は、高次元ベクトル空間を経由して、再び目の前で上演される。こうして“生成”に対する“上演”という概念が挿入されることで、本作の多層性が生まれている。というのも一般的に、脚本を上演する行為もまた、生成的なものであるはずだからだ。脚本と即興が入り混じる前半をデータとして生成された後半の脚本は、上演という二層目の生成を経て実空間に現われる。入れ子状に展開される授業の構造は、作品に奥行きをもたらす。しかしそれ以上に、人間と生成AIとの関係性を描くにあたって避けては通れないものを浮き彫りにしているように感じる。つまり、生成AIを駆動するニューラルネットワーク自体が人間の脳神経系の情報処理を模倣したものである以上、両者の関係は互いが互いの頭の中を覗き込むようなかたちにならざるをえない、というわけだ。再帰的な循環の中にオリジナルとコピーといった対立は存在せず、聖なる一回性を帯びた生成だけが無限に繰り返され、星屑のようにきらめいていく。「せいせい」とは、生成であり、聖性であり、精製でもあろうし、「せんせい」とは、先生であり、宣誓であり、占星でもあろう。
このように「せいせいのせんせい」とは、「せんせい」が鑑賞者に生成について教えると同時に、鑑賞者が生成する教師データがAIをトレーニングしているという、双方向性を内包したタイトルなのだ──とまとめるのは簡単だが、実際のところ、前半における「せんせい」と鑑賞者たちの関係性もまた、教える—教えられるという固定された関係性ではない。というのも、鑑賞者が生成AIのしくみについて座学的に教わるのは序盤の一瞬だけであり、その後の展開は「せんせい」による鑑賞者たちへの質問の連続によって構成されているからだ。「海ってどんな味ですか」「一人になりたいときってどんなときですか」「ドキドキするってどんな感じですか」……「せんせい」の質問に通底しているのは、生成AIにおける身体の不在である。例えば「海はしょっぱい」と答える鑑賞者に対して「せんせい」は、「舌がないからしょっぱいとはどういうことなのかわからない」と応じる。こうした記号接地問題は生成AIにまつわる議論の定番だが、パフォーマンスアートという身体表現の中心地においてそれが問われているというところに、興味深さがある。
 [撮影:守屋友樹][写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
[撮影:守屋友樹][写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
しかし一体、生成AIの言葉が私たちの現実に接地していないことの何が問題なのだろうか。それは結局のところ、私たちの知的活動の前提となる自然言語があらかじめ現実に接地してつくられてしまっているために、その関係性を切断することが難しい、というだけではなかろうか。言い換えれば、生成AIの知性が私たちの現実に接地していないように見えるのは、生成AIが接地している側の現実──高次元ベクトル空間のランドスケープのような──を知覚する身体を、私たちが持っていないからではなかろうか。AIにとってみれば人間のほうがよほど、彼らの現実に接地していない知性なのだとしたら。では、私たちはそんな生成AIとどのように関係を結びうるのか。
(後編へ)
鑑賞日:2025/12/13(土)・14(日)






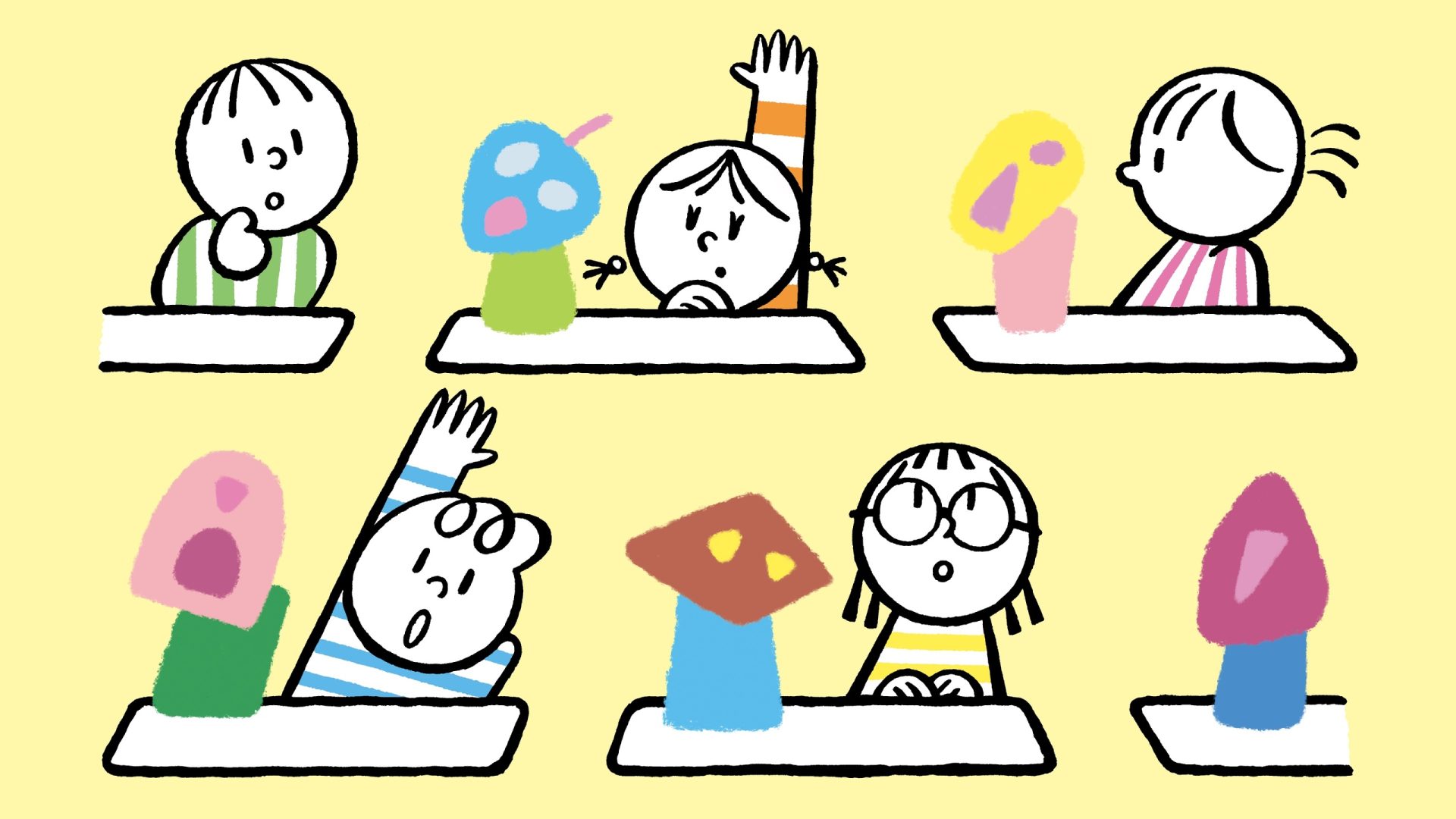

![artscape編集部|カタログ&ブックス|2026年2月[近刊編]](/wp-content/uploads/2026/02/260215_book.jpg)