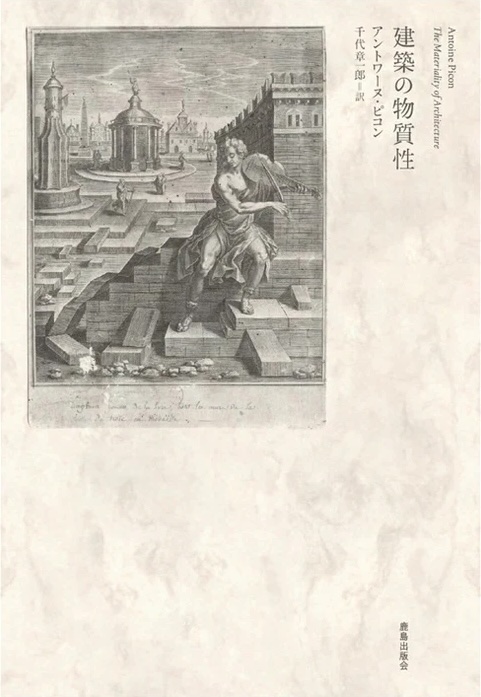
翻訳:千代章一郎
発行所:鹿島出版会
発行日:2025/12/15
公式サイト:https://kajima-publishing.co.jp/books/architecture/wk-zafnrn/
本書『建築の物質性』は、そのきわめてシンプルなタイトルゆえに、かえって読者を戸惑わせるところがあるだろう。建築が物質であることはひとつの明白な事実であり、そこで「物質性」と言ったときに何が問われているのか、そのタイトルだけでは計りかねるところがあるからだ。
著者アントワーヌ・ピコン(1957-)はフランス生まれの建築史家であり、ハーヴァード大学のデザイン・スクールで長らく教鞭をとっている。その英仏の著作一覧を眺めてみると、啓蒙期フランスの建築・技術史から、現代建築におけるデジタル技術の問題まで、幅広い興味関心を有していることがわかる。そのなかでも比較的新しい仕事に属する本書(仏:2018/英:2020)は、建築における「物質性」という核心的な問題を議論の俎上に載せるものである。
著者も序論で述べるように、本書における「物質性(materiality)」という言葉を、建築の「物質(matter)」や「材料(material)」と混同してはならない。著者いわく「物質」とは、具体的かつ抽象的な、ある事物がつくられる基盤に相当する。次に「材料」とは、木・鉄・コンクリートなどの、それがもつ特性と密接に関連した物質をさす。そして本書が「物質性」と呼ぶのは、「現象、事象、物、体系の物質的な拡がりのこと」であり、その本質は「関係性」にあるという(19頁)。
この「関係性」というタームは、本書を通じて幾度となく強調される。これが意味するのは、おおよそ次のような事柄である。すなわち、われわれ人間が物質や材料と──さらにつきつめれば物理的な世界と──結ぶ関係性こそが、ここで物質性と呼ばれるところのものである。物質性は物質そのものではないし、物質に内在する本質のようなものでもない。それは人間が物質とのあいだに取り結ぶ関係のことなのだ。
あわせて著者が導入する「物質性のレジーム(体制、制度)」という言葉が象徴するように、この人間と物質の関係はアプリオリなものではなく、時代によって大きく異なるものだ。そのような前提のもと、著者は古来のヴォールトからル・コルビュジエのドミノ・システムにいたるまで、建築を〈物質や材料を通じてみずからを顕在化させる芸術〉として捉え、それをいくつかの関連するトピックと結びつけながら論じていく。具体的には言語(第二章)、生気(第三章)、デジタル技術(第五章)などである。
本書のなかでとりわけ印象的なのは、21世紀に入ってからの思想のトレンドであったオブジェクト指向存在論(OOO)やニュー・マテリアリズム(NM)が、明らかな仮想敵とされていることだ。ピコンによれば、これらの思想においては物質の重要性が謳われているものの、そこでいう物質の内実はきわめて一面的なものにとどまっているという★。これに対して──繰り返しになるが──本書が物質性の旗印のもとに提唱するのは、人間が物質とのあいだに取り結ぶ具体的な関係性に目をむけることである。
ある見方からすると、本書は現代思想における「物質(性)」概念の氾濫にいったん懐疑的なまなざしを注ぎ、建築(技術)史の立場からそこにいくつかの建設的な議論を付け加えようとしたものである、という評価も可能だろう。たとえば、本書が第三章で問題とする「生気(animation)」は現代のマテリアリズムでも重要視されるトピックのひとつだが、本書ではこれを、「装飾」をはじめとする建築表現の問題として論じている。物質に生命を付与するという営みひとつをとっても、建築家はそれを古来より具体的な実践として行なってきた。本書はそうした現代的な問題にたいして試みられた、ひとつの歴史的なアプローチである。
★──ただし、過去に本欄でも取り上げてきたカレン・バラッドやジェーン・ベネットの理論を見るかぎり、NMにおける「物質性」は、まさに本書が主張するような歴史的・関係的な形成物にほかならない。著者ピコンが具体的にどのような論者を想定しているのか不明だが、本書の立場はNMとそこまで相反するものではないように思われる。
執筆日:2026/02/12(木)







