 |
||||||||||
|
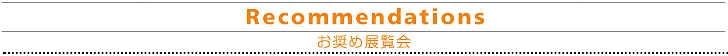 |
|
松井智惠展「寓意の入れもの」
木ノ下智恵子[神戸アートビレッジセンター] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●学芸員レポート 日本中がサッカーワールドカップで湧いた6月の余韻を残しつつ迎えた夏本番。私は世間の盛り上がりとは無関係に「芸術の秋」の到来と共に繰り広げる3つの企画「神戸アートアニュアル2002」「新開地アートストリート(SAS)」「トヨタアートマネジメント講座・チャレンジ編」の準備に追われている。 そんな悲惨な状況を元気づけてくれる「アート三都物語」が大阪・京都・神戸の各地で繰り広げられた。 4月下旬の大阪では、ギャラリー小柳、Gallery HAM、ギャラリーヤマグチなど16のギャラリーとメディアショップ、美術出版社など4つのアートブックのショップや出版社が参加する『ART in CASO 2002 Portal』(大阪/CASO)と小山登美夫ギャラリー、白土舎、ギャラリーゼロなど8ギャラリーが参加する『OSAKA ART FAIR,2002 StART』(大阪/SUMISO)の関西における本格的なアートフェアが2つ開催され、財布の紐が堅い関西アート市場に一石を投じられた。 5月の京都では、2001年の春に解散したカルト的なサブカルチャーの金字塔として『夜想』『ur』などを出版してきた「ペヨトル工房」の功績を体現した2日間限定の『ペヨトル・ファイナル・イベント「memoryメモリー」』(京都/西部講堂)と共に、幾つかのギャラリーが連動して自主企画展を同時開催する『KYOTO ART MAP』で京都のアートスペースを網羅したマップの作成、共通のフォーマットによるアートボックスの発売、ログズギャラリーのパフォーマンスによる合同パーティなどが開催され、京都文化の基礎である多くの美大生達にアートの多様性を示唆した。 5月下旬の神戸では、1994年に芸術と社会のつながりをより密接にすることを目的とする12人のアーティストによる任意団体として様々な活動を続けてきた「C.A.P. ー芸術と計画会議」が、1999年当時、空きビルとなっていた旧神戸移住センターの存在に着目し「C.A.P. HOUSE-190日間の芸術的実験」を続けてきた意義と成果が結実して、2002年、C.A.P.はNPOの認定を受け、建物の管理や資料展示の委託を神戸市から受託することを契機に、新生「C.A.P. HOUSE プロジェクト」をスタートさせた。 海外の状況を体感することも魅力だが、まずは自国の土壌を耕すことから始めなければ芽は出てこないことに危機感を覚える賢者達が、国や地域のニーズに則したシステムやアクセス方法を提案している。その環境整備を試みる一員として自分に何が出来るのか……衰える体力に寄る年波を感じる今日この頃、カフェイン飲んでタイガーバームを塗りたくって乗り切ろう!。
[きのした ちえこ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|










