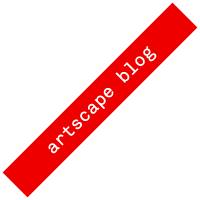「SPACE OURSELVES」とは建築を設計する専門家だけでなくその場所で生活し日々の営みを行うすべての人=私たちによって生み出され、または発見され、あるいは実践されていく空間のあり方ということを意味している。前回は、経緯とこのSPACE OURSELVESについて述べたが、今回は個別の提案を紹介しつつ、その後の展開について記していきたい。
個別の作品の紹介にあたって、SPACE OURSELVESを便宜上「つくる」と「つかう」の2つの側面から考えてみたい。これは京都展の際におこなった2回のトークイベントでもフレームとして用いたわくぐみでもある。
たとえば、「つくる」。藤田雄介の「ソーイングハット」は薄い木材を竹細工のように編む事で空間をつくり出す。ここで採用されている「編む」という行為は、誰もがそのつくるプロセスに参加できるという意味で工芸的な性格をもっている。また、近藤哲雄の「原っぱの素」も、植物の種がはいった糸を編む事で大きな敷物を作り出すという作品である。とはいえ両者ともにつくる時間だけではなく、つくった後に、そのつくったという経験を持つ人が再度関わる事ができる仕組みまで射程に入れている。また中村竜治の「コンクリートルーフ」は不思議なカタチをしたRC(鉄筋コンクリート)造の屋根だ。一般的に公共建築はRCでつくられている。それと同じものを自分たちの手で作り出す事で、素材やさらには既にある公共建築への意識も変えていけるのではないかと問いかけている。確かにコンクリートという素材は土と水をこねるという点で、工芸(ここでは陶芸)的で、そこには身体的な近さを感じさせてくれる。また元木大輔のサッカーゴールパヴィリオンのように、普段見慣れているサッカーゴールを構造体と見立て、人が集まるための大きなテントをつくろうという提案も愉快である。体育の時間や部活の時にみんなでサッカーゴールを抱えた記憶を持つ人も多いだろう。

中村竜治「コンクリートルーフ」

元木大輔「サッカーゴールパヴィリオン」
また「つかう」ということを共有するということもある。一緒に使うというだけでなくその場所の運営方法を一緒に考えるということである。島田陽の提案する「SO(C)I(A)L KITCHEN」がある。これは東北の津波の被害を受けた土地で、その海水をかぶった土を利用した版築の提案である。いまでは「がれき」と呼ばれているものが、ほんの少し前までは誰かの大切な何かであった。その事を忘れてはいけないと、そのがれきと土で人が集まる場所をつくりだす。その中心にキッチンを置く事で、地元の芋煮や、集会がひらかれる新しいコミュニティの場へと変わっていくのではないか。また、米澤隆による「わたげ」はおまつりの屋台のような小さな移動公共施建築だが、屋台のデザイン以上に、屋台がめぐることで生まれる時間(いわゆるハレとケにちかい感覚)が仮設住宅での人と空間、人と人の関係を能動的なものにしていくだろう事が意図されている。青木健の「TreePot」のように、wifiという情報インフラとベンチの組み合わせという提案ももののデザインというよりも、コミュニケーションの発生するインフラの整備という呈である。

米澤隆「わたげ」
また、白須の提案も、具体的なかたちをもっていない。ワークショップを通じた記憶の共有とデータベース化による空間、もしくは風景へのアプローチそのものを建築の新しいかたちとして提示している。街の日常を形づくっているインフォーマルな様々な痕跡は、決定的に重要でありつつ非常に失われやすく、しかも可視化されていない。そのような隠された共有されている風景を丁寧にあぶり出していく事こそ、街の公共性にとって重要ではないか、そのように述べている。

白須寛規「風景の公共性」
京都での展覧会が終了した後は、東京のArt Chiyoda 3331にて震災復興アクションプログラムの一環として巡回展を実施することとなった。この時あらたに2組の建築家が加わり総勢16の提案が、主に震災復興という枠組みの中で提示される事となる。さらに、その後浜松での巡回展示をおこなった。現在はこの一連の展覧会の記録の作成と、次の展開に向けた準備を進めている。
忘れてはならないのは、依頼から2週間少々の間に、公共の新しいかたちという問いかけに応えることができるというのは、建築家達が日頃からたとえ住宅やインテリアの設計であったとしても、人が人といる事を空間としてどう支えるのかということ=公共性を考えているからではなかろうか?そんなことに少し希望を感じた。そして、ここに提示された建築のかたちは、随分と自由に思考されているように感じられる。そのような現代の建築家達の柔軟な思考の先に、ただ物理的な強さではない強い建築がつくられていくのではないだろうか。