 「展評」とは、奇妙な慣行なのかもしれない。数多ある展覧会の中から特定のものを選り、その内容や見どころを手際よく紹介しつつ、企画趣旨や背景に対しても一家言コメントするためのスペース……多くの美術評論家にとって、この「展評」は評論活動の中心を占めるものだが、半面それは与えられる字数に乏しく、また作家や作品を直接ではなく、展覧会というバイアスを介して論評する、制約が多い上にどこか捻れを孕んだ形式ではないかという印象を、その一書き手でもある私自身強く持っている。最近では「展評」を「レビュー」と呼ぶことも多いようだが、呼称を横文字にしたところで問題の本質が変わるわけではなく、展覧会やメディアの現場において、review=再び見ることという語本来の意味が意識されることは、まずほとんどないと言ってよい。 「展評」とは、奇妙な慣行なのかもしれない。数多ある展覧会の中から特定のものを選り、その内容や見どころを手際よく紹介しつつ、企画趣旨や背景に対しても一家言コメントするためのスペース……多くの美術評論家にとって、この「展評」は評論活動の中心を占めるものだが、半面それは与えられる字数に乏しく、また作家や作品を直接ではなく、展覧会というバイアスを介して論評する、制約が多い上にどこか捻れを孕んだ形式ではないかという印象を、その一書き手でもある私自身強く持っている。最近では「展評」を「レビュー」と呼ぶことも多いようだが、呼称を横文字にしたところで問題の本質が変わるわけではなく、展覧会やメディアの現場において、review=再び見ることという語本来の意味が意識されることは、まずほとんどないと言ってよい。
だからと言うべきか、本書『写真という出来事』のあとがきで、港千尋が本書を「レビュー」と位置付けていたのは、当初いささか奇異に感じられた。もちろん、多くの美術展や写真展に対する言及があるからといって、本書は狭義の「展評集」などではないし、この数年港氏の著作に親しんできた私にとって、氏がまずそんな本を著さないことは容易に推測されることでもあった。では本書はいかなる書物なのかというと、基本的には冷戦を前後する時期(「クロニクル1988-1994」というサブタイトルがそれを物語っている)に試みられた、世界を股に掛けたフィールドワーク・エッセイ(というジャンルがあってもいいと思う)となっている。港氏の関心の対象は美術や写真に限らず多岐に渡るし、本書にはいわゆる「展評」ではまずお目にかかることのない「移動」や「群衆」といったキーワードが頻出する。港氏が本書を「レビュー」と称んでいたのに驚いたのは、もちろん冒頭で述べたような背景があってのことだが、語本来の意味からすれば、「〈レビュー〉とは異なる出来事のあいだに新たな関係の線を見つける、〈再発見の旅〉である」という港氏の見解は至極まっとうなものであり、いつの間にか「レビュー」=「展評」という図式が定着してしまった、狭い“業界”の常識の方が逆に転倒したものだと言うべきだろう。
写真家・批評家としての港千尋のキャリアについて、この場であらためて紹介するには及ぶまい。80年代半ば以降、長らくパリを拠点とした世界的規模のフィールドワークを展開してきた港氏は、カメラを触手として現実世界の様々な断面を切り取ってきた。ベンサム=フーコーの〈パノプティコン〉やホルヘ=ルイス・ボルヘスの『不死の人』にも精通した豊かな教養と、サラエボの「悲劇」をも自ら検証する行動力――この精神と身体の傑出したバランス感覚こそ港氏の散文の真骨頂であり、豊富なフィールドワークに立脚したその成果は本書や以前の『注視者の日記』で十全に発揮されている。港氏は自らの批評を地理批評geo-critiqueと称しているが、確かにこの呼称は、恐らく国際的にもあまり類例のない特異な知の探求を適切に言い表わしているだろう。
以上のような解釈は、“行動派の知識人”といった人物像と背中合わせのものであるし、また港氏が、日本人としてはただ一人、あのサルマン・ラシュディらが名を連ねる「国際作家会議」のメンバーであるという事実も、その人物像をさらに補完するだろう。だが、彼の著作活動全てがそのようなステレオタイプな枠組みに帰着するわけではない。というのも、写真家・批評家としての港氏は、既に述べた旺盛な行動と並行して、自分の本来のテリトリーである映像を、極めて原理的・思弁的に探求していこうとする姿勢をも併せ持っているからで、その成果の一端はもう一冊の新刊『映像論〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』に反映されている。正直な話、本書の議論は前著『記憶』と同一の主題を変奏している感が強く、それほど新鮮な印象は受けなかった。エティエンヌ=ジュール・マレーの「クロマトグラフィ」やサミュエル・ベケットの「フィルム」、あるいはクロード・ランズマンの「ショアー」など、港氏が映像分析のためによく引き合いに出す例も、他で多く論評されていることもあって、もはやそれほど刺激的なものではあり得ない。だが、映像の歴史をたどりながらそのアーカイヴァルな特性に注目し、その役割を「記憶」というキーワードへと収斂させていく再構成はあくまで港氏独自のものである。その豊かな構想力はやはり驚くべきもので、また港氏自らが映像の創り手である事実も、氏の議論にさらに説得力を与えているだろう。“行動派”ということもあり、港氏の言説はよくデリダやブルデューに例えられる。しかし、あくまでも私見だが、「映像」と「記憶」を結びつけるその知覚図式の分析や論の展開、頻繁に言及される具体的映像等から察して、こと映像に関する限り、港氏の関心はベルクソン=ドゥルーズ(特に『映画論』)により近接しているように思われる。
フィールドワークの記録としての『考える皮膚』『注視者の日記』と、多面的映像研究としての群衆論』『記憶』……ほぼ同時期に刊行された二冊の新刊書『写真という出来事』と『映像論』は、図らずも? 港氏の著作活動における二つの系統にそれぞれ対応するものであった。もちろん、この区分は蓋然的なものに過ぎないし、現実との密接な並行関係にある港氏の批評の今後を、安易に憶断できるわけもない。ただ一点明確なのは、「移動」「群衆」「消滅」「抵抗」「記憶」といった、系統の別を問わず氏の著作に頻出するキーワードが、あるときには写真と、またあるときにはモーション・ピクチャーと、いずれにせよ映像=イメージと分かちがたく結びついた用語であること。20世紀は映像=イメージの世紀である――あるいは、港氏の言わんとするところは、この一語に尽きるのかもしれない。 |
|

『写真という出来事
クロニクル1988-1994』
河出書房新社
\2,800
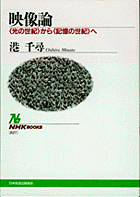
『映像論〈光の世紀〉から
〈記憶の世紀〉へ』
NHKブックス |
|