reviews & critiques ||| レヴュー&批評 |
|
||
|
|||
| 《アラーキーレトログラフス》 ―荒木経惟回顧展 |
|||
| 八角聡仁 | |||
|
|
|||
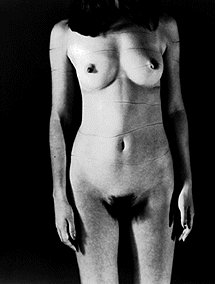 (C) 荒木経惟 |
|
| 写真には「情」がなくてはいけない、と荒木はことあるごとに口にし、作品のタイトルにもしばしばその一語を用いてきた。それに批判的な見方をする者は、人間的な感情を排した冷徹な「客観性」こそが写真の本性であることを指摘し、そこに私的な情念を持ちこもうとすることの反動性を嗅ぎとってきたし、一方で荒木を支持する者の多くは、プライヴェートな題材の選択や被写体との関係性の現われを、写真の「機械的」な冷たさに対する「現実」の温度や湿度の生々しい表出として肯定してきた。しかし、おそらく荒木の言う「情」は、個人的、内面的なパトスに発するものでも、写真の「機械的」な本性に相対するものでもない。すなわちそれは眼前の現実を「過去」へと、あるいは「死景」へと変貌させながら、「それはかつてあった」という「傷痕」を「客観的」に残していく写真というメディアそのものに由来し、したがって「現在形」のデジタル・イメージには決して見出されることのない、いわば唯物論的な「情」なのである。 | |
| タイトルが示すとおり荒木にとって国内では初の回顧展である《アラーキーレトログラフス》は、先頃とりあえず完結した『荒木経惟写真全集』(平凡社)が撮り下ろした作品を数多く含んだ「現在進行形」のものであったのと同様に、「夏小説」と題してこの数カ月に撮影された新作シリーズが、「センチメンタルな旅・冬の旅」や「エロトス」、東京の街や花の写真など、これまでの代表作とともに展示され、会期中さらに新たな撮り下ろし写真が追加されている。そこに、いかにもノスタルジックな「回顧」という全体化から逃れ、あくまでも「完結」や「完成」を拒もうとする写真家の決意を見てとることは容易い。実際、原美術館の空間を中庭や窓、あるいは常設の他のアーティストの展示室まで最大限に利用して行なわれるこの写真展から受ける印象は、作家の「全体像」などを決して構成することのない奇妙なまでの(戦略的な)散漫、平板さなのである。しかし真に興味深いのは、荒木が単に美術館的な展示の制度から逸脱してみせるのみならず、写真の物質的表層に露出する「情」に対しても従来といささか異なった姿勢を見せ始めていることだろう。つまり「傷痕」を通して否応なく産出される「不在」への感傷と「過去」への郷愁に対するイノセントな肯定が、いまや写真それ自体を「死」との戯れにおいて制度化する退嬰的な営為となりかねないことの危険に写真家はきわめて自覚的なのであり(とりわけ亡き妻をめぐる物語が写真の表層を素通りして「作品」化してしまうことへの秘かな抵抗を見逃すわけにはいかない)、最近頻繁に発表されているカラーコピーやポラロイドによる作品は、写真の「情」をその零度へと限りなく近づけることによって、「芸術」的な鑑賞形態に断じて回収されえない写真の表層的な「暴力」と「軽さ」とを同時に露呈させ、一方でそこに不可避的に残留するささやかな「情」を掬い(救い)あげていく試みにほかなるまい。 |  原美術館中庭  館内 |
| 荒木が絶えず「未完成」の状態に開いておこうとするこの写真展で実践しているのは、単に「現在」と楽天的に同調することでも、写真に刻印された過去の「傷痕」を悲劇として物語ることでもなく、つねに切断されつつ現前する「過去」と「現在」という写真の時制を、多様なスタイルと圧倒的な作品数によって錯乱させつつ、写真の「情」が発生する根源的な場所そのものを複数的、遍在的に反復することであるだろう。レトロスペクティヴとフォトグラフスを掛け合わせたタイトルそのままに、荒木は自らの歴史=物語とともに、写真というメディアの始源を新たに発見しなおそうとしているのかもしれない。 |
| 《アラーキーレトログラフス》 |
| 会場:原美術館 |
| 会期:1997年8月2日(土)〜10月12日(日) |
| 問い合わせ:Tel. 03-3445-0651 |
|
|
top | |
Copyright (c) Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1997
