キュレーターズノート
A Nightmare is A Dream Come True: Anime Expressionist Painting(悪夢のどりかむ)
山口洋三(福岡市美術館)
2012年08月15日号
カタールのドーハで村上隆の大個展「Murakami - Ego」が開催された。新聞紙上で取り上げられたし、『美術手帖』や『芸術新潮』が特集を組んだからご存じの読者も多いだろう。artscapeの執筆者のなかでこれを見に行った方はいらっしゃるだろうか。いらっしゃるのかもしれないが特に触れた方は(いまのところ)いないようだ。そういう私も残念ながら未見。しかしこれだけ海外で活躍し、作家としての名声や知名度とともに、海外における日本の現代美術の存在感をも高めているのだから、彼の作品や言動についてもっと活発に論じられてよいのではと思う(個人的なブログやツイッターではなく)。しかし、一方で彼の作品、立ち振る舞いを「毛嫌い」する向きが多いことも事実。『芸術新潮』5月号の特集の題名「まだ村上隆が、お嫌いですか?」はその状況を的確に言い当てている。

『芸術新潮』2012年5月号
去る5月20日、その村上隆を当館(福岡市美術館)に招いて、「福岡ミュージアムウィーク」の一環として講演会を開くことができた。彼と私とを接近させてくれたのは、意外かもしれないが菊畑茂久馬である。その経緯と講演内容は当館広報誌『エスプラナード』7月号に書いたので参照いただきたいが(主要な美術館で読めるはずです)、村上講演の内容は極めて良質のもので、多くの先入見や偏見が一気に氷解した。これは講演を聞いていた240人の観客も同じ思いだったに違いない。内容としては、彼の主著作である『芸術起業論』『芸術闘争論』(ともに幻冬舎、2006、2010)とかぶるところが多いし、さらに最近出版された『村上隆完全読本──美術手帖全記事1992-2012』(美術出版社、2012)でも補完される。しかしその内容を、最近の彼の大きな仕事であるドーハでの個展「Murakami - Ego」とのかかわりで生声で語られると、説得力は倍加する。私はこの講演会を、村上を「まだお嫌い」な方にこそ聞いてほしかったと思っている。
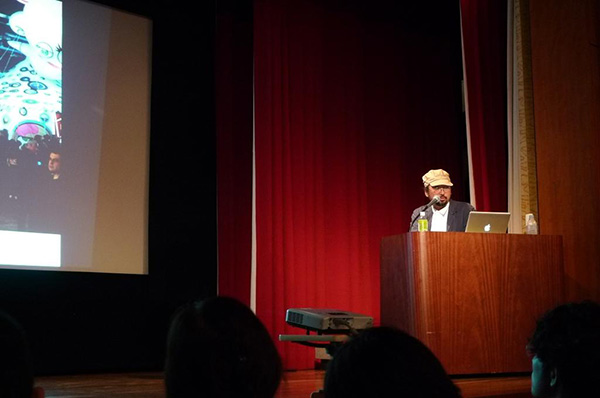
講演会風景(福岡市美術館、2012年5月20日)
さてドーハはかなわなかったのでせめて東京で、というわけでないのだが、村上隆キュレーションによる「A Nightmare is A Dream Come True: Anime Expressionist Painting」展(通称「悪夢のどりかむ」展)をカイカイキキギャラリーで見た。マンガやアニメの作風で絵画を制作する若者6人のグループ展である。展示された作品は、村上隆の作品よりもっと明確に、アニメやマンガの影響が色濃い。いわば「オタク」的な絵画。しかしこの展覧会は、「現代美術」の展覧会として提示されている。美術 vs. サブカルチャー、という図式ではない。村上は、オタクと現代美術を接続したいと真剣に取り組んでいる。
しかしそれは、村上自身これまでの仕事のなかでやってきたことでもある。等身大のアニメ風のフィギュアによる立体作品による「Miss ko2(Project ko2)」、彼が海外で企画した展覧会三部作「スーパーフラット」(渋谷パルコギャラリー、2000;ロサンゼルス現代美術館、2001)、「ぬりえ」(パリ・カルティエ現代美術財団、2002)、「リトルボーイ」(ジャパン・ソサエティー・ギャラリー、2005)がそれである(残念ながら筆者はいずれも未見)。これに加え、村上はいままた新たに、その接合を試みようとしている。
村上の本展企画意図については、カイカイキキギャラリーのウェブサイトにすべて掲げられているし、同内容のものが展覧会会場でも配布されていた。そこにはこうある。「日本の悪夢は世界の未来(悪い意味で)」。村上が2000年に刊行した画集『スーパーフラット』にも、似た響きの言葉があった。それは「日本は世界の未来かもしれない」。しかし12年前の「かもしれない」に込められた、シニカルながらもどこか楽天的な響きはここでは完全に消え失せ、震災以後の日本の社会的文化的政治的状況を「悪夢」と断じている。カタールのドーハで空前規模の大個展を開催するまでに、世界の美術シーンにおいて成功をおさめた村上が、「現代美術」が日本社会において経済的な基盤を持ち得ないままでいること、そしてそのことに気がつかない(ふりをしている)作家と業界関係者に対して深く失望している。彼はその原因を、戦後70年間の米国の保護のもとでの「愚民教育」、つまり米国式の「夢はいつか叶うもの」という価値観による教育に求める。個人が好き勝手に価値観を追い求めた結果、社会のなかの個人の位置や役割を考慮しない無秩序、無責任の蔓延する荒涼たる社会が到来してしまったというのである。国家や社会の裏打ちのないまま放任されてきた個人の表現=日本現代美術。村上は、客(=経済基盤)のいない日本ではなく、客のいる西洋に、その活路を求め(続け)る。ならば、否が応でも、作品も作家も自らのよって立つ根拠地「日本」の翻訳説明が必要になる。「好き勝手の個人」が通用するはずがないし、なぜ日本人作家も関係者もその労を怠るのかと苛立ちを隠さない。
「オタク文化」はこの悪夢の産物である。企画展「リトルボーイ」は、まさにそれがテーマとなった内容だった(図録は読みました)。しかしついに市場=客を持ち得なかった戦後の現代美術と異なり、オタクは国内に独自の市場を持ちえて、いまや海外で日本文化の紹介役を担うことすらある。
卓抜した作画技量とセンスによって、ネット上のイラストコミュニケーションサービス「pixiv」で、すでに多くのイラストを発表して評価を得ているJNTHEDや東京芸大に在籍しながらもイラストの分野でも活躍するおぐちといった作家が、この展覧会においては「アナログ」の絵画に挑んでいる。ペンタブレットを絵筆に持ち替えた、ただそれだけなのだが、「絵画」の制度性を考えればこの方向転換は大きな意味を持つ。モニタ上にしか存在しなかったものが、データをプリントするわけではなく、絵具と支持体という実体を得て目の前に現われる。そのために、彼らはカイカイキキにて制作を行ない、村上の元で「アーティスト」としての修行を積んだ。


左=JNTHED《アーバンナイト金太郎姫》、2012
Acrylic on canvas, 2590 x 1818 mm
© 2012 JNTHED/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.
右=おぐち《角》、2012
Oil on canvas, 1620 x 1303 mm
村上は、日本という「悪い場所」で独自に花開いたオタク文化の担い手たちに、「アーティスト」の意識を芽生えさせ、国家の意識を持たせようとしている。もっとも「このアニメの少女みたいな絵が『絵画』であって『国家』だって?」とまゆをひそめる向きも多いことだろう。見た目にはいわゆる「オタク絵」としか見えない彼らの作品を称揚する村上の姿勢に、西洋の美術マーケットの需要を見越して周到に準備をしているだけではないかと。そのさきには売上という結果がある。
私自身も、市場での価値観と美術的な価値観とは相いれない部分があるだろうと信じており、それはいまも変わらないのだが、しかし経済的な成功を忌避して「悪い場所」に居直り続けた結果として「客のいない」状況をもたらしてしまった美術状況を全面肯定するつもりもない。日本の作家を含む美術関係者は、作品を金に換えることについての(左翼的な)罪悪感、後ろめたさを建前としては感じつつも、しかし金なしには自らの創作基盤や美術状況が成り立たないことを本音として抱えている。彼の行動や言動は、いつもその本音の部分に切り込んでくる。
それで、今回の「悪夢のどりかむ」の作家たちであるが、彼らがその先兵足りうるかどうかに関しては、正直なところよくわからない。デジタルイラストをアナログ絵画へ落とし込む作業におけるその両者の落差に関しては、特にデジタルイラストに関しての素養が自分にはあまりないので、それほどすごいギャップなのかどうかについてすら、いまはまだ見識を示せない。
しかしひとつ言えることは、こうした表現が、毎年3月に上野で行なわれる推薦制の某公募展や、主要な現代美術画廊で見ることのできる若手の作家たちの展覧会よりもはるかに明快で、また楽しく、活気のある空間だったということである(もちろんここには私自身の趣向もおおいに反映するだろうからあまり一般化はできないが)。「アニメっぽい絵」ではない、もろに「アニメ」の絵を描く彼らがどのような活躍を見せるのか、「悪い場所」からの逆襲はなるか、しばらく追ってみたい。
A Nightmare Is A Dream Come True: Anime Expressionist Painting
会期:2012年5月26日(土)〜6月21日(木)
会場:Kaikai Kiki Gallery
東京都港区元麻布2-3-30 元麻布クレストビルB1F/Tel. 03-6823-6038



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)