キュレーターズノート
バックナンバー
映画館の歴史から辿る、まちとメディアの変貌
[2024年02月01日号(前原美織)]
遡ること20年──。2003年11月に山口情報芸術センター[YCAM]は開館した。YCAM(通称ワイカム)はスタジオ、劇場、映画館、図書館を含む公共の「複合文化施設」である。映画上映は開館当時から始めていたが、開館時には映画館の運営の経験者...
客席にいない誰かがいるということ──谷中佑輔『空気きまぐれ』、デイナ・ミシェル『MIKE』
[2024年01月15日号(谷竜一)]
「本公演は、『リラックス・パフォーマンス』です。客席に長時間じっと座っていることが難しいお客様(例えば、自閉症、トゥレット症候群、学習障害や慢性的な痛みなどがある方)を歓迎します」 これは、Co-program カテゴリーA採択企画である、...
「アートしている」人たちが確かに地域にいること──万田坑芸術祭と「おぐに美術部と作る善三展『好きなものを好きって言う』with 森美術館」からの風景
[2023年12月15日号(坂本顕子)]
万田坑とは、かつて熊本県荒尾市と福岡県大牟田市の県境にまたがるかたちで位置し、操業した三池炭鉱の代表的な坑口のひとつである。明治から昭和初期にかけて多数の石炭を産出し、日本の近代化を支えた。戦後、徐々に合理化が進められ、1997年に閉山した...
表も裏もない展覧会 「さいたま国際芸術祭2023」(メイン会場)と「Material, or 」
[2023年12月01日号(田中みゆき)]
現代アートチーム目[mé]がディレクションした「さいたま国際芸術祭2023」(本稿での記述はすべてメイン会場)は、いわゆる芸術祭や展覧会とは一風違った様相を成している。この芸術祭では、「何気ない経験の数々を、いつもより少しだけ積極...
美術館内でもっとも動的な場所から生まれるもの──府中市美術館と公開制作
[2023年12月01日号(大澤真理子)]
東京都の西側、多摩地域にも数多くの美術館が存在するが、そのなかでも府中市美術館は展示室とは別に公開制作のための部屋を擁しているのが大きな特徴だ。2000年の開館当初から、90組近くの作家による公開制作のバトンが連綿と繋がれてきた公開制作室。...
「はならぁと コア」における長谷川新「SEASON 2」の試み
[2023年11月15日号(中井康之)]
「今、最も隆盛している『現代アート』は、こうした作家(デュシャン、ウォーホル、ダミアン・ハースト、村上隆、会田誠、草間彌生:引用者注)の作品ではない。今や主流となりつつあるのは『地域アート』なのである」文芸評論家、藤田直哉が文芸誌に「前衛の...
街全体で探る、学びと体験の新しいかたち
[2023年11月01日号(平井真里)]
青森県内の五つの美術施設による連携プロジェクトが注目を集めるなか、そのうちの一館である八戸市美術館は、他県から巡回してきた展覧会にも八戸ならではの付加価値を含む鑑賞体験のあり方を、街全体を巻き込むかたちで積極的に模索している。同館の当初のコ...
生き生きと、長持ちさせる方法を巡って──『ダンスダンスレボリューションズ』と上演の軽さ
[2023年10月15日号(谷竜一)]
2023年の京都芸術センター Co-programのなかでも、カテゴリーA(公演事業)という上演演目の共同主催での採択企画「松原俊太郎 小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク 不自由な言葉を離す身体『ダンスダンスレボリューションズ』」は、...
多様な声に耳を澄ませる「セーフスペース」としての美術館と、文化事業のゆくえ──「Fukuoka Art Next」をめぐって
[2023年10月01日号(忠あゆみ)]
アジアの窓口としての地理的・歴史的文脈をもつ福岡。その周辺で活動するアーティストや展覧会などについて長きにわたり興味深いテキストを寄せてくださっていた正路佐知子氏に代わり、今回からは福岡市美術館学芸員の忠あゆみ氏にバトンタッチ。日本近現代美...











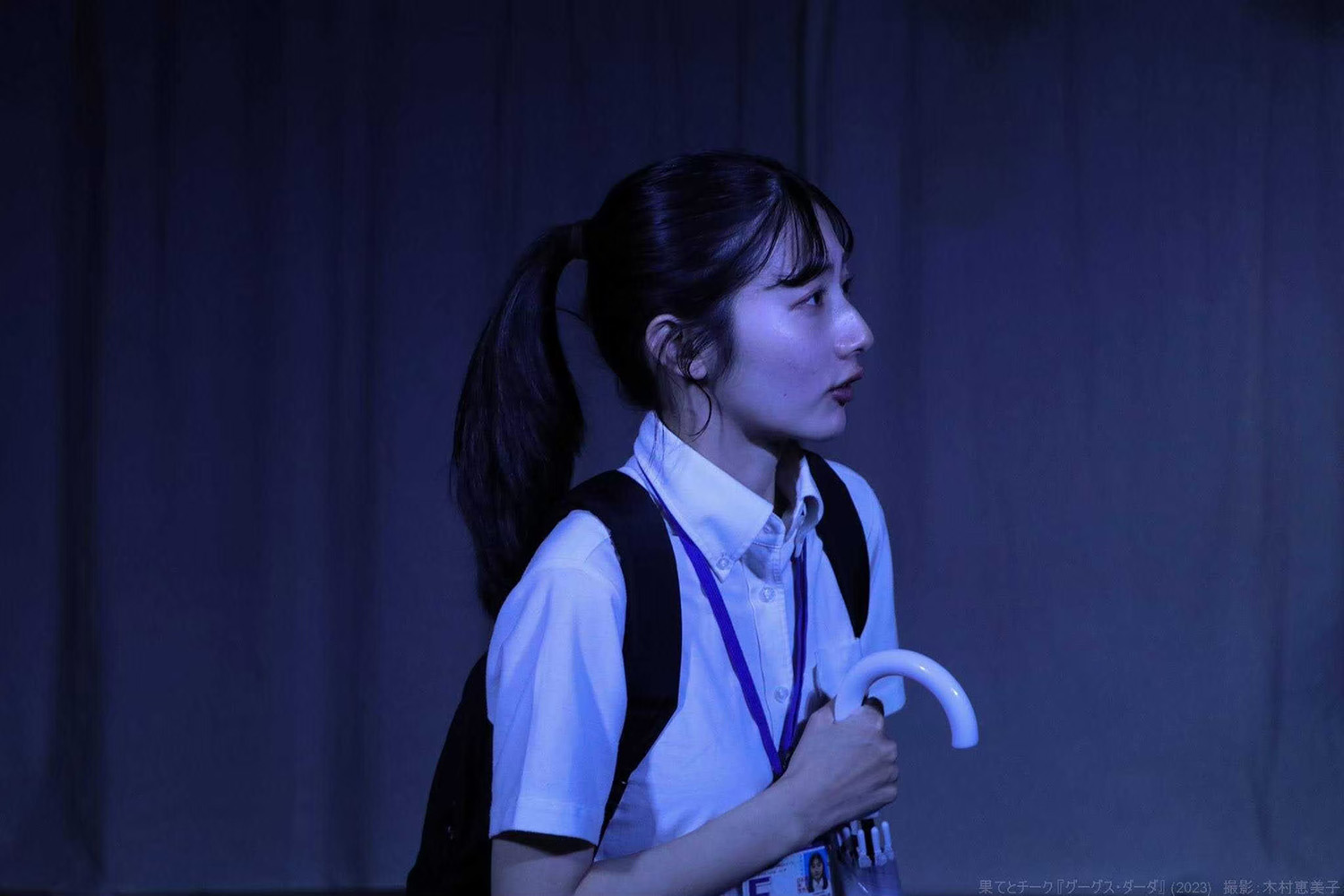


![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)
![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)