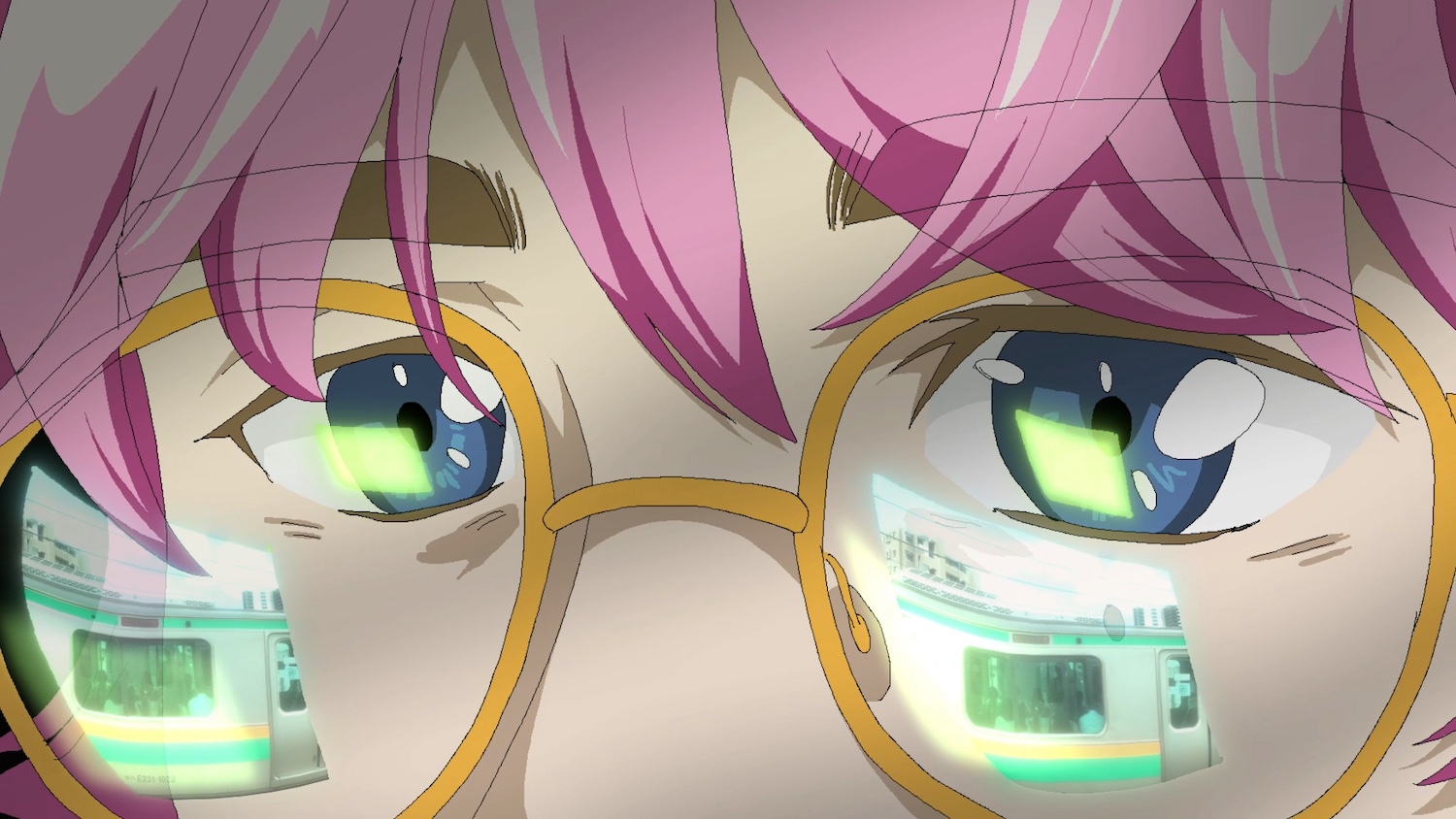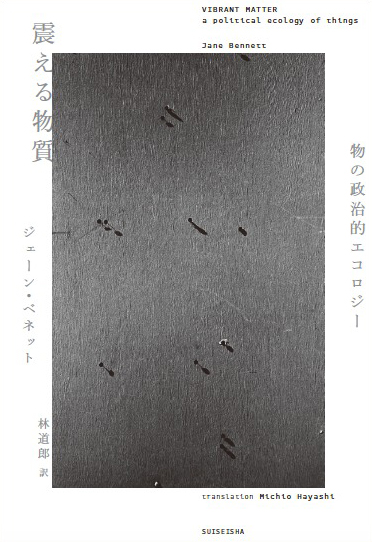
翻訳:林道郎
発行所:水声社
発行日:2024/2/10
本書の著者ジェーン・ベネット(1957-)は、アメリカの政治理論家・哲学者である。ベネットの出発点はヘーゲルを中心とする政治思想だが、アメリカの思想家ヘンリー・デイヴィッド・ソローを対象とした『ソローの自然』(Thoreau’s Nature: Ethics, Politics, and the Wild, Rowman & Littlefield, 2002)や、詩人ウォルト・ホイットマンを論じた『流入と流出』(Influx and Efflux: Writing Up with Walt Whitman, Duke University Press, 2020)など、これまで多岐にわたる仕事を世に送り出してきた。
とりわけ、現代思想におけるニュー・マテリアリズムの一書に連ねられる本書『震える物質』によって、ベネットの名前は広く知られるようになった。ここでは、本書が批判対象とする二つの立場、すなわち(1)伝統的な「唯物論/物質主義(materialism)」と(2)「生気論/生命主義(vitalism)」への批判のポイントを見ていくことで、その概要を把握していくことにしよう。
既存の唯物論/物質主義(materialism)に対するベネットの違和感は次のように要約できる。すなわち、ふつう「materialism」といえばマルクスの(史的)唯物論のことなのだが、こうした唯物論/物質主義は、本当に「物質(matter)」の実相を捉えきれているのだろうか。たとえばベネットはこんなふうに言っている。彼女が本書で追求するmaterialismというのは、「ヘーゲル−マルクス−アドルノ系統というよりは、デモクリトス−エピクロス−スピノザ−ディドロ−ドゥルーズの系統のものだ」(24頁)。ここで、ベネットはいわゆる(史的)唯物論の伝統の外から、次のような問いを投げかける。すなわち、唯物論/物質主義を人間社会──たとえば階級闘争のような──の問題に限ることなく、「停電、食事、鎖に繋がれての監禁、ゴミ放置の経験」といったものを、人間である場合もあればそうでない場合もある「存在論的に多様なアクタント」(25頁)の出会いとして理論化することはできないだろうか。
ベネットはこうしたみずからの立場を「生命的物質主義(vitalist materialism)」と呼ぶのだが、同時にそれは「あらゆる物質には生命が宿っている」というような、安易な生気論的発想とも異なっている。ベネットがめざすのは、あくまで「物質性そのものに内在している活力を理論化すること」にあるからだ(23頁)。そうした理由から、ベネットはドリーシュやベルクソンをはじめとする生気論的伝統に遡りつつ、しばしば「魂」に依拠する生気論からは慎重に距離をとる。
さほど長いものではない本書の大半は、食べ物、金属、幹細胞をはじめとする、物質のエージェンシャルな力を描き出すことに費やされている。では、それがなぜ副題にある「物の政治的エコロジー」につながるのだろうか。その理由は、人間ならざるものの「力」をみとめることは、それをいかなるしかたで遇するかという問題と切り離せないからだ。たとえばミミズは、紛れもなく生態系の活動的な一員(agency)であるが、他方でわたしたちは、ミミズを政治的なメンバーの一員(public)とみなすことはないだろう。だが、こうした両者の線引きはいかにして正当化されるのだろうか(193頁)。
なるほど、われわれは動物や植物、さらには非有機的な事物について数多くのことを知るなかで、「その〔受動的な〕ふるまいを〔能動的な〕行動として読み替えてもいいのではないか」という感覚を抱くかもしれない。しかしながら、「本当の意味でミミズを真剣に受け止めるには、彼らの活動に対する私たちの評価を変更するだけではなく、人間の独自性に対して私たちが持っているより大きな信仰を疑問に付し、その信仰に紐づけられている諸概念を発明し直す必要がある」(216頁)。具体的にここでベネットが言っているのは、たとえば「公衆(public)」という言葉ひとつをとっても、それを人間の集合からなる「公衆」としてではなく、その周囲に集結してくる(存在論的に異種混交的な)「公衆」として把握しなおす必要があるということだ。
これが途方もなく困難な試みであることは言うまでもない──というより、こうした世界の実現のためには、げんに存在する社会秩序を根本的に破壊する必要がある──が、本書が提起する「政治的エコロジー(political ecology)」が、ともすれば微温的になりがちなエコロジー思想に対して、大きな一石を投じようとしていることは評価したい。
執筆日:2024/12/10(火)