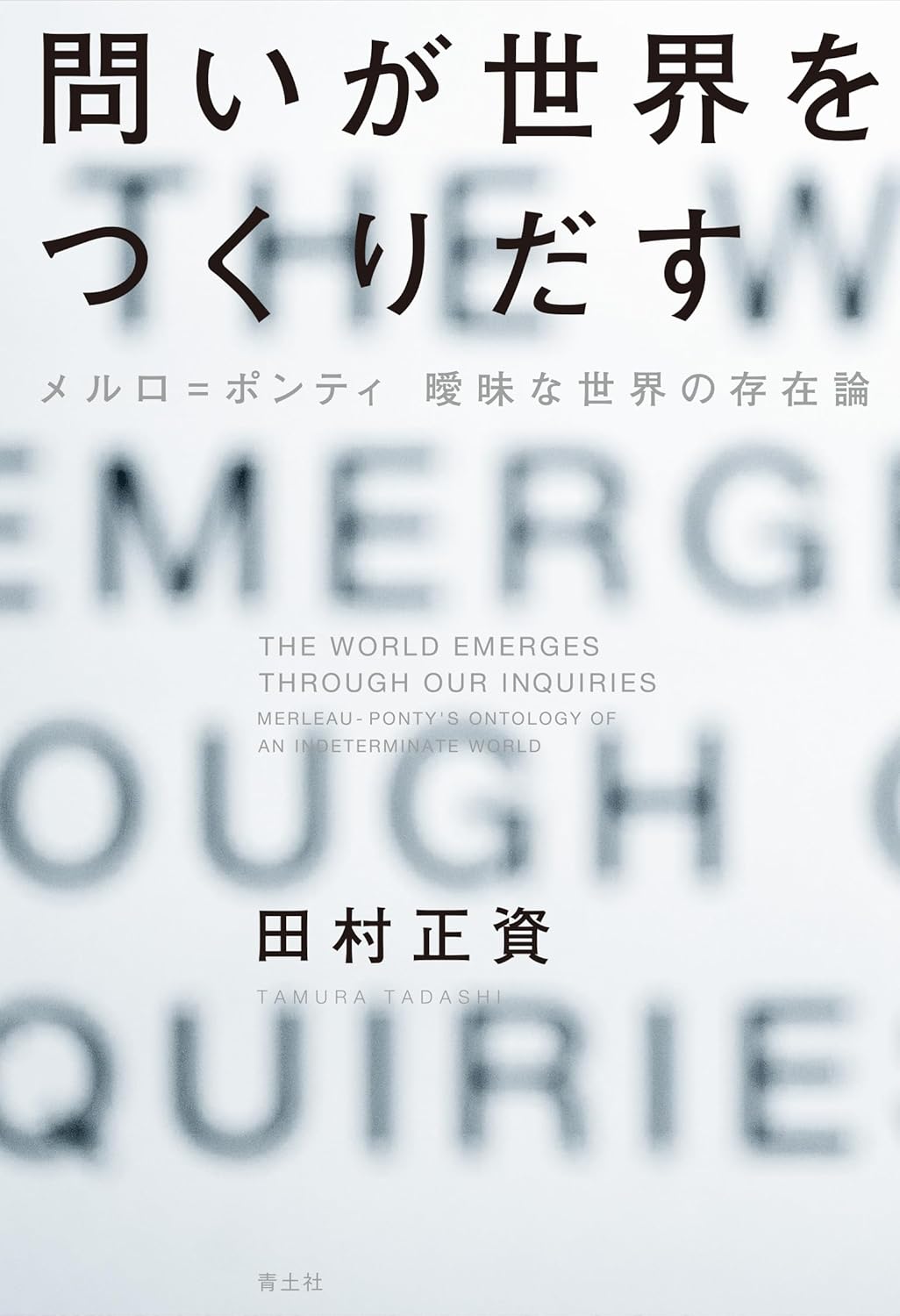
発行所:青土社
発行日:2024/08/30
公式サイト:http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3956
本書はモーリス・メルロ゠ポンティ(1908-1961)についての研究書であり、とりわけその哲学全体を「曖昧な世界の存在論」として提示する、という意欲的な試みである。こう書くといささか厳めしい印象を与えないでもないが、本書の読み味はきわめて爽やかであり、専門的知識をもたない読者にも接近しやすいさまざまな工夫がなされている。
この世界は「曖昧」である。そのような言表が意味するのは、多くの場合、わたしたちはこの世界をある特定の視点からしか経験できない──つまり、けっして世界「全体」を把握できない──ということだろう。メルロ゠ポンティもしばしばそうした議論を行なっている。だが、本書がメルロ゠ポンティに即して提示するのは、そうした「経験を構成する」曖昧さにはとどまらない。著者によれば、メルロ゠ポンティはそもそも「この世界」が曖昧な様態で実在する、と考えていた。この、われわれの経験をめぐる探求から世界をめぐる探求への跳躍こそが、本書に理論的なダイナミズムを与えている。
本書を構成する11の章は、いずれもメルロ゠ポンティにおけるさまざまな論点の明晰化に捧げられている。ただしそれらは最終的に、著者が繰り返し参照するひとつの命題に収斂していくことになるだろう。すなわちそれは、『見えるものと見えないもの』(1964)に登場する「実在する世界は試問的な様態で存在する」という謎めいたフレーズである。著者はこの言葉を冒頭で次のように敷衍する──「メルロ゠ポンティによれば、私たちは、自分たちの生きる世界が、何であるかを明確に述べることはできない。けれど世界は私たちが具体的な何かを求めて問いかけを発する地平として、私たちを包み込むように拡がっている。つまり、私たちが具体的な何かを世界のなかで経験しているとき、当の世界はその経験の周縁に『何ものか』というスタイルで存在している」(16頁)。
本書の内容をふまえて、これをさらに平たく言えば次のようになるだろう。世界はわれわれの問いかけを待っており、その問いかけに応じて、世界はさまざまな様態で現われる。そこには、われわれの問いかけに先立つ超越的な世界があるわけではなく、問いとともに、そのつど世界が新たに現われるのだ。もちろん、これはたんなる観念論でもない。本書がメルロ゠ポンティに即して明らかにするのは、あくまでわれわれの「知覚」と「世界」との独特な関係である。
こうして本書全体の試みを紹介してみても、まだどこか抽象的な印象がつきまとうかもしれない。そのうえでもう一言つけ加えると、本書をつらぬく核心的なキーワードのひとつに「動機付け(motivation)」というものがある。「動機」や「モチベーション」は日常的にもよく使われる言葉だが、メルロ゠ポンティにおいてこれは、因果性や合理性とは異なるしかたで人を特殊な行動へと促すような、ある種の規範性を内包するものとして考えられている。つまり、わたしたちはつね日ごろ、言葉になる以前のさまざまな規範を感じ取りながら、この世界のなかで、あるいは世界とともに生きているのだ。これはきわめて魅力的な世界像である。そして、本書における一連の明晰な議論は、知覚と世界の関係をめぐるメルロ゠ポンティの思想を、われわれが具体的なレベルで実感するための大きな助けとなってくれるだろう。
執筆日:2025/04/10(木)







