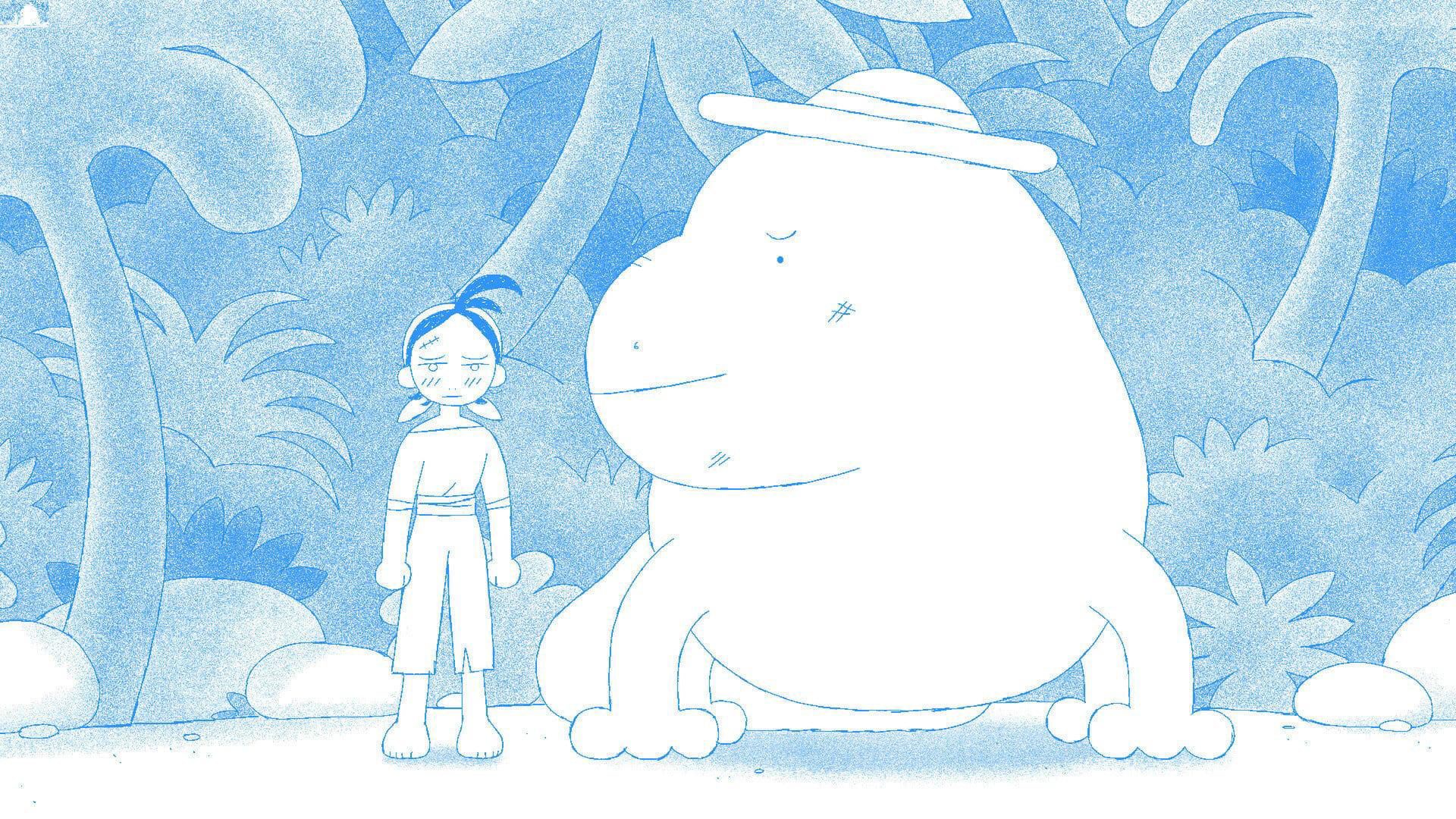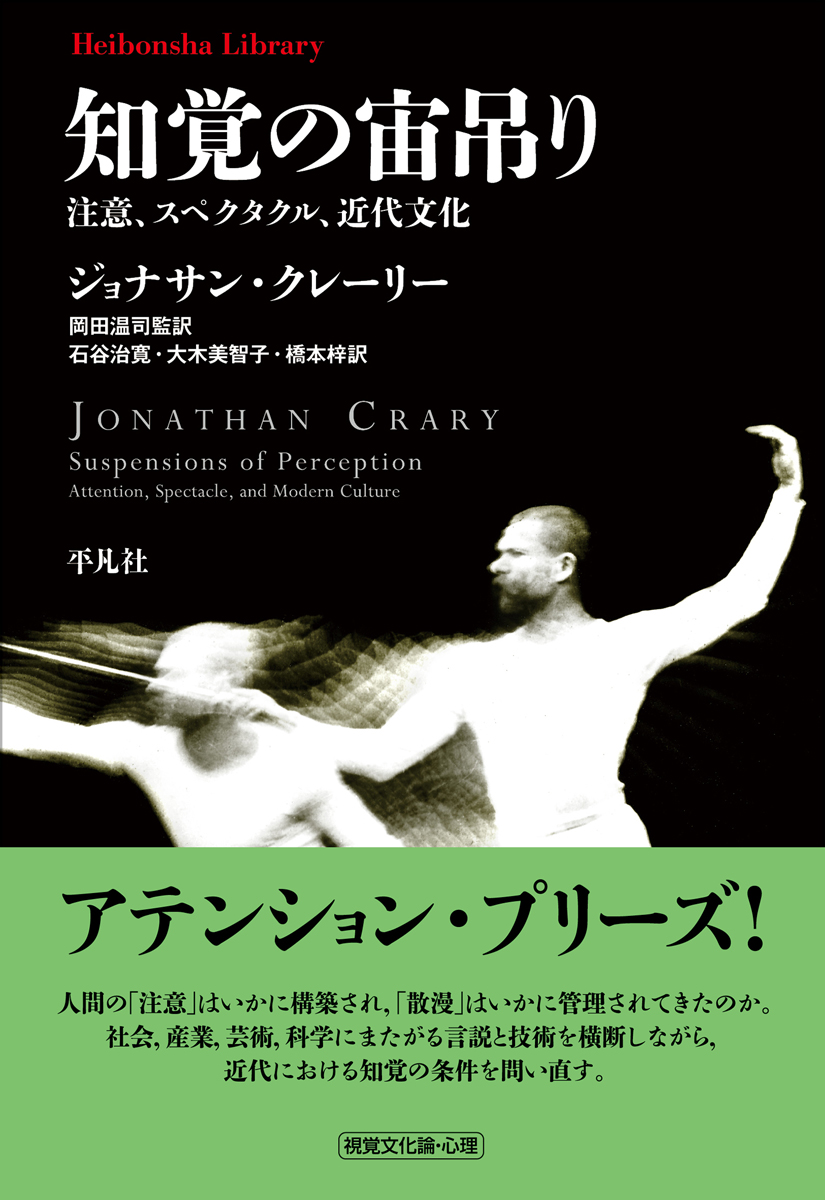
監訳:岡田温司
翻訳:石谷治寛、大木美智子、橋本梓
発行所:平凡社
発行日:2025/04/04
公式サイト:https://www.heibonsha.co.jp/book/b659318.html
(前編より)
すでに第1章でも催眠術を引き合いに注意の両義性が説かれていたが、2章で俎上にあげられるのは、エドゥアール・マネの絵画だ。著者はマネの《温室にて》(1879)に描かれる生気のない、蝋人形のような女性について言及する。クレーリーはこの女性の、集中しているようにも、散漫ともとれる眼差しに着目している。いかに知覚が、感覚の多様性と接続したり、または遊離していく流動性のなかにあるのかということを、失認症や神経症の病理学研究と重ね合わせながら論じている。
そして著者はマネの絵画を当時のファッションと関連させながら、それを新しい時代の消費者像として再定位する。こうした「知覚の再組織化と分散」は、マックス・クリンガーの版画やエドワード・マイブリッジの連続写真にも見出されることによって、マネをはじめとしたこれらの表象を同時代のものとして整理していく。
続く第3章で中心的な主題となるのはジョルジュ・スーラである。クレーリーはマネが知覚の揺れ動きを表現したのに対し、スーラは新たな認知モデルを構築しようとした画家であると冒頭で明言する。この章は分量的にもっとも多く、その議論の広がりはまさに圧巻である。まずクレーリーはスーラの知覚の組織化という命題を、同時代に勃興しつつあったゲシュタルト心理学と関連付け、知覚の断片化を再統合しようとする潮流として並行的に語る。こうした主体の再編成について、著者はさらに生理学や後期ニーチェ、エミール・デュルケームを援用し、科学から哲学へ、そして社会学へと議論を拡大していく。
この章で主要な読解の対象となるスーラの絵画は《サーカスのパレード》(1987-88)だ。同作からクレーリーは次々と解釈を繰り出していく。スーラの科学への関心をレオナルド・ダ・ヴィンチと比較したり、描かれた「0」という記号を絵画の構造と結びつける図像的アプローチを取ったりするのみならず、サーカスという主題から、やがて遊園地や映画に取って代わる娯楽体験の変容についても言及していく。美術史や映画史がその該博な知識によって新たな相貌を見せるスリリングな展開は、同書のハイライトだと言えるだろう。
第4章ではポール・セザンヌが主要な言及対象になっている。ここではまず彼の絵画から引き出される認識的特徴が、現象学との関連によって示される。そこから視覚刺激を測定するタキストスコープという実験器具や、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツの生理学について考察が深められ、また私たちの身体的「反射」についての科学的議論を経て、19世紀末に知覚の根源的構造への関心が高まったことが指摘される。そしてアンリ・ベルクソンの哲学が参照され、その持続する知覚経験が「単純化不可能なほどに『雑多で』複合的なもの」であるという見解がセザンヌと共有のものであると述べられる。結果、その「構築的」な絵画は、鮮やかに脱構築されていく。
クレーリーの記述はジークムント・フロイトが家族に向けた映画鑑賞についての書簡によって閉じられるが、改めて読み直すと、著者の議論の稠密さには目を瞠るばかりだ。単行本として邦訳されてからおよそ20年。同書におけるクレーリーのアプローチは、この日本でも表象文化論を中心に様々な論者にインスピレーションを与えてきた★。当時の哲学や美術を「注意」という主題に即して再配列しながら、時代のあだ花となってしまった視覚玩具や娯楽、すでに更新された科学者たちの実践を丹念に跡づけることによって生まれる近代の不透明な厚み。スマートフォンの普及に伴い、もはや全人類が「注意する身体」として管理されている現代において、その端緒について知ることの意義は大きい。「注意」をめぐる物語は、まだまだ終わらないのだから。
執筆日:2025/04/13(日)
★──筆者がすぐに思いつくものでは、例えば平倉圭『ゴダール的方法』(インスクリプト、2010)や、増田展大『科学者の網膜 身体をめぐる映像技術論:1980-1910』(青弓社、2017)がある。『観察者の系譜』や『24/7──眠らない社会』も含めると、クレーリーの議論を参照した著作は日本でも数多く読むことができるだろう。特に後者は、昨年話題となった三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社、2024[集英社新書])でも参照されており、クレーリーの言説が持つ射程の広さを傍証している。