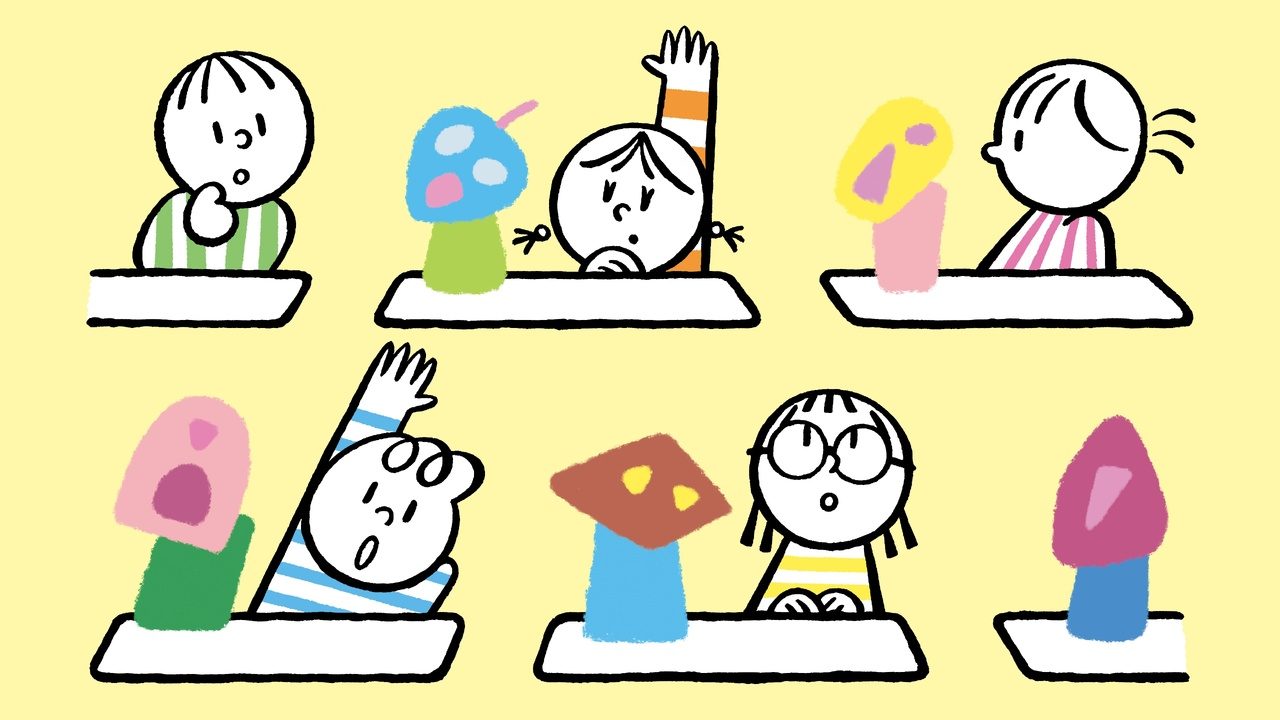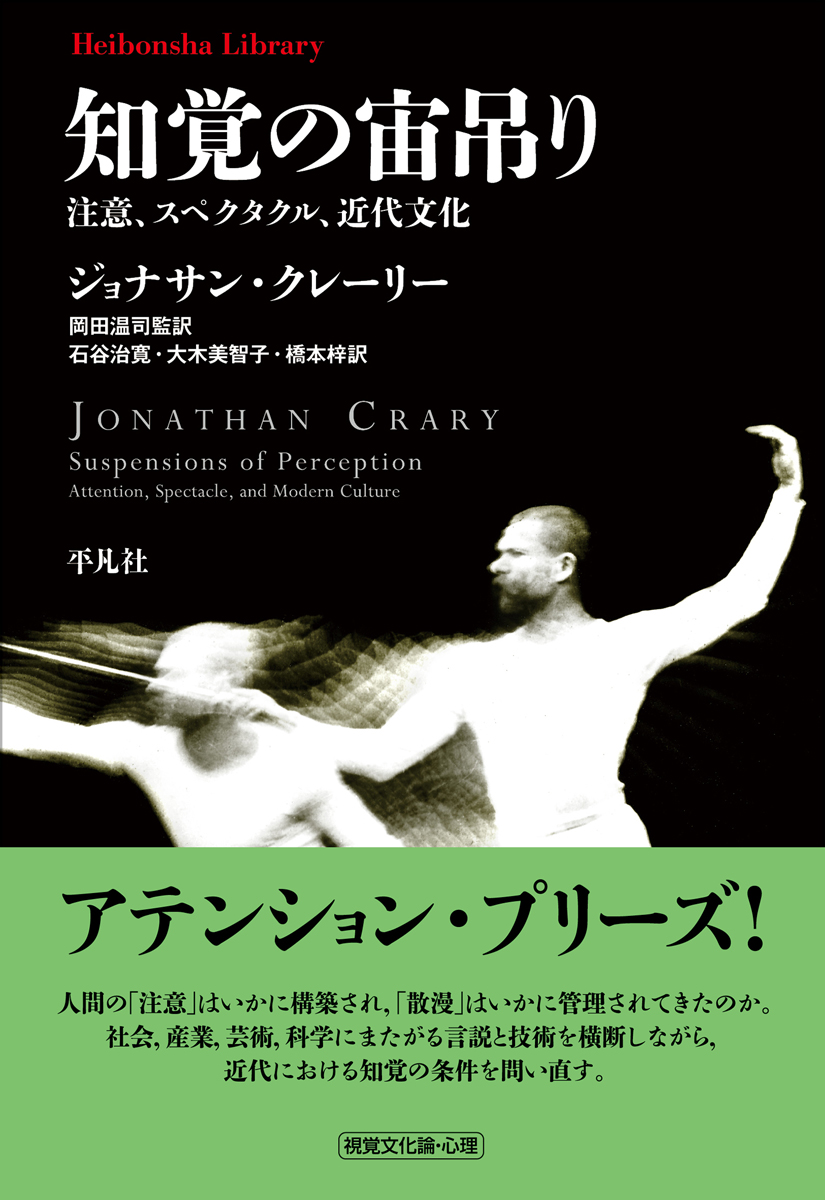
監訳:岡田温司
翻訳:石谷治寛、大木美智子、橋本梓
発行所:平凡社
発行日:2025/04/04
公式サイト:https://www.heibonsha.co.jp/book/b659318.html
「近代」という時代区分は、もはや過ぎ去ってしまった歴史なのだろうか。たしかにモダニティをめぐって、私たちはそこで起こっている諸感覚や社会の変容について繰り返し言及してきた。しかしそうした人文科学的な知性は、ビッグデータを学習したAIが生成する、お手軽な「正解」にその立場を脅かされてもいる。これが、知の今日的な状況であることは否めない。
しかし、ジョナサン・クレーリーはこのような現状にあっても、近代という問題設定を捨てることはないだろう。インターネットにアップロードされる情報の爆発的な増加は今この瞬間も継続中であり、24時間絶え間なく情報が更新され、市場への誘惑を振りまいている。彼は『24/7──眠らない社会』(2013/邦訳:岡田温司監訳、NTT出版、2015)において、こうした現代の社会を批判的に考察したが、このように休むことなく「注意」を求められる身体は、いつ出現したのだろうか。19世紀から20世紀初頭の西洋を舞台に、哲学・美術・科学をはじめとした広範な資料にあたり、この問題について歴史的に検証したのが『知覚の宙吊り──注意、スペクタクル、近代文化』である。
だが本文だけでも400ページを超え、しかも各章のタイトルも簡素かつ小見出しもない同書を読み進めるのは、なかなか骨の折れる作業である。とはいえそれだけの理由で、美術史や表象文化論にとどまらない知的興奮を与えてくれるであろう読書体験を先延ばしにしてしまうのは、同書がこのたびライブラリー版として手に取りやすくなったタイミングであるだけにもったいない。ゆえに、ここではクレーリーの議論の含蓄がある程度捨象されてしまうことを承知のうえで、同書について通読の助けとなるよう要約を試みてみたい。
わかりやすく言ってしまえば、クレーリーの手つきはミシェル・フーコー的だ。「主体」とはいかなるものなのか。それは何によって規制され、統御され、身体へと統合されていくのか。『知覚の宙吊り』は近代における身体の混成的な成り立ちを、エドゥアール・マネ、ジョルジュ・スーラ、ポール・セザンヌという3人の画家の作品を通じて検証していくのであるが、なぜここで注意が問題になるのだろうか。
序においてクレーリーが主張するのは、ヴァルター・ベンヤミンをはじめとする論者が述べる近代的な主体の危機、つまり「散漫状態における受容」を理解するには、それと裏腹にある「注意についての規範と実践の誕生の相関関係」が鍵となるということである。近代以降のメディアやテクノロジーの体験──つまり映画など芸術一般の鑑賞や労働、デジタルデバイスの操作など──における注意は、その没入や集中にもかかわらず、さまざまな「諸力や権力構造の効果」にほかならないことをクレーリーは指摘している。
第1章では、こうした前提がどのような理論的パースペクティブのなかにあるのかということがまとめられる。カント以来、私たちの認識は超越論的に綜合されるものとして捉えられてきた。しかしそれは19世紀において、科学的な実験によって外界の刺激を計量化する精神物理学によって失効してしまう。ここではすでに、クレーリーが『観察者の系譜』(1992/邦訳:遠藤知巳訳、以文社、2005[新装版])でも述べたような、主体と対象の「統一的で均質な視覚の一貫性」を持つ暗箱の視覚モデルが過去のものとなっているのである。
こうした変化はトーマス・エジソンらによる音やイメージ、情報の計量可能性へと我々を導き、ロザリンド・E・クラウスに代表される視覚芸術におけるモダニズムの議論においては、「純粋」形式としての視覚が語られるようになる。ショーペンハウアーやハンナ・アーレントは、哲学を意識についてのものではなく「生」についてのものであると再定義した。そうした流れはフーコーの規律社会、ジル・ドゥルーズの管理社会へと展開していく。こうした歴史的、思想的背景のもとで、同書は視覚の経験的な可能性が「宙吊り」にされたような事例を、一つひとつ丁寧に読み解いていく。
クレーリーはカント的認識論に懐疑が投げかけられ、なぜ19世紀以降われわれの営為がこうした展開を辿ることになったのかについて、注意をキーワードにその核心に迫るべく第2章へと筆を進めていく。
(後編へ)
執筆日:2025/04/13(日)