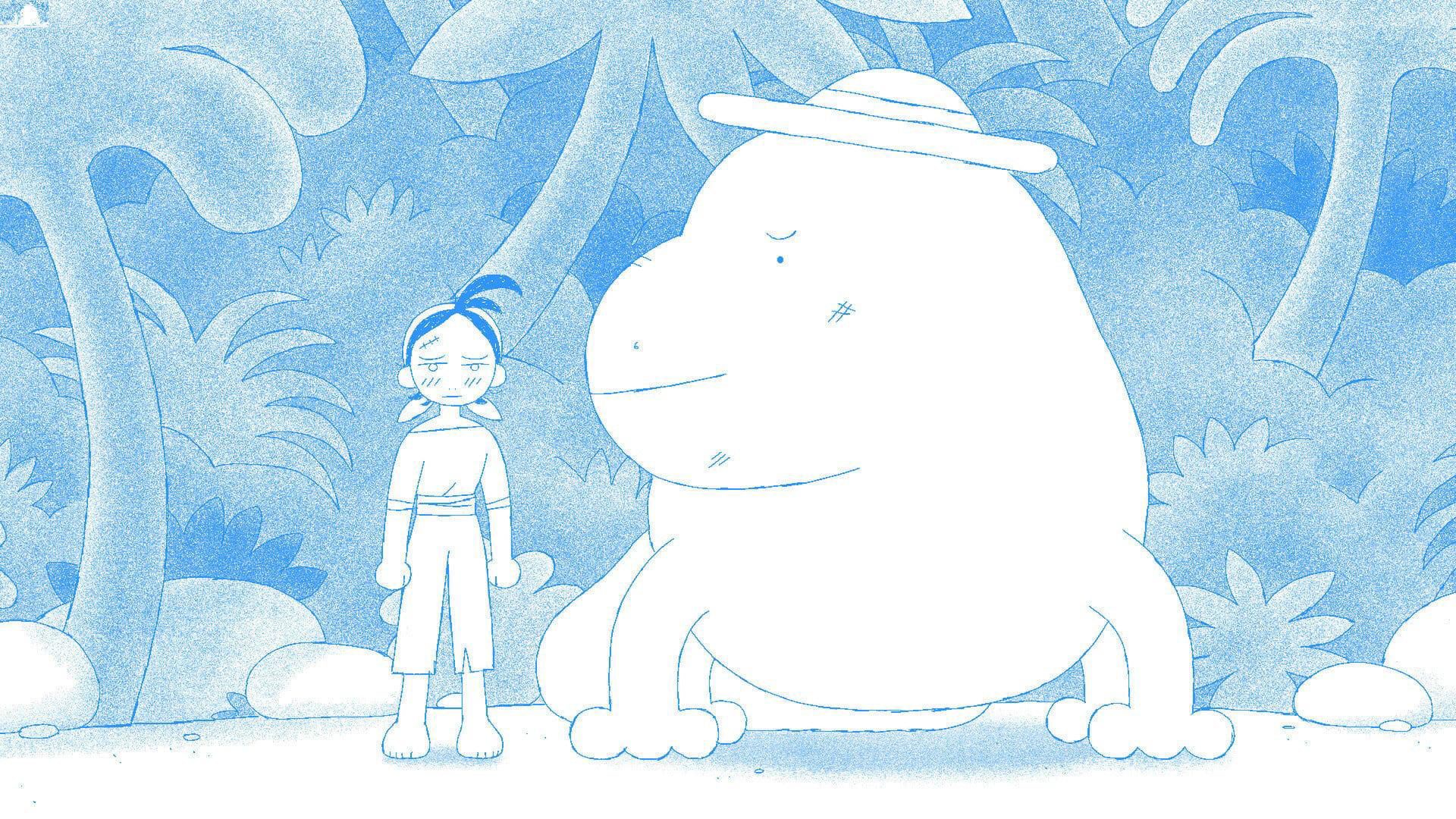所在地:東京都墨田区横網2-3-25(都立横綱町公園内)
公式サイト:https://tokyoireikyoukai.or.jp/museum/history.html
 開館時の復興記念館[資料提供:東京都復興記念館]
開館時の復興記念館[資料提供:東京都復興記念館]
「……大震火災前に於ける帝都及び帝都市政の現状を明らかにすると共に震火災の実情並びに災害による各般の打撃と公私の対災活動等を有力なる諸種の資料により市民に展示し以て変災の教訓に資し、併せて過去七年以来官民努力の結成により漸く完備の域に達せんとする帝都復興事業其他復興帝都の市政及一般市民の復興状態等を明瞭にし国都文化の紹復と市民精神の振作更張に貢献仕度存じ候(中略)展覧会の規模を雄大にし且つ権威あらしむる上において一般市民もまたおそらく喜悦するところと存じられ候に付……」
(1929年8月10日、東京市政調査会会長阪谷芳郎から外務次官吉田茂宛の書簡より)
★1
1923年の関東大震災から約7年が経過した1929年、帝都復興展覧会が開催された。7万点を超える展示物が集められ、10万人を超える人々が訪れたという。震災の学術的な調査・研究の記録や、震災復興の実行内容や方針に関わるものが、主に東京市や復興局から集められた。こうした展示資料の一部を引き継いだ施設が、隅田川のすぐ近く、横綱町公園に位置する東京都復興記念館である。横綱町公園は、震災の際、およそ3万8千人が亡くなった場所である。陸軍被服廠(軍服工場)の跡地で、東京市(当時)が公園にするため造成中の空き地だったことから、大勢が避難先としてここへ集まってきた。地震発生後、各所での火災が合流し、避難者たちの持ち込んだ家財道具や荷物にも引火し、ここに火災旋風が発生した。いまほど高層ではないにせよ、高密度に建物の立ち並ぶ東東京にぽっかり空いた一帯に、巨大な炎の竜巻が巻き起こったのだ。「大震火災」と書かれるように、災害の始まりとなる本震だけでなく、その後発生する火災の悲惨さが関東大震災の特徴と言える。一方、東京大空襲に際しては、公園は火災を免れ震災記念堂(現東京都慰霊堂)も記念館も無傷であった。火災旋風の記憶から、この広さに比して空襲時の避難民の数はとても少なかったという。
ここは後の東京大空襲を経て、二つの被災に関する記念館へと変化した。展示室は1、2階に分かれており、1階は関東大震災の発生から復興までの記録が、2階の一部に東京大空襲の記録が展示されている。
1階は、通路状の空間から展示室が始まる。片側の壁には地震計が残した揺れの記録に始まり、種々のデータによりどのような事態が発生したかを広域地図を用いて示される。報道写真はその改竄の事実と合わせて示される。
火災旋風についてのパネルは多くはないが、生存者の証言に基づく火災および火災旋風の移動経路を示す図は、ほかのどの地図資料よりも見る者に迫るものがある。人が動けるよう都市に残された道が網目のようにある上へ、まるでそのような小さな空隙は無関係に大きくうねった赤い矢印の数々。焼け止まり線と呼ばれる、大規模な空地や河川、崖の影響だけがその矢印を止めたり受け流したりしている。人間の大きさの延長にある街並みや生活の営みが、簡単に消え去ったことがむしろわかってくる★2。
報道や研究記録を見ていくと、角を曲がったところで、(全体に比して少なく、また経緯を簡易に示しているだけではあるものの)朝鮮人虐殺に関するパネルや資料の展示が現われる。こうして展示は、個人の経験的な語りを中心としたものに変わっていく。スケッチや作文による語りが、それまで見てきた“客観的な”情報に肉付けするようにイメージを増やしていく。100年前に被災した小学生の作文を、現代の小学生が朗読したものは、断片的に場所が特定しやすいものが選ばれている。朗読の声を聞きながら目にするのは、国外からの義援金集めのポスターや私的援助の記録、寄贈品である。これらの納められたガラスの展示ケースを境にして、展示は震災復興の内容説明に移っていく。燃え落ちた橋をはじめとするインフラ整備や、土地区画整理、街路の引き直しの記録が、広域地図や鳥観図によって説明されていく。展示が終わろうとした最後に現われるのは、「紙芝居関東大震災」だ。これは、「神田和泉町・佐久間町の住人たちが必死で自力消火を行い町を死守した様子が描かれて」いるもので、結果的に、空襲に備えて1937年に制定される防空法の啓発に資することになったものである。アジア太平洋戦争の開戦した1941年に、国民が自力消火を放棄して避難すると厳重に罰せられるという内容に防空法は改正された。有事に際して自分たちでどうにかすることの奨励は強制へと変わったのだ。この紙芝居によって、二つの被災はつないで語られる。
2階は、展覧会に出品された都市模型、震災の様子を描いた洋画からなる中央の展示室と、その展示室を回廊状に取り囲む1945年の東京大空襲に関する展示からなる。回廊の壁にかかった白黒写真には、一面の瓦礫となった東京の様子が写っている。1階で目にしたものとそう変わらないが、瓦礫の間に残る街路や橋といったインフラが今度はよく目立つ。
中央の展示室は主に燃える東京の様子を描いた絵画に頭上を囲まれている。このあと20年足らずのうちに、また燃やし尽くされることになる町の模型を少ししゃがんで覗き込む。これらは、この記念館にあり燃えることがなかった。ここに見えている道路の網目は、先ほどの白黒写真のそれと同じものだった。こうして、震災復興で残されたものがあり、戦災復興でまた残っていくものがあった。
残るものは、誰かに決められてしまってもいる。復興は暴力ではなく回復の象徴として元来捉えられているだろうし、個人ではどうしようもない規模の出来事に対して、大きな主体が力を発揮することのすべてに私は反対できない。だが、橋をかけ直すのも、自力消火をさせるのも、権力の側なのだ。そして、自らの力を振るうことを否定された人々は、知らず知らずにお上のすることを内面化してしまう。自力消火は、本来“した”ことであったのに。
藤野裕子『民衆暴力──一揆・暴動・虐殺の日本近代』(中央公論新社、2020)では、「民衆自身が主体的に暴力をふるっていた歴史」において、その暴力が権力だけでなく被差別者にも向けられてきた事実を追っている。本書は江戸時代の一揆の変遷から、明治初期1870年代の新政反対一揆、1884年の秩父事件、1905年の日比谷暴動、1923年の関東大震災時の朝鮮人虐殺を取り上げる。特に朝鮮人虐殺については頁の多くが割かれている。藤野は民衆の暴力を公権力が用いる暴力と明確に区別する一方、社会的な抵抗や抗議としての側面だけを重視することはしない。集団となった個人が、それまでの歴史や社会背景のなかである論理のもと行動するに至る状況を見ようとしている。
第4章、第5章の関東大震災における民衆暴力の章も必読であるが、ここではそれ以前の章を取り上げておきたい。江戸時代前半の一揆は、社会の制度を内面化したものであり、現代から想像される打ちこわしなどの暴力を伴うものではなく、訴えを言葉で伝えるものであった。良き君主と良き領民という役を演じ合うことで、身分や年貢の制度が互いに維持されてきたのだ。一方、政治の実態として良君であることが成立しなくなってきた江戸時代後期には、一揆のなかで暴力が現われていく。貧富の差が拡大した当時、「通俗道徳」が広まっていった。「通俗道徳」とは質素倹約に励み、農家の経営を維持するというものだった。これは、土地を手放して小作人になったり、あるいは農業を止め、都市部に出て働きながら自身の生活を維持しようとする考えに対するものだった。二宮尊徳が村をまわりながら伝えていったというこの思想は、村役人や豪農を中心に支持されたという。しかし、藤野も指摘するように「こうした経済の構造的な変化に伴う貧困を、個人の生活態度だけで解決するのは困難を極めた」。藤野は、「飢餓や天災」を挙げつつも、最終的にこの状況を構造的な問題であると指摘する。
また、第2章の秩父事件についても、松方デフレを発生要因のひとつとするこの暴動の後、節倹法が公布されたことが取り上げられている。「生活の困窮を挽回するのは、個々人の節倹と勤労のほかにない」と言い、「貧困の原因が個の生活態度の問題に還元されるようになる」のだ。この抑圧が、権力ではなく被差別者への暴力にも転換していったのだ。自助や共助がさまざまな面で謳われている現代においても、その助けがどこから求められ、どこに歪みをもたらしているかを改めて考えるべきだろう。
震災復興と戦災復興は、ともに都市とそこにいる人々が被ったものに対して起きたことだ。その規模や類似性は、一面を瓦礫にするような事態においても、歴史を連続したものとして、都市をその連続の記録として捉えることを可能にもしている。一方、その客体的な捉え方は、都市を私たち個人の主体的な集まりとしては自覚させてはくれない。お上がしたことのその下に私たちがいるという構図は、復興によってむしろ強化されていくのだと、記念館の展示は暗に伝えてもいる。この模型の縮尺では見えない蠢き、火災の矢印の下にあった人々の動き、写真のフレームの外にあったこと。私たちがしたことを、私はもっとよく見たい。
 2階中央の展示室の様子。ガラスケースの中に震災復興の都市模型が納められている[筆者撮影]
2階中央の展示室の様子。ガラスケースの中に震災復興の都市模型が納められている[筆者撮影]
★1──抜粋部は国立公文書館アジア歴史センターのウェブサイトから内容を確認した。また、復興記念館の展示物はデジタルアーカイブで概要を閲覧可能となっている。例えば展覧会に出展された都市模型など。
★2──一方、東京大空襲・戦災資料センターには、1945年の東京大空襲時の個人の移動記録をマッピングした広域地図が存在する。閾値を超えた数の多さを表やグラフにするのではなく、移動そのままに記述することの意義は大きい。A地点からB地点へ行くとき、その道筋に(せざるをえなかったことやできなかったことも含めて)人間の意思が残されている。
鑑賞日:2025/04/09(水)
関連レビュー
東京都復興記念館|村田真:artscapeレビュー(2017年08月01日号)