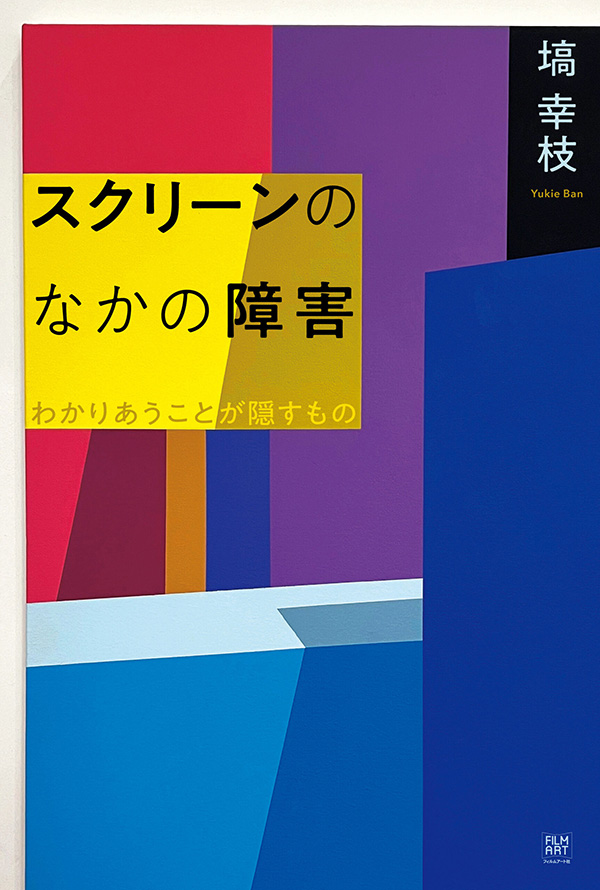
発行日:2024/11/26
発行元:フィルムアート社
公式サイト:https://www.filmart.co.jp/books/978-4-8459-2311-3/
制作と鑑賞をめぐる本でもある。しかし、そのように読む前に、具体的に取り上げられている一つひとつの分析を、まず具体的なままに受け止めていく必要がある。
本書では、作品なるものを、表象される内容だけに留めず、表象のし方や受け止め方まで連続的に論じている。障害をめぐるコミュニケーションは、スクリーンのなかだけでなく、スクリーンと私たちとの間のそれをも指している。どこまでも追っていくことが可能なコミュニケーションを構造的に問おうとする意欲的な分析が続く。
本書は五章から構成されている。
第一章「社会における障害観の変化」は障害が社会においてどのように位置づけられてきたのか、医学モデルから社会モデルへの変遷、社会モデルがもつ限界など、障害について考えるための見取り図とも言うべき概説の章である。「(前略)社会モデルへの称賛が、どのような社会モデルの理解にもとづくものであるのか」★1という問いが示されているように、本書では一貫して事物だけでなく、その受容のされ方までがつねに問われている。多面的に自己や他者を考えるための手立てのベストがいまだ出ていないことを示す章だが、だからこそ映画というものがその考えるための手立てのひとつかもしれない、と予感させる章である。
第二章「映画における障害者イメージの変遷」は映画内の表象として障害がどのように描かれてきたかを示す。障害そのものを写すということはできず、障害をめぐるコミュニケーションが本来映っているはずなのだが、かつての映画においてはそのコミュニケーションの主体だけが映っているように思われてきたのかもしれない。写せるものしか映らない、という制約が、障害を当事者たちへ担わせてきた歴史が映画史とパラレルに浮き上がってくる。恐怖→哀れみ(非力化)→共生するもの(有能力化)と、対象を変化させて描いてきたさまを追う。
第三章から第五章は、第一章と第二章を前提とし、鑑賞の次元まで組み込んで、スクリーンに映る物事が、どのように提示され、受け止められてきたのかを分析していく。
第三章「コミュニケーションの問題として描かれる障害」では、第二章に見られた表象の次元が、どのように鑑賞されるかを分析する。障害当事者の描き方の変遷は(見世物的であった始点から比較すると)好ましい変化に思えるが、このような変遷が映画のなかのストーリー立てにも用いられていることを本書は指摘する。例えば、コミュニケーションの不全から達成、わからない者からわかる者へ……といったように、映画を見終わる頃には、当事者(の役)を私たちは受け入れるようになっている。このマジョリティ側が他者をわかったと短絡することの問題が、複数の映画を例に挙げながら、物語の内容から演出の次元まで行き来しながら述べられる。また、障害と性にまつわる自己決定の問題のアンビバレントがそのまま提示されていることも本章の重要な点である。多面的に、複合的に物事を考えるとき、足が止まってしまうことはあるが、いまどのように足が止まっているのかを明確に言語化している点に本書の誠実さがある。
第四章「視覚的・聴覚的に再現される障害」においては、ろうの世界や文化が映画の文法を通じてどのように描かれているかを通じて、他者の世界を描くことと受け取ろうとすることの作用が分析されている。少なくとも現在まで、映画というものが晴眼者で聴者である者(さらに言えば映画館まで足を運べる者)を念頭に作られていることは否定しがたい。この章で示される分析によって私たちが直面するのは、異なる当事者性を抱えた他者同士の間で「同じ」経験はできるのか? ということだろう。それは鑑賞者同士の間での、あるいは作家と鑑賞者の、役と鑑賞者の……あらゆる組み合わせの間でも考えらえる。本書では映画のなかについて語られているが、言及されていないがゆえに、映画に事後的に付加される情報保障についても考えさせられる。作り手が、作る段階からどれだけ考えを尽くせるか、考え尽くした先になにを試し、うまくいかなさと向き合うかの必要性が暗に示される章である。
最後の第五章「身体的に演じられる障害」では、当事者俳優の出演・演技にまつわる問題を論じている。ここでは、障害をめぐる問題が映画のさまざまな切り口に忍び込みながら、正面から問われてこなかったことが明らかにされる。ここでは、当事者が当事者を演じたテレビドラマや、障害者が健常者を演じた事例を挙げながら、私たちが演技というものをどのように見ているかも明らかにされている。これまで障害者の役が当事者ではない者に演じられてきた事実は、(他者の身体をも演じられる、と)演技というものの範囲を広く見積もっていたようでいて、実際は(ある人がほかの人に変わるということは特定の人にしかできないし、やっても伝わらない、と)演技を短絡してきた結果だろう。映らないのではなく、写せないことを、被写体の問題に転嫁してきた結果であり、鑑賞という行為を低く見積もってきた歴史のもたらしたものかもしれない。例えば本章では、手話を母語とするろう者からの、健常者の手話の演技が自然なものとしては見えてこないという指摘が取り上げられている。これを受けて「一見すれば、これらは障害者の身体的要素を『見抜く』ことができる、(障害当事者のような)特定の人々の視点にもとづいた特異な見解に思えるかもしれません。しかし、こうした身体性の問題は、障害当事者の観客だけでなく、あらゆる観客の鑑賞行為に介在しうるはずです」★2と述べられている。ではなぜ本書で重視されている鑑賞の次元が機能しきらないのか。ここで問題は、第一章に示された社会状況や制度的な問題に回帰していく。それでも作り、受け取り、考え続けるのだという意思が本書には溢れている。
以上のように、やはり、これは制作と鑑賞をめぐる本でもあるのだが、障害について具体的に述べられた本であることを大事にしたい。個別の物事にある具体性がその構造や原理のレベルでほかの具体性と重なるのは確かだからこそ、この実践を「障害の有無にかかわらず」★3という普遍的・全方位的な対処の言い回しへ収束してはならない。この言い回しは、法律や条例だけでなく、催しの案内文、企画書の冒頭に頻出し、アートに関わる場でもいまではよく見かけるものだが、これは漸進的にだとしても、自身には障害がないと自覚する私(たち)が、障害をどうにかしていくことへ取り組み、社会に変化を起こした先でようやく言えるはずのことだ。いまはまだそのようにさまざまな物事を考えられる段階にはない。制度をつくる側の言い回しをそのまま用いることは危うい。理念は先回りしている。
いずれ、障害のあるなしに関わらない制作と鑑賞についての本として読み直せるよう、いま何に取り組めるのか。具体的に応えたい一冊である。
★1──p.30、4行目。
★2──pp.196-197の引用を受けて、p.197、6行目より。
★3──障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)の第一章第一条の冒頭で用いられている。条文は内閣府のページで公開されている。
読了日:2025/05/10(月)







