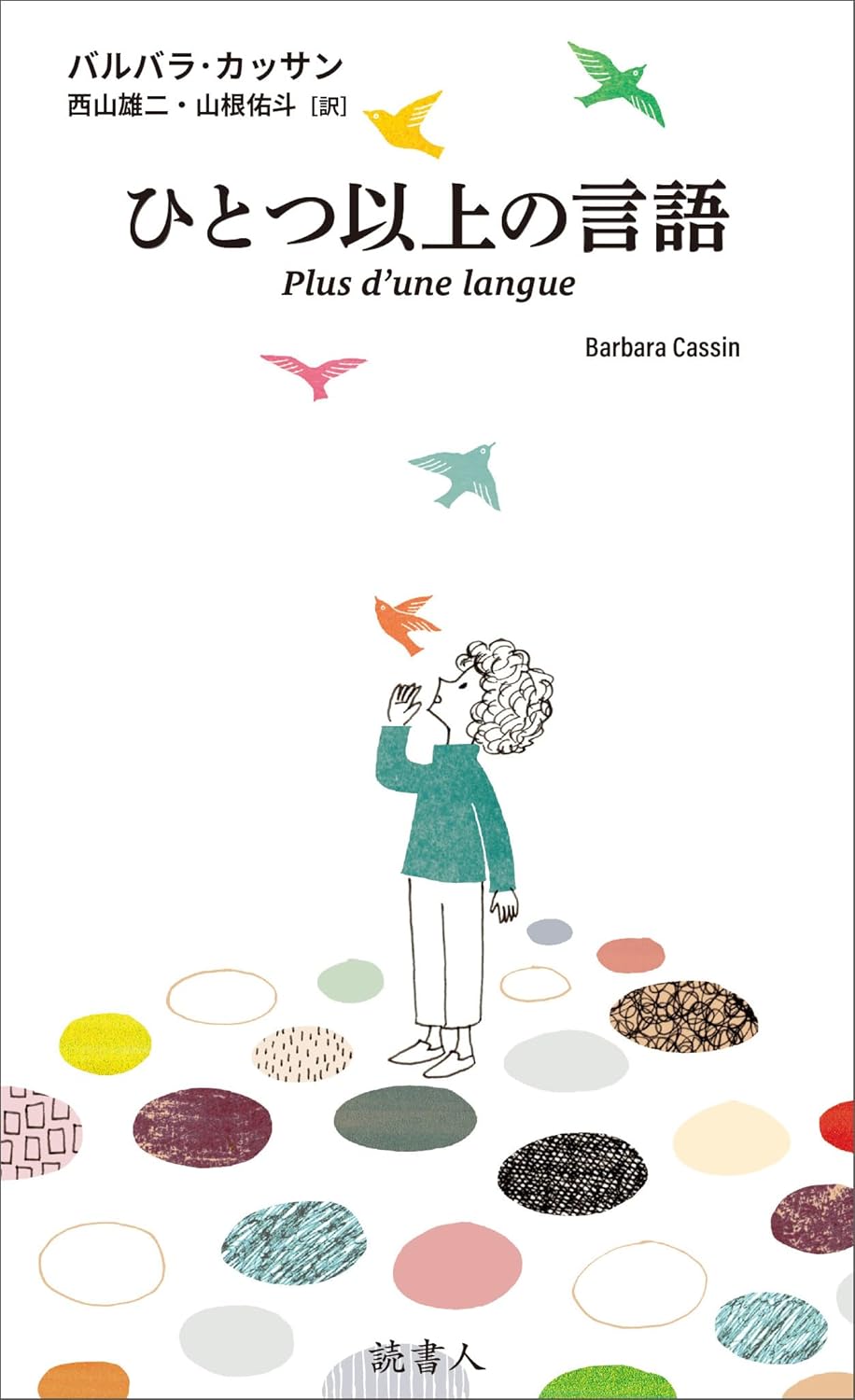
発行所:読書人
発行日:2025/03/25
フランス・パリ郊外のモントルイユ公共劇場では、2001年から現在まで「小さな講演会──子どもたちのための啓蒙」というイベントが継続的に開催されている。これは同劇場のドラマトゥルクであるジルベルト・ツァイ(Gilberte Tsaï)の発案による、10歳以上の子どもたちを対象とする講演会である。これまで、哲学者のジャン゠リュック・ナンシーや美術史家のジョルジュ・ディディ゠ユベルマンをはじめとする錚々たるメンバーが登壇しており、そのうち50点以上の講演録が書籍として刊行されている。
本書は、哲学者・文献学者のバルバラ・カッサン(1947-)による「小さな講演会」の記録である。カッサンは古代ギリシアを専門とする当代随一の古典学者だが、同時に精神分析や現代社会についての著書もあり、2018年には栄誉あるアカデミー・フランセーズの会員にも選出されるなど、社会的にも大きな影響力を有している★。
本書は、そのカッサンが2010年に「小さな講演会」で行なった、「言語」をめぐる講演と対話の記録である。講演の前半のテーマは、なぜこの世界にはひとつではなくいくつもの言語があるのか、というものだ。まず、カッサンは子どもたちに対して「母語とは何か?」と問いかけたうえで、どんな人も、本当の意味で言語を「自分のものにする」ことはできないと語る。このあたりの議論はジャック・デリダの著書が下敷きになっているが(『他者の単一言語使用──あるいは起源の補綴』守中高明訳、岩波文庫、2024)、カッサンの平明な語り口と具体的なエピソードによって、子どもたちにとっても実感しやすい内容になっている。
講演の後半でカッサンが語るのは「翻訳」の問題である。翻訳はなぜ難しく、しかしかくも豊かな経験をわたしたちにもたらすのか。かつてカッサンは、『ヨーロッパ哲学語彙──翻訳できないものの辞典』(2004/未訳)という巨大な辞典を仲間たちとともに編纂した。これは、ヨーロッパのさまざまな言語にまたがる哲学のキーワード集なのだが、そこで選ばれた単語(項目)はいずれもある言語に深く根ざした、ほかの言語に翻訳することが困難なものばかりである。およそどんな言語にも、容易には翻訳できない言葉や言い回しがある。それでもなお、翻訳には汲みつくしがたい魅力がある。なぜなら翻訳という行為は、ある世界からほかの世界へ「移行する」営みにほかならないからである。こうした議論も、『ヨーロッパ哲学語彙』という──編集期間15年にして1600ページ以上におよぶ──記念碑的な仕事をもつカッサンならではの、豊富な経験と深い実感にもとづいている。
他方、ここまで概観してきた講演パートは、本書の半分弱を占めるにすぎない。むしろ本書の真の読みどころは、講演につづいて行なわれた質疑応答の採録である、と言うべきだろう。そこでカッサンは、次々と繰り出される子どもたちの質問に対して、それぞれのバックグラウンドに応じたきめ細やかな返答を行なう。両親が英語とフランス語を話す家庭の子ども、あるいはフランス語とアラビア語を話す家庭の子ども──印象的なのは、カッサンがみずからに投げかけられた問いに、「なぜそのような問いが出てくるのか」というところまで見据えた応答を行なっていることだ。これらのやりとりを読んでいて痛感するのは、ここで鋭い質問を繰り出す「子どもたち」にとって、言語の複数性というトピックがきわめて大きなリアリティをもっているということである。それは「大人たち」が必要に迫られて、あるいは楽しみとして行なう言語学習とは、また大きく異なったものであるように思われる。そうした点に鑑みても、本書の質疑応答がわたしたちに教えてくれる事柄の大きさは計りしれない。
★──著者カッサンの多岐にわたる仕事と波乱に満ちた人生については、バルバラ・カッサン『ノスタルジー──我が家にいるとはどういうことか? オデュッセウス、アエネアス、アーレント』(馬場智一訳、花伝社、2020)の訳者解説および著作リストを参照のこと。これは筆者の知るかぎり、フランス語や英語でもほかに並ぶもののない、カッサンの著作と人生についてのもっとも充実した紹介文である。
執筆日:2025/06/08(日)







