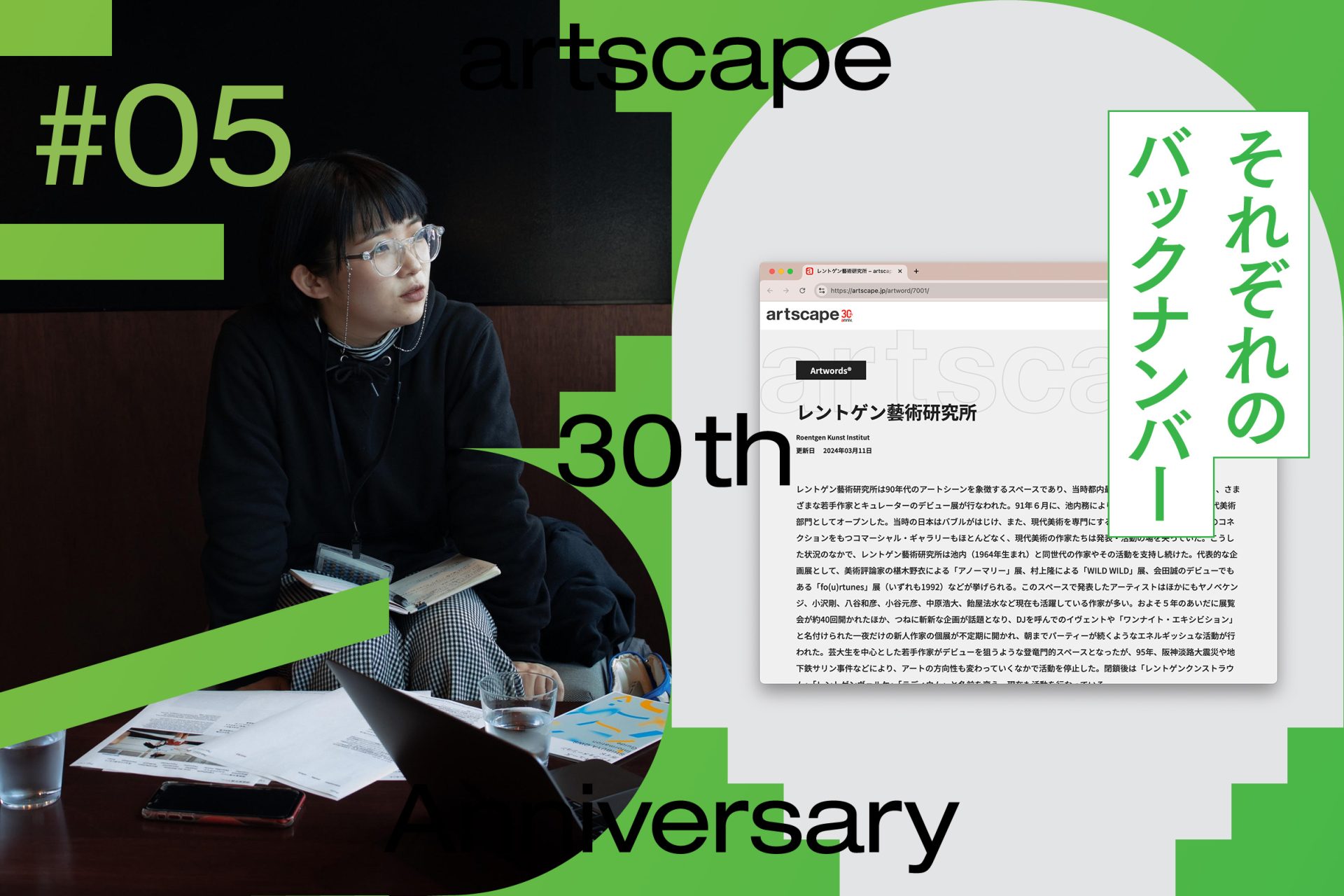近年、美術館が美術作品を展示するだけの器ではなくなったと同様に、図書館もまた本を陳列するだけの器ではなくなったようです。本がある風景の多様化は、本というメディアと都市の関係の変化を表わしているようにも思えます。今回は、五十嵐太郎さんに図書館建築の視点から遊歩していただきました。(artscape編集部)
図書館というビルディングタイプ
共編著をつとめた『日本の図書館建築──建築からプロジェクトへ』(勉誠社)を2021年に上梓したが、現在、その増補改訂版を準備している。実際、図書館というビルディングタイプは、時代にあわせて変化を続けており、ここ数年だけでも新しい事例が登場しているからだ。一方でネットで情報を簡単に得られるようになったことから、本や雑誌の売り上げは低下し、街の書店は激減している。その代わりに、TSUTAYAとスターバックスが提携するなど、居場所の添え物として本が扱われる現象が生じた。そもそもTSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が公共の図書館を運営するケースも増えている。そしてカフェが併設されることがめずらしくなくなった。2013年からCCCが指定管理者になった武雄市図書館は、その先駆的な事例として知られる。公共の図書館としての問題はあるが、筆者はここを見学し、まわりにおしゃれなカフェがない風景を確認し、正直、大都市に暮らす者が安易に批判しづらいとも感じた。しばらく前から、建築学生の卒業設計を見ると、こうした傾向がはっきりと現われている。すなわち、本を読むための空間ではなく、図書があることで人が集まる滞在型の空間というデザインの志向が強い。皮肉なことに、本が弱くなっている時代において、二子玉川蔦屋家電や枚方T-SITEなどが登場し、本はあらゆる場所に置かれるようになった。
さて、今回は2月末から6月にかけて、いろいろ訪れた図書館をまとめて振り返りたい。 5月10日、建築史家の松隈洋氏が大著『未完の建築──前川國男論・戦後編』(みすず書房、2024)を刊行したことを記念するシンポジウムが、東北大の川内キャンパスで開催されるにあたり、《東北大附属図書館本館》(1973)の見学会が行なわれた。これを設計した鬼頭梓は、前川事務所で《神奈川県立図書館》(1954)などを担当し、独立した後、図書館建築の名手として知られているからだ。筆者は普段、青葉山キャンパスにいるため、久しぶりの訪問である。特徴的なのは、建物の向こうまで見通せる中央の大きな吹抜け空間だろう。ここは開館時に「パブリック・ホール」と呼ばれていたが、なるほど両サイドの2階の閲覧室から見下ろせる、静かな都市の広場のようだ。実はかつてレファレンスやカタログのコーナーであり、図書の検索機能を中心に置き、象徴的に演出したものだった。もちろん、膨大なカードを収納する棚が並んでいたはずだが、コンピュータの導入によって不要になり、いまならこの大きな空間をもっと別の方法で活用できそうである。松隈によると、全体の規模は前川による《東京文化会館》に近いので、意識したのではないかという。ところで、これは大学図書館であり、教員や学生の研究を目的とした施設だ。したがって、前述した『日本の図書館建築』でも、公共図書館のみをとりあげており、大学図書館は入っていない。
 鬼頭梓《東北大附属図書館本館》[著者撮影]
鬼頭梓《東北大附属図書館本館》[著者撮影]
3月に新潟をまわったときに、4つの公共図書館を見学した。
竣工が古いものから順番にとりあげよう。《長岡市中央図書館》(1987)は、鬼頭が手がけており、矩形の平面と明快な左右対称軸によるクラシックな空間である。そしてファサードの大きなガラスの開口は、吹抜けに面している。筆者の世代にとっては懐かしいというか、学生のときの建築計画の教科書にのっているようなザ・図書館だった。コンクリートの壁はあまり露出させず、タイルのテクスチャーを強調し、落ち着いた表情をもつことは、《山口県立山口図書館》(1973)など、ほかの作品でも試みているが、師匠の前川の後期作品にも連なるだろう。なお、ポストモダンの時代にも突入しているので、玄関に破風のモチーフを用いている。もちろん、いまどきのカフェはない。
 鬼頭梓《長岡市中央図書館》[著者撮影]
鬼頭梓《長岡市中央図書館》[著者撮影]
内藤廣による《十日町情報館》(1999)は、映画『図書館戦争』(2013)のロケ地に使われたことで有名である。館内には実際の撮影に使われた「図書館の自由に関する宣言」のプレート、盾、案内図、当時の写真などが展示され、聖地として訪れている来場者もいた。やはり、ロケ地になった新居千秋のポストモダン建築、《水戸市立西部図書館》(1992)以上に、映画の痕跡があちこちに残る。これはバブル期の建築だけあって、装飾的な要素も多い。映画はほかに磯崎新の《北九州市立中央図書館》(1974)などでも撮影されたが、それぞれのデザインはばらばらだった(ゆえに、案内図は複数の建築を無理矢理につないでいる)。さて、十日町情報館は、シンボリックに形態を操作する水戸とは違い、シンプルな構造の形式が空間を決定する、内藤らしいダイナミックな建築である。すなわち、室内に入ると、まずプレキャストコンクリートのユニットを反復する堆雪型の大屋根が視界に飛び込む。そして奥に進むと、空間が掘り込まれることによって、天井高が増し、その分、本の壁が効果的に積み重なって立ち上がる。
 内藤廣《十日町情報館》[著者撮影]
内藤廣《十日町情報館》[著者撮影]
現代の複合化する図書館
隈研吾による《三条市図書館等複合施設まちやま》(2022)は、駅前の小学校跡が敷地だった。お得意の手法として内外に細い木の板=ルーバーを大量に貼り付けるが、あまりに表層的な印象が強く、正直、空間のデザインとしてはものたりない。むしろ、これが現代的なのは、図書館という単一のプログラムでなく、科学教育センター、鍛治ミュージアム(三条の作業である金具や定規の展示は面白い)、カフェなど、複数の機能を併設していることだろう。現在、税収が減っている地方の自治体では、建て替えに際して、異なる施設を合体させ、維持管理費を抑えるプロジェクトが増えている。ちなみに、まちやまの隣にたつ手塚建築研究所による細長いまちなか交流広場 《ステージえんがわ》(2016)も、木を使うが、こちらは幾何学を誘発する構造になっており、清々しい。
 隈研吾《図書館等複合施設まちやま》[著者撮影]
隈研吾《図書館等複合施設まちやま》[著者撮影]
新潟に足を運んだ最大の目的は、話題になった最新の図書館である、《 小千谷市ひと・まち・文化共創拠点 ホントカ。》(2024)を見学することだった。設計者は、プロポーザル・コンペで選ばれた平田晃久である。ここは小千谷市にぎわい交流課の土田昌史氏に案内してもらったが、朝早くからイベントを行ない、大勢の人が集まり、徹底的に使い倒されていた。商店街に面する変形敷地に対し、フロート(状況に応じて可動する本棚群)、アンカー(スタジオ、ファブラボ、子供の遊び場など、さまざまな個性をもった拠点)、ルーフ(遠くの山の風景と呼応する、人工的な地形のような屋上広場)と呼ばれる3つの建築的な介入が確かにうまく機能している。平田は、日本建築学会賞(作品)を受賞した《太田市図書館・美術館》(2017)でも、駅前の賑わいをとり戻していたが、《ホントカ。》ではさらに複雑なプログラムに挑戦し、成功している。人が詰まる場として、今後の地方における図書館建築のモデルになるだろう。
 平田晃久《小千谷市ひと・まち・文化共創拠点 ホントカ。》を商店街から見る[著者撮影]
平田晃久《小千谷市ひと・まち・文化共創拠点 ホントカ。》を商店街から見る[著者撮影]
 平田晃久《小千谷市ひと・まち・文化共創拠点 ホントカ。》[著者撮影]
平田晃久《小千谷市ひと・まち・文化共創拠点 ホントカ。》[著者撮影]
5月のゴールデンウィークのときに訪れた神奈川の《大和市文化創造拠点シリウス》(2016)は、大規模な施設だが、やはり図書館だけでなく、芸術文化ホール、生涯学習センター、屋内こども広場、カフェの機能を複合したものだ。オープンから約3年で、1000万人もの来館者を記録したことが報道されている。丘をイメージし、前面のプロムナードに対して段状の構成をとりつつ、植栽を施し、2階に屋上庭園も設けている。老朽化したホールと図書館を合体しつつ、建て替えたプロジェクトは、佐藤総合計画によって設計された。なるほど、評判通り、今風の居場所的な空間を全館に散りばめており、多くの来館者を集めている。ある意味では日本的な図書館の風景だが、勉強している学生も多い。また1階のギャラリーでは、ひらぎみつえの「あそべるえほん」展を開催していた。ただ、おそらく敷地所有の関係なのか、手前の外構の仕上げが完全になされていないことが気になった。
 佐藤総合計画+清水建設《大和市文化創造拠点シリウス》[著者撮影]
佐藤総合計画+清水建設《大和市文化創造拠点シリウス》[著者撮影]
2月末には大阪でも、2つの新しい図書館を見学した。駅前の《箕面市立船場図書館》(2021)と、《茨木市文化・子育て複合施設おにクル》(2023)である。前者は隣接する大阪大学の箕面キャンパスと市が連携する日本初の公立図書館に、《箕面市立文化芸術劇場》と《箕面市立船場生涯学習センター》が複合しており、久米設計と大林組が手がけたものだ。テクスチャーは「箕面」にちなんで織物をイメージし、「街のような建築」を意識したという。もちろん、カフェも併設している。
 久米設計+大林組《箕面市立船場図書館》[著者撮影]
久米設計+大林組《箕面市立船場図書館》[著者撮影]
もうひとつの《おにクル》は、大ホール、図書館、子育て支援施設、プラネタリウムなどを集約したプロジェクトであり、伊東豊雄と竹中工務店が設計したものだ。凄い人出だと聞いていたが、休日に訪れたところ、子供向けのイベントも開催され、想像をはるかに超える賑わいに驚かされた。伊東の系譜でたどると、《おにクル》はアヴァンギャルドなデザインを追求した《せんだいメディアテーク》を柔らかくしたような建築と言えるだろう。特徴的なのは、縦方向の円形の吹抜けにエスカレータを設置し、上下をシームレスにつないでいること。ちなみに、メディアテークでは、チューブ内のエレベータだった。またせんだいでは2、3、4階をライブラリーとしていたが、《おにクル》はもっと広域に図書を分散している。
 伊東豊雄+竹中工務店《茨木市文化・子育て複合施設おにクル》[著者撮影]
伊東豊雄+竹中工務店《茨木市文化・子育て複合施設おにクル》[著者撮影]
本をめぐる新しい試み
大阪では、6月に吹田市の江坂公園にある《江坂図書館》(1997)に足を運んだ。これは小さい図書館、駐輪場や駐車場を半地下に設け、その上部を緑の丘とした、いわゆる埋蔵型のデザインである。もちろん、ハイサイドライトから採光しており、内部の空間は暗いわけではない。これはバブル崩壊後に建築をランドスケープに溶け込ませ、その姿を見せないことが注目されたが、いち早く実現した事例だろう。近年、Park-PFIを導入したことで、指定管理者によるリニュアルが行なわれ、公園にカフェやレストランが導入された。
 日建設計《江坂図書館》[著者撮影]
日建設計《江坂図書館》[著者撮影]
また3月に安藤忠雄の《こども本の森 中之島》(2020)を再訪した。予約制の図書館であり、ホームページ上ではずっと先まで埋まっていたが、当日枠ではある程度の余裕を設けており、今回は並んで入った。これは大阪への恩返しとして、安藤が建設費を負担したプロジェクトである。ちなみに、すぐ近くの古典主義の《中之島図書館》(1904)も、住友家が社会貢献として寄贈したものだった。つまり、税金でまかなうものだけが、公共的な図書館というわけではない。《こども本の森中之島》は、絵本など、ビジュアルが多い書籍が多く、あらゆるところが閲覧室である。建築的には、安藤らしい打放しコンクリートの外観の内部に、ピラネージ的な迷宮空間と、パンテオンのような象徴的空間をもつ。その後、こどもの図書館のシリーズは、遠野(2021)、神戸(2022)、熊本(2024)、瀬戸内海を運行する図書館船ほんのもり号(2024)、松山(2025)と続き、台中(2026年に竣工予定)でも計画されている。
 安藤忠雄《こども本の森 中之島》[著者撮影]
安藤忠雄《こども本の森 中之島》[著者撮影]

安藤忠雄《こども本の森 中之島》、安藤忠雄「青春」展
模型は図書館船ほんのもり号[著者撮影]
台湾で思い出されるのが、《誠品書店》である。2000年代に初めて体験したとき、ギャラリー、ショップ、カフェなど、本を中心とする文化的な空間がビル全体に展開し、しかも24時間営業をしていたことに感心した。その後、日本でもこれを参考にした書店が登場している。本家が日本に上陸したのは意外に遅く、2019年にオープンしたCOREDO室町テラスの誠品生活日本橋だった。やはり本だけでなく、台湾の食材やグッズの小売店、飲食店などが入っている。またクリス・ヤオが江戸のイメージに着想源を得て、インテリアをデザインした。
 COREDO室町テラスの《誠品書店》店内[著者撮影]
COREDO室町テラスの《誠品書店》店内[著者撮影]
5月に筆者はここでトークイベント「日本橋の装飾を観察する 様式建築からポストモダンまで」を行なったが、東京建築祭のタイミングにあわせ、誠品生活日本橋が企画したものである。そして日本橋の建築マップも配布した。企画のきっかけとなったのは、筆者が監修した「さらに装飾をひもとく──日本橋の建築・再発見」展(髙島屋史料館TOKYO、2024-25)である。
ところで、2022年、神保町ではじまった共同書店に、今年の4月から筆者も参加した。これはフランス文学者の鹿島茂氏がプロデュースし、フランスの実在の通りの名前がついた棚のひとつからでも店主になれるシステムである。すずらん通りに1号店の「PASSAGE」がオープンし、筆者は神保町交差点の3号店「SOLIDA」(東京都千代田区神田神保町1丁目9−20)に棚をもつことになった。具体的には、店舗の2階のシャルル・ガルニエ広場1番地を選び、「建築と音楽の本棚」という名前をつけている。現在、自著のほか、手元にある古書を置いているので、ぜひ一度見てもらいたい(オンラインでも購入可)。ちなみに、シャルル・ガルニエは、パリのオペラ座を設計した建築家である。自分が小さな本屋をやっているというのは、実に楽しい。もちろん、ダブり本など減らすこともできるし、それが必要な人の手に届くのも嬉しい。

PASSAGEの店内[著者撮影]