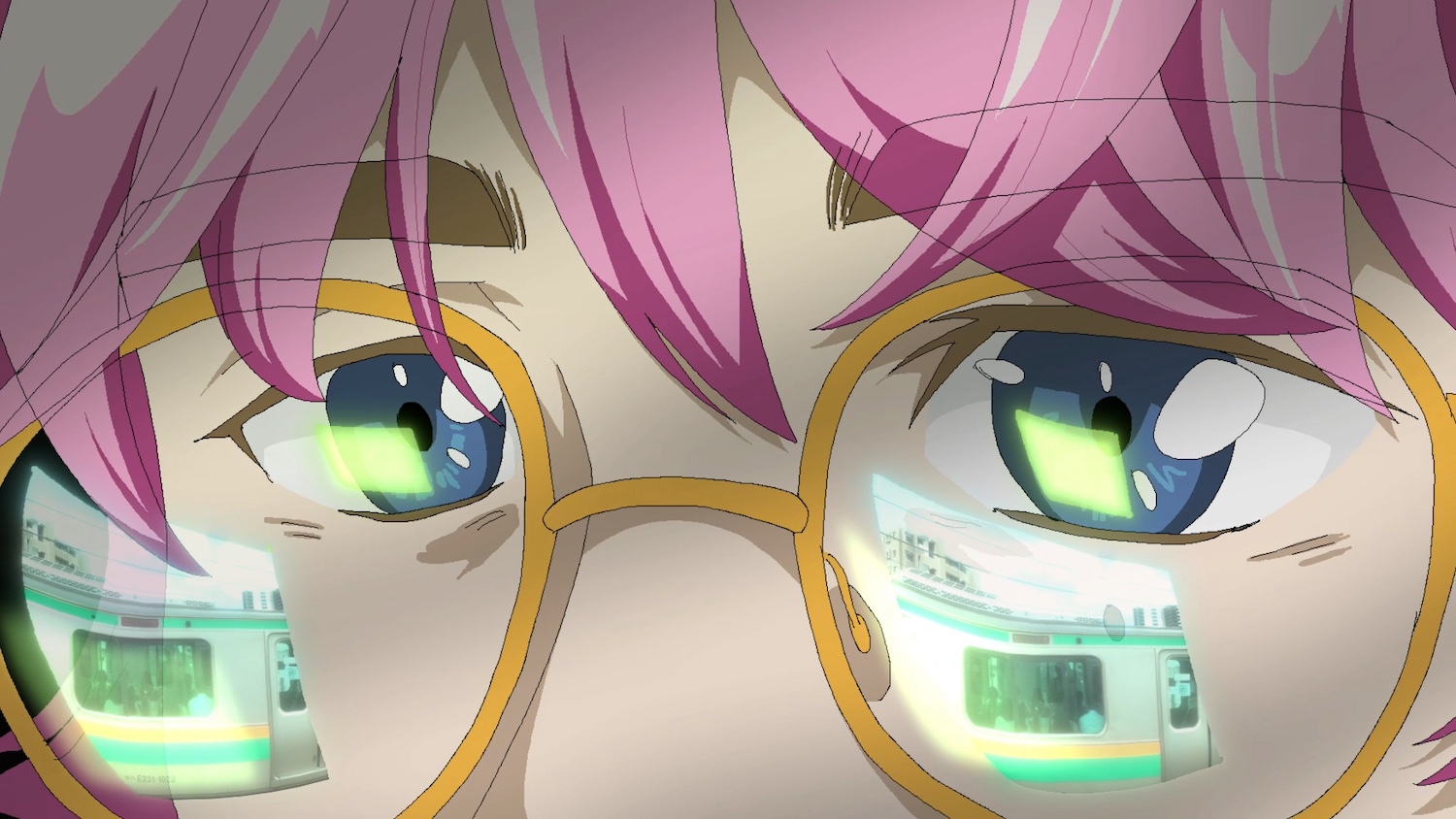会期:2025/07/29~2025/09/20
会場:Yumiko Chiba Associates[東京都]
公式サイト:https://ycassociates.co.jp/exhibitions/2025/07/19/2770/
寺田健人は、写真を軸に、コンセプチュアルな操作を加えることで、セクシュアリティやジェンダー、歴史の語りを規範化する権力や構造と、規範化の作用がもたらす周縁化・不可視化された存在について問う気鋭の作家である。現時点での代表作といえる「想像上の妻と娘にケーキを買って帰る」シリーズ(2020-)は、一見すると「普通の家族の日常的なワンシーン」を寺田自身がひとりで「セルフポートレート」として演じることで、規範化された男性性や家族像の虚構性を暴くと同時に、クィアの不可視化を浮かび上がらせる批評性をもつ★1。例えば、スーツ姿で玄関口に立った寺田が、「カメラの向こう側にいる誰か」に向かって笑顔でケーキの箱を差し出す写真。「帰宅直後の、家族思いのパパ」を撮ったスナップ風に見えるが、似たようなカットが執拗に反復され、寺田の手から「遠隔操作でシャッターを切るためのレリーズの黒いコード」が伸びていることに気づいたとき、「普通の家族の幸福な日常」というイメージは瓦解し、鑑賞者の先入観は鮮やかに裏切られる。
ここで、寺田による「虚構の家族写真」は、両義的な二重の批評性をはらむ。①サラリーマンとして「家の外」で働き、「家の中」で帰りを待つ妻子のためにケーキを買って帰る「理想的な父親像」とは虚構にすぎず、ジェンダーロールとして演じられた男性性という幻想であること。②「家族=異性愛の夫婦」「ピンクの持ち物を欲しがる子ども=娘」という異性愛規範やシスジェンダー規範に対する問い直し。ケーキの箱を持った寺田が立つ玄関口には、ピンクのスニーカーやバケツなど女児向けに商品化されたおもちゃや小物が置かれている。ただし、寺田がステートメントで「父親のパートナーは別に男でもいいし、ピンクのおもちゃで遊ぶのは男の子だっていい」と述べていることは示唆的だ。「ピンクの持ち物の主」が、画面には写らず不在化されていることは、「一般的な家族像」には収まらない、幼いトランスの女の子である可能性を想像させる。寺田の作品は、「不在化された妻と娘」に
一方で寺田は、出身地である沖縄という土地の記憶を扱ったシリーズ「聞こえないように、見えないように」(2022-)も制作しており、本展ではこちらのシリーズが展示された。「聞こえないように、見えないように」もまた、写真にコンセプチュアルな操作を施すことで、戦前から戦後の占領期を貫く沖縄の歴史の複層性とその見えにくさを浮かび上がらせる作品だ。寺田は、銃痕が残るコンクリートの構造物(監視台)や製糖工場の煙突などを撮影し、リトグラフに刷ったあと、米軍が使用した銃弾の薬莢を細かく砕いて塗料に混ぜ、銃痕の部分に金継ぎのように施した。それは、欠けた傷口を修復しつつ、傷跡自体を装飾として残す金継ぎと同様に、傷を癒すケアの行為でありつつも、「そこに傷跡があること」を消去するのではなく、違和感や物理的痕跡として指し示す。

[筆者撮影]

[筆者撮影]
無数の銃撃を受けたコンクリートの壁を写した作品表面は、金色の塗料で塗り潰され、ただれた皮膚を覆うかさぶたのようにも見える。一方、銃痕の部分に穴を開け、その下に金属の地色が露出している作品もある。写真と穴。写真と傷口。ここから直感されるのは、ロラン・バルトが写真の受容経験において論じた、ラテン語で「刺された小さな穴」や「刺し傷」を意味する「プンクトゥム」の語である。バルトは、社会的・文化的にコード化された明示的な写真の意味内容である「ストゥディウム」に対して、そうしたコード化を破壊する細部の発見を「プンクトゥム」と呼んだ。バルトにおいてはあくまで比喩であった「傷」「穴」だが、寺田は、刷られた写真イメージの表面に穴を開け、文字通り「傷」に変換する。その行為は、歴史の語りや記憶には「欠損」が内包されており、完全無欠な統一体ではないことの謂いでもある。
寺田の作品における「ストゥディウム」としての明示的な意味が、「戦争遺構や近代産業化の象徴である製糖工場跡に残る沖縄戦の痕跡」であるならば、遅れて発見され、見る者をまさに刺し貫くような「プンクトゥム」は何に相当するだろうか。本シリーズの要諦は、銃痕を撮影し、穴を開けられた被写体に「神社の鳥居と狛犬」が含まれていることだ。「沖縄の風景に鳥居があること」は、一見、とりたてて注目すべき点のない、ごく当たり前の風景に思えるかもしれない。だが、これらは、戦前に、沖縄神社(首里城内に設置)や護国神社などの創建に加えて、沖縄の聖地である

寺田健人《the gunshot still echoes – silence beneath the arch》(2025)
[© Kento Terada/Courtesy of Yumiko Chiba Associates]

寺田健人《the gunshot still echoes – stone skin, silent gaze》(2025)
[© Kento Terada/Courtesy of Yumiko Chiba Associates]
また、「米軍が使用した銃弾の薬莢の再利用」と沖縄の戦後史の関連にも目を向けたい。展示空間の冒頭には、黄色い紙に丸いエンボスを施したシートの束と、薬莢がガラス瓶に詰められている。沖縄では、黄色い紙に銭の形のエンボスを施した「うちかび」という冥銭を、死者があの世で使用できるよう、お盆などで燃やして供える風習がある。寺田は、物資不足の戦後期に米軍の薬莢を用いてエンボス加工したうちかびがつくられたことをインスタレーションとして再現するとともに、「金継ぎの素材の代用品」として薬莢を使用した。うちかびに限らず、アメリカ占領期の沖縄では、米軍の廃品を再利用してさまざまな生活道具がつくられた(例えば、現在、沖縄の土産物の定番である「琉球ガラス」は、米兵が捨てたコーラや酒のガラス瓶を砕いて溶かし、再利用したものがルーツである)。また、現在も手に入る薬莢は、本土返還後も残る基地の負担の証人である。

寺田健人《uchikabi for militarism》(2025)
[© Kento Terada/Courtesy of Yumiko Chiba Associates]
このように、寺田の「聞こえないように、見えないように」では、一枚の作品の表面に、三層の歴史のレイヤーが編みこまれている。沖縄戦の銃痕、米軍の廃品を再利用した占領期の記憶、そして近代の帝国日本による植民地化の歴史。それは、沖縄戦という断面だけを切り取るのではなく、その「前後」にまたがる見えにくい歴史を凝視する、ポストコロニアルな写真実践である。
★1──下記で詳しく論じられている。山本浩貴「不在と、その痕跡──『想像上の妻と娘にケーキを買って帰る』シリーズの写真作品を起点に、寺田健人の芸術実践について考える」『歴史・批評・芸術 003』(ユミコチバアソシエイツ、2024)、pp.76-86
★2──加治順人「沖縄の神社、その歴史と独自性」(『非文字資料研究』第16号、神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター、2018年9月)pp.37-68
★3──下道基行のウェブサイトより。http://m-shitamichi.com/work/torii/
関連レビュー
寺田健人「想像上の妻と娘にケーキを買って帰る」|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年06月01日号)
鑑賞日:2025/07/29(火)