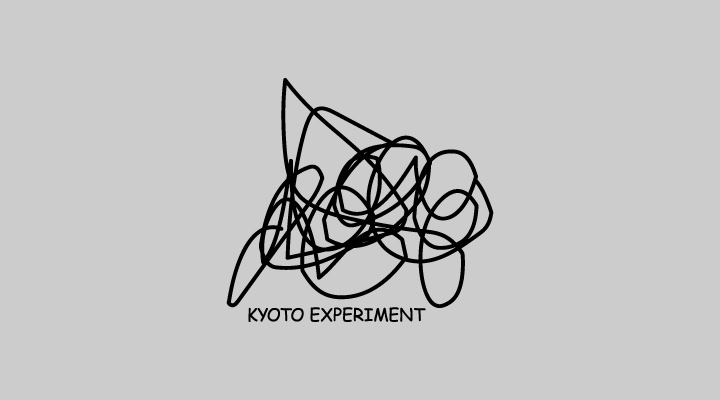会期:2025/10/24~2025/10/26
会場:ロームシアター京都 ノースホール[京都府]
公式サイト:https://kyoto-ex.jp/program/traveling-tongues/
「母語(mother tongue)」という単語が示すように、「舌」は言語を発音する身体器官であると同時に、味覚を受容する器官でもある。「慣れ親しんだおふくろの味」という舌の個人的記憶には、アジアにおける「発酵食」の伝播という文化的ルーツの共通性と、植民地支配の歴史もまた、書き込まれている……。発音と味覚、個人の記憶と歴史的パースペクティブの蓄積。本作は、こうした「舌」の多層性に着目し、「アジアの発酵食」のリサーチをテーマに、それぞれ異なる表現媒体・言語・出身地をもちつつ、韓国・台湾・フィリピンという日本の植民地支配を受けた地域をルーツとする4名のアーティストによる共同制作である。参加者は、アーティスト・コレクティブ「オル太」のメンバーで舞台作家・美術家のJang-Chi(チャンチ)、台北を拠点にパフォーマンスとビジュアル・アートを横断する李銘宸(リー・ミンチェン)、フィリピン出身の俳優・ドラマトゥルクのネス・ロケ、台湾生まれで幼少時に来日し、日本語で小説を執筆する温又柔。本作はまた、台北アーツフェスティバルが実施するリサーチプログラム「クルージング」の一環であり、ゲストキュレーターとして迎えられたKYOTO EXPERIMENTの共同ディレクターたちと、上記のアーティスト4名によって2024年に始動し、まさに「発酵」のプロセスのように、京都、台北、城崎でリサーチと創作を重ねてきた。
開場すると、舞台上にはさまざまな食材や調理道具、食と植民地支配に関する参考文献が載ったテーブルがあり、エプロン姿の出演者3名(ネス・ロケ、Jang-Chi、李銘宸)に笑顔で迎えられる。作品の序盤は、アジアにおける発酵食の伝播についてのレクチャーが実物の紹介とともになされる。だが、次第に「リサーチと創作のプロセスで行なわれた会話」を再現するような軽妙なやり取りが多言語で交わされ、フィリピンと日本の発酵食を掛け合わせた「公演限定の実験的な料理」を実際に調理するプロセスが同時進行し、舞台と客席の境界を撹拌するように、匂いが広がっていく。

[撮影:中谷利明 提供:KYOTO EXPERIMENT]
ネス・ロケによってまず紹介されるのは、魚と米を発酵させたフィリピンの「ブロ」。日本では馴染みのない料理だが、滋賀県の郷土料理の「ふなずし」と発酵方法がよく似ており、寿司の原型は東南アジアのメコン川流域から伝播したという説が紹介され、私たちが忘れてしまったつながりを記憶するものとして発酵食が語られる。
次にロケが紹介するのが、カカオで煮込んだ甘いお粥の「チャンポラード」。フィリピンでは、塩気のある干し魚と一緒に朝食として食べるという。グツグツと小鍋で煮込まれるチャンポラードを見て、Jang-Chiは、祖母が作ってくれたチゲやソルロンタンなど韓国の熱々のスープ料理を思い出すと語る。ここから本作は、メコン川流域から北上した発酵文化の伝播を逆流するように、日本から朝鮮半島、台湾、フィリピンにまたがる植民地下の文化的・言語的支配についての語りに展開していく。「あなたは韓国人ですか?」「本名って何ですか?」と李やロケから尋ねられ、答えるのを曖昧にはぐらかそうとするJang-Chi。マイノリティに「説明する負担」が課され、語ることが苦痛を再生産してしまうという回路を、観客はまなざすことになる。一方、「なぜ日本政府は朝鮮半島で創氏改名を行なったのか?」という質問に対する答えは、AIの人工音声で読み上げられ、非人間性や人工性が浮き彫りになる。スペイン統治時代のフィリピンにも同様の同化政策があったと話すロケ。現在も在日コリアンが使う通称名について、「周囲に溶け込むためのマントのようなもの」と言うロケに対し、李は「日本政府が着用を求めた制服のようなもの」と返す。

[撮影:中谷利明 提供:KYOTO EXPERIMENT]
英語、日本語、フィリピン語、台湾華語など多言語が飛び交う会話とともに、カカオで煮込むお粥に酢飯を使い、さらに魚を発酵液に漬けて干した「くさや」を混ぜた創作料理「チャンポラード寿司」が作られていく。「異文化交流や融合の象徴」として供されると思いきや、ロケが待ったをかける。「チャンポラードに酢は混ぜないし、本当の味とは違う」と。「初めてチャンポラードを食べる観客に、まずいと思われたくない」と反対するロケ。異文化交流や国際共同製作が謳う「共存」「融合」が、その背後に文化的搾取や排除の構造を抱え込んでいるのではないか。あるいは、「文化の真正性」はどこに担保されるのか、と本作は自己批評的に問いかける。というのも、ロケ自身が語るように、チャンポラードに用いるカカオ自体、メキシコの植民地化を通してスペイン統治時代にフィリピンに入ってきたからだ。

[撮影:中谷利明 提供:KYOTO EXPERIMENT]
上演の最後には、議論を経て出来上がった「チャンポラード寿司」が観客にふるまわれる。濃厚なカカオの香りと甘み、魚の塩味、柔らかいお米と干し魚の食感の対比、そして強烈な匂いが鼻を突き抜ける。どこまでが「チャンポラード」で、どこからが「寿司」なのか、舌の上で境界線は溶け合い、強い臭気だけが鼻腔にまとわりつく。

[撮影:中谷利明 提供:KYOTO EXPERIMENT]
「違和感」は、味と匂いだけではなく、「音声」にも仕込まれている。作中では、アイデンティティと料理、家族について綴る温又柔の小説の朗読に加え、李の書いたテキストが人工音声によって日本語に変換して読み上げられる。その「不自然なアクセントやイントネーション」は、異言語どうしのコミュニケーションを円滑化するツールとしてのAIと同時に、「正しくない発音」によって他者を弁別してしまう心理構造を突きつける。
最後の試食タイムには、ブロ、ふなずし、(普通の)チャンポラードなど、作中で紹介された料理に加え、台湾で売られているパクチー味のドリトスなど、「異文化コラボ商品」も供された。作中では、「アボカド寿司」や「納豆タピオカミルク」はアリなのかといったやり取りも交わされていたが、「チャンポラード寿司」も、「新感覚の味」として、国際的な舞台芸術市場でたちまち消費されてしまうのか。加速する消費資本主義のもとでは、コラボグルメも舞台芸術のマーケットも等しく、文化的差異が商品価値として消費されていくのか。舌に残るエグみや強烈な臭気は、そうした事態への抵抗となりうるのか。
2020年に新ディレクター体制に移行したKYOTO EXPERIMENT(KEX)は、特に近年、異分野で活動するアジア圏のアーティストどうしのコラボレーションを積極的に手がけている。そのひとつである本作は、台北パフォーミングアーツセンターと国際交流基金との国際共同製作でもある。「国際的コラボレーション=新たなフュージョン料理の創作」という発想のある種のわかりやすさを逆手に取り、「舌」に残る植民地支配の記憶や文化の真正性を問うとともに、文化的差異が新たな商品価値として消費される市場主義に対して自己批評を提示する本作は、KEXが積み重ねてきた「異分野の国際コラボレーション」のひとつの結実といえるのではないだろうか。
鑑賞日:2025/10/24(金)